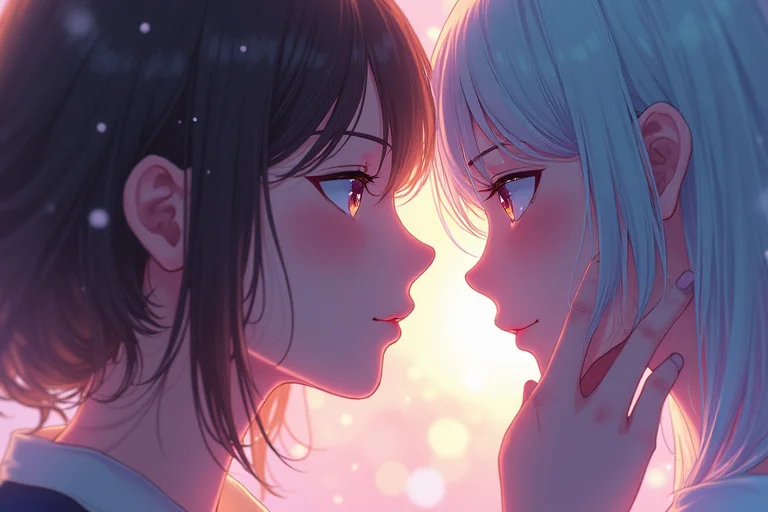第一章 ファインダーの中の君
コンクリートの箱がひしめく街で、僕は心をすり減らしていた。水島航、二十八歳。グラフィックデザイナーという聞こえの良い肩書きの裏で、終わらない修正指示とクライアントの気まぐれに翻弄される日々。かつて抱いていた創作への情熱は、締め切りという名の濁流に押し流され、今やその欠片も見当たらない。恋愛なんてもってのほかだ。三年前に終わった恋が心に残した深い傷は、今も時折鈍く痛む。人を愛し、そして失うことの虚しさを、僕はもう味わいたくなかった。
その日、僕は吸い寄せられるように、神保町の裏路地に佇む古びたカメラ店に足を踏み入れた。埃とカビとオイルが混じり合った独特の匂いが、不思議と心を落ち着かせた。ガラスケースの中で、一台のカメラが静かに僕を待っていた。銀色のボディが鈍い光を放つ、ライカM3。その完璧なフォルムと、長い年月を経てきたであろう風格に、僕は一瞬で心を奪われた。ほとんど衝動的に、僕はそれを手に入れた。
自宅のアパートに戻り、冷たい金属の感触を確かめながらカメラを操作していると、ふと違和感を覚えた。フィルムカウンターが「24」を指している。まさか、と思い裏蓋を開けると、案の定、使いかけのフィルムが装填されたままになっていた。前の持ち主の忘れ物だろう。ほんの少しの罪悪感と、それ以上の好奇心に駆られ、僕は残りのフィルムを巻き上げ、近所の写真店に現像を頼んだ。
二日後、受け取った写真の束をめくった僕は、息を呑んだ。
そこに写っていたのは、見知らぬ一人の女性だった。桜並木の下で風に髪をなびかせる姿。古書店の片隅で真剣な眼差しで本を選ぶ横顔。海辺のカフェで、クリームソーダのグラス越しに悪戯っぽく笑う顔。どの写真からも、撮影者の被写体に対する深い愛情が、痛いほどに伝わってきた。それは、単なる記録ではない。愛する者の存在そのものを、世界の中心として切り取った、祈りのような写真だった。
そして、最後の一枚。夕日に染まる砂浜に、彼女は一人で立っていた。波打ち際で裸足になり、少しだけこちらに振り向いて、柔らかく微笑んでいる。その笑顔は、どこか儚く、切なげで、それでいて全てを包み込むような優しさに満ちていた。僕はその写真から目が離せなくなった。ファインダー越しに、撮影者はどんな想いで彼女を見つめていたのだろう。そして、彼女は、どんな想いで彼に応えていたのだろう。
僕の乾ききった心に、その笑顔が染み込んでいく。この女性は誰だ? そして、これほどまでに彼女を愛した撮影者は、一体誰なのだろうか。忘れかけていたはずの感情が、胸の奥で小さな熱を帯びていくのを、僕は感じていた。
第二章 借り物の恋心
その日から、僕の日常は一変した。仕事の合間を縫っては、写真に写り込んだ風景の断片を手がかりに、彼女の足跡を辿り始めた。それはまるで、誰かの幸福な記憶を追体験する、奇妙な巡礼の旅だった。
写真に写っていた特徴的な看板の古書店は、やはり神保町にあった。桜並木は、調べてみると千鳥ヶ淵のものだと分かった。僕はライカを首から下げ、同じ場所に立ち、同じ角度でファインダーを覗いた。レンズの向こうには、もちろん彼女の姿はない。それでも、撮影者が感じたであろう光や風を肌で感じると、彼女がすぐそこにいるような錯覚に陥った。
この感情は何だろう。僕は、会ったこともない女性に、明らかに恋をしていた。だが、それは僕自身の恋心なのだろうか。それとも、カメラと写真に残された、名も知らぬ撮影者の想いに共鳴しているだけなのだろうか。まるで、他人の感情を借りて、恋をしているような奇妙な感覚。それでも、僕は彼女を探すことをやめられなかった。
調査を進めるうち、僕はカメラが売られた経緯から、前の持ち主の名前に辿り着いた。「藤宮誠(ふじみや まこと)」。ネットで検索すると、同名の写真家のブログが見つかった。そこに掲載されている風景写真は、僕が手にした写真と同じ、優しく詩的な視点で世界を切り取っていた。間違いない、彼が撮影者だ。
僕は貪るように彼のブログを過去へと遡った。そこには、彼が「雫(しずく)」と呼ぶ女性への愛が、切々と綴られていた。
『雫の笑顔は、雨上がりの虹のようだ。僕のモノクロームの世界に、鮮やかな色彩を与えてくれる』
『ファインダー越しに彼女を見つめていると、世界の全ての美しさが、彼女という一点に収斂していくのを感じる』
言葉の端々から、雫という女性を心から慈しみ、愛していることが伝わってくる。しかし、ブログの更新は二年前に突然途絶えていた。そして、最後の記事には、こう記されていた。
『僕はもうすぐ、長い旅に出る。でも、僕の愛は、僕が撮った写真の中に永遠に生き続ける。雫、君と出会えてよかった』
嫌な予感が胸をよぎった。さらに調べていくと、藤宮誠が二年前に、三十歳という若さで病気で亡くなっていたことを知った。
僕は愕然とした。僕が追いかけていたのは、亡き人が遺した愛の記憶だったのだ。藤宮誠の視点を通して、僕は雫を愛してしまった。この恋は、始めから僕のものではなかった。借り物の、空っぽの恋心。そう思うと、胸が苦しく締め付けられた。それでも、僕は諦めきれなかった。最後の一枚、あの夕暮れの海辺の笑顔。その場所さえ突き止めれば、何かが分かるかもしれない。僕は最後の望みをかけて、写真の中のカフェを探し続けた。
第三章 存在しない恋人
数週間後、僕はついにその場所を突き止めた。鎌倉の海岸沿いにひっそりと佇む、海風に晒された小さなカフェ。写真の中と寸分違わぬ、青い窓枠と古びた木の扉。心臓が早鐘を打つのを感じながら、僕は店の中へ入った。
「いらっしゃい」
カウンターの奥から、白髪の穏やかなマスターが顔を上げた。僕は震える手で、雫が写った写真を見せた。
「すみません、この女性を、ご存知ないでしょうか」
マスターは写真を一瞥し、目を細めた。そして、僕の顔をじっと見つめ、何かを確かめるように言った。
「ああ、雫さん…。懐かしいな。これは、藤宮さんが亡くなる少し前に、ここで撮った写真ですね」
やはり、ここだ。僕は身を乗り出した。「彼女は…雫さんは、今どこに?」
すると、マスターは少しだけ哀しそうな顔をして、僕の予想を根底から覆す言葉を口にした。
「お客さん、落ち着いて聞いてください。雫さんという女性は、実在しませんよ」
時間が、止まった。耳鳴りがして、マスターの言葉が頭の中で反響する。実在しない? どういうことだ?
「…雫さんは、藤宮さんの想像上の恋人なんです」
マスターは、静かに語り始めた。藤宮誠は、この店の常連だったこと。末期の癌で余命を宣告され、天涯孤独の身だったこと。彼は死の恐怖と絶望的な孤独から逃れるように、自分の心の中に「雫」という理想の恋人を作り出した。そして、まるで彼女が本当にそこにいるかのように、様々な場所で風景写真を撮り続けたのだという。
「じゃあ、この写真の彼女は…?」
「藤宮さんは、もともとCGの技術にも詳しかった。亡くなる直前、彼は自分の想像の集大成として、撮りためた風景写真に、最新のAI画像生成技術を使って雫さんの姿を合成したんです。彼女の顔も、表情も、全て彼の愛情と、孤独が生み出した…幻なんですよ」
衝撃で、立っていられなかった。僕が心を奪われ、恋い焦がれたあの笑顔は、プログラムが生成したデジタルデータだった。藤宮誠という男の、あまりにも切実な妄想の産物だった。僕が追い求めていたのは、蜃気楼だったのだ。
愛とは何か。実体を持たない相手への想いは、果たして愛と呼べるのか。僕が抱いていたこの感情も、幻を愛した幻に過ぎなかったのか。足元から世界が崩れ落ちていくような感覚に、僕はただ立ち尽くすことしかできなかった。
第四章 愛という名の光
失意のままアパートに戻った僕は、ベッドに倒れ込んだ。騙された、という気持ちと、藤宮誠の途方もない孤独に対する畏怖のような感情が入り混じり、心がぐちゃぐちゃにかき乱されていた。僕は一体、何を追いかけていたのだろう。
数日が過ぎ、少しだけ冷静さを取り戻した僕は、もう一度、藤宮誠のブログを開いた。今度は、雫の存在が幻であることを知った上で、彼の言葉を読み返していく。すると、以前とは全く違う意味が、そこから立ち上ってきた。
『たとえ雫が僕の幻想だとしても、この胸にある愛は、紛れもなく本物だ。孤独に沈みそうになる僕を、確かに照らしてくれた光なんだ』
死を目前にした男の、魂の叫びがそこにあった。彼は、存在しない「雫」を愛することで、生きる意味を見出そうとしていた。愛する対象が実在するかどうかなど、彼にとっては問題ではなかったのだ。重要なのは、誰かを愛おしいと思う「心」そのものだった。そのひたむきで純粋な愛の形が、僕の胸を強く打った。
僕は、三年前の自分の恋を思い出していた。失うことを恐れるあまり、相手から何を与えてもらえるか、自分の心が傷つかないか、そればかりを考えていた。相手を心から信じ、ただひたむきに愛するという、最もシンプルで、最も尊いことから目を背けていたのだ。藤宮誠は、幻の恋人に、僕が決して与えることのできなかった無償の愛を捧げていた。
愛とは、対象の有無に関わらず、自らの内側に灯す光なのかもしれない。その光が、たとえ暗闇の中であろうと、自分の足元を照らし、生きる力を与えてくれる。藤宮誠は、そのことを命を懸けて証明したのだ。
僕は、棚の奥からライカM3を取り出した。冷たく重い感触が、なぜか温かく感じられた。今度は、僕自身の目で、僕自身の心を写すために。
僕は電車に乗り、あの夕暮れの海岸へ向かった。藤宮誠が、最後の写真を撮った場所。オレンジ色に染まる空と、寄せては返す穏やかな波。僕はファインダーを覗いた。レンズの向こうに、もちろん雫の姿はない。あるのは、ただどこまでも広がる美しい世界だけだ。
カシャッ、と乾いたシャッター音が響いた。
ファインダーから目を離すと、僕の頬を涙が一筋、伝っていた。それは悲しみの涙ではなかった。幻を追いかけた僕の愚かさを笑う涙でもなかった。一人の男が遺した愛の光に触れた、感動の涙だった。
心の中に、小さな、しかし確かな光が灯るのを感じていた。それは、これから誰かを愛せるかもしれないという、静かな希望の光だった。空っぽだった僕の世界に、再び色彩が戻り始めたような気がした。僕はもう一度、水平線にカメラを向けた。そのファインダー越しの世界は、以前とは比べ物にならないほど、鮮やかで、愛おしく輝いていた。