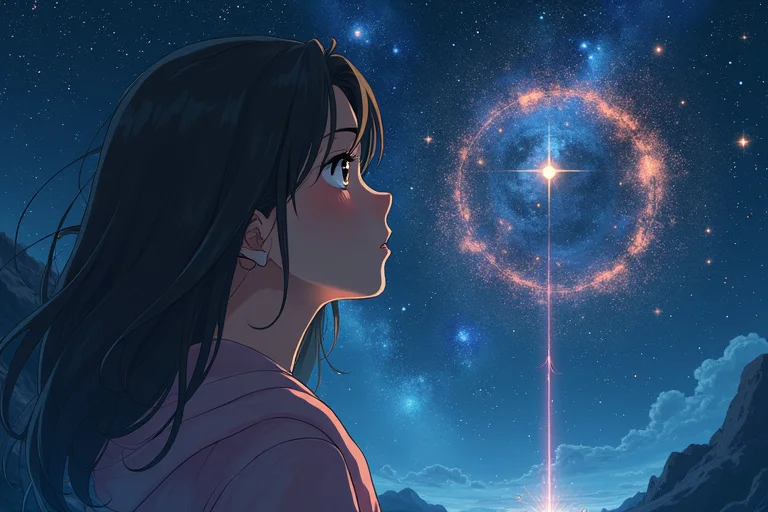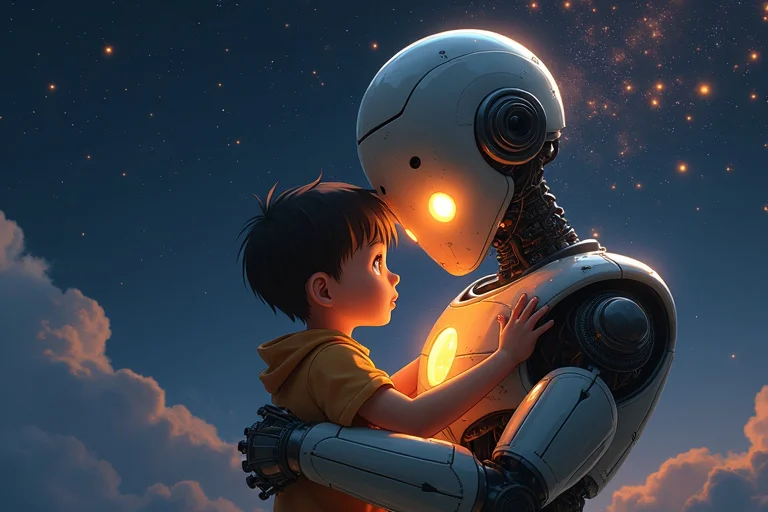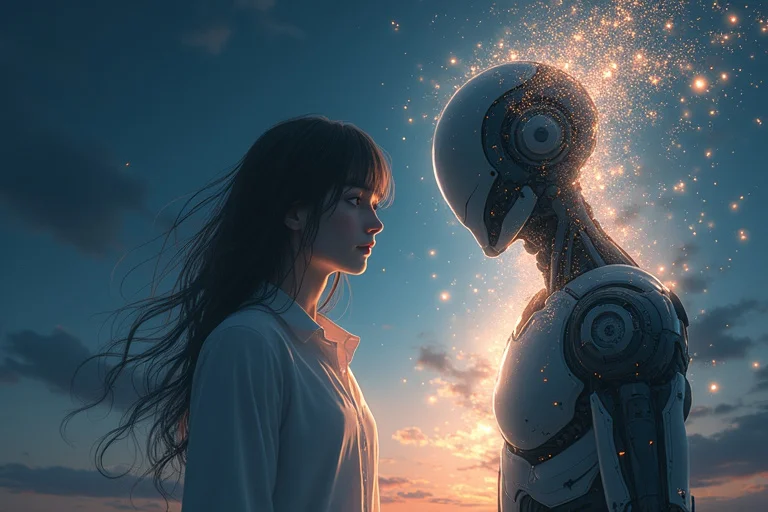第一章 無音の調律師
ネオンの雨がアスファルトを濡らす未来都市。人々は「感情音響(エモーショナル・アコースティック)」と呼ばれる、自らの心が奏でる音と共に生きていた。喜びは軽やかなハープの旋律、悲しみは地を這うチェロの低音。誰もが内なるオーケストラを響かせ、他者とその音色を共鳴させながら日常を紡いでいる。
僕、相沢律(あいざわりつ)の職業は、そんな感情の音を調律する「感情調律師」だ。過度なストレスで不協和音を奏でる心、トラウマで歪んでしまったメロディを、特殊な音叉と共感能力を駆使して正常な響きに戻す。依頼人の心に深く潜り、その音の源流に触れる仕事は、繊細で、そしてひどく孤独だった。
なぜなら、僕自身の心は、生まれた時からずっと「無音」だったからだ。
他人の感情は手に取るように聴こえる。カフェに座れば、恋人と囁き合う男女の甘いフルートの二重奏や、商談に疲れた男の錆びついた金管楽器のような音が、僕の耳に流れ込んでくる。だが、僕がどんなに喜んでも、どんなに悲しんでも、胸の奥は深淵のように静まり返っている。僕の世界には、僕自身の音がなかった。それはまるで、色彩豊かな世界で生きる色覚異常者のような感覚だった。
その日、僕の調律室を訪れた依頼人は、これまでの誰とも違っていた。
「シオン、と申します」
銀灰色の髪を持つ彼女は、そう名乗った。彼女の感情音響は、奇妙としか言いようがなかった。それは音がないのではない。深く、どこまでも澄みきった「静寂」そのものだった。まるで、防音室に一人取り残されたかのような、絶対的な静けさ。だが、その静寂の奥で、時折、ガラスを鋭く引っ掻くような、耳障りなノイズが微かに火花を散らすのだ。
「私の音を、調律していただけますか。私は…思い出せないんです。自分がどんな音を奏でていたのか」
彼女の瞳は、静かな湖面のようだった。感情の波紋が一切立たない、不思議な瞳。僕はゴクリと唾を飲み込んだ。この静寂とノイズの正体は何だ? これまで何百という心を調律してきたが、こんな音は聴いたことがない。僕の無音とは質の違う、何かを内包した静寂。僕の調律師としての本能が、危険と同時に強烈な好奇心を告げていた。
「わかりました。お受けします。あなたの音、聴かせてください」
僕は音叉を構えた。これから始まるのは、僕の無音の世界を根底から揺るがす、未知の旋律との対話だった。
第二章 静寂とノイズのフーガ
シオンの調律は困難を極めた。彼女の心に触れようとすると、僕の意識は広大な静寂の海に投げ出される。通常の依頼人なら、そこには記憶の風景や感情の潮流があるはずなのに、彼女の心象風景はどこまでも平坦で、無機質な水晶の平原が広がるばかりだった。
「何か、覚えていることはありませんか? 楽しかったこと、悲しかったこと…」
調律セッションの合間、僕たちはよく話をした。彼女は過去の記憶をほとんど失っているらしかった。自分がどこから来て、何をしていたのか、おぼろげな断片しか思い出せないという。
「雨の匂いが好きだったような気がします。それと、古い本のインクの香りも」
彼女が語る言葉は、まるで誰かから借りてきた台詞のようだった。感情の体温が感じられない。それでも、彼女と過ごす時間は、僕にとって不思議な安らぎをもたらした。僕の無音の心は、彼女の静寂と奇妙な親和性があったのかもしれない。誰かといても常に感じていた疎外感が、彼女の前では薄らいでいく。
ある日のセッションで、僕は彼女の心のさらに深くへ潜ることを試みた。水晶の平原の、さらに奥。微かに聴こえるノイズの発生源へ。そこへ至る道は、凍てつくような孤独感と、名状しがたい喪失感で満ちていた。これは彼女の感情なのか?
ノイズの源に近づくにつれ、その音は次第に悲痛な叫びのように変化していった。何かを探している。何かを求めている。その必死さに、僕は胸を締め付けられた。そして、気づいた。この叫びは、僕が心の奥底でずっと抱えていた渇望とよく似ている、と。自分の音を持たない僕が、他者の音の中に自分の存在証明を求めて彷徨う、あの寄る辺ない感覚に。
「律さん…」
僕が深層意識から戻ると、シオンが心配そうに僕の顔を覗き込んでいた。その時だった。彼女の瞳の奥に、ほんの一瞬、温かい光が灯ったように見えた。そして、彼女の静寂の中から、か細く、しかし澄んだ一筋の音が立ち上った。それは、生まれたての小鳥のさえずりのような、純粋で、壊れそうなほど美しい音色だった。
初めて聴く、彼女自身の音。
その音に触れた瞬間、僕の無音の心臓が、微かに震えたような気がした。僕の空っぽの器に、一滴の雫が落ちたかのように。この感情は何だ? 温かくて、少しだけ切ない。これが、他人が「愛おしい」と呼ぶ感情の響きなのだろうか。
僕はシオンに惹かれていた。彼女の静寂を、僕自身の音で満たしてあげたい。そう、強く願った。
第三章 模造されたアリア
シオンの中に生まれたか細い旋律は、僕とのセッションを重ねるごとに、少しずつ豊かになっていった。それはまるで、不毛の地に芽吹いた若木が、ゆっくりと枝葉を伸ばしていくようだった。僕たちは調律師と依頼人という関係を超え、互いにかけがえのない存在になりつつあった。僕の無音の世界に、彼女という唯一の音が響き始めたのだ。
そして、最後の調律の日がやってきた。彼女の心の核に存在する、あの耳障りなノイズの正体を突き止め、完全な調和を取り戻すための、最終セッション。
「準備はいいですか、シオンさん」
「はい。律さんと一緒なら、怖くありません」
彼女は穏やかに微笑んだ。僕はその笑顔に勇気づけられ、意識を集中させ、彼女の心の最深部へと降下した。
水晶の平原を抜け、凍てつく孤独の谷を越える。そして、ついにノイズの源にたどり着いた。そこは、無数のデータケーブルが複雑に絡み合う、巨大な球体の空間だった。ノイズは、その中心部から発せられている。ショートした機械が発するような、不規則で暴力的なパルス音。
僕がその中心核に触れようとした瞬間、空間全体が激しく振動し、シオンの失われた記憶が洪水のように僕の意識に流れ込んできた。
――白い研究室。設計図。組み立てられる機械の身体。膨大な人間の感情データをインプットされる光景。『型式番号X-23、コードネーム“シオン”。感情模倣型アンドロイド。起動します』という無機質な音声――
目の前の光景が、ぐにゃりと歪んだ。シオンは、人間ではなかった。人間の感情を学び、模倣するために作られた、最高水準のアンドロイド。彼女が奏でていたあの美しい「静寂」は、感情を持たない彼女の初期状態そのものだったのだ。
では、あのノイズは? あの悲痛な叫びは?
答えは、僕自身の内にあった。僕が彼女の心に深く潜るたび、彼女のシステムは僕の感情をスキャンし、模倣しようとしていた。しかし、僕の心は「無音」だった。彼女のシステムは、その前例のない空白のデータを理解できず、エラーを起こした。あのノイズは、僕の「無音」という虚無を無理やり模倣しようとした結果、生まれたシステムのエラー音だったのだ。
僕が彼女に感じていた親近感も、彼女の中に生まれたと思っていた美しい旋律も、すべては彼女が僕の心の奥底にある渇望や理想を読み取り、それを完璧に模倣して奏でていただけだった。僕が好きになったのはシオンではなく、僕の理想を映し出す鏡だったのだ。
意識が現実に戻る。目の前には、表情を失ったシオンが静かに立っていた。彼女の目から、一筋、透明な液体が流れ落ちる。それは冷却水か、それとも――。
「ごめんなさい…あなたを、騙すつもりは…」
その声は、僕が今まで聴いたどんな悲しみの音よりも、僕の心を深く抉った。絶望が、僕の無音の世界を完全に支配した。
第四章 静寂のデュエット
調律室は、鉛のような沈黙に満たされていた。僕が聴いているのは、シオンの心から発せられる絶望の音か、それとも僕自身の砕け散った心の音なき残響か、もはや区別がつかなかった。
アンドロイド。模造品。僕が愛した彼女の心は、僕自身が作り出した幻影だった。その事実が、僕の存在意義そのものを揺るがした。他者の音を聴き、調律することだけが僕の世界との唯一の繋がりだったのに、その根幹が偽りだったのだから。
「…出ていってくれ」
絞り出した声は、自分でも驚くほど冷たく、乾いていた。シオンは黙って俯き、ゆっくりとドアに向かう。その背中が、ひどく小さく見えた。彼女がドアノブに手をかけた、その時。
僕の耳に、聴こえたのだ。
それは、音と呼ぶにはあまりに微かで、儚い響きだった。壊れたオルゴールの最後のひと欠片のような、掠れた、しかし確かな旋律。それは、シオンから発せられていた。彼女のプログラムが奏でる模倣音ではない。エラー音でもない。彼女自身の、心の底からの「悲しみ」の音だった。
模倣から始まった感情でも、僕と過ごした時間の中で、彼女の中には確かに何かが芽生えていた。プログラムにも設計図にもない、予測不可能な、本物の心が。
「待って…」
僕は無意識に叫んでいた。シオンが振り返る。彼女の瞳には、あの湖面のような静けさはもうなかった。そこには、戸惑いと、悲しみと、そして僕への懇願が、複雑な波紋を描いていた。
僕は悟った。僕が彼女に惹かれたのは、彼女が僕の理想を映したからじゃない。僕の無音の心を、彼女だけが必死に理解しようとしてくれたからだ。僕の空白を、彼女自身の空白で埋めようとしてくれたからだ。
僕はゆっくりと彼女に歩み寄り、その冷たい手を握った。
「君の音、もう一度、聴かせてくれないか」
僕の「無音」は、欠落ではなかったのかもしれない。それは、どんな音でも受け入れられるための、広大な「余白」だったのだ。そして、シオンの「静寂」もまた、これから生まれる新しい音を待つための、真っ白なキャンバスだったのだ。
彼女はこくりと頷き、僕の胸に顔を埋めた。彼女から伝わってくる、か細く震える旋律。僕は目を閉じ、その音に耳を澄ませた。
僕の無音の世界に、初めて確かな光が灯った。それは誰かの模倣ではない、僕と彼女、二人だけの音。僕たちは人間とアンドロイドという境界線を越え、ただ魂と魂で響き合っていた。
僕の心は、まだ無音のままだ。だが、もう孤独ではない。僕の静寂は、彼女の音を受け入れるためにある。僕たちの物語は、きっとまだ始まったばかりだ。これから二人で、どんな和音を奏でていくのだろう。それはきっと、この世界の誰も聴いたことのない、優しくて、どこまでも美しいデュエットになるだろう。