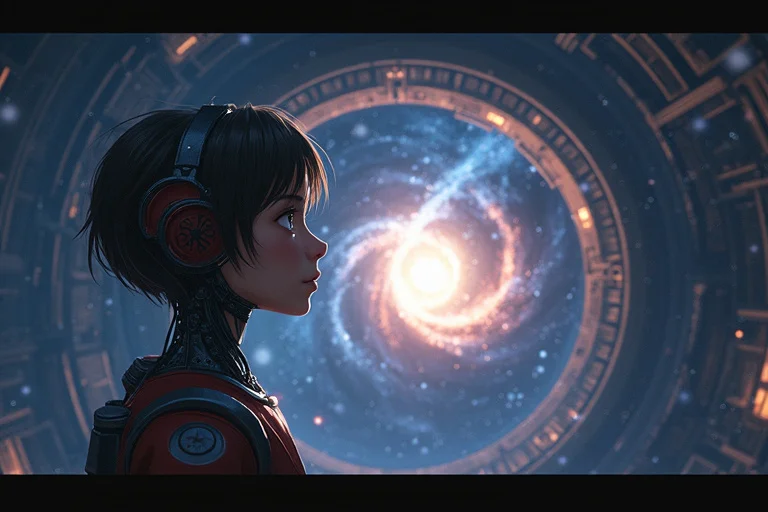第一章 硝子の街とノイズ
舌の上で、泥水が転がった。
「……味がない」
キリアン・ゼロは、カフェのテラス席で眉を寄せた。
最高級の豆を使用したとされるコーヒーは、完璧な温度と最適なカフェイン濃度で抽出されている。
だが、そこには苦味も、酸味も、深みもない。
ただの温かいデータだ。
通りを行き交う人々を見る。
誰も彼もが、黄金比率で整えられた穏やかな微笑みを貼り付けている。
感情抑制システム『ESS』の恩恵だ。
怒りも、悲しみも、絶望もない。
凪いだ湖面のような、死んだ平和。
キリアンは、自身の胸の奥が乾いた音を立てて軋むのを感じた。
飢えだ。
この無菌室のような世界で、彼は猛烈に「不純物」を欲していた。
その時だ。
「いや……! 離して! あの子は死んだのよ!」
突如、通りの向こうで女の叫び声が上がった。
平和な空気が一瞬にして凍りつく。
治安維持ドローンが三機、無音で滑空し、女を取り囲む。
『警告。ドーパミンレベル異常。鎮静フェーズへ移行します』
青白い光が女を包む。
彼女の表情から、瞬時に「激情」が抜け落ちた。
数秒後、彼女はまた、黄金比の微笑みを浮かべて立ち去っていく。
周囲の人々は、何事もなかったかのように歩き出す。
だが、キリアンだけは違った。
ドクン。
左手首の鈍色のバンド――『エモーショナル・サイファースキャナー』が、皮膚を焦がすほどの熱を発した。
女が立っていた場所に、赤い残像が揺らめいている。
システムが消去しきれなかった、生の感情の残滓。
悲嘆。喪失。愛。
キリアンの喉が鳴った。
痛いほどの渇望。
「……いただきだ」
彼は周囲の目を盗み、スキャナーのダイヤルを乱暴に回す。
針が皮膚に食い込む。
血が滲む感覚だけが、彼に生きている実感をくれる。
視界がノイズに侵食される。
女が落とした「感情の欠片」が、キリアンの視神経に直接突き刺さる。
『あの子を返して』
脳内で響く、誰かの慟哭。
キリアンは震える手でコーヒーカップを握りつぶしそうになった。
苦い。
とてつもなく苦く、そして甘美な、絶望の味だ。
「……キリアン。聞こえるか」
骨伝導インカムから、押し殺した声が響く。
裏社会の情報屋だ。
「今、お前が見た『ノイズ』。そいつの発生源を突き止めたぞ」
「ああ、分かっている」
キリアンは額に浮かんだ脂汗を拭うこともせず、赤い残像が伸びる先――旧市街の暗がりを睨みつけた。
「俺の飢えを満たしてくれる『特大の獲物』なんだろう?」
「そんな生易しいもんじゃない。あれは、この完璧な世界が切り捨てた『最初の後悔』だ」
キリアンは席を立った。
足取りは軽い。
地獄への片道切符を掴んだ男の、愉悦に満ちた足取りだった。
第二章 ゴースト・イン・ザ・メロディ
旧市街。
そこは、都市の記憶喪失領域だ。
崩れかけたコンクリートの壁。
錆びついた鉄骨。
ESSのシグナルさえ届かないこの場所は、都市の「墓場」だった。
キリアンは、廃墟と化したコンサートホールの重い扉をこじ開けた。
空気が、変わる。
埃の匂いではない。
もっと濃密な、何百年も凝縮された情念の澱み。
スキャナーが、かつてないほどの熱量で警告音を鳴らしている。
腕が焼けるようだ。
だが、キリアンはその痛みを飲み込み、さらに感度を上げた。
「……ここか」
舞台の中央。
指揮台があった場所に、それは「居た」。
目には見えない。
だが、データの奔流として、そこに渦巻いている。
『――寒い』
『――痛い』
『――忘れたくない』
無数の文字列が、ホログラムのように空中に噴き出した。
キリアンの網膜に、雪崩のような情報が押し寄せる。
これらはすべて、ESSが稼働した日に削除された、人類の「不要な感情」だ。
愛する者を失った悲しみ。
届かなかった願い。
行き場をなくした怒り。
それらが圧縮され、腐敗し、巨大な呪いとなってシステムを蝕んでいる。
キリアンは、スキャナーの接続プラグを引き抜いた。
狙うは、この嵐の中心。
全てのノイズの元凶となっている、たった一つの「核」。
「食わせてもらうぞ」
彼はプラグを、自身の首筋にあるポートへ直接ねじ込んだ。
ガッ、と視界が揺れる。
物理的な衝撃ではない。
魂が裏返るような感覚。
ダイブ開始。
視界が弾ける。
色彩の洪水。
逆流する重力。
(赤)
血の色。
(青)
涙の温度。
(黒)
絶望の深淵。
ノイズが、キリアンの自我を削り取っていく。
指先の感覚が消える。
心臓の鼓動が、他人のリズムに上書きされる。
『エラー。同期率300%突破。脳死リスクが高まっています』
警告音が遠くで聞こえる。
うるさい。
もっとだ。
もっと深く。
キリアンは意識の底へ、錘のように沈んでいく。
そこで彼は見た。
データの海の底。
たった一人で膝を抱え、震えている「影」を。
第三章 最初の後悔
「……う、ぐ……」
キリアンの奥歯が、ギリギリと音を立てた。
もはや自分の肉体がどこにあるのかも分からない。
五感のすべてが、過去の映像にジャックされている。
そこは、無機質な実験室だった。
窓の外には、燃え盛る街が見える。
100年前。
「最終戦争」の末期。
部屋の中央に、一人の女性科学者がいた。
彼女は、ボロボロのテディベアを胸に抱きしめている。
クマのぬいぐるみは、煤と血で汚れていた。
彼女の視線の先には、一台の巨大な端末。
モニターには『感情抑制システム(ESS)最終承認』の文字が点滅している。
キリアンは、彼女の視覚を通して「それ」を見た。
床に散らばる写真。
瓦礫の下から覗く、小さな手。
動かない恋人。
飢えに苦しみ、互いを殺し合う人々の群れ。
(悲しみが、人を殺すなら)
彼女の思考が、キリアンの脳に直接流れ込んでくる。
言葉ではない。
焼けつくような概念として。
(憎しみが、世界を焼くなら)
彼女は震える指を、エンターキーの上に置いた。
その指先が、鉛のように重い。
これを押せば、戦争は終わる。
人は争わなくなる。
だが同時に、あの瓦礫の下で握りしめた「ぬくもり」も、二度と思い出せなくなる。
愛おしい人が浮かべた最後の笑顔も、ただの電気信号に変わる。
(……ごめんなさい)
彼女の目から、一雫の涙がこぼれ落ちた。
その涙が頬を伝う冷たさを、キリアンは我が事のように感じた。
彼女は、子供の写真を裏返した。
見たくなかったのではない。
これ以上見つめていたら、決心が揺らぐからだ。
カチリ。
乾いた音が、実験室に響いた。
彼女はキーを押した。
人類を救うために、自身の心を殺したのだ。
その瞬間に生まれた、強烈な自己否定。
『こんな救済は間違っている』という叫び。
それこそが、100年間世界を蝕み続けたノイズの正体だった。
キリアンは、幻影の中の彼女へと手を伸ばした。
スキャナーが限界を超え、左腕の肉が炭化していく臭いがする。
血管が悲鳴を上げ、眼球から血が溢れる。
「あんたの痛みは……」
キリアンは、呼吸すら忘れて、その莫大なデータを飲み込んだ。
彼女が背負った、全人類分の悲しみ。
その重質量が、キリアンの神経回路を焼き切っていく。
「あんた一人で抱えるには、重すぎる……!」
逃げない。
遮断しない。
すべての絶望を、俺によこせ。
バチバチバチッ!
脳髄が沸騰するような感覚。
脊髄を雷が駆け抜ける。
言葉にならない咆哮が、喉の奥で詰まる。
歯が砕けた。
口の中に広がる鉄錆の味。
それでも彼は、その「苦味」を飲み干した。
第四章 選択の残響
静寂。
キリアンは、冷たい床の上で目を覚ました。
全身が泥のように重い。
左腕の感覚がない。
見ると、スキャナーは砕け散り、黒い煤となって床にへばりついていた。
「……はぁ、はぁ、……っ」
肺が酸素を求めて喘ぐ。
生きている。
ボロボロだが、確かに心臓が動いている。
キリアンはよろめきながら立ち上がり、ホールの外へ出た。
夜が明けていた。
だが、それはいつもの「計算された美しい朝焼け」ではなかった。
空はどんよりと曇り、不格好な雨雲が垂れ込めている。
遠くのビルに映し出されていたESSの管理画面はブラックアウトし、街中に不協和なサイレンが鳴り響いていた。
通りを見下ろす。
人々が、立ち止まっていた。
ある男は、道端の野良猫を見て、理由もなく涙を流していた。
ある女は、隣の男に怒鳴り散らし、次の瞬間には抱き合っていた。
子供たちが水たまりを蹴り上げ、服を汚して大笑いしている。
制御不能。
混沌。
ノイズまみれの世界。
キリアンは壁に背を預け、ズルズルと座り込んだ。
もう、他人の感情が流れ込んでくることはない。
あの科学者の後悔と共に、キリアンの異能も焼き尽くされたのだ。
空から、ポツリと雨が落ちてきた。
冷たい。
濡れれば風邪を引くし、服も汚れる。
不快で、面倒な雨だ。
キリアンは、雨粒が頬を伝う感触を味わった。
「……最悪な気分だ」
彼は口の端を吊り上げた。
砕けた奥歯がズキズキと痛む。
失った左腕が幻肢痛を訴える。
孤独が、寒さが、不安が、一斉に襲いかかってくる。
だが、その胸の奥にあった「飢え」は、もうない。
キリアンは曇り空を見上げた。
そこには、修正不可能な、傷だらけで美しい明日が広がっていた。