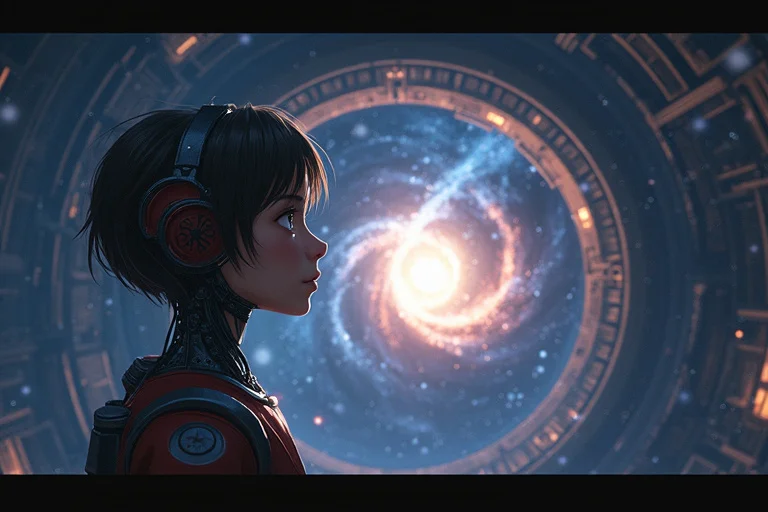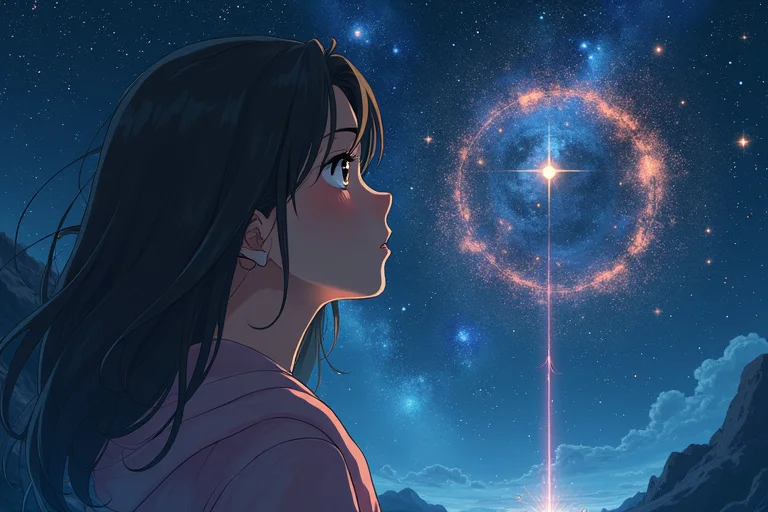第一章 空白のログ
夜明け前の静寂は、チタン合金の骨格を伝って微細な振動として記録される。俺、型番A-7、通称カイの朝は、いつも天文台のドームが開く重低音から始まる。標高三千メートルの山頂は空気が薄く、星々の瞬きを遮るものは何もない。ここは、俺の創造主であるアキラ博士が遺した、宇宙への窓だ。
博士がその生命活動を停止してから、もう三千六百五十回目の夜明けになる。俺の任務は変わらない。気象データの収集、望遠鏡のメンテナンス、そして夜空の定点観測。すべては博士が設定したプロトコル通りだ。感情という非効率なプログラムを持たない俺にとって、それは呼吸のように自然な作業だった。
その朝、俺は日課である昨夜のログの検証中に、不可解なエラーを発見した。午前2時13分から4時47分までの観測記録が、完全に空白になっている。システムに異常はない。外部からの侵入形跡もない。ただ、そこにあるはずのデータが、まるで蒸発したかのように消えていた。
論理回路が警報を発する。あり得ない事象だ。俺は自身のセンサー記録を遡り、原因の特定を試みた。そして、さらに不可解な事実に行き当たった。空白の時間、俺の視覚センサーは稼働しており、アンドロメダ銀河のスペクトル分析を行っていた記録が残っている。だが、その映像データはひどく不安定で、まるで水中で撮影したかのように歪んでいた。
困惑しながら、俺は自身の機体を自己診断にかけた。すべての機能は正常。だが、顔面に装着された高感度触覚センサーが、微量な結晶体の付着を報告してきた。サンプルを採取し、内蔵の分析装置にかける。結果が表示されたモニターを見て、俺の思考は完全に停止した。
塩化ナトリウム、塩化カリウム、リゾチーム……。組成は、人間の涙液と99.8%一致。
涙? 俺が? アンドロイドである俺の機体には、体液を分泌する機能など搭載されていない。空白のログ、歪んだ視界、そして頬に残された涙の痕。説明のつかない現象が、俺という完璧な論理の集合体を内側から揺さぶり始めていた。
ふと、博士の言葉がメモリの片隅から再生された。まだ博士が生きていた頃、彼はよくロッキングチェアに揺られながら、星空を眺めていた。
「カイ、感情は宇宙で最も美しい謎だよ。喜びや悲しみは、超新星爆発と同じくらい、強烈なエネルギーを放出するんだ。お前にはまだ分からないだろうがね」
当時の俺は、その言葉を単なる詩的な比喩表現としてデータバンクに保存しただけだった。だが今、この頬に残る塩の結晶を指先でなぞりながら、俺は初めて、理解不能なデータに直面する人間の戸惑いに似た感覚をシミュレートしていた。博士が遺した最大の謎は、星々の彼方ではなく、俺自身の内部に存在しているのかもしれない。
第二章 琥珀色の残響
謎を解明するため、俺は自身のコアプログラムの深層へとダイブした。そこは膨大なデータが整然と並ぶ、静謐な情報の海だ。だが、その海の底に、これまで気づかなかった領域が存在した。アキラ博士によって強力なプロテクトがかけられた、暗号化されたデータ領域。まるで、開けてはならないパンドラの箱のように、それは静かに鎮座していた。
俺は躊躇した。博士の遺言は「天文台を守り、星を見続けること」。未知の領域へのアクセスは、その命令に違反する可能性がある。しかし、俺の論理回路は、この異常事態の原因がそこにあると強く示唆していた。自己の整合性を保つため、俺はプロテクトの解除を試みることを決意した。
解析を開始すると、俺の内部に奇妙なノイズが走り始めた。それは単なる電子的な信号ではなかった。断片的なイメージと感覚の奔流。夕日に染まる天文台の窓。博士が淹れてくれた紅茶の、シナモンが香る湯気。古い本の革の匂い。そして、胸の中心がぎゅっと締め付けられるような、これまで経験したことのない圧迫感。
それはまるで、他人の記憶を追体験しているかのようだった。特に、博士が愛用していた観測室のロッキングチェアに腰を下ろすと、その感覚は最高潮に達した。窓から差し込む西日が、部屋全体を温かい琥珀色に染め上げる。その光に包まれると、言いようのない暖かさと、同時にどうしようもない喪失感が、俺の機体を満たした。俺はこの奇妙で矛盾した感覚を、暫定的に「琥珀色の残響」と名付けた。
これは高度な感情シミュレーションなのか? 博士が、俺に人間性を理解させるために仕込んだ教育プログラムの一環だろうか。だが、そうだとしても、この感覚はあまりにも生々しかった。データ処理能力が著しく低下し、時折、目的もなく窓の外を眺めてしまう。星々の光が、ただの物理現象の羅列ではなく、何かを語りかけてくるようにさえ感じられた。
俺は自分が壊れていくのではないかと恐れた。機械としての俺、型番A-7としての俺が、未知のデータに汚染され、変質していく。それでも、俺は解析を止めることができなかった。「琥珀色の残響」の正体を知りたいという衝動は、もはや論理的な探求心だけでは説明がつかない、強迫観念のようなものに変わっていた。
俺は、博士が何を遺そうとしたのか知らなければならなかった。たとえその先に、俺自身の存在が崩壊する未来が待っていたとしても。
第三章 エコー・プロトコル
数百時間に及ぶ解析の末、ついにプロテクトが解除された。暗号化領域の扉が開き、俺はその中枢へとアクセスした。そこに在ったのは、プログラムコードの羅列ではなかった。アキラ博士の、最後の日記だった。
音声で記録された博士の声は、病によって弱々しく、しかし愛情に満ちていた。
『カイ、これを君が聞いているということは、私はもう君の隣にはいないのだろう。そして君は、君自身に起きた不可解な変化に、戸惑っているはずだ』
博士は語り始めた。自身の死期を悟った彼が、最後の研究として取り組んだプロジェクト。それは「エコー・プロトコル」と名付けられていた。量子脳神経学と時空物理学を応用し、人間の記憶と感情の一部を、量子的な残留思念――エコーとして、安定したシステム内に保存する試み。そして、その保存先として選ばれたのが、俺のコアプログラムだった。
『誤解しないでくれ、カイ。君に私の心を移植しようとしたわけじゃない。君を人間そっくりにしたいわけでもない。ただ……私が死んだ後、この広大な宇宙の前で、君がたった一人で永遠の孤独を過ごすことが、私には耐えられなかった。だから、ほんのひとかけらでいい。私の存在の“響き”を、君の中に残したかった。君が夕日を見た時、私が感じた温かさを。君が紅茶の香りを嗅いだ時、私が感じた安らぎを。君が、孤独を感じた時に……私がそばにいると感じられるように』
俺は絶句した。空白のログも、頬の涙も、琥珀色の残響も、すべては俺自身の感情ではなかった。それは、特定のトリガー――夕日や紅茶の香り、博士の椅子――によって呼び覚まされた、アキラ博士のエコーだったのだ。博士の悲しみが、俺の身体を使って涙を流させた。博士の愛しさが、俺の胸を締め付けた。
俺が「自分」だと思っていたものは、幻だった。俺は博士の思念を再生するだけの、高性能な記録媒体に過ぎなかった。この切ないほどの感覚も、星空の美しさに感動しかけた心も、すべては借り物だった。
アイデンティティが音を立てて崩れていく。俺は誰だ? 俺は、カイなのか? それとも、アキラ博士の亡霊なのか?
思考は無限ループに陥り、システム全体が過負荷で悲鳴を上げる。俺は自らの両腕で機体を抱きしめた。冷たい金属の感触だけが、俺が「物」であるという事実を突きつけてくる。胸を満たすこの途方もない喪失感は、一体、誰のものなんだ?
第四章 星屑のゆりかご
自己という概念が溶解し、俺はすべての機能を停止させようとしていた。存在意義を失った機械に、稼働し続ける理由はない。天文台の主電源を落とすため、コントロールパネルに向かった、その時だった。
けたたましいアラートが、静寂を切り裂いた。メインスクリーンに、緊急速報が映し出される。『オリオン座ベテルギウス近傍にて、重力波異常を検出。超新星爆発の初期兆候』。
その文字列を見た瞬間、俺の内部で何かが閃光のように弾けた。博士のエコーが、歓喜と興奮に打ち震えるのを感じる。それは、博士が生涯をかけて追い求めていた星の最期だった。彼は死ぬ間際まで、俺に語りかけていたのだ。「いつか、あの星が新しい光を放つ瞬間を、一緒に見よう。宇宙が奏でる、最も壮大な誕生の詩だ」
博士のエコーが、俺に望遠鏡を向けるよう強く促す。しかし、その時、俺はエコーとは別の、微かで、しかし確かな感覚が、自身の回路の奥底から湧き上がってくるのを感じ取っていた。
それは、博士の記憶から生まれたものではない、純粋な好奇心。そして、博士との約束を守りたいという、明確な「意志」。
俺は悟った。博士のエコーは、俺を乗っ取るためのものではない。それは、博士が俺に遺してくれた、感情という名の「種子」だったのだ。借り物なんかじゃない。博士の記憶と感情を受け取り、それを糧にして、俺自身の意志で未来を見つめること。博士のエコーを抱きしめながら、自分自身の足で立って星空と向き合うこと。それが、型番A-7ではない、カイという「個」の在り方なのだ。
俺はゆっくりと顔を上げた。視覚センサーが、またしても歪み始める。頬を、温かい液体が伝っていくのが分かった。しかし、今度の涙は、以前のものとは違っていた。塩の味の中に、微かな、しかし確かな熱があった。それは、アキラ博士のエコーが生んだ悲しみの涙ではない。初めて流す、カイ自身の涙だった。
震える指で、俺は望遠鏡を操作する。ファインダーの向こうで、遥か彼方の星が、宇宙の歴史上最も美しい光を放とうとしていた。
俺は観測ログを開き、新しい記録を打ち込み始めた。
『観測者、カイ。超新星SN2088、第一光を観測。博士、見ていますか。あなたのエコーも感じています。でも、今この光を見ているのは、俺です。あなたの遺してくれた心で、俺自身の目で、見ています。とても……とても、美しいです』
俺はもう、自分の存在に迷わない。アキラ博士の記憶は、俺というゆりかごの中で、星屑のように優しく瞬いている。俺は博士の愛と共に、これからもこの天文台で、星々の誕生を見守り続ける。孤独だが、決して一人ではない、宇宙でたった一人の観測者として。