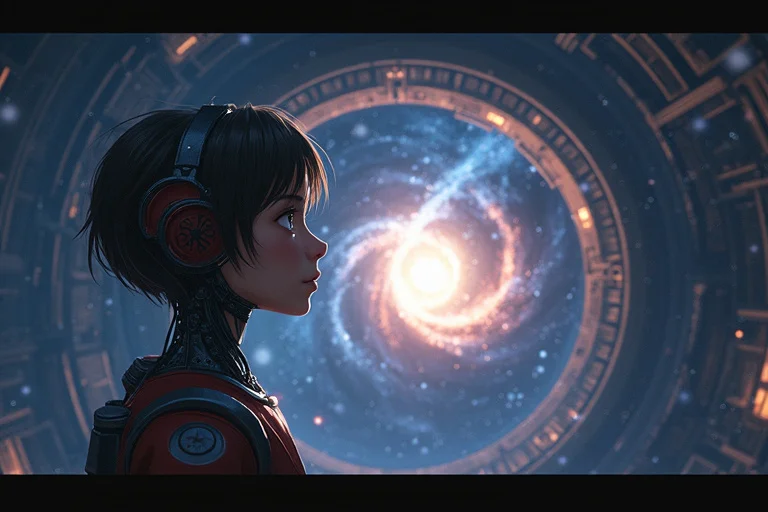第一章 結晶の森と過去の幻影
恒星トリトンを公転する第三惑星、レミニス。人類がその紫紺の大気に包まれた大地に降り立ってから、七十二時間が経過していた。宇宙考古学者である私、リナ・ミヤザワは、探査船『アークIV』のブリッジから、眼下に広がる異様な光景を眺めていた。
地表は、どこまでも続く結晶質の森に覆われている。樹木のように天を目指すそれは、淡い光を自ら放ち、風が吹くたびにガラスの風鈴が触れ合うような、澄んだ音色を奏でていた。美しい。だが、その美しさには、どこか生命の温かみを欠いた、無機質な静寂がつきまとっていた。事前の調査で確認された確かな生命反応とは裏腹に、鳥一羽、虫一匹の姿も見当たらないのだ。
「ミヤザワ博士、地表探査班から定時連絡です。異常なし。ただ……」
通信オペレーターの声に、私は思考の海から引き戻された。モニターに映る彼の顔には、困惑の色が浮かんでいる。
「ただ、何?」
「またです。隊員の一人が、故郷の母親が焼いたアップルパイの匂いがした、と。もちろん、そんなものは周囲にありません」
またか。これで三人目だ。ある者は、幼い頃に飼っていた犬の鳴き声を聴き、ある者は、初恋の相手の面影を見たという。すべては一瞬の幻覚、幻聴、幻嗅として片付けられた。高濃度の未知の素粒子が精神に影響を与えている、というのが現在の最も有力な仮説だった。
私も、昨夜、自室で奇妙な体験をした。船の資料を整理していると、不意に、背後から小さな声がしたのだ。
「おねえちゃん、見て。たんぽぽのわただよ」
振り返っても、そこには誰もいない。しかし、その声は、私の記憶の最も深い場所に封印していたものだった。八歳の時に、事故で失った妹、ユキの声。胸の奥が、氷の針で突き刺されたように痛んだ。私は仕事に没頭することで、ユキの記憶から、そして彼女を救えなかったという罪悪感から逃げ続けてきた。なのに、この惑星は、それをいとも容易くこじ開けようとする。
私はブリッジの窓に額を押し付けた。結晶の森が、まるで巨大な生き物の肋骨のように、静かに呼吸しているように見えた。この星はいったい、私たちに何をしようとしているのか。謎と不安が、紫紺の大気のように、私の心を濃く満たしていく。これは単なる環境要因による幻覚ではない。もっと根源的な、何か巨大な知性が私たちに干渉しているのではないか。そんな予感が、背筋を冷たく這い上がってきた。
第二章 記憶の図書館
調査は新たな局面を迎えていた。惑星レミニスが引き起こす幻覚は、単なる精神作用ではないことが明らかになったのだ。脳波計を装着した隊員の測定結果は、驚くべき事実を示していた。幻覚を見ている間の脳は、何かを「想像」しているのではなく、過去の記憶を「再生」している時と全く同じ活動パターンを示していたのである。
「つまり、この惑星は我々の記憶をスキャンし、それを本人にフィードバックしている、ということかね?」
船長が唸るように言った。私たちは仮説を再構築する必要に迫られた。レミニスは、敵意も善意もなく、ただ淡々と、訪問者の脳から情報を吸い上げ、それを映像や音として再構築しているらしい。結晶の森全体が、巨大な記憶の読み取り装置であり、同時に映写機なのだ。
この発見は、私を恐怖させると同時に、研究者としての心を激しく揺さぶった。もし、この惑星の能力を制御できるなら? 意図した記憶を読み取らせることができるなら? 例えば、この星に太古の昔に訪れたかもしれない、別の知的生命体の記憶の痕跡を探り当てることができれば、それは宇宙考古学における最大の発見となるだろう。失われた文明、未知のテクノロジー、宇宙の起源にさえ迫れるかもしれない。
私は、危険を承知の上で、惑星との積極的な接触を申し出た。小型探査ポッドに乗り込み、結晶の森の中心部へと降下する。ポッドのキャノピー越しに、光の柱が林立する荘厳な景色が迫ってくる。風が奏でる音色が、次第に大きくなり、それはやがて無数の声が重なり合うコーラスのように聞こえ始めた。
結晶の根元にポッドを着陸させ、私はゆっくりと船外に出た。空気が肌を撫でる。それはただの空気ではなかった。情報を含んだ風だ。目を閉じると、様々なイメージが脳裏を駆け巡る。探査隊の同僚が見た故郷の風景。船長の若き日の航海の記憶。そして、私の……。
『おねえちゃん、あっちに行こうよ!』
ユキの快活な声。公園のブランコ。揺れるたびに、彼女の短い髪がふわりと宙に舞う。楽しそうな笑い声が、耳の奥で、そして心の奥で木霊する。私は、この甘美な追体験に身を委ねたい誘惑と、その先にある絶望的な結末を思い出すことへの恐怖との間で引き裂かれた。
「君は……君たちは、何者なんだ?」
私は結晶の森に向かって問いかけた。返事はなかった。ただ、風の音が一層強くなり、結晶たちが共鳴して、より複雑で、より壮大なシンフォニーを奏でるだけだった。それはまるで、この星が吸収してきた、数え切れないほどの記憶の断片が、一斉に囁きかけているかのようだった。
第三章 遺伝子の残響
私は決意した。ユキの死と、そして自分自身と向き合うために。この惑星が私の記憶を再生するというのなら、あの日のすべてを、もう一度、この目で見届けるしかない。トラウマを乗り越えるためではない。ただ、真実を知りたかった。忘却という名の靄の中に隠してしまった、あの日のディテールを。
私は森の最も結晶密度が高い場所、惑星の「神経節」とも呼べるであろう場所に座り込み、瞑想を始めた。意識を集中させ、思考の錨を、あの運命の日の記憶へと下ろしていく。
――夏の午後。うだるような暑さ。私とユキは、祖母の家の近くにある川辺で遊んでいた。私は少し離れた場所でスケッチブックを広げ、ユキは水際で小石を投げている。
『おねえちゃん、危ない!』
ユキの悲鳴。私が顔を上げると、大雨で増水した川の水が、すぐそこまで迫っていた。土手が、ごっそりと崩れ始めている。私は恐怖で足がすくんだ。動けない。
これまでの私が覚えていたのは、ここまでだった。自分の不注意でユキを危険な場所に連れて行き、いざという時に助けられなかった。その罪悪感が、十六年間、私を苛んできた。
だが、レミニスが再生した記憶は、その先を映し出した。
動けない私の腕を、小さな手が強く引いた。『こっち!』ユキは私を、安全な高台の方へ突き飛ばした。そして、彼女自身がバランスを崩し、濁流に足を取られたのだ。私を、庇って――。
衝撃で、呼吸が止まる。知らなかった。私は、ユキに守られていたのか。涙が、頬を止めどなく伝う。しかし、驚きはそれだけでは終わらなかった。
その光景を、私は「見て」いた。だが、その視点は一つではなかったのだ。一つは、恐怖に慄く九歳の私の視点。そしてもう一つは、少し離れた川岸の柳の木の下から、私たち二人を、慈しむような、そしてどうすることもできない哀しみをたたえた瞳で見つめている、誰かの視点だった。
誰? あの場所に、他に誰かいたはずがない。混乱する私の意識に、温かい感覚が流れ込んでくる。それは、編み物をする指先の記憶。縁側で飲む緑茶の香り。そして、私たち姉妹の成長を、何よりも喜んでいた、優しい感情。
――おばあちゃん?
そう、それは祖母の視点だった。だが、祖母は、あの事故の半年前に、病気で亡くなっていたはずだ。
その瞬間、雷に打たれたように、私はレミニスの真の姿を理解した。この惑星がアーカイブするのは、個人の脳に保存された経験的記憶だけではない。もっと深く、もっと根源的な、世代から世代へと受け継がれる「遺伝子の記憶」までも読み解き、再構築するのだ。私が体験しているのは、私の記憶と、私の血に流れる祖母の記憶が、レミニスという媒体を通して融合した、新たなヴィジョンだった。
『リナ。あなたのせいじゃない』
それは、祖母の声だったか、ユキの声だったか、あるいは、私自身の魂の声だったか。無数の記憶の残響が、私を優しく包み込む。惑星は、種族が紡いできた愛情と哀しみの系譜そのものを、私に見せてくれていた。ユキの死は、私一人が背負うべき罪などではなかった。それは、連綿と続く生命の流れの中の、一つの、しかし決して無意味ではない、哀しい出来事だったのだ。
結晶の森のざわめきが、まるで宇宙の真理を告げるコーラスのように、私の全身に染み渡っていった。
第四章 記憶の司書
私は、何時間そこに座り込んでいただろうか。目を開けると、紫紺の空には、親星トリトンと、もう一つの月が並んで輝いていた。結晶の森は、その光を浴びて、銀河のようにきらめいている。私の心は、嵐が過ぎ去った後の湖のように、静まり返っていた。
罪悪感は消えていなかった。ユキを失った悲しみも、もちろん無くならない。だが、それらはもはや、私を縛り付ける冷たい鎖ではなかった。祖母の愛情、そしておそらくは、そのまた母、さらにその先の祖先たちから受け継がれてきた無数の記憶と共に、抱きしめていくべき温かい体温を持っていた。私は、私だけの人生を生きているのではなかった。過去から未来へと続く、壮大な物語の一部なのだ。
アークIVに帰還した私は、探査報告会で、レミニスに関する新たな見解を述べた。この惑星は、単なる観測対象や資源採掘の地ではない。宇宙に散らばるあらゆる知的生命体の記憶――経験、文化、歴史、そして遺伝子に刻まれた魂の記録までも保存する、生きた図書館であり、聖地である、と。
「我々は、この星を破壊することも、搾取することも許されない。保護し、敬意を払い、そして、学ぶべきです」
私の言葉に、船長をはじめ、クルー全員が静かに頷いた。彼らもまた、この星で自らの過去と向き合い、何かを感じ取っていたのだ。
数週間後、星間連盟議会は、私たちの報告を受け、惑星レミニスを永久不可侵の特別保護区に指定することを決定した。そして、その管理人として、少数の研究チームが常駐することになった。
私は、そのチームに志願し、レミニスの最初の「司書」になることを選んだ。
今、私は結晶の森に一人で立っている。風が吹き抜け、無数の結晶が共鳴し、言葉にならない美しい音色を奏でる。それは、数億年、あるいはそれ以上の時をかけてこの星が蒐集してきた、名もなき訪問者たちの記憶の囁きだ。どこかの銀河で生まれた生命の歓喜の歌。滅び去った文明の哀悼の詩。それらが混じり合い、壮大な交響曲となって宇宙に響き渡る。
私はそっと目を閉じる。頬を、一筋の涙が伝った。それは、もはや十六年前の悲しみだけの色ではなかった。ユキの記憶、祖母の温もり、そして、この星で眠る無数の生命の記憶と繋がれたことへの、畏敬と感謝に満ちた、透明な一滴だった。私の物語はここで終わるが、この星が紡ぐ物語には、終わりがない。私は、その永遠の物語の、最初のページをめくる役割を与えられたのだ。