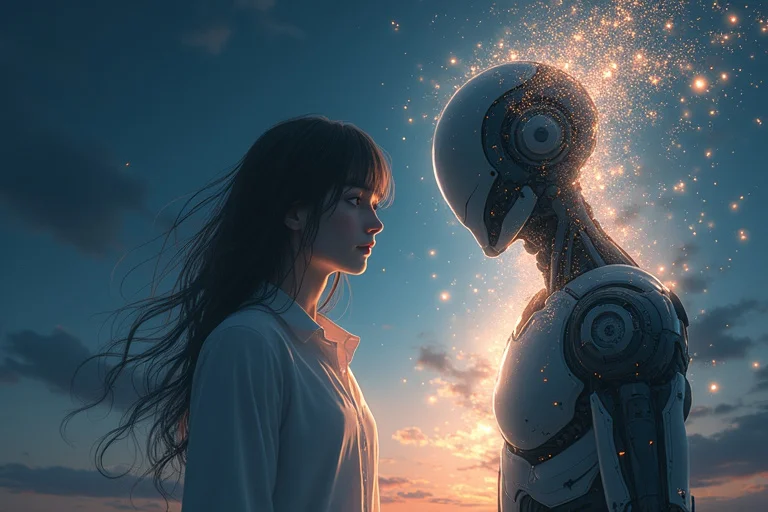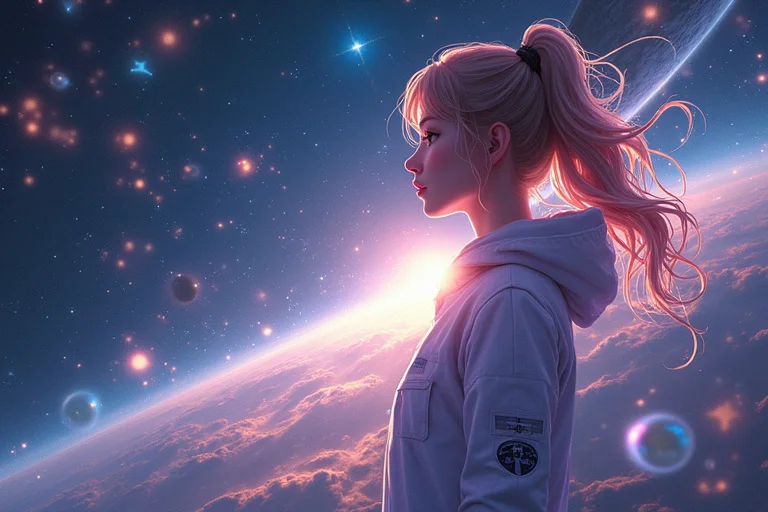第一章 灰色の取引
カイトの胸から、それがゆっくりと滲み出てくる。ずしりと重く、鉛色の光を鈍く放つ、歪な結晶。今朝生成された、彼の「絶望」だ。指先で触れると、冬の墓石のような冷たさが伝わってくる。彼はため息一つ漏らさず、その結晶を遮光ポーチに滑り込ませた。感情が商品になったこの世界で、カイトは一流の「エモーショナル・トレーダー」だった。もっとも、売っているのは常に自分自身の心の一部だったが。
煌びやかなネオンが降り注ぐ中央市場は、感情の坩堝だった。威勢のいい競売人の声が反響し、ディスプレイには様々な感情結晶(エモーショナル・クリスタル)の価格が目まぐるしく変動している。「純度98%の『歓喜』!」「極上の『郷愁』詰め合わせはいかが!」そんな喧騒の中、カイトは無表情にブローカーのカウンターへ向かう。
「今日の品はこれだ」
ポーチから取り出した鉛色の結晶を差し出すと、ブローカーは鑑定用のレンズを目に当て、舌なめずりをした。
「ほう、これは見事な『絶望』だ。不純物がない。近頃、これほど質のいいネガティブ感情は珍しい。高値がつくぞ」
取引はすぐに成立した。電子マネーの入金通知が網膜ディスプレイに表示される。その金で、彼は市場の隅にある店へ向かった。そこでは、合成されたり、誰かから買い叩かれたりした安価なポジティブ感情が売られている。彼が選んだのは、淡いピンク色に輝く小さな『安らぎ』の結晶と、太陽のかけらのような形をした『ささやかな喜び』の結晶だった。自分の魂を削って得た金で、妹のための借り物の幸福を買う。それがカイトの日常だった。
自宅アパートに戻ると、生命維持装置のかすかな電子音だけが彼を迎えた。部屋の奥のベッドで、妹のミナが静かに眠っている。数年前から、彼女は原因不明の「無感情症(アパシー・シンドローム)」を患っていた。自力で感情を生成できず、放置すれば精神が崩壊し、やがて死に至るという奇病だ。
カイトはミナのそばに座り、買ってきた『喜び』の結晶を彼女の口元へ運んだ。結晶は淡い光とともに溶け、ミナの体内に吸収されていく。やがて、人形のように無表情だった彼女の口元に、ほんのわずかな笑みが浮かんだ。
「…おにいちゃん」
か細い声。その一言を聞くためだけに、カイトは心を売り続けてきた。だが、借り物の感情で微笑む妹の顔を見るたび、彼の心はさらに冷たく、重くなっていくのだった。かつて自分の中にもあったはずの温かい感情。ミナと笑い合った日々の記憶は、色褪せた写真のように、もはや何の感触も伴わなかった。彼は空っぽの器だった。妹の命を繋ぎとめるため、自ら空になることを選んだ、ただの器だ。
第二章 純粋なる結晶を求めて
その日、ミナは発作を起こした。買ってきた『安らぎ』の結晶を摂取した直後、激しく痙攣し、その瞳から光が消えかけた。駆けつけた医師は、カイトに非情な現実を告げた。
「既製品のクリスタルに対する耐性ができてしまったようです。妹さんの精神を繋ぎとめるには、もはや純粋で、強力なポジティブ感情の結晶しかありません。例えば…誰にも汚されていない、本物の『愛情』のような」
『愛情』。市場では伝説として語られる、最高級の感情。それは、打算や欲望の混じらない、純粋な想いからしか生まれない。生成できる人間はごくわずかで、もし市場に出れば、都市ひとつが買えるほどの天文学的な価格がつくという。
カイトは自分の胸に手を当てた。この心のどこかに、まだミナへの『愛情』は残っているだろうか。彼は自室にこもり、意識を集中させた。ミナとの幼い日々の記憶を、必死にかき集める。公園で手を繋いだ温もり、誕生日を祝った時の笑顔、怪我をした自分を泣きながら介抱してくれた優しさ。
しかし、胸から生まれ出たのは、濁った紫色の小さな結晶だけだった。それは『愛情』というにはあまりに多くのものが混じりすぎていた。『後悔』『自己憐憫』『焦燥』…。長年の取引で彼の心は磨耗し、汚染されていた。純粋な感情など、どこにも残ってはいなかった。
絶望が、再び鉛色の結晶となって彼の胸を満たそうとする。だが、彼はそれを押しとどめた。諦めるわけにはいかない。彼はあらゆる伝手を頼り、情報をかき集めた。非合法な感情ブローカー、闇市場のディーラー、果ては感情を人工的に精製しようと試みる狂科学者の噂まで。
数日後、カイトは裏社会の情報屋から、あるデータチップを手に入れた。「無感情症」に関する極秘の研究記録だという。莫大な金を払い、震える手でチップを起動する。そこに記されていたのは、彼の想像を絶する、残酷な真実だった。
第三章 借り物の心臓
データには、一件の事故記録が添付されていた。十年前、カイトが瀕死の重傷を負った交通事故。彼はその事故で心臓に回復不能なダメージを負い、生命の危機に瀕した。当時の医療技術では、彼の命を救うことは不可能だったはずだ。
しかし、記録は続いていた。担当医は、当時まだ臨床試験段階だった禁断の技術に手を出した。『感情転移(エモーショナル・トランスプラント)』。それは、ある人間の感情生成能力の全てを、別の人間に移植する技術。ドナーは感情を永久に失う代わりに、レシピエントは生き永らえることができる。
ドナーの名は、ミナ。
彼女は、兄を救うため、自らの「心」を差し出したのだ。
カイトは呼吸を忘れた。世界から音が消え、網膜に映る文字だけが、恐ろしい意味を持って彼の脳を焼き尽くしていく。
ミナの「無感情症」は病気ではなかった。
カイトを救うために、彼女が自ら払った犠牲の代償だったのだ。
では、今まで自分が感じてきたミナへの『愛情』は? 彼女を救いたいと願うこの強い想いは? それもすべて、元はミナのものだったというのか?
自分が妹のために心を切り売りしてきたと思っていた。英雄的な自己犠牲だと、心のどこかで自惚れていた。だが、違った。自分はただ、妹から与えられた心を切り売りして生きてきただけだった。妹の犠牲の上に胡坐をかき、その温もりを食い潰してきた寄生虫に過ぎなかった。
「あ…ああ…っ」
声にならない嗚咽が漏れた。その瞬間、彼の胸が灼けるように熱くなった。これまで感じたことのない、強烈な感情の奔流が、干上がった心に流れ込んでくる。それは、自分の愚かさへの激しい『後悔』。ミナの底知れない自己犠牲への『感謝』。そして、それらすべてを包み込む、身を引き裂くような『愛情』。
彼は知った。感情は売買するものではない。与えられ、受け継がれ、そして育んでいくものだということを。ミナは十年前に、その全てをカイトに託していたのだ。
第四章 二人の夜明け
カイトは市場へ行くのをやめた。もう、外部から借り物の感情を買う必要はない。ミナを救うものは、すでに自分の中にあった。
彼はミナの眠るベッドの傍らに座り、そっとその冷たい手を握った。
「ミナ…ごめん。ずっと、気づかなくて、ごめん」
涙が後から後から溢れ出した。彼は語り続けた。二人で過ごした日々の思い出を、今度はありのままの感情を込めて。楽しかった記憶を語るときは心から笑い、悲しかった記憶を語るときは声を上げて泣いた。
「君が僕にくれた心で、僕は君を救おうとしていた。なんて馬鹿な兄さんだろう。君はずっと、僕の中で生きていてくれたのに」
彼が涙ながらに語りかけるうちに、その胸から、ゆっくりと一つの結晶が生まれ出た。それは、これまでカイトが見たこともないほど、温かく、複雑な光を放っていた。深い海の青、夜明けの赤、そして太陽の黄金色が混ざり合い、万華鏡のようにきらめいている。それは『後悔』と『感謝』と、そして何よりも強い『愛情』が溶け合って生まれた、カイトとミナ、二人の魂の結晶だった。
彼は、その結晶をミナに与えようとはしなかった。代わりに、彼はそれを自分の胸にそっと押し戻した。結晶は彼の体内に溶け、温かい光となって全身を駆け巡る。
「もう、借り物の感情はいらない。君がくれたこの心は、僕が大切にする。これからは、僕が君の心になる。僕が見るものを君も見て、僕が感じることを君も感じるんだ。一緒に、生きていこう」
カイトがそう囁き、ミナの手を強く握りしめた、その時だった。
ミナの指が、ぴくりと動いた。そして、固く閉ざされていた彼女の瞼が、かすかに震える。ゆっくりと開かれた瞳には、ほんのわずかだが、自らの意志による光が宿っているように見えた。
それは完全な回復ではないかもしれない。奇跡が起きたわけでもないだろう。だが、カイトには分かった。取引ではない、本当の心の繋がりが、今、確かに生まれたのだと。
二人は言葉もなく、手を取り合ったまま、窓の外が白んでいくのを見つめていた。都市の喧騒が始まる前の、静かな夜明け。空っぽだったカイトの世界は、ミナから受け継いだ心によって、今、色鮮やかに輝き始めていた。感情の価値とは、その値段ではなく、誰と分かち合うかによって決まるのだ。その答えを胸に、彼は妹と共に、新しい朝を迎えた。