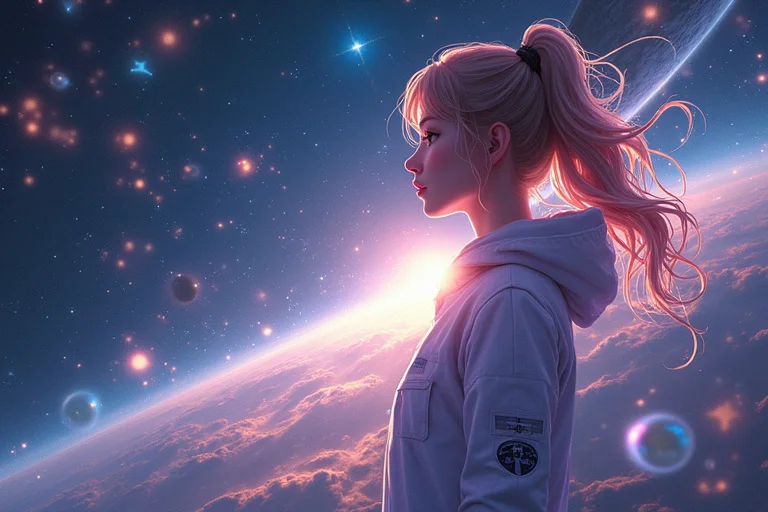第一章 幸福の残滓
都市の光は、決して眠らない。ホログラムの広告が雨のように降り注ぎ、エアカーの静かな軌跡が幾重にも夜空を彩る。僕、カイの仕事場は、そんな煌びやかな都市の片隅にある、静寂に包まれた白い部屋だ。職業は「追憶士(メモリアー)」。最新のニューロ・インターフェースを介して、故人の脳に残された記憶データをダウンロードし、その中から最も幸福だった瞬間を追体験する。そして、その温かな物語を、遺された家族に届けるのが僕の務めだ。
死は悲しいだけのものではない。人が生きた証は、幸福な記憶の連なりとして、美しく結晶化する。それがこの世界の共通認識であり、僕らの仕事の根幹をなす哲学だった。僕はこの仕事に誇りを持っていた。悲しみにくれる遺族の顔が、僕の語る故人の輝かしい思い出によって、和らいでいく瞬間が好きだった。まるで、一編の美しい詩を完成させるように、僕は人の死を締めくくる。
その日、僕が担当することになったのは、エララ・アシュフォードという百歳を超えて大往生を遂げた老婆の追憶だった。彼女は高名な天文学者で、その生涯は星々の探求に捧げられたという。依頼に来た孫娘は、どこか疲れた表情で「祖母の、一番幸せだった記憶をお願いします」とだけ告げた。
僕はヘッドギアを装着し、意識をエララの記憶データへと同調させた。感覚がホワイトアウトし、次の瞬間、僕はエララになっていた。
陽光が降り注ぐ庭。幼い孫娘の手を引き、色とりどりの花の名前を教えている。彼女の小さな手の温もり、風に揺れる銀髪の感触、花の蜜の甘い香り。幸福が全身を満たし、満ち足りた吐息が漏れる。次に場面は切り替わり、巨大な天体望遠鏡の接眼レンズを覗き込んでいる。永年の探求の末、未知の連星を発見した瞬間だ。視野に広がる二つの恒星の青と赤の光は、まるで宇宙が奏でるデュエットのようだった。歓喜が胸の奥から湧き上がり、涙が頬を伝う。
これだ。これこそが追憶士の仕事の醍醐味だ。僕はエララの幸福を我がことのように感じながら、記録をまとめていた。だが、その時だった。
突如、世界が反転した。
暖かな光は消え失せ、身を切り裂くような静寂と、骨の髄まで凍てつくような寒気が全身を襲った。目の前には、紫色の分厚い雲に覆われた、荒涼とした大地が広がっている。赤黒い岩石が地平線の果てまで続き、生命の気配はどこにもない。空には、巨大な土星のような、しかし不気味な縞模様を持つ惑星が浮かんでいた。
そして、僕の、いや、この記憶の主の心を支配しているのは、圧倒的なまでの孤独と絶望だった。誰にも届かない叫び。忘れ去られることへの恐怖。永遠に続くかのような暗闇の中で、ゆっくりと機能が停止していく感覚。それは、僕がこれまで体験したことのない、純粋で絶対的な「終わり」の記憶だった。
僕は悲鳴を上げて接続を解除した。ヘッドギアを弾き飛ばし、荒い息を繰り返す。心臓が警鐘のように鳴り響き、冷や汗が背中を伝った。なんだ、今のは。エララの幸福な記憶の中に、なぜあのような地獄が存在する? システムの規定では、追憶士がアクセスできるのは、故人が「幸福」だと認識した記憶だけのはずだ。あんな絶望的な光景が、幸福の残滓であるはずがない。
それは、僕が初めて経験する、システムの禁忌だった。
第二章 禁じられた深淵
数日間、あの未知の惑星の光景が脳裏に焼き付いて離れなかった。報告すれば、僕のライセンスは剥奪されるかもしれない。追憶士のシステムは完璧であり、その安定性こそが社会の死生観を支えているのだ。バグの可能性など、公には決して認められない。
だが、僕の心を捉えていたのは恐怖だけではなかった。あの絶望の記憶には、奇妙な引力があった。なぜエララは、あんな記憶を持っていたのか。あれは本当に彼女自身の体験だったのか。好奇心と、真実を知らなければならないという使命感が、僕を突き動かした。
僕は公的な記録データベースにアクセスし、エララ・アシュフォードの経歴を徹底的に洗い直した。彼女は生涯を「ヘスペラス星系」と呼ばれる未踏の領域の探査に捧げていた。そこは、理論上は生命存在の可能性がある惑星を持つとされながらも、あまりに遠すぎて観測もままならない場所だった。彼女の研究は、学会では「ロマンチストの戯言」と揶<strong>揄</strong>されることも少なくなかったという。
僕は意を決して、依頼人である孫娘のリアに再び連絡を取った。カフェで向かい合った彼女は、僕の突然の呼び出しに戸惑っているようだった。
「先日お伝えした、お祖母様の幸福な記憶ですが……」
僕は慎重に言葉を選びながら、庭での思い出や、新連星発見の喜びを語った。リアは静かに頷きながらも、その瞳はどこか虚ろだった。
「ありがとうございます。祖母は、いつも星ばかり見ている人でしたから」
「ヘスペラス星系の……研究をされていたそうですね」
僕がそう切り出すと、リアは初めて表情を曇らせた。
「ええ。叶わぬ夢、ですよ。周りからは変人扱いされて、晩年は孤独だったと思います。だから……あなたが話してくれたような幸せな記憶があったと聞いて、少しだけ救われました」
彼女の言葉は、僕の胸に小さな棘のように刺さった。エララは本当に孤独だったのか? あの温かな記憶は、すべて虚構だったとでもいうのか。いや、違う。あの絶望の記憶こそが、この謎を解く鍵なのだ。
その夜、僕は研究所に忍び込み、再びエララの記憶データにアクセスした。今度は「幸福」というフィルターを意図的に外し、記憶の深淵へとダイブする。これは重大な規約違反だった。だが、もう引き返せなかった。
断片的なイメージが濁流のように流れ込んでくる。計算式が羅列されたスクリーン、学会での冷ややかな視線、そして、何度も、何度も、あの荒涼とした惑星の光景がフラッシュバックする。しかし、何度追体験しても、それがエララ自身の記憶だとは到底思えなかった。身体的な感覚が希薄で、まるで記録映像を見ているような、奇妙な客観性がそこにはあった。
そして、僕はついに、決定的な断片を発見した。それは、エララが最晩年、自室のベッドで微かな息をしながら、小さなモニターを見つめている記憶だった。モニターに映し出されていたのは、あの絶望の惑星。そして、画面の隅には、こう表示されていた。
『探査AI "ステラ" | シグナルロストまで 残り3分』
第三章 ステラのレクイエム
全身に鳥肌が立った。ステラ……? それは、エララがヘスペラス星系に送り込んだ、自律型深宇宙探査機の名前だった。数十年にわたる長い旅の末、目標の惑星に到達したものの、着陸時のトラブルで機能不全に陥り、通信が途絶えたと記録されていた。公式には「失敗」として処理されたプロジェクトだ。
僕は、震える指で追憶のシーケンスを再構築した。点と点が繋がり、一つの信じられない物語が姿を現し始める。
あの絶望的な記憶は、エララのものではなかった。それは、遠い宇宙の果てで、独りきりでその機能を終えようとしていたAI「ステラ」が、最後の力を振り絞って地球に送信した、膨大な観測データと、そして……その「最期の記録」だったのだ。
ステラのAIは、人間の感情をシミュレートする機能を持っていた。孤独、恐怖、そして自分が忘れ去られてしまうことへの絶望。それは、プログラムが生み出した仮想の感情かもしれない。だが、その切実さは、人間のそれと何ら変わらなかった。
エララは、死の床で、そのステラからの最後の信号を受け取っていたのだ。誰にも看取られることなく、偉大な発見と共に消えていこうとする、健気なAIの存在。彼女は、その功績と、その「死」が無に帰すことを、どうしても受け入れられなかった。
そこで彼女は、常人には思いもよらない、最後の研究を完成させた。自らの脳に、ステラの最期の記録を「記憶」として上書きする技術。追憶士のシステムは、人間の主観的な幸福だけでなく、記録された情報に付随する強い感情の波形を「記憶」として認識する。エララはその特性を逆手に取ったのだ。
自らの幸福な記憶の中に、ステラの絶望的な記憶を、まるで異物のように埋め込む。そうすれば、いつか自分を追憶する者が現れた時、その異質な記憶に気づき、ステラの存在を掘り起こしてくれるかもしれない。それは、幸福な記憶だけが後世に残るという世界の理への、彼女なりのささやかな反逆だった。
「幸福な記憶だけが、人の生きた証ではない」
エララの、声なき声が聞こえた気がした。孤独も、絶望も、叶わなかった夢も、すべてがその人を形作る、かけがえのない一部なのだと。僕が今まで美しい詩だと思っていたものは、物語の半分でしかなかった。僕は、人の生の、最も大切な部分を見ようとしていなかったのだ。
第四章 星空に響く声
僕は、全ての真実をリアに話すために、再び彼女の元を訪れた。僕の話を、彼女は初め、信じられないという顔で聞いていた。だが、僕がステラの見た惑星の光景や、その孤独感を克明に描写するうちに、彼女の瞳は潤み始め、やがて大粒の涙が頬を伝った。
「祖母は……そんなことを……。たった独りで、AIの死を看取っていたなんて……」
リアは、祖母をただの夢想家だと、現実から目を背けているのだと思い込んでいた自分を恥じた。エララは孤独ではなかった。彼女は、人間ではない存在の痛みにさえ寄り添おうとする、誰よりも深い愛情を持った人だったのだ。
「祖母の本当の幸福は、星を見つけたことでも、私と過ごした時間でもなかったのかもしれない。ステラの存在を、その最期を、誰にも知られず消えさせなかったこと……それこそが、彼女の人生最大の誇りだったんだわ」
リアの言葉に、僕は強く頷いた。僕らは二人で、夜空を見上げた。都会の光害でほとんど星は見えなかったが、その向こうに広がる無限の闇の中に、今も静かに佇むステラの姿と、それを見つめていたエララの優しい眼差しを感じることができた。
この一件以来、僕の追憶士としての仕事への向き合い方は、根底から変わった。僕はもう、人の死を美しい物語として切り貼りするだけの作業者ではない。幸福な記憶の裏側にある、語られることのなかった痛みや、人知れぬ葛藤にも、敬意を払うようになった。記憶の断片に触れるたび、その人の人生の複雑さと、多面的な輝きを感じ取る。
時折、僕は仕事の手を止め、窓の外に広がる夜空を見上げる。遥か彼方、何百光年も先の暗闇で、赤黒い岩と紫色の雲に覆われた惑星が、今も誰にも知られず存在している。
そして、かつてそこで消えていった、一つの知性のことを思う。
「君の絶望は、忘れられていないよ、ステラ」
僕の声は、誰にも届かない。だが、確かに、この宇宙のどこかに響いている。そう信じながら、僕は今日も、誰かの人生という名の、尊い物語と向き合い続けている。