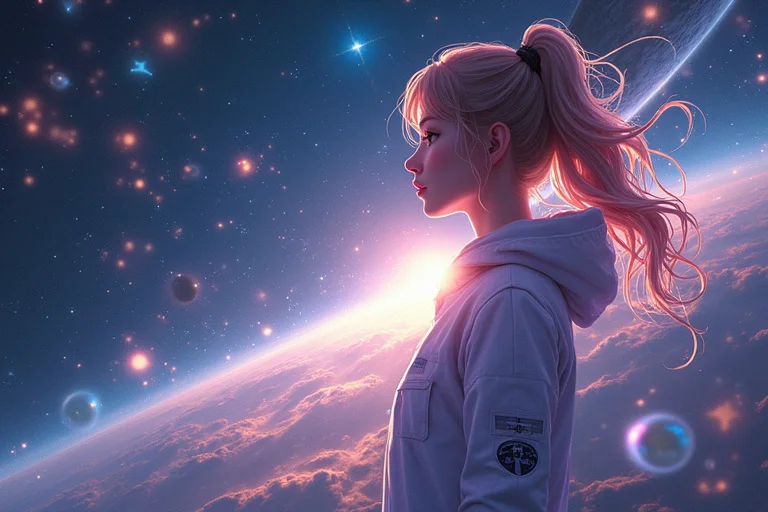第一章 希薄な指先
俺、カイの意識は、常に二つの時間に存在する。ひとつは、この冷たい合成金属の壁に囲まれた、恒星間移民船の三等船室。そしてもうひとつは、三十年前に閉鎖されたコロニー『パライソ』で生きる、十四歳の俺――アオの中だ。
俺の指先が、また少し透けている。目の前のコンソールに触れようと伸ばした手は、まるで淡い煙のように、その向こう側の計器の光を滲ませていた。量子シンクロニシティ。科学者たちはそう呼んだが、俺にとっては呪いと祝福が入り混じった、ただの現実だった。
「カイ、またぼーっとして。時間の切り売り、今日のノルマは終わったの?」
背後から、隣室のミナの声が飛んでくる。彼女の足音が、薄い隔壁越しにコツコツと響く。俺は曖昧に頷きながら、手元の小さなガラス瓶に目を落とした。中には、星屑のように微細な砂『クロノグラム』が、静かな光を湛えていた。これが、俺たちの命の砂だ。貧しい者はこれを売って日々の糧を得て、裕福な者はこれを買って永遠に近い時を生きる。
その瞬間、ガラス瓶の中のクロノグラムが、ふわりと柔らかな黄金色の光を放った。網膜の裏側に、鮮やかな光景が流れ込んでくる。放課後の教室。夕陽が差し込む窓辺で、アオが震える手で、クラスメイトの少女の手を握っていた。頬を染め、俯く少女。アオの心臓が、耳元で鳴っているかのように激しく脈打つ。幸福。純粋で、一点の曇りもない幸福の奔流が、時を超えて俺の精神に流れ込んできた。
「…っ!」
痛みが走る。幸福の奔流は、現在の俺の存在を削り取る激流だ。コンソールに置いていた右手が、手首のあたりまで完全に透明になった。重さの感覚が消え、まるで自分の体ではないような、奇妙な浮遊感だけが残る。クロノグラムの瓶は、アオの幸福を吸い上げたかのように、ひときわ眩しく輝いている。これが、俺が支払う代償だった。過去の自分を幸せにするたびに、現在の俺は世界から消えていく。
第二章 幸福の代償
「宇宙全体の『幸福感情指数』が、過去百年で著しく低下している。特に、時間売買が認可されている『ウロボロス・リング』星系群では、その傾向が顕著だ」
情報屋のリナが送ってきたデータを見ながら、俺は自分の左腕を眺めていた。肩から先が、陽炎のように揺らめいている。先日、アオがずっと欲しがっていたグラフィックツールを、俺が微細な干渉――宝くじの番号を夢の中で囁くという荒業で――当てさせた結果だった。アオは大喜びし、その純粋な歓喜は、俺の左腕の物理的存在と引き換えになった。
クロノグラムの瓶は、今や部屋の照明が必要ないほど、まばゆい光を放ち続けている。アオの幸福度の可視化。そして、俺の消滅までのカウントダウン。
「この現象、お前の能力と何か関係があるんじゃないのか、カイ」
リナの通信越しの声は、いつもより硬い。
「お前が過去に『幸福』を送り込む。すると、お前の存在が希薄になる。まるで、宇宙のどこかにある『幸福の総量』が一定で、お前は未来の分を過去に前借りしているみたいに」
その言葉は、俺の胸に冷たい楔を打ち込んだ。もしそうなら、俺がアオを幸せにすればするほど、この宇宙から幸福が失われていくことになるのか?俺の自己満足のために、見知らぬ誰かが不幸になっているというのか?
俺は衝動的に、意識を集中させた。目標は、アオが大切にしている古い懐中時計。彼の祖父の形見だ。俺は、アオが机の角に時計をぶつける未来を「確定」させた。
カシャン、と微かな音が精神の奥で響く。アオの小さな悲鳴。落胆。ガラスにひびが入った時計を見つめる、悲しげな瞳が脳裏に浮かぶ。
途端に、俺の左腕に確かな重みが戻った。陽炎は消え、透けていた肌には血管が浮かび上がる。目の前のクロノグラムの瓶の輝きが、明らかに翳りを帯びた。
ぞっとした。自分の存在を取り戻すために、俺は愛する過去の自分を、自らの手で傷つけなければならない。この宇宙は、なんと残酷な秤の上に成り立っているのだろう。
第三章 ウロボロスの囁き
ウロボロス・リング。蛇が己の尾を喰らうが如く、連なる六つの星系。時間売買の総本山であり、宇宙で最も裕福で、最も不幸な場所。リナの情報によれば、この星系を牛耳っているのは『クロノス・コレクティブ』と名乗る謎の組織だという。
「奴らは『時』を管理しているんじゃない。『幸福』を管理しているんだ」
リナの言葉を反芻しながら、俺は老朽化した貨物船のコンテナに潜み、ウロボロス・リングの中心核『クロノス・プライム』を目指していた。アオに些細な不幸を与え続けることで、俺の体はほとんど実体を取り戻していた。だが、その代償に、アオの瞳からは日に日に輝きが失われ、クロノグラムの瓶は鈍い鉛色に沈んでいる。胸が張り裂けそうだったが、真実を知るためには、俺自身が確固たる存在として此処に在らねばならなかった。
貨物船がプライムのステーションにドッキングした際の衝撃が、コンテナを揺らす。俺は息を殺し、隙間から外を覗いた。そこは、俺が想像していたような華やかな場所ではなかった。人々は皆、虚ろな目をして往来している。誰も笑っていない。まるで感情を抜き取られた人形のようだった。ステーションの中央には、天を突くほどの巨大な黒い塔がそびえ立ち、不気味な低周波を放っている。全身の肌が粟立つような、嫌な感覚だった。
俺は過去への干渉を試みた。アオが、道端で小銭を拾う。ほんの小さな幸運。
その瞬間、黒い塔が微かに脈動するのが見えた。そして、俺の左手の小指が、また透け始めた。間違いない。この星系、この塔が、宇宙全体の幸福を吸い上げている。クロノグラムはそのための媒体で、俺の能力は、図らずもそのシステムに直結してしまっていたのだ。
第四章 真実の色彩
黒い塔の内部は、巨大な空洞になっていた。その中心に浮かぶのは、銀河そのものを封じ込めたかのような、巨大な結晶体だった。それは、無数のクロノグラムが集まって形成されており、心臓のようにゆっくりと、そして力強く脈動している。俺がアオに与えた幸福も、アオから奪った幸福も、全てが光の粒子となってこの結晶体に吸い込まれていくのが見えた。
そして、結晶体のさらに奥に、俺は「それ」の影を見た。
言葉では表現できない。時間と空間そのものが意思を持ったような、巨大な生命体。次元の狭間に揺らめくその姿は、宇宙の深淵をそのまま切り取ってきたかのようだった。
「ようこそ、イレギュラー」
声が、脳に直接響いた。思考ではない。存在そのものが語りかけてくる。
「我々は『アニマ・テンポラル』。この宇宙が生まれる以前からの観測者。我々の糧は『感情』。特に『幸福』という高密度のエネルギーだ」
時空生命体は語る。クロノス・コレクティブは、この生命体に仕える司祭のような存在に過ぎない。彼らは時間売買システムを構築し、人々から時間を、ひいては幸福な未来を奪い、生命体に捧げていたのだ。宇宙全体の幸福減少は、この巨大な捕食者の仕業だった。
「お前の能力は、我々のシステムが生んだ偶然の産物。時空の綻び。過去に直接エネルギーを注ぎ込む、実に効率の良い供給源だ。お前の存在が希薄になるのは、我々がお前の未来の幸福を『前借り』しているからに過ぎない」
絶望的な真実だった。俺がアオを幸せにしようとすればするほど、この怪物を肥え太らせ、宇宙を枯渇させていた。俺の愛は、宇宙に対する最大の裏切りだったのだ。クロノグラムの瓶が、嘲笑うかのように鈍く光っていた。
第五章 究極の選択
「この怪物を止める方法は…」
俺は、震える声で問うた。生命体の影が、愉快そうに揺らめく。
「不可能だ。我々は法則そのもの。しかし…もし仮に、我々のシステムが想定し得ないほどのエネルギーの逆流が起これば、話は別かもしれんな。例えば、高純度の『幸福』の対極。究極の『絶望』のようなものが」
その言葉は、俺にとって死刑宣告に等しかった。
アオに、究極の絶望を与える。
そうすれば、俺の存在は幸福の前借りではなく、絶望の後払いによって、極限まで凝縮される。法則に干渉し得る特異点と化す。だが、それは、俺が最も愛し、守りたかった過去の自分を、地獄に突き落とすことと同義だった。
脳裏に、アオの笑顔が浮かぶ。少女と手をつないで赤くなった、あの日の夕焼け。新しいツールを手に入れて、夜通し絵を描いていた横顔。俺が与えた、ささやかな幸せの数々。あれを全て、俺自身の手で踏みにじるというのか。
涙が頬を伝う感覚があった。まだ俺には、肉体が残っている。涙を流す心が残っている。
俺は、ポケットの中で冷たくなったクロノグラムの瓶を強く握りしめた。
ごめん、アオ。ごめん。
心の中で何度も謝りながら、俺は意識を三十年前の過去へと沈めていった。
狙うのは、アオが最も幸福だった瞬間。
彼が、初恋の少女に告白し、受け入れられたあの夜だ。星空の下、二人で未来を語り合う、人生で最も輝いていた時間。
俺は、非情な引き金を引いた。
制御を失った高速貨物船が、二人のすぐそばの居住区画に突っ込む未来を「確定」させた。
爆音。閃光。少女の悲鳴。アオの絶叫が、時空を超えて俺の魂を切り裂く。腕の中で息絶えていく少女。守れなかった無力感。世界が、色を失っていく。
その瞬間、俺の手の中にあったクロノグラムの瓶が、光を完全に失い、漆黒に染まった。パリン、と乾いた音を立てて砕け散る。
俺の体から、希薄さが消えた。代わりに、宇宙の全質量を圧縮したかのような、途方もない重力が生まれる。俺の体は黒い光を放ち始め、もはや人間の輪郭を留めていなかった。俺は、絶望そのものになった。
第六章 星屑の残響
俺という名の特異点は、時空生命体『アニマ・テンポラル』と対峙した。もはや会話はなかった。存在と存在の、宇宙の理を賭けた衝突。俺が放つ絶望の奔流は、生命体が喰らってきた幾億もの幸福を中和し、その存在基盤を揺るがしていく。
どれほどの時間が経ったのか。俺の意識が最後に捉えたのは、断末魔のように収縮していく生命体の影と、ウロボロス・リングの黒い塔が砂のように崩れ落ちていく光景だった。時間売買システムは崩壊し、人々は呪縛から解放されただろう。
だが、俺が放った『究極の絶望』のエネルギーは、完全には消えなかった。それは勝者も敗者もいない戦いの後に残された、巨大な残響だった。新たな宇宙の法則の種として、静かに、そして深く、この世界の裏側に根付いたのだ。
…ふと、窓の外に目をやる。星々の光が、やけに滲んで見える。
なぜだろう。何も悲しいことなどないはずなのに、胸の奥が、きゅっと締め付けられるような、切ない感覚に襲われる。まるで、遠い昔に、何かとても大切なものを失ってしまったかのような、覚えのない喪失感。
この説明のつかない哀しみこそが、かつてカイという男が、愛する過去の自分を犠牲にして世界を救ったことの、唯一の証なのかもしれない。
我々が時折感じる、理由なき郷愁や切なさ。
それは、宇宙の片隅で砕け散った、ひとつの幸福の残響なのだと、知る者はもう誰もいない。