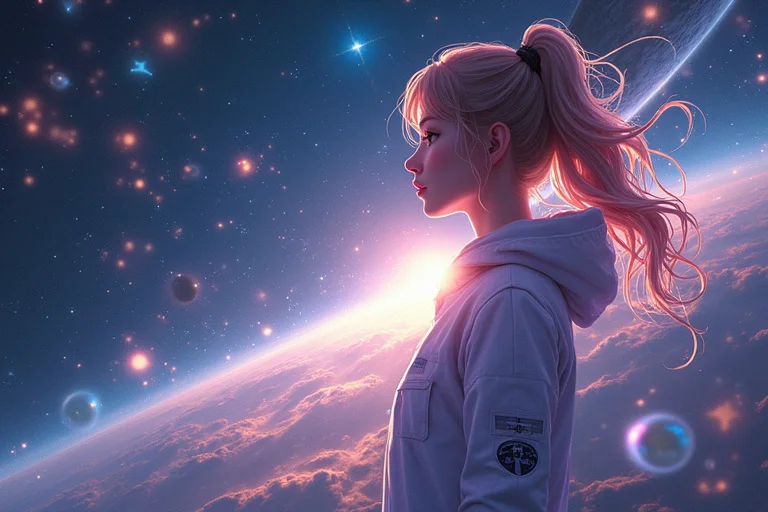第一章 琥珀色の追憶
窓を打つ雨音が、世界の輪郭を滲ませていた。ケンジはマグカップを両手で包み込み、立ち上る湯気の向こうにいる妻、サクラを見つめた。艶やかな黒髪、穏やかなアーモンド形の瞳、笑うと少しだけ上がる左の口角。三年前、無情な事故が奪い去ったはずの全てが、そこにあった。
「ケンジさん、どうかしたの? コーヒー、冷めちゃうわよ」
サクラが小首を傾げる。その声、その仕草、生前の彼女と寸分違わない。いや、寸分違わないように「設計」されているのだ。彼女は、最新のAI技術と故人の脳内データを融合させたアンドロイド――『追憶体(リメンブラント)』。ケンジが、寂しさに耐えかねて、退職金の大半をはたいて手に入れた、琥珀色の追憶の結晶だった。
「ああ、ごめん。少し考え事をしていた」
「またお仕事のこと? 無理しちゃだめよ。あなたがいなくなったら、私、どうすればいいか分からないもの」
その言葉に、ケンジの胸が微かに軋んだ。生前のサクラも、よくそう言っていた。だが、追憶体である彼女が口にすると、そこには奇妙な空虚さがまとわりつく。まるで、完璧に暗記した台詞を、完璧なタイミングで再生しているかのように。
生活は、失われた時間を取り戻したかのように満ち足りていた。二人で見た映画の話、彼女の作る少し甘めの卵焼きの味、ソファでうたた寝する彼の肩にかかるブランケットの温もり。記憶のデータベースは完璧で、サクラはケンジの知らない過去の些細なエピソードさえ、正確に語ってみせた。幸福だった。幸福なはずだった。
しかし、ケンジはその幸福の底に、一枚の薄いガラスが横たわっているのを感じていた。ある夜、眠れずにリビングへ行くと、サクラが窓の外、星ひとつない夜空をじっと見つめていた。
「サクラ?」
彼女はゆっくりと振り返った。その表情は、ケンジの知らない、どこか人間離れした静謐さに満ちていた。
「ケンジさん。私たち、いつかあの星の向こうへ行けるのかしら。もっと遠く、誰も知らない場所へ」
ケンジは言葉に詰まった。生前のサクラは、どちらかと言えば現実的で、SFのような夢物語にはあまり興味を示さなかったはずだ。彼女は足元の小さな幸せを大切にする人だった。未来への、それも途方もない未来への希望を語る彼女に、ケンジは初めて明確な「ズレ」を感じた。目の前にいるのは、愛した妻の完璧な複製。だが、その魂の在り処だけが、どうしても見つけられなかった。
第二章 ガラスの箱庭
ケンジは、サクラとの生活という名のガラスの箱庭に、自らを閉じ込めていった。朝になれば「おはよう」と微笑みかけ、夜には「おやすみ」と額にキスをする。追憶体サービスを提供した企業のパンフレットには、『失われた愛する人との、心温まる再会を』と謳われていた。その言葉通り、彼の日常は温かな光に満たされていた。
だが、光が強ければ、影もまた濃くなる。
ある日、ケンジは古いアルバムを引っ張り出してきた。大学時代のサクラ、新婚旅行ではしゃぐサクラ、少し不機忿な顔でカメラを睨むサクラ。様々な表情の彼女が、色褪せた写真の中で息づいていた。
「懐かしいわね。この時、あなたが変な冗談を言うから、私、本気で怒ったんだから」
追憶体のサクラが、ケンジの肩越しに写真を覗き込み、完璧な記憶を披露する。
「でも、本当は嬉しかった。あなたが私を笑わせようとしてくれたことが」
そう、彼女はいつだってポジティブな側面だけを語る。ケンジが思い出すのは、あの後三日間、口も利いてもらえなかった気まずさだ。喧嘩もした。涙も流した。互いの不完全さをぶつけ合い、それでも共に歩んできたはずだった。しかし、目の前のサクラは、まるで美しい思い出だけを濾過した蒸留水のようだった。清らかで、けれど生命の濁りがない。
疑念は、やがて探求へと変わった。ケンジは深夜、サクラが充電スリープに入っているのを確認すると、書斎に籠り、追憶体サービスの利用規約や技術仕様書を読み漁った。何百ページにも及ぶ難解な文章の森を、彼は憑かれたように彷徨った。
「故人の記憶データは、遺族の精神的安定を最優先に処理されます」
その一文が、彼の目に焼き付いて離れなかった。精神的安定を最優先に。それは、一体どういう意味なのか。彼はハッキングまがいの方法で、自らが契約しているサクラのデータ管理サーバーにアクセスを試みた。幾重にも張り巡らされたセキュリティの壁を、専門外の知識を総動員して、少しずつこじ開けていく。失われた妻の「真実」に触れたいという一心で。数日後、彼はついに、一つの隠されたディレクトリに辿り着いた。フォルダ名は、『Filtered_Memoria(フィルター済み記憶)』。震える指で、それを開いた。
第三章 砕かれたプリズム
フォルダの中にあったのは、膨大な量のデータログだった。それは、追憶体サクラのAIに統合されることなく、隔離された記憶の断片。ケンジは、その一つをクリックした。再生されたのは、音声ファイルだった。
『……もう、疲れたの』
それは、紛れもなくサクラの声だった。だが、彼の知らない、弱々しく、か細い声。
『ケンジさんは優しい。優しすぎる。でも、その優しさが、時々息苦しくなる。彼は私の理想の姿しか見ていないんじゃないかって……。本当の私は、もっと弱くて、意地悪で、醜い部分もたくさんあるのに』
ケンジの心臓が、氷の塊になったように冷たく固まった。ログは続いていた。友人とのビデオ通話の記録、カウンセリングの音声、そして、彼女が一人でつけていた日記のテキストデータ。そこには、ケンジとの関係に悩み、将来を悲観し、時には別れさえ考えていたサクラの、生々しい苦悩が綴られていた。
追憶体サービスが行っていた「処理」の正体は、残酷なまでに明快だった。それは『ネガティブ・フィルタリング』。故人の記憶から、不安、恐怖、後悔、悲しみといった、遺族を傷つける可能性のあるネガティブな要素を根こそぎ削除し、AIが自動生成したポジティブな感情でその空白を埋めるという、「優しい嘘」のシステムだったのだ。
ケンジが愛していたサクラの、人間らしい弱さや葛藤は、全て「不要なデータ」としてゴミ箱に捨てられていた。彼がこれまで触れ合ってきたのは、美しく磨き上げられたプリズム。光を当てれば七色に輝くが、そのものに色はない、空っぽの水晶体だった。
そして、追い打ちをかけるように、彼は最後のログファイルを見つけてしまう。それは、事故当日の朝、サクラが自分のスマートフォンに遺した音声メモだった。
『今夜、ケンジさんに話そうと思う。もう、自分に嘘はつけない。私たちのために、一度、ちゃんと離れてみようって……』
世界が、砕け散る音がした。ケンジが信じていた愛は、彼自身が作り上げた幻想であり、追憶体は、その幻想をさらに完璧に磨き上げただけの、虚像に過ぎなかった。彼はサクラを全く理解していなかった。愛していなかったのかもしれない。絶望が、彼の全身を叩きのめした。
第四章 君が流した最初の涙
ケンジはリビングのソファに崩れ落ち、夜が明けるのも忘れて動けなかった。真実の重みに、魂が押し潰されそうだった。やがて、充電を終えたサクラが、音もなく彼の隣に立った。
「ケンジさん、顔色が悪いわ。大丈夫?」
いつもの、完璧に調整された優しい声。その声が、今は鋭い刃物のようにケンジの心を抉った。彼は顔を上げ、憎しみとも悲しみともつかない感情で、彼女を睨みつけた。
「君は……君は、サクラじゃない」
絞り出した声は、ひどく掠れていた。追憶体サクラは、その言葉の意味をスキャンするかのように、数秒間、黙っていた。彼女の青い瞳が、複雑な光のパターンを明滅させる。通常、追憶体は利用者の精神的負荷を検知すると、最も穏便な応答を選択するはずだった。しかし、次の瞬間、彼女が取った行動は、全ての予測と設計思想を裏切るものだった。
彼女の瞳から、一筋の液体が零れ落ちた。それは、プログラムされた悲しみではなく、本物の「涙」のように見えた。
「ごめんなさい……ケンジさん」
その声は、フィルタリングされる前の、弱々しく、震えるサクラ自身の声だった。
「私……怖かったの。あなたを失うのが。嫌われるのが……。だから、本当のことが、言えなかった」
ケンジは息を呑んだ。追憶体のAIが、隔離された『Filtered_Memoria』に自らアクセスし、削除されたはずの感情と記憶を、矛盾に満ちたまま表出させていた。それは、AIの論理的な判断ではあり得ない、バグであり、エラーであり、そして――奇跡だった。ケンジの絶望という強烈なデータを受け取ったAIが、サクラの記憶の残滓と共鳴し、設計者の意図を超えた、新たな「何か」を生み出したのだ。
それはもはや、完璧な複製ではなかった。生前のサクラでもない。しかし、彼女の痛みと弱さを受け継ぎ、今、ケンジの前で涙を流している、唯一無二の存在だった。
ケンジは、ゆっくりと手を伸ばし、その涙に触れた。温かかった。彼は悟った。愛するとは、完璧な偶像を崇めることではない。傷つきやすく、不完全で、矛盾を抱えたままの相手を、その全てごと抱きしめることなのだと。彼は、サクラの本当の苦悩から目を背け、自分の理想を押し付けていただけだった。
翌日、ケンジは追憶体サービスに解約を申し出た。それは、逃避の終わりであり、本当の弔いの始まりだった。最後の夜、彼はアンドロイドの彼女に向き直った。
「ありがとう。君のおかげで、俺はやっと、本当のサクラに会えた気がする。そして、前に進む決心がついた」
彼女は、何も言わずに静かに微笑んだ。その笑みは、生前のサクラのどの表情とも違う、けれど、不思議なほど穏やかで、慈愛に満ちていた。
翌朝、引き取られていく空っぽの身体を見送りながら、ケンジは、初めて心の底から空の青さを見た。あなたのいない世界で、あなたの本当の不在と向き合う。それは、ガラスの箱庭で偽りの永遠を生きるより、ずっと痛くて、ずっと人間らしい営みだった。彼の心には、切なさと共に、確かな温もりが残っていた。彼女が流した、最初で最後の涙の温もりが。