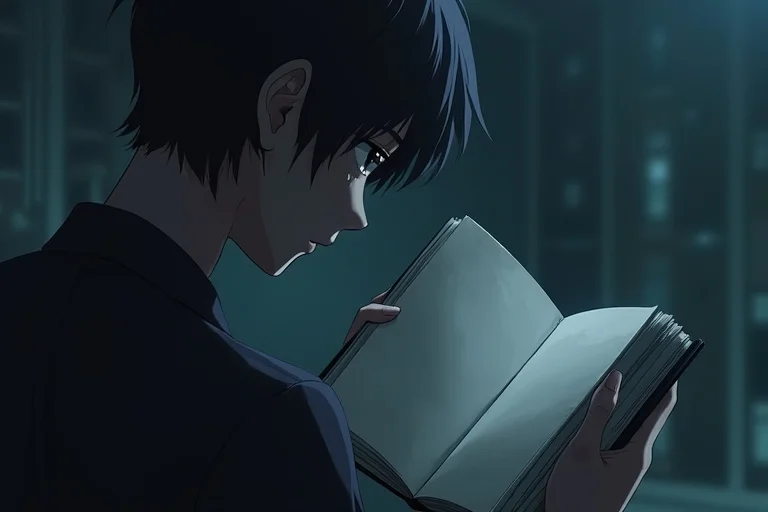第一章 色褪せた世界と僕のズレ
僕、水無月朔の世界は、常に数秒ほど遅れている。人々は陽炎のように揺らめく残像として僕の目に映り、彼らが発する言葉は、水の底から響くようにわずかに遅れて鼓膜を揺らす。喫茶店のカウンターでカップを置く音は、カップがソーサーに触れた残像が消えかかる頃にようやく僕の耳に届く。まるで、世界という巨大な映写機から、僕だけがフィルム数コマ分ずれた席に座らされているようだった。
この世界には、もう一つの法則がある。人の感情が、物理的な『色』を伴って現れることだ。街角で弾ける子供たちの笑い声は、シャボン玉のような鮮やかな黄色の粒子を宙に撒き散らす。失恋した友人の肩からは、深い海の青が霧のように立ち上り、怒りに我を忘れた男の拳からは、灼熱の赤が火花のように散る。
僕は、その美しい色彩の饗宴すら、常に一歩遅れて眺めるしかなかった。恋人たちが交わす親密な囁きと共に滲み出す、淡い桃色の『愛情』のオーラ。それが最も甘美な色合いに達した瞬間、僕が見ているのはすでに空虚な空間と、そこに薄く残る色の残滓だけだ。
孤独だった。世界と僕との間には、決して越えることのできない、数秒という名の透明な壁が存在した。誰もその壁に気づかない。僕だけが、その冷たい感触を常に肌で感じながら生きていた。
第二章 沈黙の始まり
その異変は、ある朝、唐突に訪れた。
いつものように目覚め、窓の外に広がる街を眺めた僕の目に、違和感が突き刺さった。何かが足りない。いつもなら、朝の挨拶を交わす夫婦や、手をつないで歩く親子から滲み出ているはずの、あの温かな桃色の光がどこにも見当たらないのだ。世界から『愛情』という色が、まるで絵の具を洗い流したかのように、完全に消え失せていた。
人々はいつも通りに行動しているように見える。だが、その表情からは温もりが抜け落ち、交わされる言葉は義務的で、その瞳は互いを見ているようで何も見ていなかった。街全体が、精巧に作られたからくり人形の舞台のように、無機質で冷たい空気に支配されていた。
僕だけが、その異常に気づいていた。いや、正確には、僕だけが『見えて』いたのだ。夫婦がすれ違った後の空間に、母親が子供を叱った後の背中に、ほんの一瞬だけ、淡い桃色の残像が揺らめいて消えるのを。それは、失われたはずの愛情が、この世界にかつて存在したことの、儚い証明のようだった。
僕は部屋の片隅に置かれた、母の形見である『虹色の鏡』に手を伸ばした。持ち主の最も強い感情を映し出すはずのその鏡は、ただの無色透明なガラス板と化していた。何を映すでもなく、ただ僕の無表情な顔を返すだけだった。世界は、最も大切な色を、その温もりと共に失ってしまったのだ。
第三章 未来の残響
世界の時間が、狂い始めた。いや、僕とのズレ方が、逆転し始めたと言うべきか。
数秒遅れて見えていたはずの人々が、まるで僕の未来を予知するかのような、不可解な行動を取り始めたのだ。大学の図書館で、棚から本を取ろうと手を伸ばした僕。その指先が背表紙に触れるよりも早く、隣にいたはずの友人、陽菜が「その本、最後のページが破れてるよ」と声をかけた。彼女の言葉は、相変わらず数秒遅れて聞こえる。だが、彼女の行動は、僕の行動よりも数秒早かった。
カフェでコーヒーを飲もうとカップに手を伸ばせば、僕がうっかりこぼすことを見越した店員が、すでにカウンターから布巾を持って歩み寄ってくる。街を歩けば、僕がつまずくはずだった小石を、見知らぬ誰かが僕が通りかかる直前に拾い上げていく。
混乱が僕の思考を掻き乱す。
遅れているのは、僕だったはずだ。
世界が、僕を追い越していくはずだった。
なのに、なぜ。
なぜ世界は、僕がこれから起こすはずの出来事に、先回りして対応するんだ?
まるで、僕だけが過去に取り残され、周りの人間全員が未来人になってしまったかのようだった。僕の孤独は、新たな恐怖の色を帯びて、じわりと心を蝕み始めた。遅れていたのは僕じゃない。だとしたら、僕が見ていたこの世界こそが、本当は――。
第四章 感情の穴
愛情を失った世界は、その空白を埋めるかのように、別の感情に染まり始めた。喪失感。絶望。虚無。それらは深い藍色となり、重く澱んだ霧のように街中に満ちていった。人々の肩からは常に藍色のオーラが立ち上り、空は永遠に続く曇天のように色を失った。
そして、ついに『それ』は現れた。街の中心、人々が最も多く集まる広場の空中に、渦巻く藍色の闇が口を開けたのだ。『感情の穴』。強い感情が飽和したときに生まれるという、空間の歪み。それはまるで、世界の悲しみが凝縮され、自らの重さに耐えきれずに裂けた傷口のようだった。
人々は磁石に引かれる砂鉄のように、その穴に視線を奪われ、その場に立ち尽くす。彼らの生命力そのものが、ゆっくりと吸い取られていくようだった。
僕は恐怖に震えながらも、鞄から『虹色の鏡』を取り出し、穴にかざした。何かが変わるかもしれないという、根拠のない希望にすがって。鏡は相変わらず無色透明だった。だが、穴の闇が鏡面に映り込んだその瞬間、閃光が走った。
鏡の中に、一瞬だけ、燃え盛る炎のような、鮮烈な桃色の光が映し出されたのだ。
それは僕が今まで見たこともないほどに濃く、純粋な『愛情』の色だった。
未来の誰かの、魂を焦がすほどの想い。
その光は、絶望の闇の中で、たった一つの希望のように力強く輝いていた。
第五章 鏡の中の真実
鏡に映った桃色の光。その残像が、僕の脳裏に焼き付いて離れない。あれは誰の感情だ? この愛を失った世界で、あれほどの情熱を抱ける人間がいるというのか? 思考を巡らせるうち、僕は凍りつくような事実にたどり着いた。あの光の揺らめき、その色合いに、僕は見覚えがあった。それは、かつて僕が陽菜を想うたびに、自らの胸から微かに滲み出ていた光と、あまりにもよく似ていたのだ。
鏡は未来を映していたのではない。
あれは、メッセージだった。
未来の『僕』が、過去の『僕』に向けて送った、魂の叫びだったのだ。
全てのピースが、音を立ててはまっていく。『感情の穴』は、未来からの時空の裂け目。感情が完全に枯渇し、滅びゆく未来の世界から、失われた『愛情』を求めて時間を逆流してきた、悲しみの奔流。未来からの『涙』だ。
そして、僕は。
僕は世界から遅れていたのではなかった。
常に、ほんの数秒だけ、世界の『未来』を生きていたのだ。
僕が『観測者』だったのだ。
僕が見ていた人々は『残像』ではなかった。それは、僕がいる未来の時点から見た、正真正銘の『過去』の姿だった。だから人々は僕の行動を予知しているように見えた。違う。僕が未来にいるから、彼らの行動は僕にとって当然の反応に過ぎなかったのだ。僕はずっと、誰よりも早く、未来から送られてくる世界の悲鳴を、その警告を、孤独のうちに受け取り続けていた。
第六章 最後の選択
世界を救う方法は、一つしかない。未来からの『涙』である『感情の穴』に、失われた『愛情』を注ぎ込み、時間を逆行させて未来の世界へ送り届けること。未来が救われれば、その原因である過去、つまり僕らの現在もまた、その歪みから解放される。
だが、それには途方もないほどの純粋な『愛情』が必要だった。鏡に映った、あの燃えるような桃色の光。あれを捧げられるのは、世界でただ一人。未来の自分が、その全てを託そうとした相手。
この僕しかいない。
陽菜への想い。家族への感謝。この不器用な世界そのものへの、名付けようのない愛おしさ。僕の中に燻っていた感情の全てが、最後の灯火のように燃え上がった。これを捧げれば、世界は救われる。だが、それは僕自身が、感情という人間性の核を完全に失うことを意味していた。
それでも、構わなかった。
僕が見ていた桃色の残像は、未来の僕がすでに成し遂げた、自己犠牲の『残光』だったのだ。彼は、この選択を過去の自分に託すために、ずっと孤独なメッセージを送り続けていた。数秒遅れの会話も、人々の残像も、全ては未来の僕から現在を生きる僕への、道標だったのだ。
「行くよ」
僕は誰に言うでもなく呟き、『虹色の鏡』を強く握りしめ、藍色の穴へと向かって歩き出した。
第七章 残光の観測者
渦巻く『感情の穴』の前に立ち、僕は『虹色の鏡』を静かに掲げた。陽菜の笑顔を思い浮かべる。彼女と交わした、数秒遅れの他愛ない会話。その一つ一つが、僕の世界を彩る、かけがえのない宝物だった。ありがとう。ごめん。そして、愛している。言葉にならない想いの全てが、僕の胸から鮮烈な桃色の光となって溢れ出し、鏡に吸い込まれていく。
光は激しさを増し、一本の巨大な光線となって『感情の穴』の中心へと突き刺さった。藍色の闇が桃色の光に飲み込まれ、浄化されていく。空を覆っていた藍色の霧が晴れ、世界にゆっくりと、ゆっくりと、失われたはずの温かな色が戻り始めた。戸惑いながらも互いを見つめ合う人々から、再び淡い桃色のオーラが立ち上り始めるのが見えた。
僕の胸から、最後の光の粒子が離れた瞬間、僕の世界から一切の色と感覚が消え失せた。喜びも、悲しみも、もう感じない。僕は、ただそこに存在するだけの、完全な『観測者』となった。
その時、数秒遅れの世界から、陽菜の声が届いた。
「ありがとう、朔」
それは、僕が感情を捧げる数秒前の、過去の彼女が発した感謝の言葉だった。僕にはもう、その言葉に応える感情は残っていない。
それでも、僕の口元には、微かな笑みが浮かんでいた。
僕が救った未来。人々が再び愛を取り戻したこの世界。
その光景だけが、色を失った僕の目に焼き付いている。
それこそが、未来の僕が過去の僕に送り続けた、たった一つの希望の残光だったのだから。