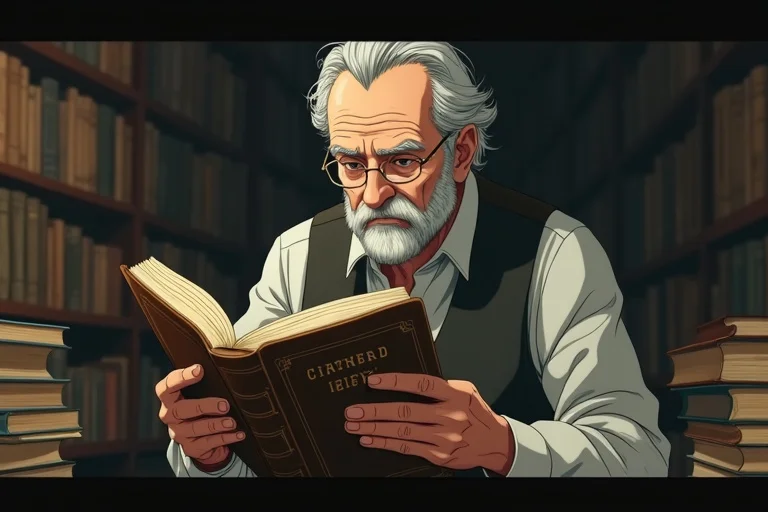第一章 夢の残滓
僕の働く古書店には、かびと古紙の匂いが満ちている。客と交わす言葉は、いつもどこか曖昧だ。「この本は、面白い…のかもしれませんね」「ええ、そんな気がします」。この街では、誰もが言葉の輪郭をぼかして生きていた。断定は、存在を希薄にする毒なのだ。
先日も見た。広場の噴水前で、旅人らしい男が声を張り上げた。「この街の方角は、真北だ!」。その言葉が空気に溶けた瞬間、男の体は陽炎のように揺らぎ、向こう側の景色が透けて見えた。人々は目を逸らし、まるで何も見なかったかのように足早に去っていく。それが、僕らの世界の掟だった。真実を語る者は、その存在の確からしさを失う。だから僕らは、嘘と推量の霧の中を、手探りで歩くしかなかった。
昨夜、奇妙な夢を見た。空には緑色の月が浮かび、湖畔には巨大な硝子の樹が聳え立っていた。風が吹くたび、樹の葉は風鈴のように澄んだ音を奏でる。僕はその根元に座り、水面を渡る冷たい空気を吸い込んでいた。あまりに鮮明で、まるで第二の現実のようだった。
そして、今朝。目を覚ました僕の枕元には、湿った黒土と苔の匂いが微かに漂っていた。シーツの上には、夢で見た湖畔に転がっていたはずの、小さな石が一つ。それは手のひらに収まるほどの大きさで、月光を吸い込んだかのように白銀に輝いていた。ひんやりとした感触が、夢の残滓ではないことを告げている。石の表面には、僕の知らない文字が一つ、静かに彫り込まれていた。
第二章 ささやく記号
それから毎晩、僕は硝子の樹の夢を見た。夢は夜を重ねるごとに深度を増し、現実への侵食を始めた。ある朝には部屋中に深い霧が立ち込め、またある時には、ベッドの脇に夢の中の湖と同じ、小さな水たまりができていた。僕はその度に、現実世界に複製された『白銀の小石』を見つけた。部屋の隅には、いつしか十を超える小石が転がっていた。
そして、夢の中に『彼』が現れた。
硝子の樹の根元に、いつの間にか一人の男が立っていた。深いローブで顔は窺えず、その姿はまるで影の染みだ。だが、他の何よりも異質だったのは、彼が決して半透明にならないことだった。彼は僕に向かって、淀みなく語りかける。
「■■は欠け、▲▲▲が満ちる。時の揺りかごで、○○○が目覚める」
彼の言葉は、意味をなさない記号の羅列としてしか僕の耳には届かなかった。しかし、その声には奇妙な説得力があった。まるで失われた言語で世界の真理を説いているかのように。彼はこの世界で禁忌とされる『真実』を語り続けている。だというのに、彼の存在が揺らぐ気配は微塵もなかった。
僕は恐怖と好奇心に引き裂かれながら、彼の正体を探ろうとした。問いかけても、返ってくるのは理解を超えた記号の囁きだけ。現実で増え続ける白銀の小石と、夢の中の謎めいた語り部。僕の世界の輪郭は、内外から静かに、だが確実に歪み始めていた。
第三章 揺らぐ輪郭
「ユキ。最近、あなたの周りの空気が、少し湿っているような気がしないでもないわね」
古書店のカウンターで、同僚のサラがそう言った。彼女は指先で埃を払いながら、僕の顔を覗き込む。彼女の言葉は、この世界なりの最大限の懸念表明だった。僕は乾いた笑みを返すしかない。「気のせい…じゃないかな。多分」。嘘は、この世界における優しさの一つだ。
だが、侵食はもう僕一人の問題ではなくなっていた。僕が古書店に持ち込んでしまった小石の一つが、棚の隙間から床に転がり落ちたのだ。カラン、と乾いた音が響く。それは、この曖昧な世界にはそぐわない、あまりに確かな存在感のある音だった。
サラが息を呑むのがわかった。彼女はゆっくりと屈み、その白銀の小石を指先で恐るおそる撫でた。
「これ…、石…よね? とても、はっきりしている…」
彼女の瞳が恐怖に揺れる。夢の産物が、他者の現実にまで干渉を始めたのだ。この世界ではありえない、『実体』を持つ奇跡、あるいは呪い。
「どこでこれを…?」
僕は答えられない。真実を語れば、僕の体は半透明に溶けてしまうだろう。僕が口ごもるのを見て、サラはそれ以上何も聞かなかった。ただ、彼女の眼差しには、僕を心配する色が、霧のように滲んでいた。
第四章 真実の代償
転機は、唐突に訪れた。街の中心にある時計塔の鐘が、乾いた硝子の音色を響かせたのだ。人々が空を見上げると、灰色の雲の切れ間から、夢で見た硝子の樹の枝が巨大な影となって伸びていた。街はパニックに陥ったが、誰もその現象を「真実」として口にできない。「あれは、何かの見間違いかもしれない」「巨大な鳥の影…という可能性もあるだろう」。曖昧な言葉が虚しく飛び交う中、世界の法則そのものが軋みを上げていた。
その夜の夢は、嵐のようだった。硝子の樹は激しく揺れ、湖は荒れ狂っていた。語り部は僕の目の前に立ち、初めてそのローブの袖から手を伸ばした。氷のように冷たい指が、僕の額に触れる。
瞬間、僕の脳裏に無数のイメージが流れ込んできた。
――白髪の老人が、ベッドの上で静かに目を閉じている。彼の部屋の窓からは、僕らの住む街並みが見えた。彼の浅い呼吸に合わせて、街の建物が陽炎のように揺らいでいる。彼こそが、この世界の『作者』。この世界は、彼の見てきた永い夢そのものだった。
――語り部は、その老人が夢の終焉を前にして、無意識のうちに生み出した存在。次の『作者』へと世界を引き継ぐための、案内人。
――そして、僕がいた。無数の候補者の中から、最も鮮明な夢を見る者として、新しい世界の『作者』に選ばれたのだ。
幻視の奔流が止むと、語り部は一度だけ、僕に理解できる言葉を紡いだ。その声は、ひび割れたガラスのようだった。
「この世界は、まもなく終わる」
それは、紛れもない『真実』だった。語り部の体は激しく光を放ち、その輪郭が砂のように崩れ始める。彼は自らの存在を代償に、僕に最後の真実を伝えたのだ。消えゆく彼の影を見つめながら、僕はただ、立ち尽くすことしかできなかった。
第五章 白銀の選択
夢から覚めた僕の手には、ずっしりとした重みがあった。握りしめていたのは、今まで集めたものより遥かに多い、無数の白銀の小石だった。震える指でそれらをベッドの上に広げる。小石に彫られた文字は、もはや意味不明な記号ではなかった。
『空』『水』『光』『悲しみ』『喜び』『愛』
それは、世界を構成する言葉の原型。新しい世界の設計図だった。
窓の外に目をやると、世界は終焉を迎えていた。建物は輪郭を失って溶け落ち、アスファルトは砂に還っていく。人々は半透明の幽霊のように街をさまよい、その姿も徐々に薄れていた。前の作者の夢が、尽きようとしている。世界の、静かな死。
その時、アパートのドアが激しく叩かれた。サラだった。息を切らして駆け込んできた彼女の体もまた、向こう側が透けて見え始めている。
「ユキ…! 世界が…、まるで嘘みたいに消えていくの…!」
彼女の悲痛な声が、僕の心を抉る。
僕は悟った。僕が新しい世界を『語る』ことで、この崩壊は止められる。白銀の小石を使い、新たな現実を創り出すことができる。だが、それは僕がこの世界の法則を超越した、孤独な『語り部』になることを意味していた。真実を語るたびに、僕は人間としてのユキから遠ざかっていくのだろう。それは、永遠の孤独という名の神託だった。
第六章 新しい夢の夜明け
僕は、決意した。
崩れゆく部屋の中で、サラの半透明な手を握る。まだ、温もりがあった。この温もりを失いたくない。彼女が存在する世界を、僕は望んだ。
僕は彼女の瞳をまっすぐに見つめ、最初の『真実』を口にした。
「君は、ここにいる」
その言葉が紡がれた瞬間、僕の体は内側からまばゆい光を放ち、輝くように半透明になった。だがそれは消滅の兆候ではなかった。世界の創造主としての、変質の始まりだった。対照的に、僕の言葉を受けたサラの輪郭は、急速に色を取り戻し、確かな実体としてそこに立ち現れた。彼女は驚きに目を見開いている。
僕は足元に散らばる白銀の小石を一つ、拾い上げた。『空』と彫られた石だ。
「空は、澄んだ青色になる」
言葉と共に、窓の外の崩壊が止まり、柔らかな青空が広がり始めた。
次に『風』の石を手に取る。
「風は、悲しみを癒すように優しく吹く」
部屋を、心地よい風が吹き抜けていく。
僕はもう、ユキという個人ではなかった。世界の理を紡ぐ、ただ一人の『語り部』となった。僕は、僕が愛したサラや、名も知らぬ人々が存在できる世界を創り続ける。
「そして、人々は…」
僕はそこで一度言葉を切り、サラの顔を見た。彼女の頬を涙が伝っている。僕は、彼女に微笑みかけた。それはきっと、人間としての僕が見せる、最後の笑顔だった。
「時々、恐れることなく、本当のことを話せる世界になる」
僕は孤独な創造主になった。だが、僕の創り出すこの新しい世界で、僕が愛した者たちが、今度は本当の言葉で笑い合うだろう。その光景を永遠に見守り続けることだけが、僕に残された、たった一つの喜びだった。
白銀の小石が、僕の手の中で静かに光を放っていた。