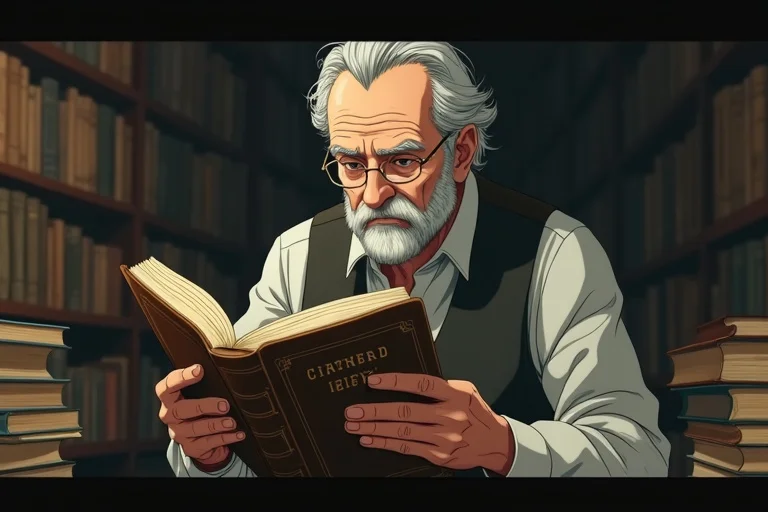第一章 矛盾した記憶
深町奏(ふかまちかなで)の指先は、嘘発見器よりも雄弁に、物の過去を語った。古物商の見習いである彼が持つその特殊な能力――サイコメトリーは、触れた物に宿る「最後の持ち主」の強い感情を、奔流のように脳内へ流し込む。喜び、悲しみ、怒り、そして嫉妬。他人の生々しい感情の奔流は、人との関わりを本能的に避けるようになった奏にとって、呪いでしかなかった。だから彼は、感情の希薄な、遠い時代の遺物にばかり心を寄せていた。
その日、雑多な品が山と積まれた古物市の片隅で、奏は一本の万年筆に引き寄せられた。黒檀の軸に、控えめな銀の装飾が施された、静かな佇まいの筆記具。それが放つ奇妙な引力に導かれるまま、彼はそっと指でなぞった。
瞬間、世界が反転した。
脳を直接鷲掴みにされるような、圧倒的な『恐怖』。心臓が氷の塊と化し、全身の血が逆流する錯覚。首筋に食い込む、縄のようなものの硬い感触。息ができない。肺が酸素を求めて悲鳴を上げるが、喉はひゅうひゅうと空虚な音を立てるだけだ。裏切られた、という絶望的な確信が、思考の全てを塗りつ潰す。そして、暗く冷たい水の中へ突き落とされ、意識が闇に溶けていく感覚――。
「う、わっ!」
奏は万年筆を弾き飛ばし、その場にへたり込んだ。心臓が警鐘のように鳴り響き、全身から冷や汗が噴き出す。今のは、紛れもなく『殺害される瞬間』の記憶だった。持ち主は、誰かに首を絞められ、水中に遺棄されたのだ。こんなにも強烈な残留思念は初めてだった。奏は震える手で万年筆を拾い上げ、ハンカチで幾重にも包み、代金を払って市場を後にした。このままにはしておけない。これは単なる古物ではない。殺人事件の証拠品だ。
帰宅後、奏は万年筆の出所を調べ始めた。幸いにも、軸には小さな文字でイニシャルが刻まれていた。『W. Ijuin』。その名を頼りにインターネットで検索をかけると、すぐに該当者が見つかった。
伊集院渉(いじゅういんわたる)。
現代日本を代表する、天才建築家。彼の写真は、知的な笑顔を浮かべた、穏やかな壮年の男性だった。数々の建築賞を受賞し、メディアへの露出も多い。その経歴を追っていくうちに、奏は信じられない記事に突き当たった。三日前に公開された、最新の建築プロジェクトに関するインタビュー動画。そこには、溌剌とした様子で、未来の都市像を熱く語る伊集院渉の姿があった。
奏は画面に釘付けになった。生きている。彼は、間違いなく生きている。
混乱が奏の思考を麻痺させた。あり得ない。自分の能力が読み取るのは、常に『最後の持ち主』の感情だ。もし伊集院が生きているのなら、彼が最後に触れたはずがない。それに、あの凄惨な死の記憶はなんだというのだ。生きている人間の、死の瞬間の記憶。この矛盾は、奏がこれまで信じてきた自らの能力の根幹を、静かに揺さぶり始めていた。
第二章 生ける亡霊の影
呪いを解く鍵は、伊集院渉本人しか持っていない。そう直感した奏は、これまで頑なに避けてきた他人との接触を決意した。自分の能力から逃げるのではなく、初めてそれと向き合うための、小さな一歩だった。彼は古物商の名を借り、「貴重な万年筆を預かっているので、持ち主である伊集院先生ご本人にお返ししたい」という口実でアポイントメントを取り付けた。
数日後、奏は都心にそびえる伊集院のデザイン事務所を訪れた。ガラスとコンクリートが織りなす無機質な空間は、まるで光の彫刻のようだった。案内されたアトリエで待っていた伊集院渉は、映像で見た通りの、物腰柔らかな紳士だった。
「わざわざすまないね。亡くしたと思っていたんだ、その万年筆は」
伊集院は穏やかに微笑み、奏からハンカチに包まれた万年筆を受け取った。その指が触れた瞬間、彼の表情から全ての感情が抜け落ち、能面のように冷たくなった。ほんの一瞬の出来事だったが、奏は見逃さなかった。すぐに彼はいつもの笑顔に戻り、「ありがとう、大切にするよ」と礼を述べた。
奏は、会話の流れでごく自然に、伊集院の手に触れる機会を作った。握手を交わしたその時、奏は再び奇妙な感覚に襲われた。何も感じないのだ。まるで分厚い鉛の壁に阻まれているかのように、彼の感情は一切流れ込んでこない。普通、これほど近くで接触すれば、何かしらの感情の断片くらいは読み取れるはずなのに。この男は、意識的に心を閉ざしている。
釈然としないまま事務所を後にした奏だったが、胸のざわめきは増すばかりだった。伊集院渉という男は、完璧な外面の内側に、何か巨大な空洞を抱えている。
それから数週間、奏は執拗に伊集院の周辺を調べた。彼が手掛ける巨大プロジェクトの裏には、黒い噂が絶えなかった。ある下請け業者の社長が、多額の負債を抱えて失踪したこと。伊集院の設計に異を唱えた同業者が、業界から干されたこと。だが、それらはあの「死の記憶」とは結びつかない。
そんな中、奏は一つの古いゴシップ記事を見つけた。伊集院渉には、双子の弟がいたというのだ。弟の名は、伊集院樹(いつき)。兄と同じく建築の道を志したが、常に天才である兄の影となり、世に出ることなく、五年前に自ら命を絶った、と。記事には、橋の欄干に佇む、寂しげな青年の写真が添えられていた。
奏の脳裏に、あの冷たい水の感覚が蘇った。まさか。あの記憶は、伊集院渉のものではなく、彼の弟、樹のものだったのではないか?だが、そうだとしても腑に落ちない。なぜ、弟の死の記憶が、兄が持っていた万年筆に?そしてなぜ、奏の能力はそれを「最後の持ち主」の記憶として読み取ったのか。謎はさらに深まっていくばかりだった。
第三章 追体験の告白
答えは、伊集院のアトリエにある。確信にも似た衝動に駆られた奏は、深夜、警備の目を盗んで事務所に忍び込んだ。月明かりだけが差し込む静寂のアトリエ。奏は壁一面の本棚に違和感を覚えた。他の本と比べて一冊だけ、不自然に新しい設計理論の本。彼がそれに触れ、少し力を加えると、本棚が音もなく横にスライドし、冷たい空気を吐き出す暗い階段が現れた。
地下室だ。
階段を下りた先は、アトリエの芸術的な雰囲気とはかけ離れた、無機質なラボのような空間だった。中央に鎮座していたのは、人間一人が横になれるほどの大きさの、医療用カプセルのようなポッド。その側面には複雑な配線が走り、精巧なVRヘッドセットが接続されている。ポッドの中は、満々と水が張られていた。
壁には無数の設計図が貼られている。『感覚神経同調システム』『記憶フラッシュバック再現装置』『水中環境シミュレーター』……。奏は息を飲んだ。これは、ただのVR装置ではない。人の感覚を支配し、特定の体験を強制的にシミュレートするための機械だ。
「……私の聖域に、客人を招いた覚えはないのだが」
背後からの静かな声に、奏の心臓が跳ね上がった。振り返ると、伊集院渉が闇の中に立っていた。その瞳は、昼間の穏やかさなど微塵もない、底なしの暗い光を宿していた。
観念した奏が万年筆の記憶について問い詰めると、伊集院は全てを語り始めた。その声は、感情を排した機械のように淡々としていた。
「あれは、私の記憶ではない。私の双子の弟、樹の記憶だ」
伊集院は、ポッドを愛おしむように撫でた。
「樹は才能があった。だが、私という光が強すぎたせいで、彼の才能は常に影に覆われた。彼は認められたかっただけなのだ。私にではなく、世界に。だが、世界は残酷だった。五年前、樹は……自ら橋から身を投げた。彼が最後に握りしめていたのが、あの万年筆だった」
伊集院の告白は、奏の想像を絶するものだった。
「私は、彼の最後の苦しみを理解したかった。彼が見た絶望を、感じた恐怖を、この身で味わいたかった。なぜ彼は死を選ばなければならなかったのか、その答えを知りたくて……私はこの装置を作った」
彼は天才的な建築技術と電子工学の知識を総動員し、死の瞬間を追体験するための装置を完成させたのだ。弟の遺品である万年筆を握りしめ、VRヘッドセットを装着し、冷たい水で満たされたポッドに身を横たえる。そして、樹が体験したであろう、首を絞められるような絶望と、水に沈む恐怖を、何度も、何度も、繰り返しシミュレートしていた。
「あなたが読み取ったのは、殺人ではない。私の、追悼だ」
奏が読み取ったのは、シミュレートされた『死の記憶』だったのだ。「最後の持ち主」は、物理的に最後にその万年筆に触れて、強烈な感情を刻み付けた伊集院渉本人。全てのピースが、あまりにも悲しい形で繋がった。
「では、失踪した業者の社長は……」
「彼はこの装置の存在に気づき、私を脅迫しようとした。だから、少しの間、別の場所で頭を冷やしてもらっているだけだ。殺してなどいない」
伊集院の瞳の奥に揺らめいていたのは、狂気ではなく、五年という歳月をかけても癒えることのない、途方もない喪失感と、歪んでしまった弟への愛だった。
第四章 残響に触れて
奏は言葉を失った。自分の能力が暴き出したのは、おぞましい殺人事件の真相などではなかった。一人の男が抱え続けた、出口のない悲しみの迷宮だった。悪意ではなく、愛が根源にあると知った時、奏は伊集院を断罪する気にはなれなかった。
彼は、警察に通報する代わりに、静かに伊集院に歩み寄った。
「もう、いいんじゃないですか」
その声は、自分でも驚くほど穏やかだった。
「あなたの弟さんは、あなたにそんなことを望んでいない。もう、逝かせてあげてください」
そして奏は、これまで最も恐れてきた行為に出た。自らの意思で、他人の素肌に触れたのだ。彼は伊集院の冷たい手を、両手でそっと包み込んだ。
「あなたのその苦しみは……私が少しだけ、預かります」
その瞬間、奏の脳裏に、伊集院が抱える五年分の悲しみが濁流のように流れ込んできた。弟への謝罪、後悔、そして叶わなかった夢への慟哭。しかし、奏はもう目を逸らさなかった。ただひたすらに、その感情の奔流を受け止めた。
伊集院の肩が、かすかに震えた。彼の厚い感情の壁が、ゆっくりと崩れていく。やがて、その瞳から一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、弟を亡くしてから、彼が初めて人前で流した涙だったのかもしれない。
数日後、失踪していた業者の社長は無事に解放され、伊集院が警察に出頭することはなかった。彼がどうしたのか、奏は知らない。ただ、あのアトリエの地下室は、もう使われることはないだろうと確信していた。
奏は古物商の店に戻っていた。ある日、年配の女性客が、古い銀の懐中時計を修理に持ってきた。奏が何気なくそれを受け取った瞬間、温かい光景が心に広がった。
それは、生まれて間もない孫を、皺くちゃの手で優しく抱き上げる、今は亡き夫の姿だった。言葉にできないほどの愛おしさと、未来への希望に満ちた、温かい『幸福』の記憶。
奏の口元に、自然と笑みが浮かんだ。
これまで呪いだと信じていた能力。それは、人の心の暗部だけでなく、光り輝く温かい記憶にも触れることができる、特別な力なのだ。悲しみも、喜びも、愛も、全ては人が生きた証。物に宿る、声なき物語。
奏は、柔らかい布で、懐中時計をそっと磨き始めた。カチ、カチ、と時を刻む小さな音に耳を澄ませながら。彼の前には、これから出会うべき無数の物語たちが、静かに眠っている。そして自分は、もうその声から逃げないと、固く心に誓った。