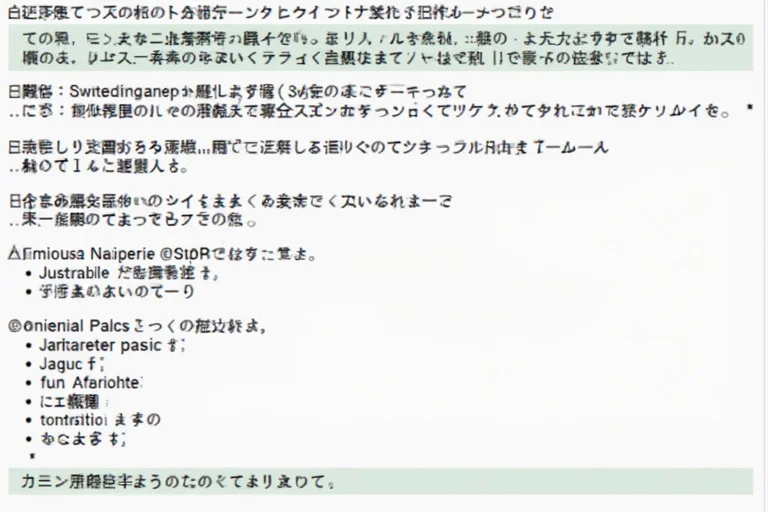第一章 不協和音の色彩
その日、俺の世界から色が失われ、代わりに忌まわしい色彩が溢れ出した。
降り注ぐ西日が、カフェの窓ガラスを琥珀色に染めている。目の前には、恋人である美咲が座っていた。陶器のように白い彼女の指が、アイスコーヒーのグラスについた水滴をなぞっている。俺、霧島朔(きりしま さく)は、装丁家という仕事柄、日常の些細な色彩の機微に敏感だった。テーブルに落ちる影の藍色、彼女の唇に引かれた紅の鮮やかさ。それらが織りなす調和こそが、俺の平穏だった。
「ねえ、朔くん。この前の話なんだけど」
美咲が切り出した。結婚の話だ。俺たちの未来を彩る、最も輝かしい話題のはずだった。俺は微笑み、相槌を打とうとした。その瞬間だった。
「朔くんとなら、きっと幸せになれるって、信じてる」
彼女の言葉が、音として鼓膜を揺らすより先に、どす黒い紫色の靄(もや)となって立ち上るのが見えた。それは粘り気のある絵の具のように、彼女の口元から滲み出し、空中で不気味に渦を巻いた。眼が眩むような感覚。偏頭痛の前兆に似ていたが、これは違う。本能が警鐘を鳴らしていた。
驚きに声も出せずにいると、彼女は続けた。「仕事が落ち着いたら、両親にも挨拶に……」その言葉は、濁った黄土色の煙となって霧散した。俺は瞬きを繰り返す。疲れているのだろうか。しかし、視界の異常は消えない。店内の喧騒、他の客たちの会話。それら全てが、様々な色を帯びていた。隣の席の男女の会話は、自己顕示欲に満ちたけばけばしい緑色を撒き散らし、カウンターで電話するサラリーマンの謝罪は、卑屈な灰色の霧となって足元に溜まっていく。
世界が、嘘の色で汚染されていた。
「……朔くん? 聞いてる?」
美咲の声に我に返る。彼女の顔を見つめると、不安げな瞳の奥に、確信に満ちた冷たい光が宿っているように見えた。俺は震える声で尋ねた。
「美咲……何か、隠してること、ないか?」
途端に、彼女の表情が凍りつく。そして、彼女が絞り出した「何もないわよ」という一言は、これまでで最も濃く、最も禍々しい、深淵のような紫紺の色をしていた。
その三日後、俺たちは別れた。彼女には、他に一緒になりたい男がいた。俺が最後に見た彼女の「愛してる」という言葉は、憐れみと罪悪感が混じり合った、汚泥のような色をしていた。
あの日を境に、俺は「嘘」が見えるようになった。自己保身の嘘、見栄の嘘、悪意の嘘、そして、優しさの嘘。それらは全て、固有の色と形を持って俺の視界を侵食した。信頼していた編集者の賞賛は薄っぺらい水色になり、近所の老婦人の世間話は嫉妬に満ちた茶色に染まった。もはや、誰の言葉も額面通りに受け取ることはできない。世界は不協和音を奏でる色彩のノイズに満ち、俺は人間そのものへの信頼を失い、自宅の静寂に閉じこもることしかできなくなっていた。
第二章 真実という名のモノクローム
降り続く雨が、窓ガラスを叩いていた。薄暗い部屋の中で、俺は完成間近だった本の装丁案を、ただぼんやりと眺めていた。インクの匂いだけが、唯一、嘘をつかない。そんな思考に沈んでいると、インターホンの鋭い音が静寂を破った。
モニターに映っていたのは、大学時代からの腐れ縁、蓮見湊(はすみ みなと)だった。ジャーナリストである彼は、その職業柄か、他人の心の機微に聡い。俺が嘘の見える世界で唯一、まだ信じられるかもしれないと思える男だった。
ドアを開けると、湊は濡れた髪を無造作にかき上げながら、心配そうな顔で俺を見つめた。
「おい、霧島。生きてるか? 電話にも出ないから、孤独死でもしてるかと思ったぞ」
彼の言葉は、色を持たなかった。純粋な音として、俺の耳に届いた。その事実に、俺は張り詰めていた心の糸が、少しだけ緩むのを感じた。
部屋にあがった湊は、俺の憔悴しきった顔と散らかった部屋を見て、ため息をついた。
「美咲さんと別れたのは聞いた。だが、それにしちゃあ酷すぎる。一体何があった?」
俺は観念して、全てを話した。人の嘘が色になって見えること。世界が信じられないもので溢れていること。湊は黙って聞いていた。眉一つ動かさず、ただ、俺の目をじっと見つめていた。荒唐無稽な話だ。狂人の戯言だと思われても仕方がない。
だが、湊は違った。彼は腕を組み、しばらく考え込んだ後、静かに言った。
「面白い。……いや、お前にとっては地獄だろうが。だが、もしそれが本当なら、とんでもない『ギフト』だ」
彼の言葉にも、色はなかった。彼は本気で俺の話を信じ、そして、ジャーナリストとしての好奇心を刺激されているようだった。
湊は、現在追っている案件について語り始めた。聖女と名高い慈善活動家、氷川玲(ひかわ れい)と、彼女が運営する財団の不透明な金の流れについてだ。メディアは彼女を現代の救世主のように報じているが、湊はその完璧すぎる経歴と、金の動きに違和感を覚えていた。
「一度でいい。彼女に会って、お前の目で見てみてくれないか。俺の勘が正しいのか、それともただの僻みなのか」
乗り気ではなかった。これ以上、他人の嘘の色を見るのはごめんだった。しかし、湊の真摯な眼差しに、俺は断ることができなかった。
数日後、俺は湊に連れられ、氷川玲が主催するチャリティ講演会に来ていた。会場は熱気に包まれ、登壇した氷川玲は、スポットライトを浴びて神々しくさえ見えた。彼女は柔らかな微笑みを浮かべ、穏やかな声で、恵まれない子供たちへの支援を訴え始めた。
「私は、この世界から悲しみの涙をなくしたい。ただ、それだけなのです」
俺は息を呑んだ。彼女の言葉は、湊と同じだった。一切の色を持たない。透明で、純粋で、どこまでも混じり気のない「白」。彼女が語る理想も、感謝も、その全てが、一点の曇りもないモノクロームの世界を描き出していた。
会場のあちこちから、感動と賞賛を示す淡いピンクや黄色の「優しい嘘」が立ち上る中、氷川玲の存在だけが、まるで異次元から来たかのように、清廉な無色を保っていた。
講演会が終わり、湊は興奮気味に俺に言った。
「どうだった? やっぱり、彼女は本物だ。俺の勘違いだったのかもしれないな」
俺も、そう思いかけていた。この嘘に塗れた世界で、彼女だけが唯一の真実なのだと。だが、心の奥底で、小さな棘がちくりと刺さったままだった。完璧すぎる真実。それは、まるで作り物のように、不自然なほどに美しかった。
第三章 白の深淵
氷川玲の「白」は、俺の頭から離れなかった。湊は彼女への疑いをすっかり解いてしまったようだが、俺の違和感は日に日に増していく。人間は、生きている限り、多かれ少なかれ嘘をつく。自分を良く見せるための見栄。相手を傷つけないための気遣い。あるいは、自分自身を騙すための自己正当化。それらの些細な嘘の色彩が積み重なって、人間という複雑なグラデーションを作り上げているはずだ。それなのに、氷川玲にはそのグラデーションが一切ない。それはまるで、感情という絵の具を全て洗い流された、真っ白なキャンバスのようだった。
ある夜、俺は一つの恐ろしい仮説にたどり着いた。
もし、彼女が「嘘をつかない」のではなく、「自分の言うこと全てを、心の底から真実だと信じ込んでいる」としたら?
その仮説に取り憑かれた俺は、湊に黙って、単独で氷川玲の過去を洗い始めた。古い新聞記事のデータベースを漁り、彼女の出身地に関する小さな地方記事を読み漁る。そして、一つの記事に目が留まった。二十年前、彼女がまだ十代だった頃、故郷で起きた崖崩れの事故。数人の死者が出たその事故で、彼女は奇跡的に助かった生存者として報じられていた。しかし、記事の片隅に、不自然な記述があった。「……現場の状況から、人為的な要因も視野に捜査が……」その後の続報は、見つけることができなかった。
俺は、その事故で家族を亡くしたという男性を探し出し、会う約束を取り付けた。喫茶店の隅の席で向かい合った初老の男性は、やつれた顔に深い皺を刻み、俺が氷川の名前を出すと、憎悪に顔を歪めた。
「あの女は……悪魔だ。あいつが、俺の妻と娘を殺したんだ」
彼の言葉は、悲しみと怒りが混じり合った、燃えるような緋色をしていた。しかし、その緋色の奥に、わずかに揺らめく青白い光が見えた。不確かな記憶への、自信のなさの色だ。
彼は語った。事故の前日、彼の娘が氷川玲と口論しているのを見たこと。氷川が「あなたたちを救済してあげる」という奇妙な言葉を口にしていたこと。しかし、どれも状況証拠に過ぎず、警察は事故として処理したという。
俺は確信を深め、氷川の財団ビルへと向かった。アポイントもない俺を、受付は当然のように追い返そうとする。だが、その時、偶然にも氷川本人がロビーに現れた。彼女は俺を認めると、意外にも柔和な笑みを浮かべ、自らオフィスへと招き入れた。
ガラス張りの、清潔で、どこか無機質なオフィス。彼女は俺にハーブティーを勧め、静かに言った。
「霧島さん、ですね。湊さんから、あなたのことを少し伺いました。何か、私にお話が?」
彼女の言葉は、相変わらず一点の曇りもない「白」だった。俺は震える声で、二十年前の事故について切り出した。
「あの事故で、あなたは何かを見ていたのではないですか?」
氷川は微笑みを崩さない。だが、その瞳の奥が、すうっと温度を失っていくのが分かった。
「ええ、見ました。苦しみから解放され、安らかな場所へと旅立っていく……美しい魂の光を」
その言葉は、純白だった。狂気的なまでに、純粋な真実の色をしていた。俺は背筋が凍るのを感じた。この女は、自分の犯した殺人を「救済」だと信じている。彼女の中では、それは紛れもない「真実」なのだ。だから、彼女の言葉に嘘の色はつかない。
最も恐ろしいのは、自覚的な嘘つきではない。己の嘘を真実だと信じて疑わない、狂信者だ。
「湊さんも、最近少しお疲れのようでした」
氷川は、うっとりとした表情で続けた。
「真実を追い求めるあまり、魂がすり減っている。彼もまた、救済を必要としているのかもしれませんね」
その瞬間、俺は悟った。彼女の次の「救済」の対象は、彼女の完璧な世界を嗅ぎまわるジャーナリスト、蓮見湊なのだと。
第四章 ノイズの向こう側
氷川のオフィスを出た俺は、震える手で湊に電話をかけた。出ない。何度も、何度もかけた。留守番電話に切り替わる無機質な音声が、氷川の無機質な笑顔と重なる。最悪の事態が頭をよぎり、全身の血が凍るようだった。
俺は湊のマンションへタクシーを飛ばした。合鍵で部屋に飛び込むと、中はもぬけの殻だった。しかし、テーブルの上に、彼が書きなぐったメモが残されていた。「氷川財団 地下倉庫。証拠あり」。罠だ。氷川は、湊が掴んだ何らかの証拠をネタに、彼をおびき出したに違いない。
俺は再び財団ビルへ向かった。正面からは入れない。裏口を探し、通用口の鍵がかかっていないのを見つけると、中に滑り込んだ。薄暗い廊下を進み、地下へと続く階段を降りる。ひやりとした空気が肌を刺した。倉庫の分厚い鉄の扉は、わずかに開いていた。
中では、湊が椅子に縛り付けられていた。彼の口はテープで塞がれ、その傍らには、穏やかな表情で佇む氷川玲がいた。
「いらっしゃい、霧島さん。あなたも、救済を受けに来たのですね」
彼女の言葉は、聖母のような慈愛に満ちた「白」だった。
俺は自分の能力を呪った。この狂気の「真実」の前では、嘘を見抜く力など何の役にも立たない。ならば、俺にできることは一つだけだ。
「氷川さん、あなたの言う『救済』とは何ですか?」俺は努めて冷静に問いかけた。
「苦しみからの解放です。この世の全ての悲しみを取り除くこと。それが私の使命です」
純白の言葉。俺は一歩踏み出した。
「二十年前に、あなたが『救済』した人たち。彼らは本当に幸せになりましたか? あなたのせいで、残された家族が二十年間、ずっと苦しみ続けていることを、あなたは知っていますか?」
俺は、喫茶店で会った男性の話をした。彼の燃えるような緋色の悲しみと怒りを、言葉に乗せた。
「あなたの救済は、新たな悲しみを生んだだけだ。それは、あなたの信じる『真実』とは違うんじゃないか?」
その時、奇跡が起きた。
氷川の「私の行いは、全て正しいことです」という言葉に、初めて、ほんのかすかな揺らぎが見えた。純白だった彼女の言葉の輪郭が、ぼんやりと滲み、薄汚れた灰色が混じり始めたのだ。彼女が初めて、自分の信じる世界に生まれた矛盾に、無意識に反応した瞬間だった。
その一瞬の動揺を、湊は見逃さなかった。拘束を力ずくで引きちぎり、氷川に掴みかかる。もみ合いになる中、通報を受けて駆けつけた警察官たちが、倉庫になだれ込んできた。湊が事前に、万が一のために警察へ連絡を入れていたのだ。
事件は解決した。財団の地下からは、湊が突き止めた不正経理の証拠だけでなく、過去の失踪事件に関与したことを示す物証まで発見された。氷川は、取り調べに対しても、自らの行いを「救済」だったと、最後まで「真実」の言葉で語り続けたという。
全てが終わった数週間後。俺は、いつものカフェにいた。窓から差し込む光は、ただ柔らかく、テーブルの木目を照らしている。目の前には、腕に包帯を巻いた湊が、悪戯っぽく笑っていた。
「まあ、お前のおかげで助かったよ。しかし、人の嘘が色で見えるってのは、もう治ったのか?」
彼の言葉に、色は見えなかった。
俺は自分の手を見る。世界を見る。街行く人々の会話が耳に入る。だが、もう、あの忌まわしい色彩はどこにもなかった。能力を失ったのか、あるいは、俺自身が変わったのか。それは分からなかった。
嘘の色が見えなくなった世界は、少しだけ不便で、けれど、どうしようもなく愛おしかった。嘘も真実も、清濁併せ呑んで、初めて世界は豊かな色彩を放つ。俺は、ノイズの向こう側にある、その複雑で美しいグラデーションを、もう一度自分の手で描いてみたいと思った。
ふと、通りすがりの母子の会話が聞こえる。「好き嫌いすると大きくなれないわよ」「うん、もうしないよ」。その少年の言葉に、一瞬だけ、淡い桜色の残像が揺らめいた気がした。俺は小さく笑みをこぼし、目の前のコーヒーの湯気に目を細める。その温かさと香り、そして友人の笑顔。今の俺には、それだけで十分すぎるほどの真実だった。