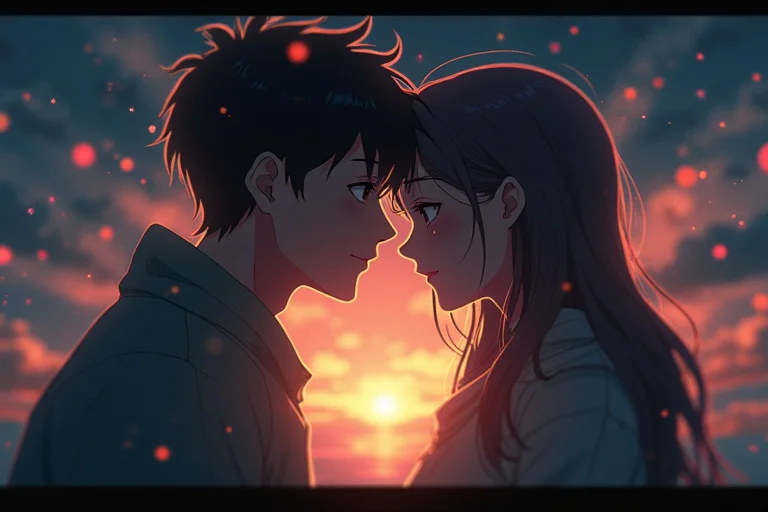第一章 昨日の私
ネオンの滲む路地裏で、俺はグラスに残った琥珀色の液体を揺らしていた。今日の名前はカイト。悪くない響きだ。バーカウンターの向こうで、白髪混じりのバーテンダーが退屈そうにグラスを磨いている。彼のくたびれた瞳に、俺は記憶の糸をそっと投げかけた。
――あんたは俺を十年以上知っている。俺は口数の少ない常連で、たまにこうしてツケで飲む。
微かな抵抗の後、彼の眉間の皺がふっと和らいだ。「カイトさん、また例ので?」と彼は呟く。俺は無言で頷いた。これで今夜の勘定は、存在しない過去へと消える。これが俺の能力。他人の精神に、さも当然のように記憶の断片を彫り込む力。
街の時計塔が、夜の終わりを告げる鐘の音を響かせ始めた。十一下五十分。人々は口々に、今日という一日を惜しむ言葉を交わす。それはまるで、毎夜繰り返される小さな葬儀のようだった。友人、恋人、家族。その温かい繋がりが、あと十分で泡のように融けていく。誰もがその刹那の別れに慣れ、そして諦めていた。
俺は店を出た。冷たい夜気が肺腑を刺す。街灯の下で立ち止まり、首から下げた銀色のペンダントに触れた。名前も模様も刻まれていない、ただ滑らかなだけの金属片。だが、それに指を重ねると、いつも名も知らぬ誰かの強い感情が流れ込んでくる。今夜は、深い、深い哀しみだった。
時計塔の針が真上を指す。世界から音が消え、そして――閃光。
目を開けると、見慣れないアパートの一室だった。いや、昨日まで俺が住んでいた部屋だ。頭の中に新しい名前が響く。リオ。今日から俺はリオだ。昨日のカイトという男の記憶は、古い映画のワンシーンのようにぼんやりと霞んでいる。これが世界の法則。忘却による、毎夜の救済。俺は窓を開け、新しい一日を吸い込んだ。
第二章 残響の欠片
リオとしての三日目の昼下がりだった。カフェの壁にかけられた大型スクリーンが、緊急ニュースを映し出す。テロップには『中央記録保管局への不法侵入者、現在も逃走中』とある。俺はぼんやりとコーヒーを啜っていたが、画面に映し出された監視カメラの粗い映像に、心臓が凍りついた。
黒いフードを目深にかぶった人物。その逃走経路。それは、俺がまだカイトだった夜、気まぐれに、ある情報屋の男に植え付けた偽の記憶そのものだった。組織の機密データ保管場所への最短ルート。冗談半分の、全くの作り話のはずだった。
なのに、映像の中の人物は、その架空のルートを寸分違わず進んでいる。そして、追っ手の黒服の男たちから逃げ延びていた。なぜ? 名前と共に個人的な記憶は曖昧になるはずだ。ましてや、他人に植え付けられた記憶など、真っ先に消え去るただのノイズに過ぎない。
「嘘だろ……」
喉から絞り出した声は、自分でも驚くほど震えていた。俺の能力が、意図しない形で現実を侵食している。あの人物は、俺が植え付けた記憶を、世界の法則を超えて保持している。
胸のペンダントが、じりじりと熱を帯びるのを感じた。指で触れると、脳裏に鋭い感情のフラッシュバックが突き刺さる。強い恐怖。そして、それを上回るほどの、燃えるような決意。映像の人物が抱いた感情だ。俺は席を立った。この謎を放置することは、自分自身を否定することに等しい。俺は彼女を、記憶の残響を追わなければならない。
第三章 銀色の導き
ペンダントが放つ微かな感情の痕跡だけが、俺の羅針盤だった。それはまるで、闇夜に瞬く消え入りそうな星の光を追いかけるような、心許ない追跡だった。彼女が駆け抜けたであろう雑踏、身を潜めたであろう廃ビル。その場所に立つたびにペンダントに触れると、焦燥、孤独、そして時折混じる不思議な安らぎといった感情の記憶が、波のように押し寄せては引いていった。
追跡の果てにたどり着いたのは、街の片隅にある古びた公立図書館だった。高い天井まで届く書架が迷宮のように入り組み、古い紙とインクの匂いが空気に澱んでいる。ペンダントの反応が、ここで最も強く脈打っていた。
俺は息を殺し、書架の影から影へと渡り歩く。そして、一番奥の歴史書のコーナーで、彼女を見つけた。床に座り込み、一冊の分厚い本を膝に広げている。フードは外され、月明かりが彼女の真剣な横顔を照らしていた。
俺がゆっくりと一歩踏み出した瞬間、彼女は弾かれたように顔を上げた。警戒に満ちた瞳が、俺を射抜く。
「誰?」
「あんたを探してた」
俺は両手を上げて敵意がないことを示す。彼女の視線が、俺の胸で光る銀色のペンダントに注がれた。その瞬間、彼女の瞳から警戒の色が薄れ、代わりに何かもっと深い、運命的な光が宿った。
「あなただったのね」彼女は静かに立ち上がった。「ずっと、探していた」
彼女の言葉に、俺は眉をひそめた。「俺を? どうして」
「あなたの記憶が、私をここに導いたから」
「名前は?」俺は尋ねた。この世界で最も不確かで、最も重要な問いかけだ。
彼女は、まるで当然のことのように答えた。
「エリス。昨日も、その前も、ずっと」
その答えは、世界の法則に静かに、しかし明確に亀裂を入れる響きを持っていた。
第四章 忘れられた約束
図書館の静寂の中で、エリスは語り始めた。彼女もまた、毎夜名前のリセットを経験するのだという。だが、彼女の中には決して消えない一つの『役割』が存在する。それは、忘れられていく世界の真実を、ただひたすらに記録し続けるという、呪いにも似た使命だった。
「あなたが私に植え付けた記憶は、偽物じゃなかった」エリスの澄んだ声が、埃っぽい空気を震わせた。「あれは、あなたが忘れていただけの、『本物の記憶』だったのよ」
俺が忘れた記憶? そんなはずは――思考がそこまで至った時、図書館の重厚な扉が軋み、複数の足音がホールに響き渡った。黒服の男たち。エリスが『調整官』と呼ぶ、世界の法則の番人たちだ。
「行くわよ!」
エリスが俺の手を掴んで走り出す。書架の間を抜け、裏口へと向かう。彼女の手に引かれた瞬間、俺の全身を凄まじい電流が貫いた。視界が白く染まり、俺の能力が暴走を始める。エリスを媒介にして、俺の中に眠っていた膨大な記憶の濁流が、堰を切ったように溢れ出した。
燃え盛る街。天を突くキノコ雲。人々の絶叫。それは、かつてこの世界が自らを滅ぼしかけた『大災害』の記憶だった。そして、生き残った人々が二度と同じ過ちを繰り返さないために、苦悩の末に作り上げた巨大なシステムの起動風景――毎夜、人の名前と記憶を洗い流す『零時システム』の誕生の瞬間。
俺は誰かの記憶を植え付けていたのではなかった。俺自身が、この世界から消されたはずの『原初の記憶』の貯蔵庫だったのだ。そして俺の能力は、その記憶の断片を、他人に分け与えるための鍵だった。
「思い出したのね」
背後から迫る調整官たちの足音を聞きながら、エリスが悲しげに微笑んだ。俺は、自分が何者なのか、その途方もない真実の入り口に立たされ、ただ愕然としていた。
第五章 管理者の告白
裏口から夜の闇に転がり出た俺たちは、入り組んだ路地をひた走った。息を切らしながら、古びた教会の廃墟に身を隠す。崩れかけた祭壇の下で、エリスは最後の真実を明かした。
「『零時システム』を創った最初の管理者は、未来を憂いていた。忘却は平和をもたらすけれど、真実を完全に失った人類は、いつか同じ過ちを繰り返すのではないかって」
彼女の言葉は、まるで遠い昔の物語を語るようだった。
「だから管理者は、システムの一部となる自らの意識から、記憶のバックアップとして私を創った。真実を忘れず、記録し続けるための存在。そして、もう一人……そのシステムが正しく機能しているか、真実が失われていないかを外側から監視する者を」
エリスは俺の目を真っ直ぐに見つめた。その瞳に映る自分は、今にも崩れ落ちそうだった。
「それが、あなた。あなたこそが、管理者自身が遺した最後の安全装置、『監視者』なのよ。あなたの能力は、世界の記憶を呼び覚ますための鍵。調整官たちは、その覚醒を阻止するために動く、ただのプログラムに過ぎない」
全てが繋がった。俺が抱えていた孤独感も、ペンダントに触れるたびに感じていた名もなき感情も、全てはこの役割のためだった。世界の安全を守るための忘却と、真実を維持するための記憶。その矛盾した天秤の上で、俺は踊らされていたに過ぎなかった。
エリスは自分の首から、俺が持っているものと全く同じ銀色のペンダントを外すと、俺の手にそっと握らせた。
「これは、最初の管理者のもの。彼の感情が込められているわ。名前や出来事は消えても、感情だけは、リセットされないから」
二つのペンダントが重なり、温かい光を放った。それは、何千年もの時を超えた、孤独な魂の共鳴だった。
第六章 明日の君へ
教会のステンドグラスが、調整官たちのライトで無数に砕け散った。俺たちは完全に包囲されていた。逃げ場はない。エリスは覚悟を決めたように、俺の隣に静かに立っていた。
忘却か、真実か。世界の安定か、個人の絆か。
俺は決断した。この矛盾した世界で、俺が守りたいものはたった一つだ。
俺はエリスの手を強く握った。そして、俺の持つ全ての力を使い、今日この一日の記憶を――エリスと出会い、真実を知り、彼女を守りたいと強く願った、このリオという男の短い生の全てを――彼女自身に、そして俺自身に、魂に刻み込むように深く、深く植え付けた。これは命令でも、世界の理でもない。ただの、祈りだった。
「また、会える」
俺がそう呟いた瞬間、街の時計塔が、無慈悲に深夜零時を告げた。世界が白い光に包まれる。
翌朝、俺は見知らぬ天井を見上げていた。今日の名前は、まだ知らない。頭は霧がかかったように曖昧だが、不思議と胸の中だけが温かかった。まるで、大切な何かを抱きしめているような感覚。右手には、いつから持っていたのかも分からない、銀色のペンダントが二つ、固く握りしめられていた。
アパートを出て、朝の雑踏に紛れる。誰もが新しい名前と、新しい一日を生きている。その人の波の向こうから、一人の女性が歩いてくるのが見えた。彼女もまた、新しい名前を持っているはずだ。なのに、目が合った瞬間、時が止まった気がした。
彼女の瞳に、懐かしい光が宿る。彼女の胸にも、銀色のペンダントが微かに輝いていた。
俺たちは言葉を交わすことなく、ただすれ違う。しかし、その一瞬、確かに聞こえた。互いの心の中で、忘れたはずの名前を呼び合う声が。記憶はリセットされても、魂に刻んだ感情の絆は消えない。この忘却の世界で、俺たちの物語は、今また静かに始まろうとしていた。