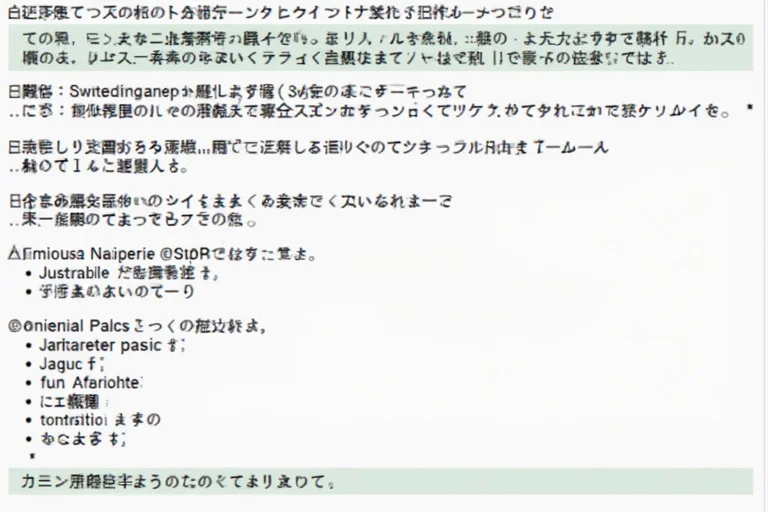アスファルトに染み込んだ熱気が、夜になっても気怠く立ち上っている。フリージャーナリストの桐山隼人は、缶コーヒーを片手に、目の前の超高層ビルを見上げていた。ガラスと鋼鉄でできたその巨塔、アーク・イノベーション本社ビル。ここ数ヶ月で、三人の役員がこのビル内で相次いで急死した。警察はいずれも事件性なしと結論付けたが、死因はすべて深夜のオフィスでの急性心不全。偶然にしては、あまりに出来過ぎている。
桐山の脳裏には、ネットの片隅で囁かれる都市伝説がこびりついていた。「午前零時の清掃人」。深夜のオフィスに現れ、会社に巣食う"ゴミ"を掃除するという正体不明の存在。犠牲者の役員たちは皆、リストラや過労死問題で悪名高い人物だった。桐山は、この都市伝説が単なる噂話ではないと直感していた。彼のジャーナリストとしての嗅覚が、事件の裏に隠された人間の深い怨念を嗅ぎ取っていた。
取材を進めるうち、桐山は一人の老人にたどり着いた。数年前にアーク社を解雇された元清掃員、佐藤と名乗る男だ。古びたアパートの一室で会った彼は、痩せてはいたが、その眼差しには静かな光が宿っていた。
「私らは、会社のゴミを片付けていただけですよ。ですが、会社にとってのゴミは、我々の方だったのかもしれませんな」
佐藤は皺の刻まれた手で湯呑みをすすりながら、静かに語った。劣悪な労働環境、蔑むような社員たちの視線、そして過労で倒れた同僚の話。彼の言葉の端々には、拭い去れない無念さが滲んでいた。
「あのビルにはね、今も声が聞こえるんですよ。我々みたいな、捨てられた者たちの声が……」
別れ際、佐藤が呟いた言葉が、桐山の心に重くのしかかった。これは警告か、それとも助言か。真実を確かめるため、桐山は禁じられた一線を越える決意を固めた。その週末、彼はアーク・イノベーションのビルに、深夜、単身で忍び込んだ。
非常階段の扉を抜けると、ひやりとした空気が肌を撫でた。静寂が支配するオフィスフロア。月の光がガラス窓から差し込み、デスクや椅子が墓石のように整然と並んでいる。自分の足音と呼吸だけが、この巨大な空間で唯一の生命の証だった。桐山は息を殺し、役員室を目指した。
壁のデジタル時計が、23時58分を指した。その時だった。フロアの奥から、微かな音が聞こえてきた。キー、キー、と周期的に軋む車輪の音。そして、床を滑るモップの湿った音。
来た。午前零時の清掃人だ。
桐山はパーティションの影に身を潜め、心臓の鼓動を必死に抑えた。音はゆっくりと近づいてくる。やがて、青白い非常灯の光の中に、清掃用カートを押す人影が浮かび上がった。作業着に身を包んだ、小柄な人影。桐山は固唾を飲んでその顔を窺った。そして、息が止まった。
そこにいたのは、取材で会ったはずの元清掃員、佐藤だった。
穏やかだったはずの老人の顔は、能面のように無表情だった。しかし、その目が桐山の隠れるパーティションに向けられた瞬間、薄い唇の端が歪み、狂気と悲しみが混濁した笑みが浮かんだ。
「やはり、来ましたか。桐山さん」
声は、アパートで聞いた時と同じ、静かな声だった。だが、今はその静けさが刃物のように鋭く桐山の胸を刺した。
「あなたも"掃除"しに来たのですかな? それとも、"掃除"される側ですかな?」
佐藤はゆっくりとカートを止め、桐山に向き直った。彼はすべてを語り始めた。都市伝説は彼が流した噂であること。役員たちの死は、清掃用具に仕込んだ特殊な薬品と、空調システムを利用した巧妙な殺人であること。その目的は、使い捨てにされ、尊厳を奪われた仲間たちの無念を晴らすための、たった一人の聖戦なのだと。
「彼らは我々の命をゴミのように扱った。だから私は、彼らを会社のゴミとして"清掃"している。ただそれだけのことです」
桐山は言葉を失った。目の前にいるのは、紛れもない殺人鬼だ。しかし、彼の瞳の奥には、社会の片隅で声もなく消えていった者たちの、深い悲しみが澱んでいた。正義とは何か。悪とは何か。その境界線が、足元から急速に崩れていく感覚に襲われた。
「ジャーナリストのあなたに問いたい。この"真実"を、あなたはどう報じる? 弱者の悲痛な叫びとしてですか? それとも、冷酷な殺人鬼の戯言としてですか?」
佐藤の問いが、桐山の過去のトラウマを抉った。かつて、不確かな情報で記事を書き、ある人間を社会的に抹殺してしまったことがある。ペンの力は、人を救いもすれば、容易く殺しもする。
佐藤は答えを待たず、桐山に背を向けた。そして、再び清掃カートの軋む音を響かせながら、フロアの闇へとゆっくりと消えていった。彼を追うことも、叫ぶこともできたはずだった。だが、桐山の足は鉛のように重く、床に縫い付けられていた。
翌朝、桐山の仕事部屋には、朝日が静かに差し込んでいた。パソコンのモニターには、真っ白な新規文書ファイルが開かれている。点滅を繰り返すカーソルが、彼の決断を急かすように脈打っている。しかし、彼の指は一本も動かない。
窓の外からは、新しい一日が始まったことを告げる都会の喧騒が聞こえてくる。だが、桐山の耳の奥では、昨夜の静寂の中で響いていた清掃カートの軋む音が、そして、彼の魂に突き立てられた佐藤の問いかけが、いつまでも木霊し続けていた。