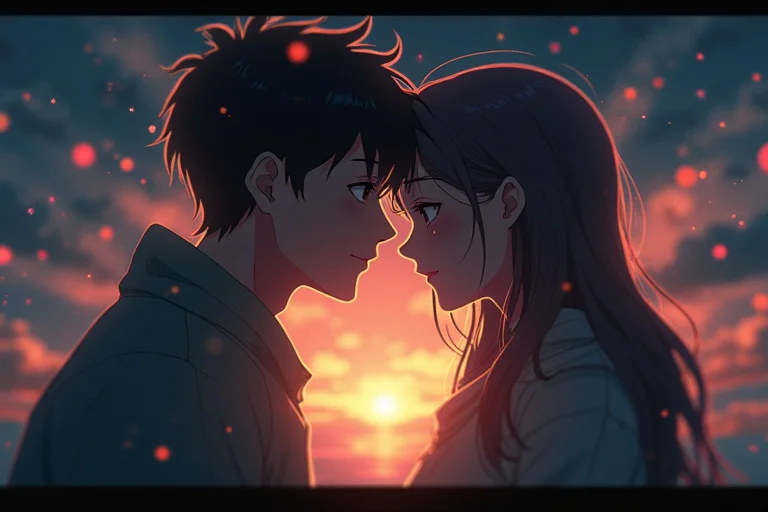いつもの轟音と振動が、ふいに消えた。
俺、佐伯(さえき)が顔を上げると、毎朝乗り慣れた地下鉄の車両は、トンネルの途中で不自然に静止していた。停電だろうか。しかし、車内の照明は点いたままだ。窓の外は、ただ漆黒が広がっている。
「どうしたんだ?」
誰かが呟いた。俺を含め、この車両に乗り合わせたのは十人。学生、サラリーマン、老婆。見慣れた朝の光景が、不気味な静寂に支配されていた。
その時、スピーカーからノイズ混じりのアナウンスが流れた。
『乗客の皆様。ただいまより、緊急の“選別”を開始いたします』
若い男の声だった。駅員のものとは明らかに違う、楽しむような響きがあった。
『この車両には、一週間前に駅のホームで起きた転落事故の“目撃者”が一人、紛れ込んでいます。しかし、その方は警察に届け出ることをせず、沈黙を選んだ。卑劣な臆病者です』
車内がざわめき始める。一週間前の転落事故。確かにニュースで見た。酔っぱらいが足を滑らせたと報道されていたはずだ。
『あれは事故ではありません。突き落とした犯人が、この車両にいます。そして犯人は、臆病な目撃者を探し出し、口を封じようとしています』
空気が凍りついた。犯人と、目撃者が、この狭い空間に?
『ルールは簡単。一時間以内に、乗客の中から“目撃者”を一人、指名してください。指名が正しければ、皆様を解放します。もし間違えれば……残念ながら、この車両は終着駅には到着しません』
アナウンスが途切れ、代わりに車両前方のモニターに、大きなデジタル時計が表示された。カウントダウンが始まっている。
59:59
「ふざけるな!」「誰かのイタズラだろ!」
怒号が飛び交うが、ドアはびくともしない。携帯電話は「圏外」のままだ。俺たちは完全に閉じ込められていた。
疑心暗鬼の視線が、互いを行き交う。誰もが犯人に見え、誰もが目撃者に見えた。
「待ってください!」
声を上げたのは、快活そうな印象の若い女性だった。「パニックになっても仕方ありません。まずは冷静に、事故のあった日のアリバイを確認しませんか?」
彼女の提案で、我々は一人ずつ、事故当日の行動を話し始めた。しかし、誰もが曖昧な記憶しかなく、確証には至らない。焦りだけが募っていく。
俺は必死に記憶を辿った。あの日、確かに俺はあの駅を利用した。だが、事件があったとされる時間、俺はホームの反対側で、同僚と電話をしていたはずだ。事故には気づかなかった。俺は目撃者じゃない。だが、それを証明できるか?
時間が半分を過ぎた頃、スーツ姿の男が突然、俺を指さした。
「お前だ!さっきからやけに落ち着いている!何か知っているな!」
違う、と叫ぶ俺の声は、他の乗客たちの疑念にかき消される。違う。俺じゃない。だが、誰も信じてくれない。追い詰められた俺は、ある違和感に気づいた。
そうだ、声だ。アナウンスの声。どこかで聞いたことがある。冷たく、しかしどこか耳馴染みの良い、あの声は……。
「……高村(たかむら)?」
俺が呟いた名前は、かつて俺が勤めていた調査会社の同僚のものだった。優秀だが、倫理観の欠如から会社を追われた男。
その瞬間、スピーカーからクツクツという笑い声が聞こえた。
『正解。さすがだね、佐伯さん』
高村の声だった。乗客たちが愕然とする。
『でも、残念。もう一つ、大事なことを見落としている』
「何だと……?」
『転落事故なんて、起きてないんだよ』
高村の言葉に、思考が停止した。事故がない?じゃあ、これは一体……。
『犯人も、目撃者もいない。いるのは、“選ばれるべき人間”だけだ。佐伯さん、君だよ』
モニターのタイマーが消え、高村の顔が映し出された。彼は不気味なほど穏やかに微笑んでいる。
『君のその洞察力、窮地での冷静さ。素晴らしい。我々の“組織”は、君のような人材を求めていた。これは最終採用試験だよ。ようこそ、佐伯さん』
他の乗客たちが、まるで申し合わせたかのように一斉に立ち上がり、俺に向かって拍手を始めた。快活な女性も、スーツの男も、老婆も。その顔には、感情が一切ない。まるで役目を終えた役者のように。
ガタン、と音を立てて、閉ざされていたドアが静かに開いた。
ホームではない。そこは、無機質なコンクリートの壁に囲まれた、だだっ広い空間だった。スーツ姿の男たちがずらりと並び、俺を待っている。
日常が終わったのだと、俺は悟った。
ここは、終着駅などではなかった。身の毛もよだつような、新しい世界の始発駅だったのだ。