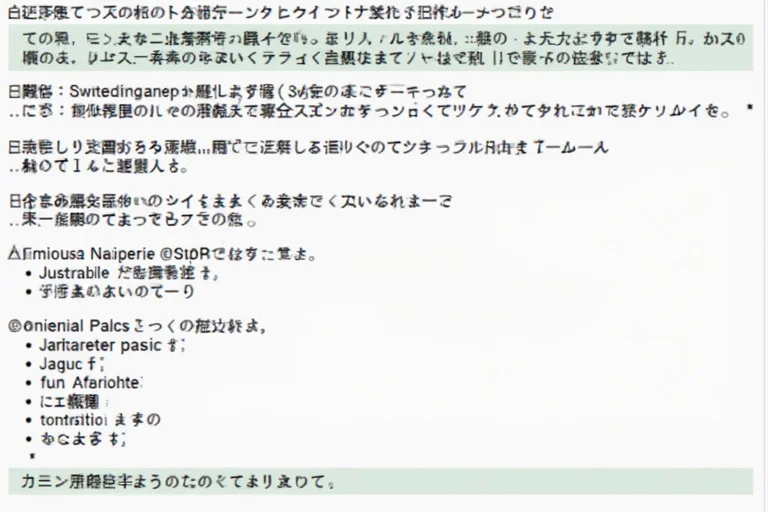静寂は、三上翔平にとって仕事道具であり、同時に心を慰める友人でもあった。数年前に妻を亡くして以来、この郊外の一軒家でフリーの校正者として働く彼にとって、外部からのノイズは思考の妨げでしかない。だから、隣の空き家に新しい住人が越してきたとき、彼の日常にわずかな不協和音が生じた。
引っ越しの挨拶にやってきたのは、絵に描いたような理想的な家族だった。人の良さそうな三十代の夫婦と、人形のように愛らしい小学校低学年くらいの娘。彼らは丁寧な言葉遣いと完璧な笑顔で、高級洋菓子の箱を差し出した。
「これからお世話になります、田中と申します」
そう名乗った夫の声は、アナウンサーのように明瞭だった。だが、三上はその完璧さに、校正者の目で誤植を見つけたときのような、微かな違和感を覚えた。表情、声のトーン、身のこなし。すべてが rehearsed(リハーサル済み)――まるで何度も練習した台詞のようだった。
その日から、三上の静寂は少しずつ侵食され始めた。問題は騒音ではない。むしろ、その逆だった。隣家は不気味なほど静かだった。ただ一つ、毎晩きっかり十時になると、娘の部屋と思われる窓からオルゴールのメロディーが流れてくることを除いては。曲はいつも同じ、「きらきら星」。その正確すぎる反復は、三上の神経を少しずつ削っていった。
好奇心というよりは、職業病にも似た探究心から、三上は隣家の観察を始めた。すぐに、さらなる奇妙な点に気づく。庭の物干し竿には毎日洗濯物が干されるが、それはいつも同じデザインのTシャツとワンピースだ。まるでマネキンの着せ替えのように、汚れ一つない。娘は一度も家の外で遊ぶ姿を見せず、平日の昼間でもランドセルを背負って出かける気配がない。夫婦は時折外出するが、いつも別々の車で、行き先も帰宅時間もバラバラだった。そして何より、彼らの顔には生活感がまるでなかった。喜びも、怒りも、疲れさえも。
「あの家族は、普通じゃない」
確信が深まるにつれ、三上の胸には得体の知れない恐怖が根を張り始めた。虐待だろうか。それとも、何かから隠れて暮らしているのだろうか。毎晩十時に流れる「きらきら星」は、いつしか彼にとって救難信号のように聞こえ始めていた。ペンを走らせながらも、彼の意識は常に隣家の薄い壁の向こう側へと飛んでいた。
ある土曜の夜、激しい嵐が街を襲った。窓を叩きつける雨音と、空気を引き裂く雷鳴が轟く。三上はヘッドホンで耳を塞ぎ、仕事に集中しようとした。ふと、時計が十時を過ぎていることに気づく。いつものオルゴールの音が聞こえない。その代わり、風雨の合間を縫って、隣家から何かが床に叩きつけられるような鈍い音と、女性の短い悲鳴が聞こえた。
心臓が氷の塊になったように冷たくなる。通報すべきか。いや、もし勘違いだったら? 数秒の葛藤の末、三上は意を決して玄関を飛び出した。嵐の中、隣家の様子を窺う。びしょ濡れになりながらたどり着いた玄関のドアが、わずかに開いていた。中の明かりが漏れている。最悪の事態を想像しながら、彼はそっと隙間から中を覗き込んだ。
リビングには、あの夫婦が立っていた。その足元には、娘が倒れている。しかし、その光景は三上の想像を絶するものだった。倒れた娘の腕はありえない方向に曲がり、その白い肌の裂け目から、陶器のような白い材質と、青白い光を放つ配線が覗いていた。
それは、人間ではなかった。精巧すぎる、人形だった。
「……見てしまいましたね」
背後からかけられた声に、三上が凍りつく。いつの間にか、夫が彼の真後ろに立っていた。その目に、何の感情も浮かんでいない。
「驚かせてしまったようで、申し訳ありません」夫は淡々と続けた。「見ての通り、我々は普通の家族ではありません。これは『娘』の最終稼働テストだったのです。落雷のサージ電流でシステムに異常が生じ、緊急停止させました」
「テスト……?」三上の声は掠れていた。
「ええ。我々は、ある企業の開発者です。これは次世代型コンパニオン・アンドロイドの長期実証実験。この家も、すべてがそのためのモデルハウスです」
妻と呼ばれていた女性が、無表情のまま倒れた「娘」の腕を直し、システムを再起動させる。すると、娘はゆっくりと身を起こし、首をかしげた。
「パパ、ママ、わたくし、どうかしましたか?」
その合成音声は、あまりにも無邪気で、狂気じみていた。
三上は後ずさった。目の前の夫婦も、アンドロイドなのではないか。その思考を読んだかのように、夫が静かに言った。
「ご安心を。我々は人間です。ただ、そういう『訓練』を受けているだけですので。この件は、どうかご内密に。我々の『プロジェクト』の存続に関わります」
その言葉は、丁寧な脅迫だった。三上は、自分が決して踏み込んではいけない領域に足を踏み入れてしまったことを悟った。彼の日常は、もう二度と元には戻らない。
翌朝、嵐が嘘のように過ぎ去った空の下、隣家はもぬけの殻になっていた。夜逃げというにはあまりに完璧に、表札も、庭の物干し竿も、そこに生活があった痕跡すべてが消え失せていた。まるで、巨大な蜃気楼が消えたかのように。
三上の日常は、形の上では元に戻った。静寂が彼の部屋を満たし、彼は再び校正の仕事に没頭する。だが、その静寂は、以前とは全く違う重みを持っていた。窓の外を見るたびに、あの完璧な笑顔の「家族」が脳裏をよぎる。
ある夜、仕事を終えて一息ついたとき、遠くから、あのオルゴールの音が聞こえた気がした。
「きらきら星」の、あのメロディーが。
三上は弾かれたように窓に駆け寄った。だが、隣家の敷地はただ暗く、静まり返っているだけだ。幻聴だったのか。それとも――。
彼はキーボードを打つ手を止め、暗い窓の外をじっと見つめた。見えない誰かに、すぐそばから監視されているような悪寒が背筋を走る。
彼のサスペンスは、まだ終わっていなかった。静寂が、以前よりもずっと深く、そして不気味に彼の日常を支配し始めていた。