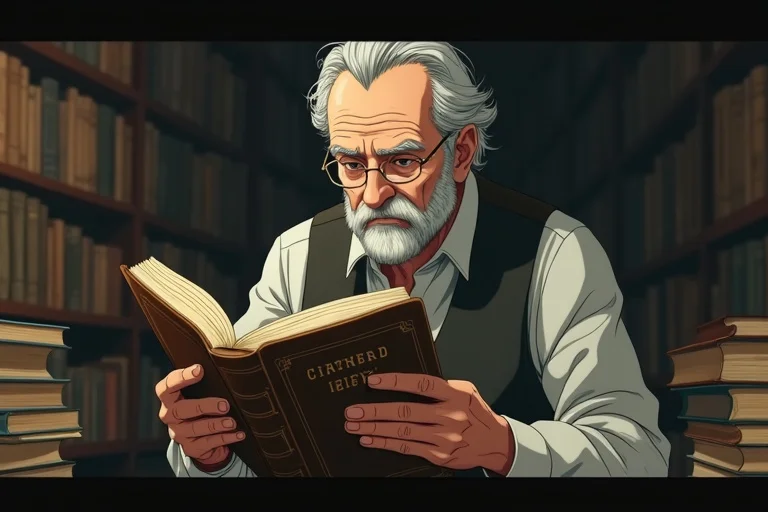黒川奏(くろかわかなで)の耳は、呪いと言えるほどに正確だった。一度聴いた音は、その響き、質感、僅かな揺らぎに至るまで、脳内のライブラリに永久保存される。人々はそれを「絶対音感」と呼んで羨んだが、調律師である彼にとっては、街の騒音すら不快な交響曲と化す厄介な代物だった。
その日、彼が訪れたのは丘の上に立つ壮麗な屋敷だった。依頼主は、メディアにも度々登場する資産家の老人、桐谷正宗。客間に置かれた漆黒のグランドピアノは、主の威光を映すかのように鎮座していた。
「頼む。最高の音にしてくれたまえ」
皺だらけの顔に鋭い光を宿し、桐谷は言った。
調律を始めると、すぐに違和感を覚えた。完璧に調整されたはずのピアノの内部から、ごく微かな、しかし明らかな「異音」が聞こえる。キィ……キィン……。金属が擦れるような、冷たく周期的な音。
「桐谷さん、このピアノ、何か……」
「気のせいだろう。私の耳には何も聞こえんよ」
桐谷は不機嫌そうに手を振った。黒川はそれ以上何も言えず、作業を続けた。だが、彼の耳は、その金属音の微細な響きの変化を、決して忘れられない音として記憶してしまった。
一週間後、テレビのニュースが桐谷正宗の失踪を報じた。警察は事件と事故の両面で捜査しているというが、手掛かりは皆無らしかった。
黒川の脳裏に、あの日の異音が蘇る。キィ……キィン……。あれは何だったのか。単なる機械の軋みか。いや、違う。あの音には、もっと無機質で、冷徹な意志のようなものが感じられた。
彼は自らの聴覚ライブラリを探った。記憶の中のあらゆる金属音と照合する。鍵、歯車、時計の秒針。どれも違う。三日三晩、その音のことだけを考え続けた末、彼は一つの結論に辿り着いた。
あれは、古い時限式金庫のロック機構が作動する音だ。しかも、特定の周期でしか開錠できない、特殊なモデル。彼は古物商の友人を訪ね、該当する金庫の存在を突き止めた。それは「クロノスの棺」という物々しい異名を持つ、スイス製のアンティーク金庫だった。一度閉ざされれば、設定された年数が経過するまで、内からも外からも開けることはできない。
まさか。桐谷は、あのピアノの側にあった金庫に?
警察に話しても、妄想だと一蹴されるのが関の山だろう。証拠は何もない。あるのは、自分の耳が記憶した、百万分の一の響きの破片だけだ。
いてもたってもいられなくなった黒川は、満月の夜、桐谷邸に忍び込むことを決意した。警察には「桐谷邸のピアノを調べてほしい。何かあるはずだ」とだけ書いた匿名の手紙を投函してから。
息を殺して客間にたどり着くと、ピアノは変わらずそこに在った。壁に耳を当て、ピアノの内部に聴診器のように意識を集中させる。
静寂。
中から音はしない。もう、手遅れだったのか。絶望が全身を貫いた、その時。
「そこで何をしている?」
背後に、冷たい声が響いた。振り返ると、桐谷の忠実な秘書、長谷川が氷のような目をして立っていた。
「やはり来たか、耳の良すぎる調律師さん」
長谷川は歪んだ笑みを浮かべた。
「その通りだよ。会長は、あのピアノの裏に隠された『クロノスの棺』の中だ。開くのは五十年後。私の長年の屈辱を晴らす、完璧な復讐さ。君を呼んだのは、あの老人の断末魔を、世界で一番美しい音色で飾り付けてやるためだったんだよ」
狂気が長谷川を支配していた。彼は鈍く光るスパナを手に、黒川に詰め寄る。絶体絶命。万事休すかと思われた瞬間、黒川は最後の賭けに出た。彼は振り返り、ピアノの鍵盤を叩いた。
―――ソ、ミ、レ、ド、ソ。
それは、あの「異音」と共に、彼の耳が捉えていたもう一つの、幻聴のように微かな音の連なりだった。おそらく、閉じ込められる直前の桐谷が、最後の力を振り絞って口ずさんだメロディ。それがピアノの弦に共鳴し、奇跡的に残響として漂っていたのだ。黒川の呪われた耳だけが拾い上げた、沈黙の中のSOS。
そのメロディが奏でられた瞬間、世界の時間が止まった。
ゴゴゴゴゴ……。
ピアノの背後の壁が、重々しい地響きと共にゆっくりとスライドしていく。現れたのは、巨大な金庫の分厚い扉だった。呆然と立ち尽くす長谷川の目の前で、その扉が静かに開いていく。
中から、衰弱しきった桐谷が転がり出てきた。
「……よく、気づいてくれた」
息も絶え絶えの桐谷が黒川を見上げる。その直後、割れた窓から複数の警察官がなだれ込んできた。
逮捕される長谷川の絶叫が、屋敷に木霊した。
黒川は、助け出された桐谷と警察官たちに背を向け、静かにピアノの蓋を閉じた。
彼の耳には、救急車のサイレンも、人々の喧騒も、まるで遠い世界の不協和音のように聞こえていた。ただ、自らが奏でた五つの音が、澄んだソノリティとなって、いつまでも脳内で鳴り響いていた。