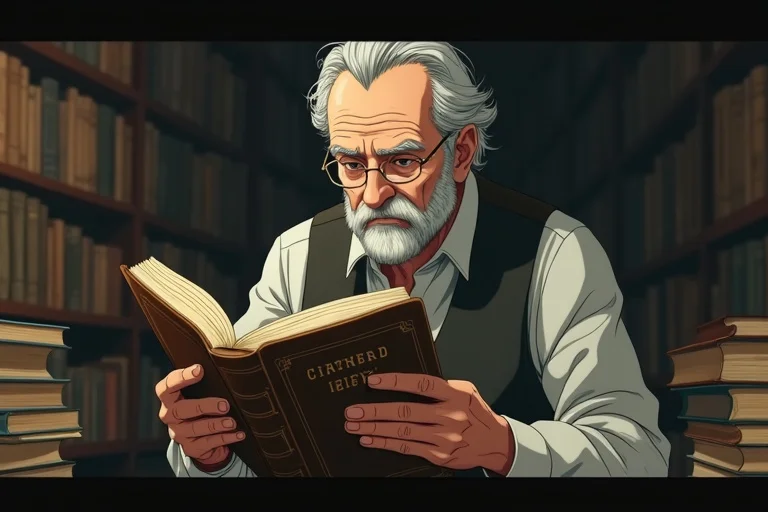第一章 影の招待状
湿ったアスファルトの匂いが、夜の空気を重くしていた。神木健人(かみき けんと)は、現像液の酸っぱい記憶が染みついた指先で、無機質な封筒を弄んでいた。差出人の名はない。ただ、彼の名前と古いアパートの住所だけが、印刷された無感情な活字で記されている。
元報道カメラマン。その肩書きを捨ててから、もう三年になる。今は風景写真家を名乗り、人のいない景色ばかりを追いかけていた。人を信じられなくなった男にとって、決して裏切ることのない自然は、唯一心を許せる被写体だった。
封筒を破ると、中から滑り落ちたのは一枚の写真。L判の光沢紙に写し出された光景に、健人の呼吸が止まった。
五年前、彼自身が撮ったものだ。
都心の公園。初夏の眩しい光の中、一人の女性が弾けるような笑顔で誰かに手を振っている。高遠美咲(たかとう みさき)。当時、ある大物政治家の秘書を務めていた彼女は、一年前に世間を騒がせた連続失踪事件の最後の被害者として、今も行方不明のままだ。
健人はこの写真を未発表にしていた。政治家のスキャンダルを追う過程で偶然撮れた一枚。結局、決定的な証拠にはならず、彼の膨大なデータの中に埋もれていたはずだった。なぜ、これが今、ここに?
指が震えた。写真の右隅。美咲の背後にあるビルの壁に、奇妙なものが写り込んでいる。黒く、歪んだ人影のようなシミ。健人は撮影した当時、レンズの汚れか光の悪戯だろうと気にも留めなかった。だが、改めて見ると、それはまるで、彼女の笑顔にまとわりつく不吉な予兆のようだった。
写真を裏返す。そこには、万年筆で書かれたであろう、流麗だが力のない文字があった。
『あなたは真実を見ていない』
その一文は、健人が目を背け続けてきた過去そのものを、鋭いナイフのように突きつけていた。シャッターを切ることで真実を切り取るのだと信じていた、かつての自分への嘲笑。健人は、埃をかぶったカメラバッグを、押し入れの奥から引きずり出した。ファインダーを覗くことだけが、この謎への唯一の入り口だと、直感が告げていた。
第二章 過去の残像
警視庁の古びた廊下は、消毒液と諦めの匂いがした。連続失踪事件の担当刑事、島崎(しまざき)は、健人が差し出した写真を前に、深く眉間に皺を寄せた。
「五年前の写真、ですか。高遠美咲が失踪するずっと前の…これが何だと?」
「この写真が、昨日俺の元に送られてきたんです。この影、何か心当たりは?」
島崎は写真を光に透かし、ルーペで検分したが、首を横に振るだけだった。「ただのノイズでしょう。それより神木さん、あんたは五年前、彼女の周辺で何を嗅ぎ回っていた?」
刑事の疑念に満ちた視線が、健人の心の壁を厚くする。三年前、健人が報道の現場を去るきっかけとなった誤報事件。警察のリーク情報を鵜呑みにした結果、無実の人間を社会的に抹殺してしまった。あの過ち以来、彼は権力も、そこに群がる人間も信じられなくなったのだ。
「…教える義理はない」
健人はそれだけ言うと、刑事課を後にした。警察に頼るつもりはない。この謎は、自分の手で解き明かす。
健人は、写真に写された公園を訪れた。五年という歳月は、木々を少しだけ成長させ、ベンチの色を褪せさせていた。記憶のピントを合わせるように、ファインダーを覗きながら同じアングルを探す。シャッター音が、忘れていた高揚感を呼び覚ます。
「あの…神木健人さん、ですか?」
背後からの声に振り返ると、一人の青年が立っていた。歳の頃は二十代半ば。その潤んだ瞳には、見覚えがあった。高遠美咲によく似ている。
「姉の弟の、翔太です」
高遠翔太(たかとう しょうた)と名乗った青年は、深々と頭を下げた。「姉のことで、何か分かったのではないかと…。あなたがここに来るような気がして、ずっと待っていたんです」
彼の声は震えていた。姉を想う純粋な祈りが、痛いほど伝わってくる。健人は、他者と関わることを避けてきた自分の殻が、少しだけ軋むのを感じた。
「まだ何も。だが、諦めたわけじゃない」
翔太の瞳に、わずかな希望の光が宿った。
「手伝わせてください。俺も、姉のためにできることなら何でもしたい」
健人は一瞬ためらった。だが、一人では限界があることも分かっていた。何より、翔太の必死な眼差しを、どうしても振り払うことができなかった。
「…分かった。だが、深入りはするな」
頷きながらも、健人は心のどこかで警鐘が鳴るのを聞いていた。人を信じることは、再び自分を闇に引きずり込む危険な賭けなのだと。
第三章 偽りの涙
健人と翔太の調査は、困難を極めた。五年前の記憶は断片的で、有力な手がかりは見つからない。それでも翔太は、文句一つ言わず、健人の指示に従った。彼のひたむきな姿は、健人の凍てついた心を少しずつ溶かしていく。いつしか健人は、翔太と行動を共にすることに、一種の安らぎさえ覚え始めていた。
転機は、思わぬところから訪れた。写真に写り込んでいたビルの所有者を突き止め、当時のテナントリストを調べたところ、一つの名前に目が留まった。美咲が秘書として仕えていた政治家の、ライバル派閥が運営するペーパーカンパニー。その会社は、公園近くの古い雑居ビルに事務所を構えていた。
二人がそのビルを訪れると、そこは既にもぬけの殻だった。しかし、施錠されていなかった一つの部屋の床に、埃にまみれた革張りの手帳が落ちていた。高遠美咲の日記だった。
ページをめくる指が震える。そこには、政治家の不正の証拠を掴み、告発の準備を進めていた美咲の、緊迫した日々が綴られていた。脅迫めいた電話、誰かにつけられている気配。彼女は孤独な戦いの中で、日に日に追い詰められていた。
そして、最後の日付のページ。健人は息を呑んだ。
そこには、彼が撮った写真と全く同じ構図の、稚拙だが丁寧なスケッチが描かれていた。そして、その下にはこう記されていた。
『もし私に何かあったら、この写真を報道カメラマンの神木健人さんに送ってほしい。彼は、私が唯一信じられるジャーナリスト。彼ならきっと、この写真に隠した私の最後のメッセージに、気づいてくれるはずだから』
メッセージ? 健人は混乱した。写真を見返す。あの不気味な影。あれがメッセージだというのか。まさか。
健人は、報道カメラマンとしての知識を総動員して、写真を再検証した。光の屈折、反射、レンズフレア…。そして、ある可能性に行き着いた。
「反射だ…」
ビルの窓ガラスに反射した光。それが、計算されたパターンで写り込んでいる。モールス信号だ。美咲は、健人のカメラマンとしての観察眼を信じ、彼にしか解読できないであろう方法で、最後の言葉を託したのだ。
健人はノートに信号を書き出し、解読を始めた。指先が冷たくなっていく。現れた言葉は、犯人の名を示唆していた。健人の思考が停止する。ありえない。何かの間違いだ。
『たすけて 犯人は―――』
そこに記されていたのは、あまりにも残酷な真実だった。健人は、隣で心配そうに自分を覗き込む翔太の顔を見た。その瞳の奥に、今まで気づかなかった深い闇が揺らめいていた。日記の最後のページには、追伸があった。
『翔太、ごめんね。あなたを巻き込みたくなかった』
美咲は、弟が自分の身を案じるあまり、危険な行動に出ることを予感していたのだ。メッセージは、健人へのSOSであると同時に、弟への警告でもあった。
「…翔太」健人の声がかすれた。「お前だったのか」
翔太の表情から、純粋な弟の仮面が剥がれ落ちた。彼の口元が、歪んだ笑みの形に引きつる。
「気づいたんだ。やっぱり、姉さんの言った通りだった。神木さんなら、って」
彼の涙は、偽りだった。姉を想う心は、歪んだ独占欲だった。すべては、健人を監視し、捜査を攪乱するための芝居だったのだ。
第四章 ファインダー越しの真実
「姉さんを守りたかっただけなんだ!」
翔太の絶叫が、廃ビルの空虚な空間に響き渡った。彼は、姉が政治家の不正を告発しようとしているのを知り、その身を案じるあまり、何とかして止めようとした。しかし、正義感の強い美咲は聞き入れない。口論はエスカレートし、カッとなった翔太は、姉を突き飛ばしてしまった。頭を打って気を失った姉を見て、パニックに陥った彼は、姉をこのビルの一室に監禁し、失踪したように見せかけたのだという。
「姉さんがいなくなるくらいなら、俺が閉じ込めてでも守る。それの何が悪いんだ!」
健人は、静かにカメラを構えた。レンズが、歪んだ愛情に囚われた青年の顔を捉える。三年前の悪夢が蘇る。ファインダー越しに見た、絶望にくれる無実の男の顔。シャッターを切る指が、重い。
だが、今、目の前にいるのは加害者だ。そして、自分は被害者から真実を託された唯一の人間だ。
「君の姉さんは、最後まで俺を信じてくれた」健人の声は、震えていなかった。「俺が報道カメラマンであることを、ジャーナリストであることを、信じてくれていた。俺は、その信頼に応えなきゃならない」
カシャリ、とシャッター音が鳴った。しかし、それは証拠写真のためではなかった。健人が自分自身に、過去との決別を誓うための音だった。彼はカメラを下ろすと、翔太の目を見据えた。
「行け。行って、全部話せ。それが、お前の姉さんに対する、唯一の償いだ」
数日後、翔太は自首し、彼の供述通り、美咲は無事保護された。衰弱はしていたが、命に別状はなかった。ただ、事件のショックからか、彼女は弟に関する記憶だけを都合よく失っていた。
健人は、再び報道の世界に戻ることを決めた。ある新聞社の小さな写真部。派手さはないが、一枚の写真の重みを理解してくれる場所だった。
退院した美咲が入所した、郊外の療養施設の庭が見える丘の上。健人は、望遠レンズでそっとその姿を追っていた。車椅子に乗り、穏やかな表情で空を見上げる美咲。彼女の周りには、もうあの不吉な影はなかった。
健人は、息を止め、一度だけシャッターを切った。
ファインダーの中の彼女は、五年前と同じ、優しい笑顔を浮かべていた。
その一枚を胸に、健人は静かに丘を降りた。
美咲が写真に託した最後のメッセージ。犯人を告発する言葉の裏に、弟を赦してほしいという悲痛な願いが隠されていたことを、健人だけが知っている。
真実を写すとは、どういうことか。何を暴き、何を赦すのか。その答えの出ない問いを、これからの人生でずっと探し続けるのだろう。だが、もう彼は一人ではなかった。ファインダーの向こうに、信じるべき光が見えていたからだ。