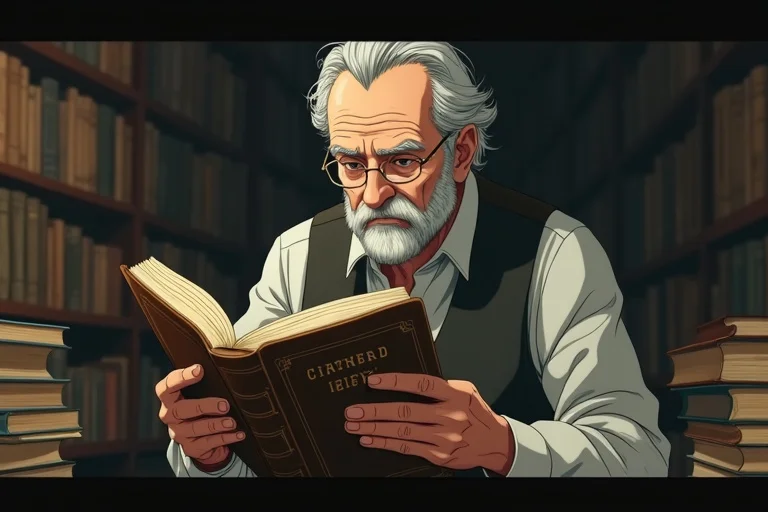第一章 置き去りの予言
神保町の裏路地にひっそりと佇む古書店『天野堂』の店主、天野湊の時間は、埃と共にゆっくりと積もっていた。色褪せた背表紙の森に埋もれ、インクと古い紙の匂いに満たされたこの場所は、彼にとって世界そのものであり、外界から身を守るための静かな要塞でもあった。五年前に妻の沙織を事故で亡くして以来、湊の心は時の流れを拒絶していた。
ある雨の日の午後だった。店のドアベルが、錆びた音を立てて来客を告げる。入口に立っていたのは、黒いワンピースを着た、どこか儚げな印象の女性だった。雨に濡れた髪が白い肌に張り付き、その瞳は店の薄闇の中でも異質なほど澄んで見えた。
「あの、本を探しているのですが」
鈴を転がすような、けれど芯のある声だった。
「『水底のソネット』という詩集をご存じですか。著者は、月村カオル」
湊は眉をひそめた。あまりにもマイナーな、戦前にごく少数だけ出版された詩集だ。そして、その名は彼の心を鈍く抉った。沙織が愛し、何度もその一節を口ずさんでいた本だったからだ。
「……在庫にはありません。かなり稀覯本なので」
事務的に答え、視線を帳簿に戻す湊に、女は構わず続けた。
「沙織さんの、ご主人ですよね」
湊の指が止まる。女は自分を、千景(ちかげ)と名乗った。沙織の知り合いだというが、湊の記憶には全くなかった。
「妻が、何か?」
警戒を滲ませる湊に、千景は悲しげな微笑みを浮かべた。
「その本は、ただの本ではないんです。未来を映す鏡のようなもの。沙織さんも、そう信じていました」
荒唐無稽な言葉だった。湊は黙り込む。千景は彼の心を見透かすように、静かに言った。
「一つ、お伝えします。三日後の夕方、この店で誰かが血を流します。気をつけて」
それは予言というにはあまりに具体的で、脅迫めいてもいた。彼女が何を企んでいるのか、湊には見当もつかない。千景はそれだけ言うと、会釈して店を出ていった。雨上がりのアスファルトに反射する光の中に、彼女の黒い姿は溶けるように消えていった。
残された湊は、言いようのない不安に包まれた。積年の埃が舞う静寂の中で、カチ、カチ、と古時計の秒針だけが、不吉なカウントダウンのように彼の鼓膜を打ち続けていた。
第二章 血の証明
千景が残した言葉は、湊の静かな日常に投げ込まれた石のように、波紋を広げ続けた。馬鹿げている、と頭では否定しながらも、心のどこかでその不吉な響きが反響していた。彼は無意識のうちに、店の入口に注意を払い、見慣れない客が来ると身構えるようになった。閉ざしていた世界に、他者の存在という亀裂が走っていく。
予言の三日目がやってきた。空は皮肉なほど青く澄み渡っている。湊は開店準備をしながらも、何度もカレンダーに目をやった。血を流す、という言葉が生々しく脳裏をよぎる。強盗か、通り魔か。様々な憶測が、彼を苛んだ。
その日は奇妙なほど、客足が途絶えた。静寂はかえって緊張感を増幅させる。夕刻が近づくにつれ、湊の心臓は早鐘を打ち始めた。閉店時間を迎え、もう何事も起こらないだろうと安堵のため息をついた、その瞬間だった。
「おっと!」
店の奥で、甲高い声が上がった。常連客の古川老人が、高い棚の本を取ろうと脚立に上り、バランスを崩したのだ。鈍い音と共に床に倒れ込んだ老人の額から、赤い筋がすっと流れた。
「古川さん!」
湊は慌てて駆け寄る。幸い、傷は浅く、意識もはっきりしていた。救急車を呼び、騒ぎが収まった頃には、店の外はすっかり闇に包まれていた。
血は流された。千景の予言は、歪んだ形で現実となった。
これは偶然か、それとも。湊の心は乱れた。彼は千景を探さなければならないと強く感じた。彼女は何者で、何を知っているのか。
数日後、湊は神保町の喫茶店で千景と再会した。彼女はすべてを予期していたかのように、静かにコーヒーを啜っていた。
「信じていただけましたか」
「……あれは、あなたが仕組んだことじゃないのか」
湊が問い詰めると、千景は静かに首を振った。
「私は、ただ『視える』だけです。そして、次も視えています」
彼女の澄んだ瞳が、まっすぐに湊を射抜く。
「次に失われるのは、あなたが最も大切にしている『記憶』です」
記憶、という言葉に湊は息をのんだ。沙織との思い出か。それとも。
「あなたの妻、沙織さんの事故……あれは、本当にただの事故だったのでしょうか」
千景の言葉は、湊が心の奥底に封じ込めていた最大の疑問を、容赦なく抉り出した。あの日、どうして沙織は車道に飛び出したのか。自分との間に何があったのか。ショックのあまり曖昧になった記憶の断片が、痛みと共に蘇る。
「真実を知りたければ、ご自身の記憶の扉を開けてください。その鍵もまた、『水底のソネット』に隠されています」
千景はそう言い残し、再び彼の前から姿を消した。湊は、逃れることのできない巨大な渦の中心に、自分が立っていることを悟った。
第三章 砕かれた記憶の欠片
千景の言葉は、湊を行動へと駆り立てた。彼は埃を被った段ボール箱から、沙織の遺品を取り出した。その中には、彼女がつけていた日記があった。ページをめくる指が震える。事故の数週間前から、日記には頻繁に『K』というイニシャルの人物が登場していた。そして、繰り返し引用される『水底のソネット』の一節。
《深い水の底で、私は真実の光を待つ》
湊の心に、黒い疑念が鎌首をもたげた。『K』とは千景(Chikage)のことではないか。彼女が沙織を追い詰め、事故に見せかけて殺したのでは――。その考えに至った途端、湊はいてもたってもいられなくなった。彼は千景がアルバイトをしているという画廊に乗り込んだ。
「あなたが妻を殺したんだろう!」
声を荒らげる湊に、画廊の客たちが驚いて振り返る。千景は彼を静かに店の裏へと促した。二人きりになった小部屋で、彼女は初めて、感情を露わにした。その瞳には涙が浮かんでいた。
「……予言なんて、全部嘘です」
絞り出すような声だった。
「私は、予言者なんかじゃありません。ただの、臆病者です」
そして、彼女はすべてを告白した。
千景の父親が、五年前に沙織を轢いた車の運転手だったのだ。
「父は、あの事故以来、心を病みました。毎日、あなたの奥様の夢を見ては魘され、今はもう、まともに会話もできません。私は、ずっとあなたに謝罪しなければと思っていました。でも、怖かった。憎まれるのが、怖かったんです」
だから、彼女は「予言」という回りくどい手段を使ったのだという。最初の「血を流す」予言は、湊が気づいていなかった店の脚立の古さに目をつけ、常連の古川老人が使いそうなタイミングを狙った、危険な賭けだった。すべては、湊の注意を引き、彼に過去と向き合わせるための、歪んだシナリオだった。
「『次に失われるのは記憶』……そう言ったのは、あなたに、あなた自身が蓋をしている本当の記憶を思い出してほしかったからです」
千景の言葉が、湊の脳を激しく揺さぶる。
「事故の日……あなたは、沙織さんと喧嘩をしていたはずです」
その一言が、引き金になった。
堰を切ったように、忘却の底に沈んでいた光景が蘇る。
些細な言い争い。将来への不安。苛立ちから、湊が放った心ない一言。泣きながら部屋を飛び出していく沙織の後ろ姿。追いかけようとして、くだらない意地で踏みとどまってしまった自分。
「行かないでくれ!」と叫べなかった後悔。
沙織は、心ここにあらずの状態で、雨の車道へ足を踏み出してしまったのだ。それは、紛れもない不幸な事故だった。だが、その引き金を引いたのは、間違いなく自分自身だった。湊がずっと抱えてきた「自分のせいだ」という罪悪感は、歪んだ形ではなく、あまりに生々しい事実として彼の胸に突き刺さった。
「あなたが殺したんじゃない。誰のせいでもない。ただ、悲しい偶然が重なっただけ……。そう思わなければ、父も、あなたも、私も、前に進めない」
千景は床に崩れ落ち、嗚咽した。加害者の娘として、彼女もまた、この五年間、癒えない傷を抱え、水底のような苦しみの中でもがいていたのだ。
第四章 夜明けの詩
すべてを思い出した湊は、その場に立ち尽くした。激しい自己嫌悪と、沙織への申し訳なさで、息が詰まるようだった。しかし同時に、彼の心を長年縛り付けていた「妻は殺されたのかもしれない」という黒い呪縛が、音を立てて解けていくのを感じた。目の前で泣きじゃくる千景は、殺人犯でも、謎の予言者でもない。自分と同じ、過去の重荷に喘ぐ一人の人間に過ぎなかった。
「……顔を上げてください」
湊の声は、自分でも驚くほど穏やかだった。
「あなたを許すとか、許さないとか、僕にそんな資格はない。僕も、あなたのお父さんも、そしてあなたも……ただ、この事実を背負って、生きていくしかないんだと思う」
それは赦しではなかったかもしれない。だが、二人の間にあった見えない壁が、静かに消えていく瞬間だった。
店に戻った湊は、まるで何かに導かれるように、書棚の一番上の段に手を伸ばした。そこには、一冊だけ客観から外され、埃をかぶった詩集があった。手に取ると、それは紛れもない『水底のソネット』だった。
忘れていた。これは、沙織が持っていたものではない。ずっと昔、まだ付き合い始めた頃に、自分が彼女への贈り物として買ったものだった。
震える指で最後のページを開く。そこには、見慣れた沙織の優美な文字で、短いメッセージが記されていた。
《湊へ。
たまに喧嘩もするけれど、それでも私は、あなたを愛しています。
いつか、この息苦しい水底から、一緒に光を見上げましょうね。
沙織》
涙が、次から次へと古びたページに染みを作った。それはもう、後悔や絶望の涙ではなかった。失われたと思っていた愛が、確かにそこにあったことを知った、温かい涙だった。沙織は、自分を責めてなどいなかった。彼女もまた、未来を信じていたのだ。
湊はゆっくりと顔を上げ、店の窓の外を見た。夜が明け、神保町の路地に、柔らかい朝の光が差し込み始めていた。
彼は店の扉を開け放つ。新鮮な空気が、淀んだ店内の埃を優しく外へと運び出していく。
五年間止まっていた彼の時間が、今、静かに動き始めた。その光の中で、湊はもう一度、生きていこうと、強く思った。水底から見上げる光は、あまりにも眩しく、そして希望に満ちていた。