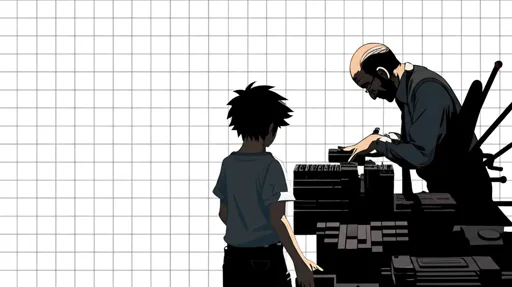坂井美月の携帯が鳴ったのは、クライアントとの打ち合わせが白熱している最中だった。画面に表示された「実家」の二文字に、胸の奥が小さくざわめく。折り返しの電話で告げられたのは、父の死だった。実感が湧かなかった。病院のベッドで最後に会った父は、ただ眠っているように穏やかで、その顔を見ても涙は一滴もこぼれなかった。
「頑固で、仕事一筋で、私のことなんて見ていなかった」。美月にとって父は、そういう人間だった。大学進学で上京して以来、父とまともに話した記憶はない。母が亡くなってからは、その距離はさらに開くばかりだった。
事務的な手続きが終わり、埃っぽい父の書斎で遺品整理を始めた。本棚の奥、古びた木箱の中に、それらはあった。分厚い手紙の束。すべて万年筆で書かれ、封はされているのに、宛名も切手もなかった。一通手に取ると、消印のない日付印が押されている。それは、美月が家を出た日だった。
好奇心と、わずかな罪悪感に駆られ、美月は封を切った。
『美月へ。今日からお前のいない朝が来た。静かすぎる。食卓の椅子が一つ、やけに大きく見える。』
訥々とした、それでいて温かい文字が並んでいた。次の手紙、また次の手紙と読み進めるうちに、美月の知らない父の姿が浮かび上がってくる。
『近所の金木犀が咲いた。お前が好きな香りだ。来年は、一緒に見られるといい。』
『テレビでお前の会社のCMを見た。すごいな。誇らしい。』
『風邪を引いたと母さんから聞いた。好物の林檎を送ろうとしたが、お節介かと思い、やめた。ちゃんと食べているか。』
手紙は、美月が父に伝えなかった日々の出来事を、まるで隣で見ているかのように捉えていた。父は見ていないのではなく、声をかけられなかっただけなのだ。仕事で評価された日、恋人に振られた夜、父はすべてを知っていたかのように、その日の手紙で不器用なエールを送っていた。投函されなかった言葉の数々に、美月の頬を熱いものが伝っていく。なぜ、送ってくれなかったのか。その問いだけが、積もった後悔と共に心を締め付けた。
手紙の束は、亡くなる一週間前の日付で終わっていた。最後の一通は、いつもの便箋ではなく、少し上等な和紙に認められていた。震える指で封を開けると、中から一枚の地図がはらりと落ちた。手紙には、こう書かれていた。
『美月へ。お前が初めてメインで担当したという、駅前の大きな広告を見てきた。写真で見るより、ずっと立派だった。まるで、お前が「ここまで来たぞ」と胸を張っているようだった。幼い頃、お前は言ったな。「お父さん、いつか私が作ったもので、世の中をびっくりさせてあげる」と。その約束を、お前は覚えていないだろう。だが、父さんはずっと待っていた。あの頃のお前との約束を、今、果たしに行こうと思う。この手紙を持って、お前の広告の前で待っている。もし、これをお前が読んでいるのなら、それは父さんが、約束を果たせなかったということだ。だが、この手紙だけは、お前への最後のラブレターとして、きっと届くと信じている。』
地図が示していたのは、美月が心血を注いだ広告が掲げられている、あの場所だった。父は、あの日、あの場所で、美月を待っていたのだ。会って、この手紙を渡すために。しかし、その約束は、病魔によって永遠に果たされなくなってしまった。
美月はコートを羽織り、アパートを飛び出した。地図を握りしめ、電車に乗り、父が最後に向かおうとした場所へと走った。
夕暮れの光が差し込む駅前の広場。見上げると、自分がデザインした化粧品の広告が、巨大なスクリーンに誇らしげに映し出されている。きらびやかなモデルが微笑むその下で、美月は立ち尽くした。
「お父さん…」
声にならない声が漏れる。父はここにいたのだ。この広告を見上げ、娘の成長をその目に焼き付けていた。投函されなかった手紙は、不在を嘆くものではなかった。いつか来る再会の日を夢見て綴られた、希望の記録だったのだ。
「見てる? 私、ちゃんとやったよ」
美月は空を見上げて呟いた。返事はない。けれど、頬を撫でる風が、まるで不器用な父の大きな手が、優しく頭を撫でてくれたような気がした。父からの最後のラブレターを胸に抱きしめ、美月はゆっくりと顔を上げた。その瞳には、もう迷いはなく、明日へと向かう確かな光が宿っていた。