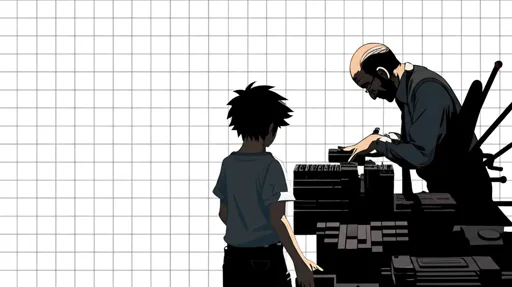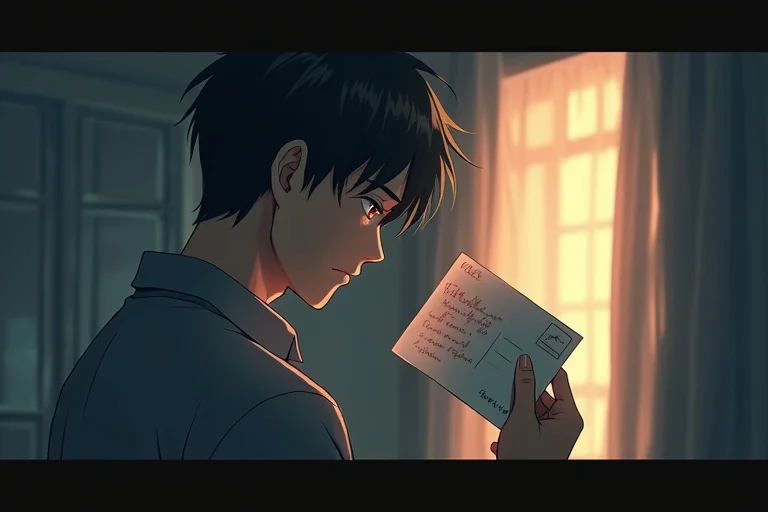潮の香りが染みついた厨房で、橘蓮(たちばな れん)は無心にアジを捌いていた。かつて「神の舌」と謳われた繊細な指先は、今や大衆食堂「キッチン・カモメ」の無骨な包丁を握っている。客のいない昼下がり、古びたラジオから流れる気怠いポップスが、錆びついた蓮の心のようだった。
その静寂を破ったのは、店のドアベルが告げた、場違いなほど高価な革靴の音だった。
「…よう、蓮。まだそんな安物の魚をいじっているのか」
振り返った先に立っていたのは、黒木隼人(くろき はやと)。パリに三つ星レストランを構え、世界の美食家を唸らせるスターシェフ。そして、蓮のかつての親友であり、最大のライバルだった。
黒木は、蓮が料理界から逃げ出したあの日から、一度も会うことのなかった男だ。
「何の用だ。ここはあんたのような高級な客が来るところじゃない」
蓮が吐き捨てると、黒木は店の隅のテーブルに腰掛け、挑戦的な笑みを浮かべた。
「お前に勝負を申し込みに来た。テーマは、師匠が遺した幻のレシピ、『追憶のポトフ』だ」
心臓が氷水で掴まれたように冷たくなる。師匠のレシピ。それは、蓮がコンテストで大失敗し、すべてを捨てた因縁の一皿だった。
「断る。俺の料理はもう死んだんだ」
「死んだ? ふざけるな。お前の才能をこんな港町の食堂で腐らせる権利は、お前自身にすらない!」
黒木の激しい言葉が、蓮の古傷を抉る。だが、蓮の心は頑なに閉ざされたままだった。
その夜、店の常連である漁師の源さんが、大きな鯛を抱えてやってきた。
「蓮さんよぉ、落ち込んでるんだって? 黒木とかいうすげぇシェフが来たんだろ」
「…」
「俺たちはさ、あんたのメシに救われてんだ。仕事でヘマした日も、娘と喧嘩した日も、あんたのアジフライ食やあ、明日も頑張るかって思えんだよ。そりゃ三つ星の味じゃねぇかもしれねぇが、俺たちにとっちゃ世界一だ」
源さんの言葉に、小さな灯りが心に灯るのを感じた。俺の料理は、まだ死んでいなかったのか。
翌日、蓮は黒木に電話をかけた。
「勝負、受けてやる。ただし、場所はこの『キッチン・カモメ』だ。食材も、この店にあるものしか使わない」
約束の日。厨房には二人の男だけが立っていた。黒木は世界中から取り寄せた最高級の黒トリュフやA5ランクの和牛を並べる。一方、蓮の前にあったのは、源さんがくれた鯛、近所の農家がくれた不揃いの野菜、そしてこの店の厨房にいつもある、ありふれた調味料だけ。
火花が散るような緊張感の中、調理が始まった。黒木は寸分の狂いもない完璧な手際で、芸術品のような一皿を創り上げていく。対する蓮は、目を閉じ、深く息を吸い込んだ。潮の香り、客たちの笑い声、この町で過ごした時間。そのすべてを鍋に溶かすように、ゆっくりと、しかし確かな手つきで調理を進めた。
やがて、二つの「追憶のポトフ」が完成した。
黒木のポトフは、宝石のように輝き、芳醇な香りが鼻腔をくすぐる。一口食べれば、誰もが幸福のため息をつくだろう完璧な味だ。
蓮のポトフは、見た目は素朴な、ただの野菜スープだった。
二人は無言で互いの一皿を口にした。
黒木は、蓮のスープをスプーンですくった瞬間、目を見開いた。口に含んだ途端、彼の脳裏に、今は亡き師匠と三人で、喧嘩しながら厨房に立った若き日の記憶が鮮やかに蘇った。高級食材では決して出せない、懐かしくて、温かい味。それは、人を愛し、人に愛された者だけが作れる味だった。
「…参ったな」
黒木はスプーンを置き、静かに呟いた。「これは、俺には作れない。…俺の負けだ」
蓮は首を横に振った。
「勝ち負けじゃない。俺は思い出しただけだ。誰のために、何のために料理を作るのかをな」
その顔には、失っていたはずの自信に満ちた笑みが浮かんでいた。
黒木は満足そうに頷くと、「世界大会の席、一つ空けておくぞ、天才」と言い残し、店を去っていった。
一人になった厨房で、蓮は錆びついていたはずの愛用のスプーンを手に取った。磨き上げられたそれに映る自分の顔は、晴れやかだった。
「さて、と」
蓮は新しい油を鍋に注ぎ、アジに衣をつけ始める。もうすぐ、腹を空かせた常連客がやってくる時間だ。
「キッチン・カモメ」のラスト・オーダーは、まだ終わらない。厨房には再び、小気味の良い揚げ物の音が鳴り響き始めた。