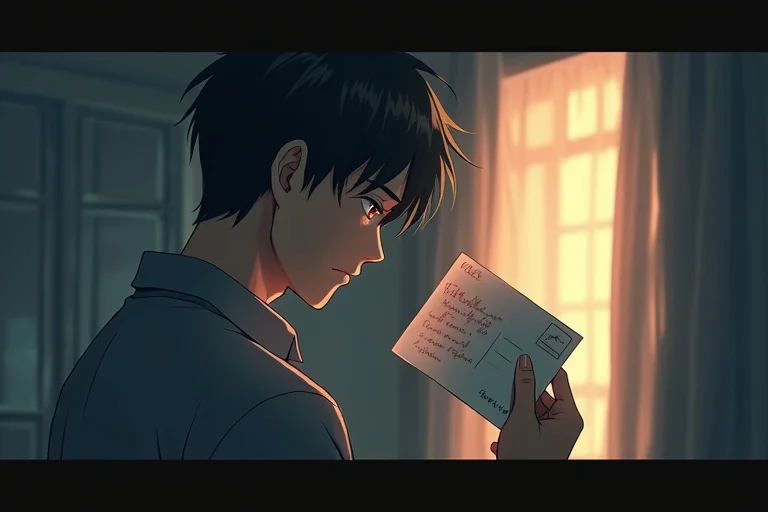第一章 インクが紡ぐ見知らぬ声
神保町の古書街の片隅に、俺の営む「月読堂」はひっそりと息づいている。父から継いだこの店は、埃と古い紙の匂いが染みつき、時間の流れが止まった化石のようだ。俺、相葉健人(あいばけんと)もまた、その化石の一部だった。三十代も半ばを過ぎ、人生に大きな期待もせず、ただページをめくるように単調な毎日をやり過ごしていた。
父は三年前、静かに逝った。無口で、何を考えているのか分からない人だった。親子らしい会話の記憶はほとんどなく、俺にとって父は、この古書店の背表紙と同じ、ただそこに「在る」だけの存在だった。店を継いだのも、他に生きる術を知らなかったからに過ぎない。
そんなある雨の日、店の奥にある開かずの引き出しを整理していると、黒檀の軸に銀の装飾が施された、一本の古い万年筆を見つけた。父の遺品だろうが、こんな上等なものを持っているとは知らなかった。手に取ると、ひんやりとした重みが心地よい。ペン先は摩耗しているが、丁寧に手入れされてきたことが窺える。
好奇心から、引き出しの隅にあった古典インクの瓶を開け、コンバーターに深い藍色の液体を吸い上げた。何を書こうか。特に思い浮かばず、目の前にあった古びた便箋に、試しに一本の線を引いてみた。
その瞬間、俺は目を疑った。
俺が引いた覚えのない、流麗な筆跡が、まるで滲み出すように紙の上に現れたのだ。それは、一本の線ではなく、言葉だった。
『――海鳴りの音が、遠くで聞こえる。あなたの好きな、あの音』
心臓が跳ねた。幻覚か。もう一度、ペン先を紙に滑らせる。すると今度は、別の言葉がひとりでに浮かび上がった。
『窓辺に置いたゼラニウムが、今年も赤い花をつけた。あなたに見せたかった』
パニックに陥りかけた頭で、必死に思考を巡らせる。これは、なんだ? この万年筆に宿った、誰かの記憶か何かだというのか。非現実的な結論にたどり着きながらも、目の前の現象を否定できない。インクを補充するたびに、この万年筆で過去に書かれた言葉が、亡霊のように紙の上に再現されるのだ。
浮かび上がる言葉は、どれも断片的だった。しかし、そこには一貫した「誰か」の視点があった。繊細で、感受性豊かで、そして、おそらくは女性であろうその人物は、世界の美しい瞬間を切り取っては、大切な「あなた」に語りかけているようだった。
俺は、その見知らぬ声の主に、強く心を惹きつけられていた。停滞した俺の時間に、一滴の鮮やかなインクが垂らされたような、抗いがたい予感がした。
第二章 亡霊の足跡
それからの俺は、亡霊に取り憑かれたみたいに、万年筆が紡ぎ出す言葉の虜になった。店の営業が終わり、古びたランプの灯りの下でインクを補充する時間が、一日のうちで最も心躍る瞬間となった。
『今日は、谷中の坂道を歩いた。夕焼けが猫の背中を金色に染めていたわ』
『駅前の喫茶店。ここのブレンドコーヒーは、少しだけ酸っぱい。あなたはきっと、眉をひそめるでしょうね』
その文章は、まるで宝の地図の断片だった。俺は、その言葉を頼りに、彼女の足跡を辿ることを始めた。休日のたびに電車に乗り、谷中の坂道を歩き、夕焼けを待った。地図アプリを頼りに駅前の古い喫茶店を探し当て、彼女が飲んだであろうコーヒーを注文した。
それは、俺にとって小さな冒険だった。今まで見過ごしてきた世界の風景が、彼女の言葉を通して、一つ一つ意味を持って輝き始めた。アスファルトの隙間に咲く名も知らぬ花。電車の窓から見える、ありふれた街並み。そのすべてが、彼女のフィルターを通すことで、かけがえのないものに思えた。
彼女は、どんな人だったのだろう。どんな顔で笑い、どんな声で話すのだろう。そして、彼女がこれほどまでに想いを寄せる「あなた」とは、一体誰なのだろう。
想像は膨らむばかりだった。彼女の文章から滲み出るのは、穏やかで、それでいて芯の通った、凛とした女性の姿だった。彼女が愛した「あなた」は、きっと幸せな男に違いない。俺は、いつしかその架空の恋愛物語に自分を重ね、嫉妬にも似た奇妙な感情を抱いていた。
万年筆は、ある日こんな言葉を綴った。
『海が見たい。あなたの故郷の、あの静かな海が。潮風に吹かれながら、二人でどこまでも歩きたい』
俺の父の故郷は、房総半島の小さな港町だった。まさか、とは思ったが、いてもたってもいられなくなった。翌週、俺は店を臨時休業にし、始発の電車でその町へ向かった。
潮の香りが鼻腔をくすぐる。錆びついた防波堤に腰を下ろし、海を眺めた。灰色の空と海の境界線は曖昧で、カモメの鳴き声だけがやけに鮮明に響いていた。ここで、彼女も同じ景色を見ていたのだろうか。俺は万年筆を取り出し、新しいインクを詰めた。紙の上を滑るペン先から、祈るように言葉が浮かび上がるのを待った。
『約束の場所で、待っています。星が一番よく見える、あの丘の上で』
その言葉を見た瞬間、俺の全身を電流のようなものが駆け抜けた。星が一番よく見える丘。その場所を、俺は知っていた。
第三章 展望台の真実
その丘には、小さな展望台があった。子供の頃、父に何度か連れてこられた場所だ。父は決まって何も話さず、ただ遠くの漁火を二人で眺めるだけだった。俺にとっては、父との数少ない、そして気まずい思い出の場所でしかなかった。
「約束の場所」。その言葉が頭から離れない。まさか、あの万年筆が紡ぐ物語と、俺の人生が交差するなんてことがあるのだろうか。心臓は嫌な音を立てていたが、確かめずにはいられなかった。俺は車を走らせ、夜の展望台へと向かった。
展望台には誰もいなかった。冷たい夜風が頬を撫でる。眼下には、宝石を散りばめたような街の灯りが広がっていた。俺は震える手で万年筆を取り出し、最後のインクを吸い上げた。これが、この万年筆に込められた、最後の言葉になるだろう。
便箋を膝の上に置き、祈るようにペン先を当てる。
やがて、インクが滲み、ゆっくりと言葉の形を成していく。しかし、そこに現れたのは、俺が慣れ親しんだ、あの流麗な筆跡ではなかった。不器用で、角張っていて、それでいて力強い……紛れもない、父の筆跡だった。
『――今日、健人が生まれた。お前にそっくりな、大きな瞳をした子だ。美月(みつき)、見ていてくれるか』
時が止まった。呼吸も忘れた。美月。それは、俺が生まれる前に病で亡くなった、母の名前だった。
俺が追いかけていた亡霊の正体。あの繊細で、感受性豊かで、世界を愛おしむように見つめていた人物は、無口で不器用だと思っていた、俺の父だったのだ。
父は、若き日に愛した妻――俺の母――を亡くした後も、ずっと彼女に語りかけ続けていたのだ。母が愛用していたこの万年筆で。俺が女性のものだと思い込んでいた、あの美しい言葉の数々は、すべて父が天国の母へ向けて綴った、壮大なラブレターだった。
『健人が初めて歩いた。お前が夢見ていた光景だ』
『健人が、俺に似て本が好きらしい。嬉しいような、少しだけ寂しいような』
次々と浮かび上がる父の言葉。そこには、俺の知らない父の姿があった。深い喪失の悲しみを抱えながらも、息子の成長を不器用な愛情で見守り、その喜びを亡き妻と分かち合おうとしていた男の姿が。
父は俺に冷たかったのではない。愛情の表現の仕方を知らなかっただけなのだ。愛する人を失った痛みを、誰にも見せずに、たった一人で抱え込んでいたのだ。この古書店を守り続けたのも、本が好きだった母との思い出が詰まった場所だったからに違いない。
展望台の冷たい手すりにもたれかかり、俺は声を上げて泣いた。父さん。ごめん。俺は、あなたのことを何も知らなかった。漆黒の夜空から、星が涙のように降り注いでいた。
第四章 白紙のページに
父の真実を知ってから、俺の世界は色を取り戻した。いや、もとから世界は色鮮やかだったのだ。それに気づかなかったのは、俺自身の心が灰色だったからだ。
父が遺した万年筆は、インクを使い果たし、沈黙を取り戻した。俺はそれを丁寧に拭き清め、父の写真が飾られた棚の、一番よく見える場所に置いた。もう、過去の言葉を追いかける必要はない。父の愛は、確かに俺の中に届いたのだから。
月読堂の空気が、少しだけ変わった気がした。埃っぽい匂いの中に、どこか澄んだものが混じっている。俺は店の隅々まで掃除をし、窓を大きく開け放った。春の柔らかな光が差し込み、本の背表紙をきらきらと照らす。
この店は、父が母を愛し、そして俺を想った記憶の結晶だ。そう思うと、無価値だと思っていたこの場所が、途端にかけがえのない聖域に思えた。
ある晴れた午後、俺はカウンターに座り、真っ白な日記帳を開いた。そして、自分で買った真新しい万年筆に、空の色をしたインクを満たした。父が過去を綴ったように、俺は未来を綴るのだ。
ペン先を紙に下ろす。どんな言葉を書こうか。一瞬迷って、そして微笑んだ。
『――今日は、とても良い天気だ』
ありふれた、けれど確かな一文。それは、俺自身の言葉で、俺自身の物語を始めるための、最初の一歩だった。
カウンターの向こうで、カラン、とドアベルが鳴った。入ってきた客に、俺は今まで一度も見せたことのないような、晴れやかな笑顔で「いらっしゃいませ」と声をかけた。
父が遺してくれたのは、万年筆だけではなかった。それは、見えないインクで綴られた、愛という名の物語。そして、白紙のページから人生を再び始めるための、静かで力強いエールだったのだ。俺はペンを置き、ゆっくりと立ち上がった。俺の時間は、今、確かに動き始めている。