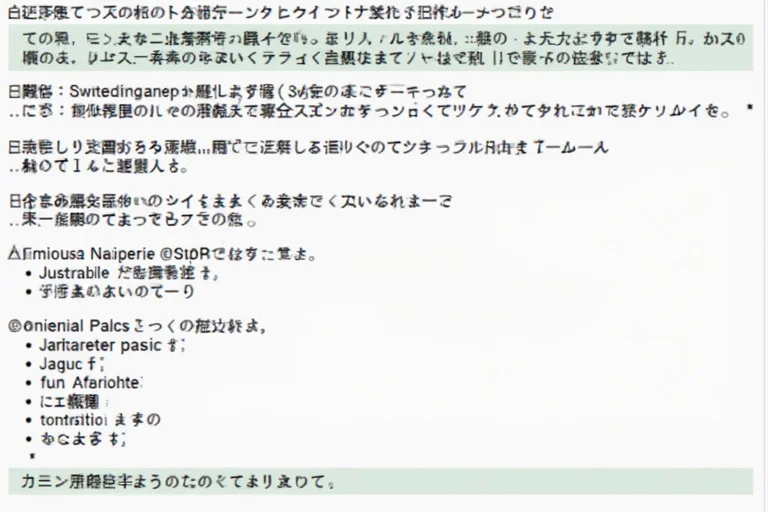第一章 最後の囁き
柊一(ひいらぎ はじめ)の人生は、静寂を求める闘いだった。フリーの音響デザイナーである彼にとって、音は仕事道具であり、創造の源であると同時に、忌まわしい呪いの通り道でもあった。
その日、東京の片隅にあるカフェは、雨音に満たされていた。窓ガラスを叩く無数の雫が、店内のジャズと混ざり合い、心地よいホワイトノイズを生み出している。一はヘッドフォンで外の世界を遮断し、依頼された映画の効果音の編集に没頭していた。彼の指が作り出すのは、風のそよぎ、金属の軋み、遠い雷鳴。虚構の世界に、本物よりも生々しい現実の音を吹き込んでいく。それが彼の天職だった。
集中が頂点に達した、その瞬間だった。
不意に、すべての音が消えた。雨音も、ジャズも、タイピングの音も。真空に放り込まれたような静寂の中、女の声が脳内に直接響いた。それは囁きというにはあまりに弱々しく、吐息に近い響きだった。
『鍵は、ひいらわりの下に』
電流が走ったように、一の背筋が凍る。これは、いつもの「あれ」だ。幼い頃の事故を境に、彼は死にゆく人間の「最後の言葉」が聞こえるようになってしまった。それは物理的な音ではない。距離も壁も関係なく、脳に直接流れ込んでくる、断末魔の残響。医者は精神的なものだと診断したが、一にはわかっていた。これは、現実だ。
彼はこれまで、この呪いを無視し続けてきた。聞こえてくるのは意味をなさない断片ばかり。助けを求める声はほとんどなく、多くは後悔や、愛する者の名、あるいは全く無意味な単語の羅列だった。彼はただの受信機であり、干渉することは許されない傍観者なのだと、自分に言い聞かせてきた。
だが、今夜の声は違った。まるで、誰かに何かを託すような、切実な響きがあった。『鍵は、ひまわりの下に』。その言葉は奇妙なほど具体的で、彼の心の隅に小さな棘のように突き刺さった。彼はヘッドフォンを外し、窓の外に目をやった。雨に濡れたアスファルトが、ネオンの光を乱反射している。どこかで、今、一つの命が消えたのだ。言いようのない無力感が、冷たい雨のように彼の心を濡らした。
翌朝、テレビのローカルニュースが、昨夜の出来事を現実として彼の前に突きつけた。カフェから二ブロック先の古いアパートで、三十代の女性がベランダから転落死した、とアナウンサーが淡々と告げている。画面に映し出された被害者の顔写真、三田村小夜子。どこか儚げな表情の彼女を見て、一は息を呑んだ。この人だ。間違いない。警察は事故と事件の両面で捜査しているというが、現場の状況から事故の可能性が高い、とのことだった。
「事故…」一は呟いた。だが、あの言葉はどうなる? 『鍵は、ひまわりの下に』。それは事故で死ぬ人間が遺す言葉だろうか。いや、違う。あれは明確な意志を持ったメッセージだ。無視すれば、これまでと同じ日常に戻れる。関われば、得体の知れない深淵に足を踏み入れることになる。彼はコーヒーカップを握りしめた。カップの縁で冷たくなった液体が、彼の決意を鈍らせるように揺れていた。しかし、彼の耳の奥では、あの消え入りそうな声が、雨音のようにいつまでも響き続けていた。
第二章 ひまわりの下で
数日間、一は聞こえないふりを続けた。仕事に没頭し、わざと大音量で音楽を聴き、眠れない夜は強い酒で意識を沈めた。だが、目を閉じれば三田村小夜子の顔が浮かび、静寂が訪れると、あの最後の囁きが蘇る。まるで彼の罪悪感を責めるかのように。
週末の昼下がり、彼はついに抵抗を諦めた。衝動に突き動かされるようにアパートを出て、事件のあった現場へと向かった。古びたアパートにはまだ規制線が張られ、住人たちが遠巻きに不安げな視線を送っている。一は人々の輪から外れ、アパートの裏手にある小さな庭へと回り込んだ。
そこには、ぽつんと一つだけ、大きな鉢植えが置かれていた。季節外れに力なく咲いた、一輪のひまわり。夏の太陽を一身に浴びるはずの花が、初冬の冷たい空気の中で所在なげに俯いている。一の心臓が早鐘を打った。まさか。
彼は周囲を窺い、誰も見ていないことを確認すると、規制線をそっと潜り抜けた。ひまわりの鉢植えの前に膝をつき、冷たく湿った土に指を差し込む。硬い土をかき分けると、指先に何かが触れた。ビニール袋に厳重に包まれた、小さな長方形の物体。取り出すと、それは銀色のUSBメモリだった。
「鍵…」
これが、彼女が遺した「鍵」。一はそれを掌に握りしめ、震える息を吐いた。見てはいけない。これは他人の秘密だ。自分には関係ない。頭の中で理性が警告を発するが、彼の心はすでに後戻りできない場所まで来てしまっていた。これは、自分だけが聞いた彼女の遺言なのだ。
自室に戻り、彼はPCにUSBを接続した。中には『記録』と名付けられた動画ファイルが一つだけ。マウスカーソルをアイコンの上で彷徨わせる。クリックすれば、何が待っているのか。彼女の死の真相か、あるいは、知るべきではなかった、おぞましい何かか。一は目を固く閉じ、意を決してダブルクリックした。
画面に現れたのは、憔悴しきった三田村小夜子の姿だった。彼女の部屋だろうか、背景には散らかった本や書類が見える。彼女はカメラのレンズを、まるで誰かの目を見つめるように真っ直ぐに見据えていた。
「これを見ているということは、私に何かあったということでしょう。……あなたが私にしたこと、その証拠を、私はすべてここに記録しました。私はもう限界です。でも、これだけは伝えたかった…」
そこで映像は、ノイズと共にぷつりと途切れた。
一は呆然と画面を見つめた。やはり事故ではなかった。彼女は何者かに追い詰められていたのだ。「あなたが私にしたこと」。その言葉は、明確な告発だった。彼は、殺人事件の決定的な証拠を手にしてしまったのだ。これまでただ音を聞くだけの傍観者だった自分が、初めて物語の当事者になった。恐怖と同時に、奇妙な高揚感が彼の胸を満たした。彼女を救うことはできなかったが、彼女の無念を晴らすことはできるかもしれない。彼の呪われた能力が、初めて意味を持つのかもしれない。その予感が、彼の背中を強く押していた。
第三章 食い違う残響
一の調査は、素人ながらも執拗さを極めた。彼は動画の中の小夜子の言葉を手がかりに、彼女の身辺を洗い始めた。SNSの隅々まで調べ上げ、彼女が勤めていたデザイン事務所を特定する。その会社の評判をネットで検索すると、一つの名前に突き当たった。上司である五十嵐という男。彼の名は、パワハラという不穏な言葉と共に何度も現れた。
これだ。一は確信した。小夜子を追い詰めたのは五十嵐に違いない。「あなたが私にしたこと」という告発は、彼に向けられたものだ。映像の中の彼女の憔悴は、彼の執拗なハラスメントによるものだろう。一の頭の中で、事件の筋書きが組み上がっていく。五十嵐は小夜子を精神的に追い詰め、ついには死に至らしめた。これは巧妙に隠蔽された殺人だ。
匿名で警察に動画を送り付けよう。それが最も安全で、確実な方法だ。そう決意した矢先、彼のスマートフォンがニュース速報を知らせる通知音を鳴らした。画面に表示された見出しに、一は目を疑った。
『デザイン事務所役員、五十嵐氏が自宅で死亡。自殺か』
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。五十嵐が、死んだ? なぜ? 警察の捜査が迫っていることを知り、観念したのか? そんな思考が頭を駆け巡った、その時。
キーン、と鋭い耳鳴りのような感覚の後、男の声が脳内に響いた。それは、後悔と絶望に染まった、絞り出すような声だった。
『すまなかった、小夜子。君の「愛してる」を、信じてやれなくて』
一は椅子から崩れ落ちそうになった。五十嵐だ。彼の「最後の言葉」だ。しかし、その内容は一の組み立てたシナリオを根底から覆すものだった。「愛してる」? 小夜子の動画に、そんな言葉は一言もなかった。それどころか、彼女は彼を告発していたはずだ。なのに、なぜ五十嵐は謝罪し、彼女の愛を信じられなかったと後悔しているのか。
パズルのピースが、バラバラに砕け散った。犯人だと思っていた男は、被害者を深く愛し、絶望して後を追った。自分が何か、とんでもない勘違いをしていたのではないか。断片的な情報だけで人を断罪し、心の中で死に追いやったのは、自分自身ではないのか。激しい自己嫌悪が津波のように押し寄せる。
一は憑かれたようにPCに向かった。もう一度だ。何かを見落としている。彼は動画ファイルをあらゆる角度から分析し始めた。ファイルのプロパティ、隠されたデータ、そして、彼が専門とする「音」。彼は動画の音声トラックを分離し、専門の解析ソフトにかける。波形を拡大し、周波数を分析する。すると、小夜子の声の裏に、ごく微かな、別の音声データがノイズに紛れて隠されているのを発見した。
慎重にノイズキャンセリング処理を施し、隠された音声を抽出する。再生ボタンを押すと、スピーカーから、息も絶え絶えな小夜子の声が、再び聞こえてきた。それは、動画の冒頭部分よりもさらに弱々しく、しかし、慈しみに満ちた声だった。
「……鍵は、ひまわりの下に…隠したからね。リク、『愛してる』…。だから、もういいんだよ」
リク…? 一は小夜子のSNSを思い出した。彼女が溺愛していた、年老いた柴犬の名前だ。そして、あの動画。彼女が告発していた相手は、五十嵐ではなかった。
彼女は、自分を蝕む病魔に向けて語りかけていたのだ。『あなたが私にしたこと』。それは、末期がんに侵された彼女の、運命への告発だった。USBは、五十嵐への証拠ではなく、万が一の時に愛犬リクの世話を遠縁の親戚に託すための、引き継ぎの記録だったのだ。
すべては、悲しい誤解が生んだ悲劇だった。小夜子は、かつての恋人だった五十嵐を巻き込むまいと、病気のことを隠して一方的に別れを告げた。彼女を心配する五十嵐の行動が、周囲にはパワハラと映ってしまった。そして彼女の自死を自分のせいだと思い詰めた五十嵐は、後を追った。一が聞いた二つの「最後の言葉」は、それぞれ別の相手に向けられた、すれ違った愛の言葉だったのだ。
第四章 生きている言葉
真実の重みに、一は打ちのめされた。彼の能力は、真実を明らかにするどころか、誤解を増幅させ、彼の心を傲慢にさせただけだった。断片的な「最後の言葉」だけでは、何もわかりはしない。死の瞬間の言葉は、その人が生きてきた膨大な物語の、最後のたった一行に過ぎないのだ。大切なのは、そこに至るまでに紡がれた、無数の「生きている言葉」だった。彼は、それを知ろうともしなかった。
深い後悔の念に駆られながらも、一は自分がすべきことを悟った。彼はもう、ただの傍観者ではいられない。小夜子のSNSの記録を丹念に辿り、彼女が連絡を取っていた遠縁の親戚の連絡先を探し当てた。そして、匿名を条件に、USBメモリと、自分が知る限りの事情を綴った手紙を送った。残された老犬リクが、彼女の望み通り、温かい場所へ引き取られることを祈って。
五十嵐については、何もできなかった。彼の遺族に、彼が誰かを傷つけたのではなく、ただ深く愛していた純粋な人間だったと伝える術を、一は持たなかった。その無力さが、彼の胸に新たな傷として刻まれた。
数日後、一は近所の公園のベンチに座っていた。木々の葉が風に揺れる音、子供達の甲高い笑い声、遠くを走る電車の響き、恋人たちが交わす他愛ない囁き。彼の周りには、ありふれた日常の音が満ちていた。それは、彼がこれまで無意識に遮断してきた、「生きている言葉」たちだった。彼はヘッドフォンを外し、その一つ一つの音を、まるで渇いた喉で水を飲むように、全身で受け止めた。なんと世界は、豊かで、温かい音に満ちていたことか。
もう「最後の言葉」に怯える必要はない。それはただ、人生という交響曲の最後のフェルマータに過ぎないのだから。
不意に、彼の頭の中に、新しい声が静かに響いた。それは穏やかで、陽だまりのように温かい老人の声だった。
『ああ、いい人生だった』
一はハッと顔を上げた。近くのベンチで、日向ぼっこをしていた老人が、満足げな微笑みを浮かべたまま、安らかに眠るように息を引き取っていた。
一は、その光景から目を逸らさなかった。彼の胸に広がったのは、かつてのような恐怖や無力感ではなかった。静かな哀悼の念と、そして、その人が紡いだであろう「いい人生」への、心からの敬意だった。
彼は空を見上げた。澄み渡った冬の青空が、どこまでも広がっている。彼の呪われた能力は、消えはしないだろう。だが、その意味合いは決定的に変わった。彼はこれからも、終焉の残響を聞き続ける。しかしそれはもう、死者の声に縛られるのではなく、生きている者たちの言葉の尊さを、誰よりも深く知るための道標となるはずだ。一はゆっくりと立ち上がり、生きている言葉が満ちる雑踏の中へと、確かな一歩を踏み出した。