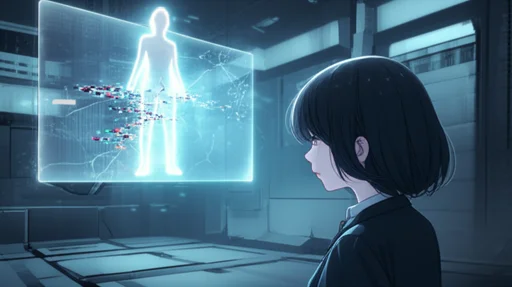第一章 残響の依頼人
時枝響(ときえだ ひびき)の世界は、音で構築されている。十年前に光をほとんど失って以来、彼の聴覚は異常なまでの鋭敏さを獲得した。それは単に遠くの音や微かな音を拾うだけではない。彼は、空間に染み付いた「音の記憶」を聴くことができた。特定の湿度、温度、そして物質の配置。条件が揃ったとき、まるでレコードの針を落とすように、その場所で過去に響いた象徴的な音が、響の鼓膜にだけ蘇るのだ。
その能力を活かし、彼はピアノ調律師として生計を立てていた。完璧な調律は、ピアノが「記憶」している最も美しい音を引き出す作業に他ならなかったからだ。しかし時折、彼の元には風変わりな依頼が舞い込む。警察が匙を投げた、音を手がかりとする事件の調査依頼だ。
その日、彼の仕事場である防音スタジオの重い扉を叩いたのは、倉持小夜子と名乗る女性だった。黒いスーツに身を包み、気丈に振る舞ってはいるが、その声には疲労と悲しみが細いひびのように走っていた。
「父が、一週間前に亡くなりました」
彼女の父、倉持源一郎は、著名なアンティーク収集家であり資産家だった。書斎で亡くなっているのが発見され、警察は心臓発作による事故死と断定した。しかし、小夜子は納得していなかった。
「父の書斎は、内側から鍵がかけられていました。完全な密室です。ですが、妙なことがあるのです」
彼女は一枚の写真を取り出した。重厚なマホガニーの机、革張りの椅子、そして床に砕け散ったアンティークのオルゴールが写っている。
「警察は、父が発作の苦しみに、そばにあったオルゴールを払い落としたのだろうと。でも、父はあのオルゴールを何よりも大切にしていました。まるで自分の心臓のように。そんな父が、あれを壊すなんて考えられません」
響は黙って彼女の話に耳を傾けていた。彼の興味は、事件の状況よりも、彼女が発する声の響きにあった。それは、答えの出ない問いに苛まれる者の不協和音だった。
「時枝さん。あなたなら、そこに残された音を聴くことができると伺いました。お願いです。父が最期に聴いた、あるいは発した音を教えてください。それがどんな音であれ、私には知る必要があるのです」
光の乏しい響の瞳が、初めて真っ直ぐに小夜子を捉えた。彼女が求めているのは、事件の真相ではない。父の心の、最後の響きだった。
「わかりました。調律、いたしましょう。あなたのお父様の、最後の時間を」
第二章 聞こえない旋律
倉持源一郎の書斎は、時が止まったかのような静寂に満ちていた。壁一面の本棚、年代物の天球儀、そして主を失った巨大なデスク。空気はインクと古い紙、そして微かな樟脳の匂いがした。響は、警察から許可を得て再現された現場に、小夜子と共に足を踏み入れた。
「父は、ここでいつも一人でした」と小夜子が呟く。「私とも、あまり話をしない人で…」
その声には、父親との間にあったであろう距離感が滲んでいた。
響は何も言わず、携えてきた精密な温湿度計とレーザー距離計を取り出した。彼は、事件当日の気象データに基づき、部屋の環境をミリ単位で再現していく。エアコンの温度を調整し、加湿器で霧を発生させ、家具の位置を写真と寸分違わぬ場所へと戻す。それは、失われた音を呼び覚ますための、厳粛な儀式だった。
すべての準備が整うと、響は部屋の中央に置かれた椅子に静かに腰掛け、目を閉じた。世界の雑音が消え、意識が研ぎ澄まされていく。彼の聴覚が、空間の微細な振動を探り始める。古い木の軋み、壁を伝う水の音、遠い街の喧騒。それらのノイズを濾過し、さらに深く、記憶の底へと潜っていく。
十分、二十分。額に汗が滲む。小夜子は息を殺してその様子を見守っていた。諦めかけた、その瞬間だった。
「……聴こえた」
響の唇から、か細い声が漏れた。彼の脳内で、一つの音が鳴り響いた。それは、オルゴールの音楽ではない。人の声でも、物が倒れる音でもない。
「チリン……」
澄み渡る、小さな鈴の音。しかし、その響きはどこか奇妙に歪み、長く尾を引いていた。まるで、水中で鳴らしたかのように。
「鈴、ですか?」小夜子が尋ねる。「書斎に鈴など、ありませんでしたけれど…」
「ええ。ですが、確かに聴こえました。一度だけ、鋭く響いた音です」
響は目を開けた。彼の内なる世界で鳴り響いた音は、現実の謎をさらに深めるだけだった。オルゴールとは無関係の、場違いな鈴の音。それは一体、何を意味するのか。
調査は振り出しに戻った。響は、源一郎の交友関係や過去を洗い直すことにした。彼は、数人の若き芸術家や研究者に、匿名で援助を行っていたことが判明する。その中に、相馬蓮(そうま れん)という名の、若き音響発明家がいた。彼は、音をエネルギーに変換するという、夢のような研究に没頭していたが、最近、源一郎からの支援が突然打ち切られ、研究が行き詰まっているという。
逆恨みによる犯行か?しかし、現場は密室だ。響の頭の中で、澄んだ鈴の音と、打ちひしがれた若者の姿が、不穏な和音を奏で始めた。
第三章 時を渡る和音
相馬蓮は、響が訪ねたとき、ガラクタに埋もれた小さな研究室で、虚ろな目をして座っていた。源一郎の死を知らされて以来、彼は絶望の淵にいた。
「倉持さんは、僕の唯一の理解者でした。彼がいなければ、僕の研究は…」
蓮の声は力なく、彼の発明品である奇妙な集音装置が、沈黙の中で埃を被っていた。響は彼に動機があるとは思えなかった。彼の悲しみは、あまりに純粋なものに感じられた。
捜査は暗礁に乗り上げた。密室、動機不明の容疑者、そして謎の鈴の音。響は自身の能力にさえ、疑念を抱き始めていた。あの音は本当に過去の残響だったのか?自分の疲れた精神が生み出した幻聴ではないのか?
彼はもう一度だけ、あの音を確かめる必要があった。小夜子に無理を言って、再び倉持家の書斎を訪れた。前回とまったく同じ条件を、寸分の狂いもなく再現する。彼は再び椅子に座り、意識を集中させた。
今度は、もっと深く。もっと繊細に。
彼はあの「チリン」という音の、さらに奥にあるものを探った。音の響き、その質感、余韻の消え方。すべてを分解し、再構築する。すると、彼の意識は奇妙な事実に気づいた。あの音は、過去から響いてくる音特有の「減衰」が感じられない。まるで、今ここで鳴っているかのように、生々しいのだ。
そのとき、響の脳裏に、相馬蓮の言葉が蘇った。『音をエネルギーに変換する研究』。
まさか。ありえない。しかし、もし、その逆が可能だとしたら?エネルギーを、未来の特定の瞬間に「音」として変換することができたなら?
全身に鳥肌が立った。犯人はいない。これは殺人事件ではない。
源一郎は、自らの死を選んだのだ。そして、彼の死は、ある壮大な計画の一部だった。
響は、現場をもう一度見渡した。壊れたオルゴール。床に落ちた、写真には写っていなかった小さな金属片。それは、源一郎が大切にしていた懐中時計の鎖についていた、小さな鈴だった。
彼は、最後の瞬間にオルゴールを床に叩きつけ、同時に懐中時計の鈴を鳴らした。その二つの音が発する微弱な音響エネルギーを、あらかじめ部屋に仕掛けられていた蓮の発明品のプロトタイプが吸収した。そして、そのエネルギーを、一週間後の「今、この瞬間」に、一つの音として再放出するようにプログラムしたのだ。
響が聴いた「チリン」という歪んだ音。それは、オルゴールの最後の不協和音と、鈴の澄んだ音が、時を超えて混ざり合い、再構成された「和音」だったのだ。
それは、過去の残響ではなかった。
未来へ向けて放たれた、時限式のメッセージだった。
第四章 心を調律する音
「お父様は、あなたを憎んでいたわけでも、絶望して命を絶ったわけでもありませんでした」
響は、小夜子と蓮を前にして、静かに語り始めた。彼は、自らがたどり着いた驚くべき真相を、一つ一つ丁寧に説明した。源一郎が、自らの死を賭してまで、若き発明家・蓮に伝えたかったメッセージの存在を。
「彼は、君の才能を誰よりも信じていたんだ、相馬君」響は蓮に向き直った。「支援を打ち切ったのは、君を憎んだからじゃない。自分の死期を悟り、最後の資金を、この計画のために使ったんだ。彼は、自分の死をもって、君の発明が本物であることを証明したかった。時を超えて音を届けるという、奇跡を」
蓮は、わなわなと震えていた。彼の目から、大粒の涙がとめどなく溢れ落ちる。支援者の死に打ちひがれ、すべてを諦めかけていた彼にとって、それはあまりにも衝撃的で、そして温かい真実だった。源一郎が残したかったのは、単なる音ではない。それは「君の理論は正しい。その道を、進め」という、魂からのエールだったのだ。
隣で聞いていた小夜子も、静かに涙を流していた。厳格で、自分を避けているとさえ思っていた父。その最後の行動が、これほどまでに誰かの未来を想う、優しさに満ちたものだったとは。彼女は、父が壊したオルゴールの本当の意味を、ようやく理解した。あれは、古い時代との決別と、新しい才能への希望を託した、最後の演奏だったのだ。父と娘の間にあったわだかまりが、時を超えて届いた優しい音色によって、静かに溶けていくのが分かった。
事件は、解決した。しかし、それは誰も罰せられることのない、切なくも美しい結末だった。
響は、倉持邸を後にした。彼の世界は、まだ光に乏しいままだ。しかし、彼の心には、確かな光が灯っていた。これまで、音を客観的な「証拠」や「情報」としてしか捉えてこなかった。だが、今日、彼は知ったのだ。音には、人の心や想いが宿ることを。時さえも超えて、誰かの心を温める力があることを。
彼の能力は、単に過去の音を聴くためのものではない。それは、音に込められた心を拾い上げ、人と人とを繋ぐための「調律」なのだ。
帰り道、響の耳に、街の様々な音が流れ込んでくる。車のクラクション、人々の笑い声、遠くで練習する子供のピアノの音。それら一つ一つの音が、今はすべて、誰かの想いを乗せたメロディのように聴こえた。彼はそっと目を閉じ、その温かい不協和音に、静かに耳を傾ける。世界は、こんなにも豊かな音楽で満ち溢れていた。彼の残響調律師としての、本当の人生が始まった瞬間だった。