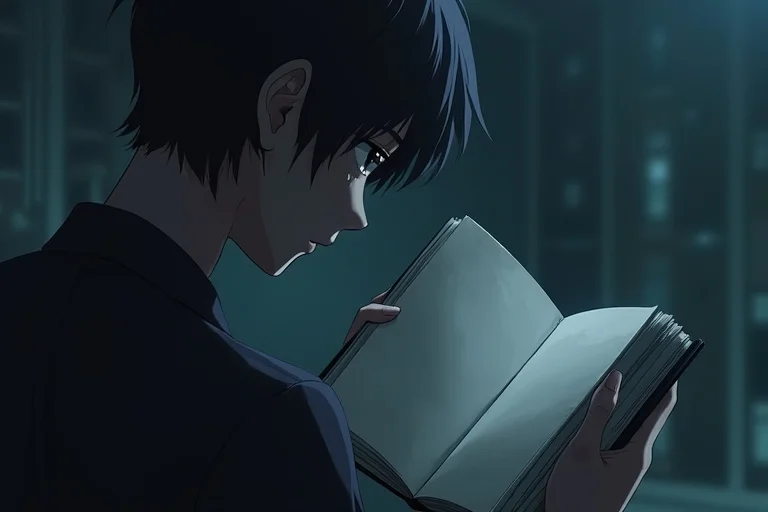第一章 色彩のない依頼人
古びた紙の匂いと、微かなインクの香り。僕の営む古書店『言の葉の森』は、静寂を愛する者たちのための聖域だ。背表紙の褪せた本棚に囲まれ、埃の粒子が光の筋となって踊るこの空間で、僕は世界との間に心地よい距離を保っていた。僕には、人々の言葉に色が視える。嘘をつく時、その声には粘つくような色彩がまとわりつくのだ。自己保身の嘘は汚れた黄色に、悪意に満ちた嘘は濁った血のような赤に。この共感覚のせいで、僕はとうに人間を信じることをやめていた。だから、この店は僕にとって最高の隠れ家だった。
その日、店のドアベルが澄んだ音を立てた時、僕はカウンターの奥で稀覯本の修繕をしていた。入ってきたのは、雨に濡れた紫陽花のような儚げな女性だった。歳は二十代半ばだろうか。透き通るような白い肌と、不安げに揺れる黒い瞳が印象的だった。
「あの……」
彼女の声は、まるで磨かれた水晶のようだった。そして、何よりも僕を驚かせたのは、その声に一切の色がまとわりついていないことだった。無色透明。それは、僕がこの世で最も稀有だと感じる、一点の曇りもない真実の色だった。
「店主の方ですか? 相談したいことがあって……」
僕は警戒しながらも顔を上げた。「うちは探偵事務所じゃないですよ」
「知っています。でも、あなたなら、と。人探しの名人だと、噂で聞きました」
そんな噂が立つはずがない。僕は人との関わりを極力避けてきたのだから。誰かが流した悪質なデマだろう。だが、彼女の言葉はどこまでも透明だった。
「兄が、一週間前から行方不明なんです」彼女は言った。「名前は高遠朔(たかとお さく)。警察にも届けましたが、事件性がないと積極的には動いてくれなくて。どうか、力を貸していただけませんか」
彼女――高遠美咲(たかとお みさき)と名乗った――の瞳は、純粋な憂慮で満ちていた。僕は普段なら一瞥もくれずに断る依頼だ。しかし、目の前の透明な存在が、僕の心の壁を静かに溶かしていくのを感じていた。色のない言葉。それは、僕がずっと探し求めていた、汚染されていない世界の欠片だった。
「……分かりました。少しだけですよ」
僕は、自分の口から滑り出た言葉に自分で驚いていた。美咲の顔に、ぱっと安堵の花が咲く。その笑顔もまた、一点の曇りもない透明な輝きを放っていた。僕は、この色彩のない依頼人に、抗いがたい引力のようなものを感じ始めていた。
第二章 濁色の証言
翌日、僕と美咲は、失踪した兄・朔のマンションを訪れた。部屋はまるでモデルルームのように整然としており、生活感というものが希薄だった。几帳面な人物だったのだろう。美咲は「兄は昔から潔癖なところがあって」と、やはり透明な声で呟いた。
部屋を調べていると、書斎の机に一冊だけ、不自然に開かれたままの古い詩集が目に留まった。ポール・エリュアールの詩集だ。栞も挟まっていない。まるで、何かを読んでいた途中で、ふと立ち上がってそのまま消えてしまったかのように。僕はその詩集をカバンにしまった。
僕たちは、朔の足取りを追って関係者への聞き込みを始めた。そこで僕は、再び色に満ちた世界の濁流に飲み込まれることになった。
最初に会ったのは、朔の職場の同僚だった。彼は心配そうな顔で言った。
「高遠さんは本当に優秀な人でした。彼がいなくなるなんて、信じられません」
だが、その言葉には、嫉妬を示すどす黒い緑色がまとわりついていた。彼は朔の才能を妬んでいたのだ。
次に会ったのは、朔の恋人だと名乗る女性だった。彼女は泣きはらした目で僕たちを迎えた。
「朔さんがいなくなるなんて……私には何も心当たりがありません。ただ、最近少し、何かに怯えているようには見えました」
彼女の涙声は、悲しみを示す深い藍色ではなかった。それは、恐怖を隠すための冷たい灰色に染まっていた。彼女は何かを知っている。そして、それをひどく恐れている。
誰も彼もが、言葉とは裏腹の色彩を放っていた。保身、欺瞞、嫉妬、恐怖。僕は彼らの嘘を簡単に見抜くことができたが、それが朔の失踪にどう繋がるのかは全く分からなかった。色の洪水は、僕に優越感を与えるどころか、方向感覚を失わせる霧のように思考を掻き乱した。
僕が苛立ちを募らせる一方で、美咲は終始、落ち着いていた。彼女は関係者たちの色のついた言葉に耳を傾け、悲しそうに眉をひそめるだけだった。彼女の存在だけが、この濁った世界における唯一の救いだった。彼女の言葉は常に透明で、その純粋さが僕の荒んだ心を洗い流してくれるようだった。
「響介さん、ありがとうございます。あなたといると、なぜか安心します」
喫茶店で休憩している時、彼女はそう言って微笑んだ。その透明な微笑みに、僕は少しだけ胸が高鳴るのを感じた。この人のためなら、必ず兄を見つけ出してやろう。そう、強く思った。僕の能力は、この人のためにこそあるのだと信じ始めていた。
第三章 透明な嘘
捜査は完全に行き詰まっていた。関係者たちの嘘は分かっても、それが失踪の核心を突くものではない。僕は古書店に戻り、朔の部屋から持ち帰ったエリュアールの詩集をもう一度手に取った。何か見落としがあるはずだ。
僕はページを一枚一枚、指先で確かめるようにめくっていった。すると、いくつかの単語の、特定の文字の上に、肉眼ではほとんど見えないほどの小さな針の穴が開いていることに気づいた。偶然できた傷ではない。意図的に、誰かが印をつけたものだ。
僕は息を殺して、印のつけられた文字を順番に拾い上げていった。「う」「そ」「つ」「き」「は」「お」「ま」「え」「だ」。
――嘘つきはお前だ。
その言葉が脳内で再生された瞬間、背筋を冷たいものが走り抜けた。これは誰から誰へのメッセージだ? 朔から、僕らへの? いや、違う。これは、もっと根源的な何かを指し示している。
その時、雷に打たれたような衝撃と共に、ある仮説が僕の頭を貫いた。僕の能力は、「嘘」そのものを見ているわけじゃない。人が「これは真実ではない」と自覚しながら言葉を発する時、その罪悪感や背徳感が「色」として現れるに過ぎないのだ。だとしたら……もし、話している本人が、自分の嘘を心の底から真実だと信じ込んでいたら? その言葉は、きっと、何の色も持たないはずだ。無色透明に、響くはずだ。
美咲の顔が浮かんだ。彼女の言葉は、いつも透明だった。一点の曇りもなかった。僕は彼女の純粋さを信じていた。だが、もし、それが純粋さの証明ではなかったとしたら?
僕は震える手でスマートフォンを取り、ある精神科医の友人に電話をかけた。記憶障害や人格解離について、矢継ぎ早に質問を浴びせる。友人の説明を聞くうちに、僕の中で恐ろしいパズルが完成していった。
僕は美咲を店に呼び出した。彼女はいつものように、儚げな微笑みを浮かべてやってきた。
「響介さん、何か分かりましたか?」
その声は、やはりどこまでも透明だった。
「美咲さん、あなたにはお兄さんが本当にいたのですか?」
僕の問いに、彼女はきょとんとした顔をした。「もちろんです。何を言っているんですか?」
「では、そのお兄さんは、どこにいるんですか?」
僕はゆっくりと、彼女に問いかけた。核心に触れるように。
「だから、探しているんじゃありませんか。一週間前から、行方不明で……」
彼女の声が、わずかに揺れた。僕は続けた。
「詩集のメッセージは、あなた自身に向けられたものではありませんか? あなたの中にいる、もう一人の……『お兄さん』から」
その瞬間、美咲の顔から表情が消えた。純粋な少女の顔が、能面のように冷たく、硬直していく。そして、次の瞬間、彼女の口元が歪み、聞いたこともないような低く、冷たい声が響いた。
「……余計なことを嗅ぎまわるな、古本屋」
その声には、色がついていた。今まで見たこともないほど深く、おぞましい、憎悪に満ちた漆黒の色が。
美咲は、解離性同一性障害を患っていたのだ。彼女の中には、厳格で支配的だった亡き父親のイメージを投影した、攻撃的な別人格――彼女が「兄」と呼ぶ存在――がいた。彼女はその「兄」という人格に長年苦しめられていた。そして一週間前、彼女はついに、自分の中から「兄」を消し去るために、ある種の精神的な自死行為に及んだのだ。彼女は「兄を殺し」、その記憶に蓋をした。そして、自分を守るために「兄は失踪した」という新しい物語を創り上げ、それを完璧な真実として信じ込んでいた。だから、彼女の言葉は「透明」だったのだ。兄は失踪したのではない。彼女自身の手によって、彼女の心の一番深い場所に封印されたのだ。
第四章 世界が色を取り戻す時
目の前で、美咲は小さな子供のように蹲り、嗚咽を漏らしていた。漆黒の声を放った人格はもういない。そこにはただ、自らが作り出した物語の崩壊に怯える、傷ついた一人の女性がいるだけだった。
僕は、自分の能力を呪った。色が見えることに驕り、人の心の複雑さから目を逸らしていた。透明な言葉を純粋さと信じ込み、その裏に隠された、あまりにも深い絶望と孤独に気づけなかった。真実とは、色の有無で判断できるほど単純なものではなかったのだ。
僕は警察に電話する代わりに、精神科医の友人に連絡を取った。僕がすべきことは、彼女を裁くことではない。彼女が、自らの内なる闇と向き合い、壊れてしまった心の欠片を拾い集める手助けをすることだ。
数日後、専門の医療機関に入院することが決まった美咲が、僕の店に挨拶に来た。彼女の顔にはまだ深い疲労の色が浮かんでいたが、その瞳には、微かな光が宿っているように見えた。
「響介さん、ありがとうございました。そして……ごめんなさい」
彼女の声は、もう完全な透明ではなかった。微かに、だが確かに、後悔や不安を示す淡い色が混じっていた。それは、彼女が自分の心と向き合い始めた証拠だった。
「いいんですよ」僕は静かに言った。「ゆっくり、あなたの言葉を取り戻してください」
彼女は小さく頷き、店を去っていった。ドアベルの音が、やけに寂しく店内に響いた。
事件は一応の終わりを迎えた。しかし、僕の心には、晴れやかな達成感など欠片もなかった。ただ、深い切なさと、一つの問いが残った。真実とは何だろうか。嘘とは何だろうか。彼女にとって、「兄の失踪」は紛れもない真実だったのだ。
僕はカウンターの椅子に座り、窓の外を行き交う人々を眺めた。彼らの会話から漏れ聞こえる声には、相変わらず様々な色がまとわりついている。以前は汚らわしいとさえ感じていたその色彩が、今は少し違って見えた。それは、人が必死に生きている証なのだ。弱さを隠し、虚勢を張り、誰かを思いやり、自分を守るために紡がれる、不器用で人間らしい色の数々。
世界は、こんなにも多くの色で満ち溢れていた。
僕はこの古書店で、これからも言葉と向き合って生きていくだろう。だが、もう色だけに惑わされることはない。本当に大切なものは、目に見える色の奥にある、声にならない心の叫びなのだから。
窓から差し込む西日が、埃を金色に照らし出していた。僕には、その光が無色透明に見えた。