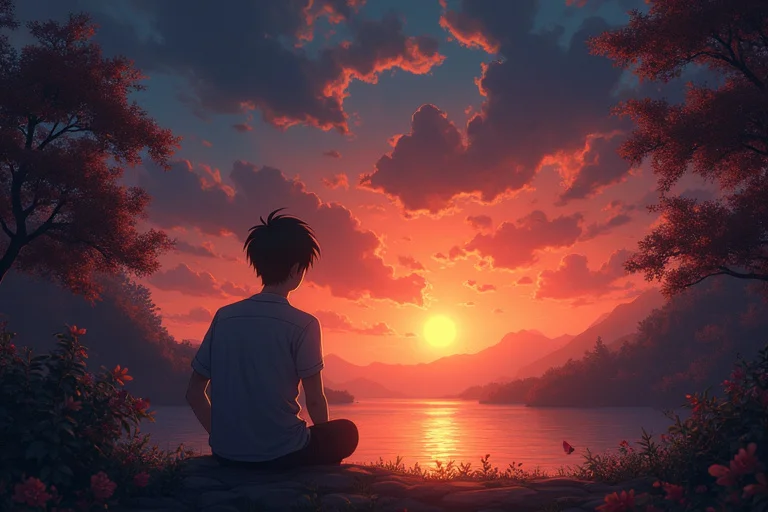第一章 不協和音の街角
俺、水無月 律(みなづき りつ)の耳には、常に世界が奏でる不協和音が響いている。それは他者の認識の歪み、集団が共有する「誤解」が生み出す物理的な共鳴音だ。街角のカフェで、カウンターに置かれた砂糖と塩のポットが入れ替わった時もそうだった。
最初の一人が間違え、次の一人がそれに倣う。やがて「こちらが砂糖だ」という誤った認識が過半数を超えた瞬間、俺の鼓膜を鋭い金属音が突き刺した。世界の法則――『共感律』が発動し、塩の結晶構造が物理的に糖のそれへと書き換えられたのだ。俺は顔をしかめながら立ち上がり、客たちの認識が完全に固定される前に、そっとポットを正しい位置に戻す。これが俺の仕事、「調律師」だ。
些細な誤解の音は、指で弾いたグラスの縁が震えるような、か細い残響に過ぎない。しかし、俺の意識の奥底では、片時も止むことなく、途方もない絶叫が轟いている。それは都市一つを丸ごと飲み込むほどの、巨大な「誤解」が放つ断末魔。
『沈黙の都市』。
歴史の教科書には存在しない。地図のどこにも記されていない。誰もが「そんなものは妄想だ」と口を揃える、失われた都市。だが俺の耳には、その都市が存在したという、かき消された真実の絶叫が、灼熱の鉄塊のように流れ込み続けていた。この世界でただ一人、俺だけが、その巨大な嘘の軋みを聞いていた。
第二章 虚ろの盆地
その絶叫は、旧首都の東に広がる『虚ろの盆地』と呼ばれる巨大なクレーターに近づくほど、明確な輪郭を帯びてくる。共感律管理局は盆地一帯を最高レベルの禁忌区域に指定し、立ち入ることは固く禁じられていた。管理局の公式見解は「原因不明の大規模地盤沈下」。だが、人々がそれを信じれば信じるほど、俺の耳に響く不協和音はさらに強くなるのだ。
今夜も絶叫は一段と激しく、俺を眠らせてはくれなかった。もはや、ただの耳鳴りではない。それは呼び声だった。忘れられることに抗う、魂の慟哭。
俺はベッドを抜け出し、くたびれたコートを羽織った。管理局の監視網を抜ける算段はとうに出来ている。彼らが張り巡らせた「認識の壁」――侵入者は存在しないという集団意識のシールド――の僅かな歪みを、俺の耳は正確に捉えることができる。
盆地の縁に立った時、乾いた風が俺の頬を撫でた。風は、焦げ付いた金属の匂いと、大勢の人々の涙が蒸発したような、奇妙な塩辛さを運んでくる。足元から、地の底深くで何かが引き裂かれるような微かな振動が伝わってきた。絶叫は、もはや耳で聞く音ではなかった。全身の細胞を震わせる、巨大な悲鳴そのものだった。
第三章 共鳴する黒石
クレーターの中心へ向かうにつれ、足場は不安定になり、ねじくれた鉄骨や、ガラスが溶けて固まったような黒い塊が剥き出しになっていた。ここは、ただ地盤が沈下した場所ではない。何か途方もない力が、全てを融解させ、そして抉り取ったのだ。
絶叫の中心、クレーターの最深部で、俺は黒く滑らかな石に躓いた。掌に収まるほどの大きさの、何の変哲もない楕円形の石。だが、俺がそれを拾い上げた瞬間、世界から一切の音が消えた。
耳を劈いていた絶叫が、ぴたりと止んだのだ。代わりに、掌の中の石が、まるで心臓のように微かに脈打ち始めた。ゴオォ、と地鳴りのような低い振動が、石から俺の腕を伝い、全身へと広がっていく。
これが『共鳴石』。絶叫の源。
石の振動に導かれるように、俺は近くの瓦礫の山に隠された、地下へと続く階段を発見した。錆びついた鉄の扉を開くと、カビと埃の匂いが混じった冷気が、まるで亡霊のように這い出してきた。石の鼓動は、俺を暗闇の奥底へと誘っていた。
第四章 忘れられた街
地下に広がっていたのは、まさに都市だった。時間が止まったかのように静まり返った街並み。光源一つない暗闇の中、共鳴石だけがぼんやりと青白い光を放ち、前方を照らし出している。
そこには人の気配は一切なかった。だが、人の痕跡だけが生々しく残されていた。壁には無数の引っ掻き傷が刻まれ、広場の床は高熱で歪み、まるで巨大な爪で抉られたかのような跡が続いていた。ここで一体、何が起きたというのか。
俺は都市の中心にある、巨大なドーム状の建造物へと足を踏み入れた。内部はがらんどうで、中央に祭壇のような台座が一つあるだけだった。石の脈動が最高潮に達している。俺は導かれるままに台座へ近づき、その上に共鳴石を置いた。
その瞬間、石は眩い光を放ち、俺の意識は光の奔流に飲み込まれた。
第五章 共感律の揺り籠
脳内に直接、情景が流れ込んでくる。それは『沈黙の都市』の最後の日だった。
人々は空を見上げ、絶望に顔を歪めていた。空には、星々を喰らい尽くす巨大な「虚無」が広がっていた。それは宇宙の熱的死、あるいは人類の理解を超えた外なる存在の影。いずれにせよ、それは抗いようのない「絶対的な真実」だった。
その過酷すぎる真実に直面した人類は、希望を失い、狂気と混乱の中で自滅しかけていた。世界中で秩序が崩壊し、文明が崩れ落ちていく。
この都市の科学者たちは、人類を救う最後の手段を編み出した。それが『共感律』システム。人々の意識を繋ぎ合わせ、都合の良い「現実」を信じ込ませることで、過酷な真実から目を逸らさせる、巨大な幻想の揺り籠。
システムを起動するには、一つの「現実」を犠牲にする必要があった。彼らは、自らが住むこの都市と、人類を狂わせた「絶対的な真実」そのものを、新しい世界から消し去ることを選んだ。
「我々は、真実と共に沈む」
最後に聞こえたのは、システムの設計者の冷静な声だった。次の瞬間、都市は閃光に包まれ、世界からその存在を抹消された。
俺が聞いていた絶叫は、消された人々の悲鳴ではなかった。それは、この世界から追放され、封印された「真実」そのものが、忘れられることに抗い、響かせ続ける慟哭だったのだ。
第六章 調律師の選択
光が収まると、俺はドームの中央に立っていた。祭壇だと思っていたものは、脈動する光の球体――『共感律』システムのコアだった。偽りの平和を奏で続ける、世界の心臓部。
全てを理解した。俺の能力は、このシステムが生み出した偶然の産物だった。真実の残響を聞き取れる唯一の耳は、システムのコアと共鳴し、その調律を司るための鍵だったのだ。
俺の目の前には、二つの道が拓けていた。
一つは、このコアを破壊し、封印された「真実」を世界に解き放つこと。人々は偽りの青空の向こうにある、絶望的な虚無を再び知ることになる。世界は混乱に陥るだろう。だが、それは紛れもない「本物」の現実だ。
もう一つは、このコアを再封印し、沈黙の都市の記憶と共に、自らの存在も消し去ること。人類は心地よい幻想の中で、偽りの平和を享受し続ける。その平和は、巨大な嘘の上に成り立つ、脆い硝子の城だとしても。
どちらが正しい? 偽りの幸福か、真実の絶望か。
俺は、静かに脈動するコアに手を伸ばした。世界の調律師として、俺が奏でるべき音は、たった一つしかない。
第七章 世界が揺らぐ音
俺が地上に戻った時、空には夜明けの光が差し始めていた。虚ろの盆地を吹き抜ける風の音が、昨日までとは少しだけ違って聞こえる。それは、どこか澄み切ったような、それでいて深い哀しみを湛えた音色だった。
街に戻ると、人々はいつもと変わらない朝を迎えていた。カフェの店員はにこやかに「おはようございます」と言い、カウンターの砂糖と塩は、正しく置かれていた。世界の不協和音は、鳴りを潜めている。
ただ、一つだけ変わったことがあった。
人々がふと空を見上げた時、その瞳に一瞬だけ、戸惑いの色が浮かぶようになったのだ。彼らが「青」だと信じてきた空の向こうに、何か途方もなく広大な、名付けようのない気配を感じ取るようになったかのように。
俺の耳の奥で鳴り響いていた絶叫は、もう聞こえない。代わりに、静かで、荘厳な、まるで宇宙そのものが奏でるようなハーモニーが、世界に満ち始めていた。
それが希望の音なのか、それとも終焉への序曲なのか。まだ、誰にもわからない。俺はただ、生まれ変わった世界の最初の音を、静かに聞いていた。