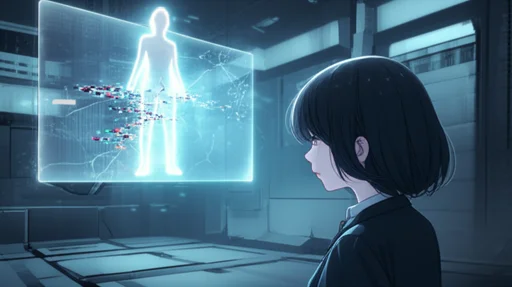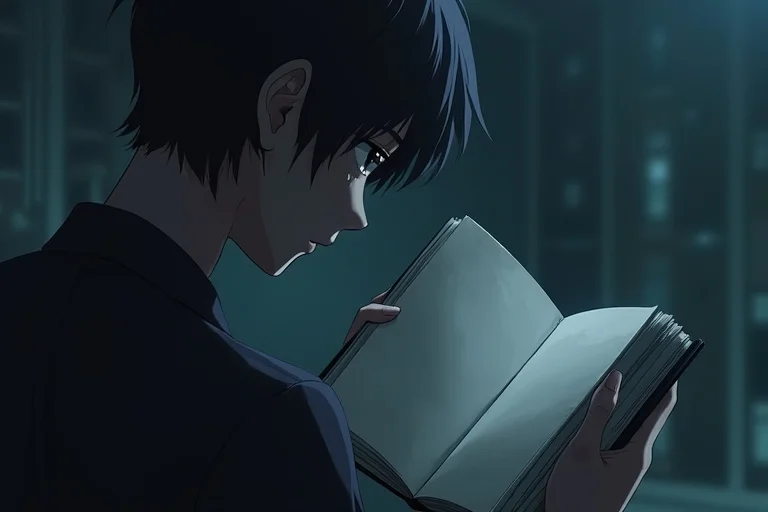第一章 静寂の不協和音
俺、月森響介(つきもり きょうすけ)の世界は、音で彩られている。言葉は形を持ち、音楽は風景を描き、沈黙でさえ微かな色を帯びていた。共感覚(シナスタジア)。医者はそう診断したが、俺にとっては生まれながらの現実だ。他人の声が、真実を語るときは澄んだ青に、嘘をつくときは澱んだ黄土色に見えるこの力は、人間関係を煩わしいものに変えた。だから俺は、決して嘘をつかないピアノの調律師になった。百二十本の弦が織りなす純粋な音の世界だけが、俺の安息の地だった。
その日、俺を静寂から引きずり出したのは、一本の電話だった。相手は、長年の顧客であり、かつて俺に音楽の道を拓いてくれた恩師、藤堂千鶴女史の家政婦からだった。
「奥様が、どうしても月森様に最後の調律をお願いしたい、と……」
その声は、不安げに揺れるすみれ色をしていた。最後の調律。その言葉に胸がざわつくのを感じながら、俺は海沿いの崖に建つ彼女の屋敷へと車を走らせた。
潮風が古い木の扉を軋ませる。通された音楽室は、グランドピアノの黒壇が鈍い光を放ち、午後の光が埃を金色に照らし出していた。そして、そのピアノの前に、千鶴先生はいた。椅子に深く身を沈め、鍵盤に指を置いたまま、永遠の眠りについていた。
駆けつけた警察は、現場の状況と老齢であることから、心臓発作による自然死だと早々に結論づけた。穏やかな最期です、と刑事は言った。だが、俺には分かった。この部屋の「音」が、狂っている。
静寂には色がある。安らかな静寂は、真珠のような乳白色だ。しかし、この部屋に満ちる静寂は、まるで黒い絵の具に砂を混ぜたような、ざらついた、不快な灰色をしていた。それは、暴力的な音の残響。誰かが絶叫したかのような、耳には聞こえない悲鳴の痕跡。そして、ピアノ。千鶴先生の指が触れていた鍵盤から、微かに、本当に微かに、腐った血のような赤黒い「音」が滲み出ていた。
これは、ただの死じゃない。この静寂の中には、聞かれなかったはずの不協和音が、確かに存在している。俺の冒険は、いつもこうして、誰も気づかない音の違和感から始まるのだった。
第二章 偽りの色彩
千鶴先生の葬儀は、粛々と執り行われた。集まった親族たちの言葉は、悲しみを表す深い藍色ではなく、欲望や欺瞞が混じり合った、不快なまだら模様をしていた。特に、一人息子の雅彦氏。彼は、母の思い出を涙ながらに語ったが、その声の「色」は、薄っぺらなレモンイエローに、利己的な緑が滲んでいた。遺産の話になると、その緑はさらに濃く、深く染まった。
「母は幸せな最期だったと思います。愛するピアノの側で……」
雅彦氏の言葉は、俺の鼓膜を不快に撫でた。彼の言葉が紡ぐ音の風景は、あまりに空虚だった。俺は、彼の言葉を遮るように尋ねた。
「先生が亡くなる直前、何か変わったことはありませんでしたか? 例えば、奇妙な音がしたとか」
雅彦氏は一瞬、怪訝な顔で俺を見た。彼の視線が発する音は、硬質な銀色をしていた。
「音? いいえ、何も。ただの静かな午後でしたよ。月森さん、あなたには何か聞こえたとでも?」
その問いかけには、棘のある紫色の響きがあった。俺の特異な感覚を、どこかで聞き知っているのかもしれない。俺はそれ以上追及するのをやめ、彼らの会話から距離を置いた。彼らの言葉は、真実を隠すためのノイズに過ぎない。手掛かりは、あの音楽室に残された「音の記憶」だけだ。
俺は再び、許可を得て藤堂邸を訪れた。担当の根岸刑事は、俺の「音で犯人がわかる」という突飛な主張に、呆れ顔を隠そうともしなかった。
「月森さん、気持ちはわかるが、これは事件じゃない。あんたの耳がいくら良くても、聞こえない音は証拠にならん」
彼の声は、誠実ではあるが、固定観念に縛られた、分厚いコンクリートのような灰色をしていた。説得は無駄だろう。俺は一人、あの音楽室の扉を開けた。
窓を閉め切り、光を遮断する。完全な暗闇と静寂の中、俺はピアノの前に座り、目を閉じた。意識を、聴覚だけに、そしてその先にある「色彩」だけに集中させる。
風の音、木の軋み、遠い波音。それらは日常の音だ。澄んだ水色、温かい茶色。俺が探しているのは、その調和を乱す異物。あのざらついた灰色と、血のように赤黒い音の正体だ。
記憶のチューニングを、あの日あの時間に合わせていく。千鶴先生が淹れていた紅茶の湯気が立てる、か細い白金の音。彼女が楽譜をめくる、乾いた紙の音。そして、彼女が鍵盤に指を置き、最初の和音を奏でようとした、その瞬間――。
ぞわり、と鳥肌が立った。
記憶の底から、あの赤黒い音が蘇る。それはピアノの音じゃない。もっと機械的で、無機質で、生命を冒涜するような響き。そして、もう一つ。ごく微かな、本当に耳を澄まさなければ捉えられないほどの、別の音が混じっていた。
それは、錆びついたゼンマイが軋むような、鈍い赤銅色の音。まるで、古いオルゴールのような……。その瞬間、俺の脳裏に、雅彦氏が葬儀で語っていた言葉が蘇った。
「母は、私が幼い頃に贈ったオルゴールを、それは大切にしてくれていました」
だが、彼のその言葉が発していた色は、澄み切った空のような青だった。思い出を語る、純粋な色。しかし、俺がいま聴いているこの「オルゴールの音」は、明らかに違う色をしていた。何かが、おかしい。
第三章 聞こえない凶器
オルゴールの音。それが突破口になるかもしれない。俺は屋敷の中を歩き回り、その音の出所を探した。書斎、寝室、客間。だが、それらしきものはどこにもない。雅彦氏が語ったオルゴールは、彼の思い出の中にしか存在しないのかもしれない。
諦めかけた俺が、再び音楽室に戻った時だった。視界の隅に、グランドピアノの足元に置かれた、古めかしい木箱が映った。それは、このピアノがただの楽器ではないことを示すもの。自動演奏装置の制御ユニットだった。
千鶴先生は、高齢で指が思うように動かなくなってからも、音楽を諦めなかった。この自動演奏ピアノで、かつて自身が録音した名演や、偉大なピアニストたちの演奏を聴くのが日課だったのだ。
俺は木箱に近づき、そっと手を触れた。ひんやりとした木の感触。そこからは、何の音も聞こえない。だが、俺は確信していた。謎を解く鍵は、この沈黙の箱の中にある。
根岸刑事に連絡を取り、半ば強引に専門家を呼んでもらった。俺の異常なまでの剣幕に、彼も何かを感じ取ったのかもしれない。やってきたのは、デジタル音響の専門家だった。彼は制御ユニットを分解し、内部のプログラムを解析し始めた。
数時間後、専門家が驚愕の声を上げた。
「なんだこれは……信じられない」
彼の声は、驚きを示す鮮やかなオレンジ色に染まっていた。
「このピアノの自動演奏プログラムに、何者かが細工をしています。特定の時刻になると……通常の演奏データに加えて、特殊な信号が出力されるようになっている」
専門家の説明に、俺は息をのんだ。その信号とは、人間にはほとんど聞こえない高周波と、体の内側で響くような超低周波を組み合わせた、特殊な音波だった。単体では無害だが、特定の組み合わせで、特定の時間に浴び続けると、心臓に深刻な負荷をかける。心臓に持病を持つ人間ならば、発作を引き起こして死に至らしめることも可能だという。
「殺人のための音……」俺は呟いた。
物理的な証拠は何も残らない。ただ、標的の心臓を止めるためだけに設計された、完全犯罪のための「聞こえない凶器」。千鶴先生が亡くなったあの日、彼女はいつものように自動演奏を聴こうとしていた。そして、ピアノは音楽ではなく、死の周波数を奏でたのだ。
あの血のように赤黒い音は、この殺人音波の「色」だった。そして、錆びついた赤銅色のオルゴール音は、この殺人プログラムが起動する際に、制御ユニットから発せられる、ごく微かな電子ノイズだったのだ。
犯人は、雅彦氏しかいない。彼だけが、母の習慣を知り、この装置に細工をする機会があった。遺産を早く手に入れるため、彼は世界で最も美しい楽器を、最も卑劣な凶器に変えたのだ。
根岸刑事は、呆然と立ち尽くしていた。彼の灰色の世界が、俺の言葉によって、信じられない色に塗り替えられていくのが分かった。
「聞こえない音が……凶器だと?」
俺は頷いた。
「ええ。そして俺には、その悲鳴の色が見えたんです」
第四章 黄金色のレクイエム
雅彦氏は、動かぬ証拠を突きつけられ、全てを自白した。彼は、母が自身の才能を認めず、いつまでも古い音楽に固執することに苛立ち、そして何より、その莫大な遺産を一日も早く手にしたかったのだ。彼は、母が最も愛したピアノを使って、母の存在そのものを消し去ろうとした。
事件は解決した。だが、俺の心には、冷たい虚無感が広がっていた。音楽を愛した人が、音楽に殺された。美しい音を生み出すはずのピアノが、人の命を奪うために使われた。その事実が、俺の信じる世界の調和を、根底から揺さぶっていた。俺のこの力は、結局、人の心の醜さや、世界の歪みを暴くだけのものなのか。
打ちひしがれて音楽室のピアノの前に座った俺の目に、一枚の楽譜が留まった。それは、千鶴先生が亡くなる直前に見つめていたであろう、手書きの楽譜だった。走り書きのような音符が並び、途中でインクが途切れている。未完の曲。彼女の「最後の曲」になるはずだったものだ。
俺は、その楽譜に描かれた音を、頭の中で鳴らしてみた。それは、どこか物悲しいが、同時に、深い愛情と希望に満ちた旋律だった。長年、俺を苦しめてきた「音の色」が、その旋律を奏でた瞬間、穏やかで温かい、黄金色の光となって心に満ちていくのを感じた。
俺は、鍵盤にそっと指を置いた。そして、千鶴先生の想いを引き継ぐように、その未完の旋律の先を、即興で紡ぎ始めた。
最初は、彼女を悼むレクイエム。深い悲しみの藍色。やがて、彼女との思い出が蘇り、旋律は温かい橙色を帯びる。そして、雅彦氏への、あるいは自分自身への、複雑な怒りと赦しが、深紅と純白の入り混じった音となって溢れ出す。
俺は弾き続けた。自分の内側にある、あらゆる感情を、ありのままに音に変えていく。それは、俺が初めて、自分の能力を使って何かを「創造」した瞬間だった。
弾き終えたとき、音楽室には、夜明けの光のような、柔らかくも力強い、黄金色の残響が満ちていた。それは、死の不協和音を浄化し、新たな始まりを告げる音だった。
俺は理解した。この力は、世界の醜悪な音を暴くためだけにあるのではない。隠された美しい音、声にならない想い、未完のまま終わった旋律を見つけ出し、それを世界に響かせるためにもあるのだと。
内向的で、自分の殻に閉じこもっていた俺の世界は、この日を境に変わった。ピアノの調律師であることは変わらない。だがこれからは、ただ音を合わせるだけでなく、そこに込められた人の心、その「色彩」をも調律していこう。
窓の外では、朝日が昇り始めていた。世界は、まだ俺が聴いたことのない、無数の美しい音で満ちている。俺はゆっくりと立ち上がり、新たな朝の光の中へと、一歩を踏み出した。その足音が、希望に満ちた、確かな緑色をしているのを、俺は確かに感じていた。