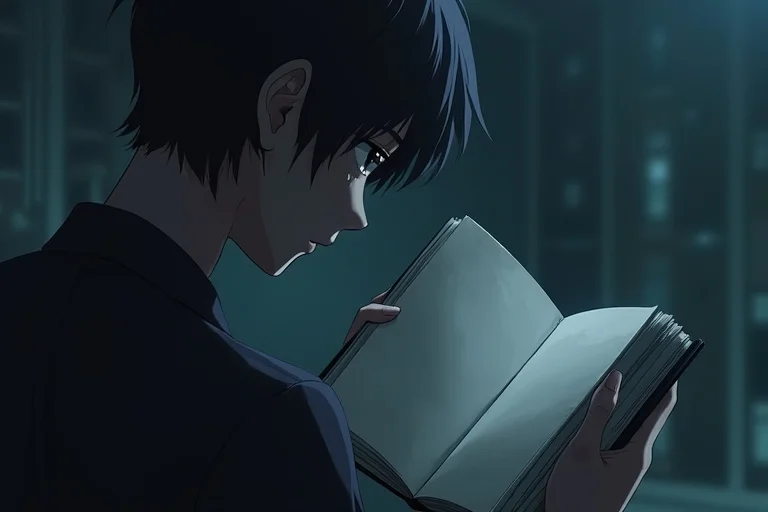第一章 残響の色彩
元刑事である俺、音羽奏(おとわ そう)の視界は、常にやかましい。人の感情が、オーラのように色を帯びて見えるのだ。怒りはどす黒い緋色、喜びは弾けるレモンイエロー、嘘は淀んだ泥の色。この共感覚のせいで人間関係に疲れ果て、刑事という職も辞した俺の静かな生活は、一本の電話で唐突に終わりを告げた。
「音羽、頼む。お前の『眼』が必要だ」
受話器の向こうで懇願するのは、警視庁捜査一課の長谷川。俺が能力のことを唯一打ち明けた、かつての相棒だ。
現場は、都心の一等地に立つタワーマンションの最上階。完璧な密室。被害者は、霧島怜(きりしま れい)。メディアにも度々登場する、カリスマ的な調香師だった。ドアには内側から複雑な鍵がかけられ、窓はすべて嵌め殺し。鑑識がどれだけ調べても、第三者の侵入した痕跡は一切見つからなかった。
「現場を見てくれ。何か『残って』いないか?」
長谷川の言葉に促され、俺はリビングへと足を踏み入れた。そこは、まるで時が止まったかのような静寂に包まれていた。高級そうな革のソファに、霧島は眠るように腰かけていた。外傷はない。毒物による中毒死が疑われたが、毒物の特定には至っていない。問題は、その空間に渦巻く『色』だった。
殺人現場には、通常、犯人の強烈な感情が残滓として漂う。激情の赤、憎悪の紫、あるいは冷徹な計画殺人の場合の、氷のような無色の空洞。だが、この部屋に満ちていた色は、そのどれとも違っていた。
一つは、目の醒めるような、鮮やかな黄金色。それは純粋な、一点の曇りもない「歓喜」の色だった。まるで、人生で最も幸せな瞬間を味わっているかのような、祝祭の色。
そしてもう一つ。その黄金色に寄り添うように、静かに漂う深い藍色。それは、胸が張り裂けるような「悲哀」の色。大切な何かを永遠に失った、取り返しのつかない喪失の色だった。
歓喜と悲哀。殺人現場にはあまりにも不釣り合いな、矛盾した二つの感情。まるで光と影のように絡み合い、この密室を満たしている。これが、犯人が残した色だと? 長谷川が訝しげな顔で俺を見る。俺は首を横に振ることしかできなかった。こんな不可解な感情の残響は、今まで一度も見たことがなかった。
第二章 偽りのパレット
捜査は暗礁に乗り上げていた。霧島怜の周辺を洗っても、彼を殺害するほどの動機を持つ人物は浮かんでこない。彼の才能に嫉妬する同業者は数多くいたが、誰もが鉄壁のアリバイを持っていた。
俺は長谷川と共に、数人の関係者と顔を合わせた。そのたびに、俺の眼は彼らの内面を無遠慮に暴き立てた。
最初に会ったのは、霧島の主席弟子である青年、結城(ゆうき)。彼は霧島の死を心から悼んでいるように見えたが、その表面的な悲しみの薄墨色の奥で、チリチリと焦げ付くような「野心」のオレンジ色が燻っていた。師の死は、彼にとって好機でもあるのだ。だが、現場に残された黄金色と藍色とは、まったく異質の色だった。
次に、霧島のパトロンであり、恋人だったと噂される女性実業家。彼女は気丈に振る舞い、その感情は硬質なダイヤモンドのように無色透明に見えた。だが、時折その表面に亀裂が走り、そこから「恐怖」を示す、ぬらりとした緑色が漏れ出てくる。彼女は何かを恐れていたが、それは悲しみではなかった。
誰もが何かを隠し、偽りの色を身にまとっている。彼らの感情のパレットは、一様に濁っていて醜い。だが、あの現場にあった純粋な歓喜と悲哀の色を持つ者はいなかった。俺は焦燥感に駆られた。この能力は、人の嘘を見抜くことはできても、真実を指し示すとは限らない。かつて、俺はこの眼を過信し、無実の人間を犯人だと断定しかけたことがある。その過ちが、俺を刑事の座から引きずり下ろしたのだ。
「どうなんだ、音羽。何か掴めたか?」
「いや……ダメだ。全員が嘘つきで、全員が怪しく見える。だが、あの色じゃない」
俺の答えに、長谷川は失望を隠さなかった。俺自身、自分の無力さに打ちのめされていた。共感覚という呪われた才能は、またしても俺を迷宮に突き落とすだけなのか。霧島怜は、一体どんな感情の中で死んでいったというのか。歓喜しながら、絶望する。そんなことがあり得るのだろうか。俺は思考の袋小路に迷い込んでいた。
第三章 追憶のフレグランス
捜査が行き詰まり、数日が過ぎた。俺は半ば諦めかけていたが、一つの疑問が頭から離れなかった。なぜ、調香師が? 彼の職業と、この奇妙な事件に関係はないのだろうか。俺は長谷川に無理を言って、再び事件現場である霧島の部屋を訪れた。目的は、彼のアトリエを調べることだった。
警察の規制線が解かれた部屋は、がらんとしていた。あの鮮烈な感情の色も、今はもう陽光の中に溶けて消えかかっている。俺はリビングを抜け、アトリエの扉を開けた。
そこは、何百というガラス瓶が壁一面に並ぶ、香りの聖域だった。甘い花の香り、落ち着く木の香り、スパイシーな香辛料の香り。様々な匂いが混じり合い、荘厳なシンフォニーを奏でている。その中央に置かれた作業台の上に、一つの小さなガラス瓶と、一枚の処方箋が残されているのを、俺は見つけた。
処方箋には、万年筆の美しい文字で、こう記されていた。
『追憶(L'Évocation)』
そして、その下には難解な香料の名前がいくつも並んでいた。これが、霧島が最後に作っていた香りか。俺は吸い寄せられるように、小瓶の蓋を開け、中に残っていた試作品の香りを、そっと嗅いだ。
その瞬間、世界が一変した。
香りが鼻腔を抜けた途端、俺の眼に、あの二つの色が奔流となって流れ込んできたのだ。弾けるような黄金色の歓喜と、深く沈む藍色の悲哀。それは、現場に残っていた残響など比較にならないほど、鮮烈で、濃密な感情の奔流だった。
違う。これは犯人の感情じゃない。これは、霧島怜自身の感情だ。彼は、自らの「記憶」と「感情」を、香りに封じ込めたのだ。
黄金色は、彼が初めて自分の作った香水で人を笑顔にできた日の、無垢な喜びの色。藍色は、彼が愛した人を病で失った日の、どうしようもない喪失の色。人生で最も輝かしい光と、最も深い影。その二つが渾然一体となって、この『追憶』という香りを構成していた。
全てのピースが、音を立ててはまった。密室も、毒物反応が出ないのも当然だ。これは殺人事件などではない。霧島怜は、自ら死を選んだのだ。不治の病に侵され、自身の才能が衰えていくことを悟った彼は、人生の最高傑作として、自らの人生そのものを香りに昇華させ、その香りに包まれながら、静かに旅立っていったのだ。
第四章 彼が遺したもの
事件は「自殺」として処理された。霧島怜が末期の脳腫瘍を患っていたことが、後の解剖で判明した。彼は、自らの記憶と尊厳が病によって損なわれる前に、最も美しい形で人生の幕を引くことを選んだのだ。
だが、俺の中には一つの疑問が残っていた。なぜ、彼は自分の死を、あたかも難解なミステリーのように演出したのか。
その答えは、彼の弟子である結城との再会で明らかになった。事件の真相を告げると、彼は愕然とし、やがて堰を切ったように泣き崩れた。彼の悲しみの色は、今度は本物の、深い藍色をしていた。
「先生は……僕に言っていました。『才能は伝説になることで、初めて永遠を得る』と。そして……僕が、先生の才能を超えられないことを、誰よりも分かっていた」
霧島は、自分の死が凡庸な病死として扱われることを嫌ったのだ。彼は、愛弟子である結城が自分の影に苦しむことなく、新しい道を歩めるように、そして「天才調香師・霧島怜」の名が謎に包まれたまま永遠に語り継がれるように、この最後の舞台を演出したのだった。それは、彼が遺せる、最後の、そして最大の贈り物だった。
現場に残された「歓喜」と「悲哀」。それは、殺人犯の感情でも、単なる被害者の断末魔でもなかった。それは、一人の人間が生きた証そのものであり、絶望の淵で見出した希望であり、愛する者へ向けた、あまりにも切なく、美しいメッセージだったのだ。
俺は刑事の職には戻らないだろう。だが、この事件を通じて、俺は自分の能力を少しだけ許せるようになった気がした。感情の色は、善悪や真偽を断罪するためのものではない。それは、言葉にならない想いや、人が生きた記憶の複雑な綾(あや)を、静かに映し出す鏡なのかもしれない。
帰り道、どこからか風に乗って、ふと、あの『追憶』の香りがした。黄金の光と藍色の影が、俺の視界を優しくよぎっていく。そのあまりに人間的な色彩に、俺は初めて、美しいとさえ思った。