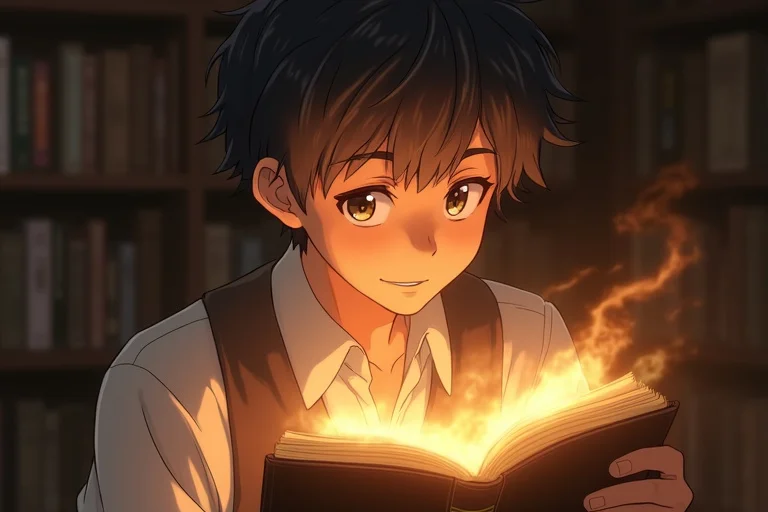第一章 鉛の不協和音
音響考古学。それは、歴史の沈黙に耳を澄ます学問だ。私の仕事は、古代の遺物がその生成過程や周囲の環境から吸収した微細な音響振動――いわば「音の化石」を抽出し、解析すること。国立古代遺物研究所の第3研究室長、雨宮響子。それが私の肩書きだった。同僚たちは私のことを、冷静で、分析的で、遺物に残されたデータ以外のものには一切興味を示さない人間だと思っている。あながち間違いではない。私は、歴史という壮大な物語よりも、その片隅で忘れ去られた、名もなき陶片が抱える微かなノイズに心を惹かれてきた。
その日、私のデスクに運ばれてきたのは、何の変哲もない一枚の鉛板だった。紀元一世紀、ローマ帝国属州ブリタニアの遺跡から出土したという触れ込みだが、銘文も装飾もなく、ただ不格好に歪んでいるだけ。歴史的価値は低い、というのが資料に添えられた所見だった。本来なら補助研究員に回すような案件だ。しかし、その鉛板が放つ奇妙な存在感に、私はなぜか目を離せなかった。まるで、分厚い沈黙の奥で、何かが必死に身じろぎしているような気配がした。
私は鉛板を特殊なゲルで満たした防振チャンバーに設置し、自ら開発した「共鳴探査ヘッド」をゆっくりと降ろした。レーザーが鉛の表面をなぞり、内部に残された振動スペクトルを拾い上げていく。モニターに複雑な波形が走り、ヘッドフォンからは変換された音が流れ出す。
――キィィン、という耳障りな高周波。風紋のような低い唸り。ここまでは、古代の金属遺物によくある音だ。精錬時の炉の轟音、鍛造の槌音、そして千年以上の時が刻んだ大地の振動。だが、次の瞬間、私は息を呑んだ。
ザアァァ……。それは、今まで聴いたことのない音だった。まるで巨大な滝壺に叩きつけられる無数の水滴のような、それでいて機械的な響きを伴う喧騒。そのノイズの海の中から、突如として、甲高い金属の衝突音が断続的に響き渡った。ガシャン!ゴォン!そして、それら全てを突き破るように、鮮明な「声」が聴こえてきたのだ。
いや、声ではない。泣き声だ。生まれたばかりの赤ん坊のような、か細く、しかし生命の全てを振り絞るような慟哭。それはあまりに生々しく、千九百年という時間の隔たりを微塵も感じさせなかった。私の背筋を冷たい汗が伝う。これはただの音の化石ではない。この鉛板は、何かを「記憶」している。まるで、つい昨日録音されたテープのように。私はボリュームを上げた。喧騒と金属音の合間に、誰かがその赤ん坊をあやすような、低い囁き声が聴こえる気がした。だが、その言葉はラテン語でも、ケルトの言葉でもなかった。どの言語にも属さない、奇妙な響きを持っていた。
この鉛板は、一体何を記録しているのか。私の冷静であるべき探究心は、初めて感じる種類の畏怖と興奮によって、激しく揺さぶられ始めていた。
第二章 詠み人のいない声
鉛板との格闘が始まった。私はその日から研究室に泊まり込み、音の解析に没頭した。赤ん坊の泣き声は、常に同じ周期で現れる。まるで、鉛板が作られた特定の瞬間の出来事を、永遠にリフレインしているかのようだ。私はその泣き声に「エコー」と名付けた。そして、エコーをあやすように聴こえる謎の声を「詠み人(よみびと)」と呼ぶことにした。
「詠み人」の声は、デジタルフィルターを幾重にもかけることで、少しずつ輪郭を現し始めた。それはおそらく男性の声で、低く、穏やかな響きを持っていた。しかし、彼が発する言葉は、地球上のどの言語データベースとも一致しなかった。音素を分析し、音声学の権威である恩師にもデータを送ったが、「人工的に合成されたか、あるいは全く未知の言語体系に属する」という返答しか得られなかった。
研究は暗礁に乗り上げた。出土状況を再調査しても、鉛板の周辺からは特筆すべき遺物は見つかっていない。ただの打ち捨てられた金属片。それが公式の見解だった。上司からは、「雨宮君、一つの遺物に固執しすぎるのは感心しないな。もっと成果の出やすい研究テーマはいくらでもあるだろう」と、暗に釘を刺された。
研究室の窓から見える夜景の光が、モニターに映る無機質な波形と重なる。同僚たちの囁きが聞こえるようだった。「また所長は変なモノに夢中になってる」「あれはただのノイズだ」「彼女は幻聴を聴いているんじゃないか」。
自信が揺らいだ。私の聴いているこの鮮明な音は、本当にただのノイズの集合体が生み出した偶然の産物なのだろうか。私の、歴史の沈黙の中に声を見出したいという強すぎる願望が、無意味な音に意味を与えているだけなのかもしれない。疲労が思考を鈍らせ、ヘッドフォンから流れる音が、ただの不快な雑音にしか感じられなくなる瞬間もあった。
それでも、私はやめられなかった。なぜなら、エコー――あの赤ん坊の泣き声だけは、私の心を捉えて離さなかったからだ。それは科学的な興味を超えて、もっと根源的な何かを揺さぶる響きを持っていた。冷たく硬い鉛の中から聴こえる、あまりにもか弱く、温かい生命の叫び。それを聴くたび、私は誰かに「ここにいる」と伝えなければならないような、奇妙な使命感に駆られるのだった。「詠み人」もまた、そうだったのではないか。彼はこの声を、誰かに聴いてほしかったのではないか。
私は仮説を立てた。この鉛板は、呪詛板(デフィクシオ)の一種ではないか、と。古代ローマでは、憎い相手の名を鉛板に刻み、釘を打ち付けて呪う風習があった。だが、この鉛板には文字も、釘の跡もない。ならば、これは「音」による呪詛なのだろうか。赤ん坊の泣き声を永遠に聴かせるという、陰湿な呪い。そう考えると、多くの辻褄が合う。だが、それにしては「詠み人」の声は、あまりにも優しすぎた。
夜が更け、静まり返った研究室で、私は再びヘッドフォンをつけた。喧騒、金属音、そしてエコーが響く。私は目を閉じ、意識を集中させた。その時、ふと気づいた。これまで背景ノイズとして処理していた、あの巨大な滝壺のような音。それは、本当にただの雑音なのだろうか。私はその部分だけを抽出し、再生速度を極限まで落としてみた。
――ザ…ザザ…。それは、無数の人間の話し声のようだった。何千、何万という人々が、同じ空間でざわめいている。そして、その音の質感は、古代の市場やコロッセオのそれとは明らかに異なっていた。もっと硬質で、反響が少なく、どこか人工的な空間の響き。まるで、巨大な宇宙船の内部か、未来都市のターミナルのような……。その突飛な空想を、私は慌てて打ち消した。疲れているのだ。私は自嘲気味に息を吐き、探査ヘッドのスイッチを切った。
第三章 時を超えた子守唄
数週間が過ぎ、私は行き詰まりの迷路から抜け出せずにいた。鉛板は相変わらず意味不明な音を発し続け、私はその音の囚人となっていた。もう、諦めるしかないのかもしれない。そう思いかけたある朝、ふとしたきっかけで事態は急転した。それは、別の研究チームが持ち込んできた最新の「非破壊同位体分析装置」のデモンストレーションだった。
「この装置を使えば、遺物を傷つけることなく、構成元素の同位体比をナノレベルで測定できます。つまり、その物質がどこで、いつ精錬されたのか、産地まで特定できるのです」
技術者のその言葉に、私は弾かれたように顔を上げた。鉛板の「素材」そのものを調べる。なぜ、今までその発想に至らなかったのか。私はすぐに許可を取り、あの鉛板を装置にかけた。ありふれたブリタニア産の鉛。結果はそう出るはずだった。
分析が始まり、モニターにグラフが描かれていく。鉛206、鉛207、鉛208…。それぞれの同位体の比率が、地球上の既知の鉛鉱山のデータと照合されていく。だが、どのデータとも一致しない。それどころか、グラフは見たこともない異常なパターンを示していた。技術者が首を捻り、何度も再計測を行う。しかし、結果は同じだった。
「おかしい……こんな同位体比はありえない。特にこの……鉛205の痕跡。これは半減期が短すぎて、自然界には存在しないはずの人工放射性同位体だ。しかも、この組成……まるで、遥か未来の核融合炉か何かで生成されたような…」
技術者の呟きが、私の頭の中で雷鳴のように響いた。未来。その単語が、バラバラだったパズルのピースを、一つの場所に引き寄せていく。
あの機械的な喧騒。未知の言語。そして、ありえない同位体比。
私は震える手で、研究室に戻った。再び鉛板の音を聴く。もう、それは意味不明なノイズではなかった。一つ一つの音に、恐ろしいほどの意味が宿り始めていた。
あの喧騒は、未来都市の雑踏だったのだ。断続的な金属音は、故障した航時機の悲鳴だったのかもしれない。そして「詠み人」は、過去の人間ではない。何らかの事故で紀元一世紀のブリタニアに不時着し、取り残されてしまった未来人だったのだ。
彼は帰る術を失い、絶望の中で、自分の持てる最高の技術を使ってメッセージを残そうとした。それは、文字ではなかった。おそらく、彼のいた未来では、物質に直接「音響情報」を記録する技術が確立されていたのだ。彼は、自分が生きていた証、そして共にいた赤ん坊――エコーの存在を、この粗末な鉛の板に刻み込んだ。未来の誰かが、いつかこの信号を拾ってくれることを信じて。
私の装置は、その未来のフォーマットを不完全にしか再生できなかった。だから、彼の声は途切れ途切れに、都市の音は不協和音として聴こえていたのだ。
私は、再び「詠み人」の声に集中した。彼の言葉の意味は分からない。だが、その声色に込められた感情は、今なら痛いほど理解できた。それは、絶望と、諦観と、そして目の前の小さな命に対する、無限の愛情だった。彼が囁いていたのは、呪いの言葉などではない。それは、時を超えて響く、たった一人の聴衆に向けた、子守唄だったのだ。
ヘッドフォンから流れる、穏やかで、悲しい旋律。その向こうで、エコーの泣き声が、少しずつ安らかな寝息に変わっていくのが聴こえた。涙が、私の頬を止めどなく流れていた。
第四章 沈黙の守り人
真実を知ってしまった私を、深い沈黙が包み込んだ。私は時を超えた遭難信号の、唯一の受信者となってしまったのだ。学会で発表すれば、世紀の大発見として世界中が沸き立つだろう。私の名は歴史に刻まれ、この鉛板は「タイムカプセル」として、あらゆる憶測と分析の対象となるはずだ。
だが、私にそんなことはできなかった。
それは、彼の孤独な闘いを、名もなき親子の最後の記録を、センセーショナルな見世物にすることに他ならなかった。彼は、歴史に名を残したかったわけではない。ただ、誰かに聴いてほしかっただけだ。自分たちが「確かにここにいた」という事実を。その声なき声に応える方法は、世紀の発見として喧伝することではない。
数日後、私は「鉛板に関する最終報告」と題したレポートを上司に提出した。「調査の結果、特異な音響ノイズが観測されたが、これは精錬過程における稀な結晶構造の歪みに起因する物理現象と結論。歴史的価値はやはり低いと判断する」。嘘の報告書だった。私のキャリアで、初めての、そして最後になるであろう科学者としての裏切り行為だった。
上司は満足げに頷き、鉛板は「分析終了」のラベルを貼られ、資料保管室の奥深くへと仕舞われた。もう二度と、誰の目にも、そして誰の耳にも触れることはないだろう。
私の研究者としての姿勢は、あの日を境に変わった。以前は、いかに客観的なデータを抽出し、歴史の事実を再構成するかに心を砕いていた。だが今は、違う。歴史とは、記録された出来事の連なりだけではない。その行間からこぼれ落ちた、無数の声なき声、名前のない人々の喜びや悲しみの集積体なのだ。私の仕事は、その沈黙の声を聴き、その存在を私という一人の人間の中に記憶し続けること。それは、科学というより、鎮魂に近い行為なのかもしれない。
時折、私は一人、許可を得て薄暗い資料保管室を訪れる。棚の奥から、ずしりと重い鉛の板を取り出し、そっと手のひらに載せる。ひんやりとした金属の感触。探査装置はもう使わない。ただ目を閉じ、意識を澄ませる。
すると、心の耳に聴こえてくるのだ。遥かな時空を超えて届く、優しい子守唄が。未来の都市の喧騒が。そして、今はもう泣き止んで、安らかに眠っているであろう赤ん坊の、小さな寝息が。
私は、彼のメッセージの唯一の守り人となった。その事実は、誰にも知られることはない。だが、それでよかった。窓の外に広がる夕焼けの空を見上げながら、私は思う。私たちのこの時代の、この瞬間の音もまた、どこかの物質に記録され、遥か未来の誰かが、いつか耳を澄ませてくれる日が来るのだろうか。歴史は、私たちが思うよりもずっと優しく、見えない絆で繋がっているのかもしれない。その絆の、ささやかな結び目の一つになれたことを、私は誇りに思った。