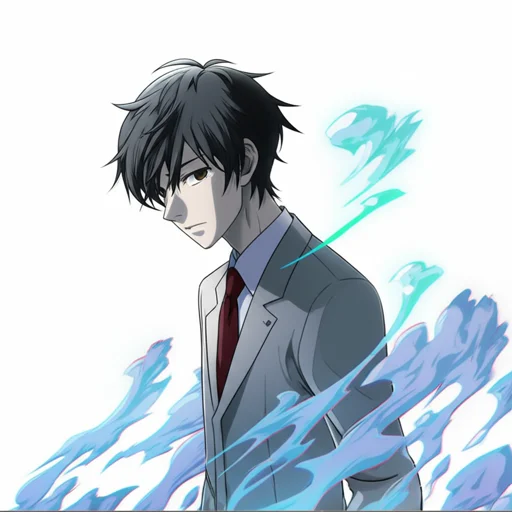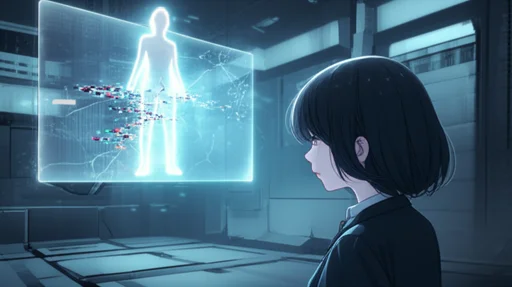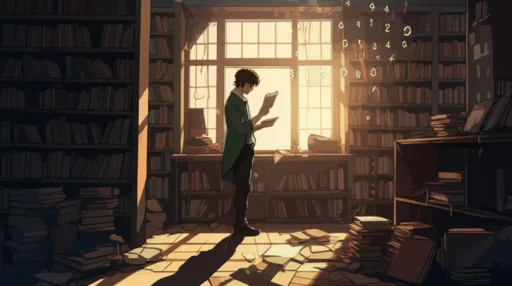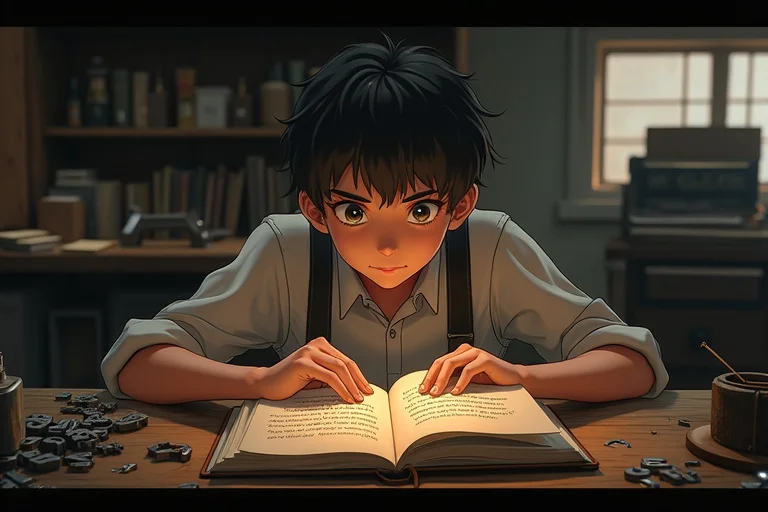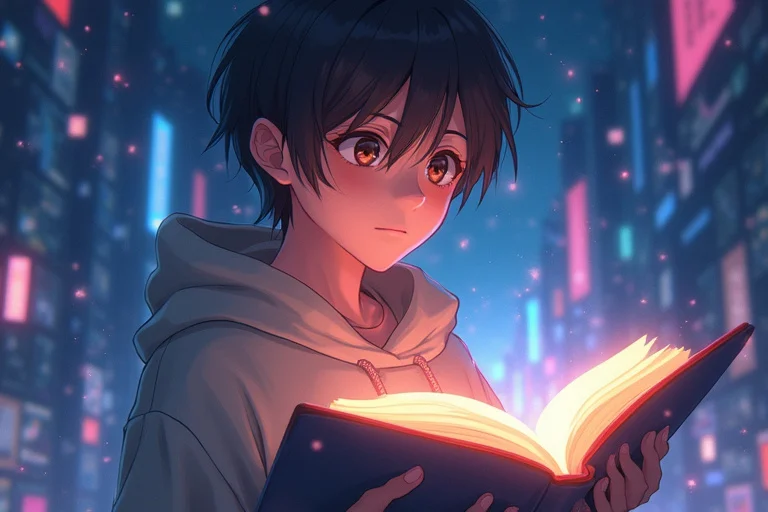第一章 無色の証言者たち
音無律(おとなしりつ)の世界は、色に満ちていた。それは絵画的な色彩ではない。人の声が放つ、感情のオーラだ。歓喜は陽光のような黄金色にきらめき、深い悲しみは水底の藍色に沈む。そして、嘘は、決まって腐った泥のような赤黒い色を帯びて、律の網膜にまとわりついた。
元ピアニストだった律は、事故で演奏家としての未来を絶たれた。その代償のように、この奇妙な共感覚「色聴」が彼の中に芽生えた。以来、彼はその能力を使い、人の嘘を見破る私立探偵として糊口をしのいでいる。嘘が可視化される世界で、真実を見つけるのは、かつて完璧なソナタを奏でるより、ずっと簡単だった。少なくとも、今日までは。
「有栖川玲(ありすがわれい)は、その日、確かに一人でアトリエに籠っていました。私たちは誰も、彼女の邪魔などできませんでしたから」
目の前の青年、相田樹(あいだいつき)の声は、澄み切った湧き水のように無色透明だった。律は眉をひそめる。彼の言葉には、嘘を示す赤黒い淀みがひとかけらも混じっていない。
事件は三日前に起きた。世界的な天才調香師として名を馳せた有栖川玲が、鍵のかかった自身のアトリエで死体となって発見されたのだ。警察は状況から自殺と事故の両面で捜査しているが、彼女の遺族は納得していない。律は、玲の弟から依頼を受け、彼女の三人の弟子に話を聞きに来ていた。
相田樹。穏やかで、最も玲からの信頼が厚かったとされる一番弟子。
次に話を聞いたのは、野々村花(ののむらかえで)。怜悧な美貌を持つ女性で、玲のライバルとしてしばしばメディアに取り上げられていた二番弟子。
「先生は完璧主義者でした。新作に行き詰まり、思い詰めてしまったとしても、不思議ではありません」
彼女の声もまた、氷のように冷たく、そしてどこまでも透明だった。
最後に、最年少の弟子、水上蓮(みなかみれん)。気弱で、いつも玲の影に隠れるようにしていた青年だ。
「僕が……僕が最後に先生にお会いしたんです。でも、その時はいつもと変わらないご様子で……」
おどおどと話す彼の声もまた、揺らめく陽炎のように、色を持たなかった。
三者三様。しかし、彼らの証言は、律の世界では同じ意味を持っていた。――誰も、嘘をついていない。
律は苛立ちを隠せない。三人にはそれぞれ、玲が亡くなった推定時刻に、確固たるアリバイがなかった。誰もが動機を持ちうる。玲の才能への嫉妬、後継者の座を巡る争い、秘められた愛憎。にもかかわらず、彼らの言葉は、まるで磨き上げられた水晶玉のように、何の濁りもないのだ。
自分の能力が狂ったのか?それとも、この事件には、嘘という概念が存在しないとでもいうのか。
律はアトリエのドアノブに手をかける。そこには、玲が最後に嗅いだであろう、甘く、そしてどこか心を空っぽにさせるような、奇妙な香りがまだ微かに残っていた。その香りは、律が知るどんな色にも染まらない、不可解な透明さで彼の感覚を通り抜けていった。
第二章 空白のパルファム
有栖川玲のアトリエは、彼女の魂そのものだった。壁一面に並んだ何百もの香料瓶が、まるでパイプオルガンのように荘厳な沈黙を守っている。中央には、彼女が使っていたであろう調香台(オルガン)。そこには、創りかけの香水を示す数本のビーカーと、白紙のままの処方箋が残されていた。
「先生の最高傑作になるはずでした」
依頼主である玲の弟が、悄然と呟く。「『記憶』をテーマにした、誰も嗅いだことのない香りだと……。でも、そのレシピだけが、どこにもないんです」
律は室内を注意深く観察する。密室状況。争った形跡はない。しかし、拭い去れない違和感が空間に澱んでいた。それは、第一章で感じた、あの不可解な香りだった。甘美でありながら、心の奥にある大切な何かをすくい取っていくような、空虚な香り。それは弟子たちの衣服からも、微かに香っていた。
律は再び三人の弟子と個別に面会した。今度は、彼らの過去や、玲との個人的な関係に踏み込んでみる。
「先生は、私の光でした」相田樹は遠い目をして語った。「私の才能を最初に見出してくれた。彼のためなら、何でもできます」その声は、敬虔な祈りのように、純白だった。
「彼女は壁だったわ」野々村花は唇を噛んだ。「超えられない、圧倒的な才能の壁。……憎らしいほど、尊敬していた」嫉妬を隠さない言葉ですら、色を帯びていない。まるで、他人事のように。
「僕は……怖かったんです」水上蓮は俯いたまま言った。「先生の期待に応えるのが。先生の隣に立つのが」その恐怖さえも、洗い流されたように無色だった。
律は混乱の極みにいた。彼の「色聴」は、感情の機微にこそ鋭く反応する。強い感情は、鮮やかな色となって現れるはずなのだ。嫉妬、崇拝、恐怖。それらが、これほどまでに無味乾燥な「無色」であることなど、あり得ない。
焦燥感に駆られた律は、旧知の香りの専門家、霧島教授の研究所を訪ねた。現場に残っていた微かな香りの成分を分析してもらうためだ。
「面白いな、これは」霧島はガスクロマトグラフィーのデータを見ながら言った。「いくつかの成分は特定できる。心を鎮静させる効果のある植物由来のオイルだ。だが、この未知の分子構造……これは、天然には存在しない。おそらく、有栖川玲が合成した、新しい香料だろう」
「効果は?」
「シミュレーション上では……驚くべき結果が出ている」霧島は眼鏡を押し上げた。「これは、脳の海馬、記憶を司る領域に直接作用する可能性がある。特に、情動記憶と呼ばれる、感情を伴う記憶に強く干渉するようだ」
「干渉……?」
「平たく言えば、特定の記憶を、別の情報で『上書き』する、とでも言おうか。まるで、テープに新しい音を録音するように」
その言葉は、律の脳天を貫く雷鳴となった。記憶の上書き。もし、そんなことが可能だとしたら?
嘘の色が見えなかったのではない。彼らは嘘をついていなかったのだ。なぜなら、彼らが語っていたのは、植え付けられた「新しい真実」だったからだ。犯人は、玲を殺害した後、この香水を使って関係者全員の記憶を書き換えたのだ。律が絶対の指標としていた「主観的な真実」そのものが、汚染されていたのだ。
第三章 真実の不協和音
律の世界は、その日、色を失った。いや、色の意味が根底から覆された。彼が追いかけていたのは、真実ではなかった。ただ、人が「真実だと信じているもの」の表層をなぞっていたに過ぎない。その事実は、かつてピアニストとしての指を失った時と同じくらいの、深い喪失感を彼に与えた。
だが、律は絶望の淵で立ち止まらなかった。能力が通用しないのなら、それ以外のすべてを使えばいい。観察、推理、そして、人間そのものへの洞察。彼は、色というフィルターを外し、初めて裸の目で事件と向き合った。
記憶は書き換えられても、事実は消えない。
律は、弟子三人の行動を徹底的に洗い直した。犯行があったとされる夜、彼らは全員、別々のアトリエで作業していたと証言していた。しかし、水上蓮のアトリエからだけ、玲が使っていた特殊なガラス器具の、微細な破片が見つかった。警察が見逃した、小さな、しかし決定的な物証だった。
そして、香り。あの「忘却のアロマ」を完成させ、使うことができたのは誰か。玲の極秘の研究ノートを盗み見ることができ、かつ、彼女が最も心を許していた人物。それは、彼女の影のように常にそばにいた、気弱な青年、水上蓮だった。
律は、蓮を調香台の前に呼び出した。他の二人も同席している。
「君だったんだな、蓮君」
律の声は、色を探すことをやめていた。ただ、静かな確信だけがそこにあった。
蓮は、か細い声で否定する。「何を……言っているんですか?僕は何も……」
彼の声は、相変わらず無色だ。彼は、自分の罪を本気で覚えていないのだ。
「君は玲さんを殺害した。そして、彼女が完成間近だった『忘却のアロマ』を使い、相田さんと野々村さん、そして君自身の記憶を書き換えた。『玲さんは新作に行き詰まり、自ら命を絶った』という、新しい物語を全員に信じ込ませたんだ」
相田と野々村が息をのむ。蓮は血の気の引いた顔で震えている。
「そんな……嘘だ!」
「嘘じゃない。これは、君のアトリエで見つかったガラス片だ。玲さんのアトリエでしか使われていない、特注のビーカーの破片だよ」
律は小さな証拠品の袋をテーブルに置いた。
「君は玲さんを崇拝するあまり、彼女の才能を独占したくなった。彼女が『記憶』をテーマにした最高傑作を世に出せば、彼女はさらに手の届かない存在になってしまう。それが怖かった。だから、君は彼女から、その香水と、未来と、命そのものを奪った」
その時、蓮の無色だった声に、初めて亀裂が入った。それは、赤黒い嘘の色ではない。悲しみでも、怒りでもない。ひび割れたガラスのような、痛々しい不協和音。書き換えられた記憶と、心の奥底に封印された真実が、軋みを上げていた。
「……違……う」蓮は、頭を抱えてうずくまった。「先生は、僕だけのものじゃなきゃいけなかったんだ……。あの香りは、先生と僕だけの秘密のはずだった……!僕たちが、悲しい記憶をすべて忘れて、幸せになるための……!」
ついに、色なき告白が始まった。それは、歪んだ愛情の果てに行き着いた、悲しい罪の顛末だった。犯した罪の重さに耐えきれず、自らが生み出した香りで記憶を消し、偽りの平穏に逃げ込んだ男の、哀れな独白だった。
第四章 不完全なソナタ
事件は解決した。水上蓮は逮捕され、彼の告白によってすべての謎は解き明かされた。相田と野々村は、操られていたとはいえ、師を失った悲しみと、友人が犯人だったという二重の衝撃に打ちひしがれていた。
律は、自らの探偵事務所に戻り、埃をかぶったグランドピアノの蓋を開けた。事故で傷ついた右手は、もう昔のように滑らかには動かない。それでも彼は、鍵盤の上に指を置いた。
ポツリ、ポツリと、不器用な音が紡がれる。それは、かつて彼が聴衆を魅了した華麗なソナタではなかった。つっかえ、リズムを乱し、時に不協和音を響かせる、不完全なメロディ。
彼の世界から、声の色は消えないだろう。だが、彼はもう、その色だけを信じることはない。人の心は、嘘か真実かという単純な二元論で割り切れるものではない。嘘をつかずに人を欺き、真実を語りながら自らを偽る。そこには、無数のグラデーションと、言葉にならない感情の揺らぎがある。
偽りの記憶の中でさえ、蓮の声は悲痛な軋みを上げていた。あの軋みこそが、彼の魂の本当の色だったのかもしれない。色として視認できなくとも、確かに存在する、心の叫び。
律は、鍵盤を叩く指に少しだけ力を込めた。奏でられる不完全なメロディは、どこか切なく、それでいて、不思議な力強さを帯びていた。それは、絶対的な真実などないと知った世界で、それでも何かを信じようともがく、彼自身の心の音だった。
嘘の色が見える世界で、彼は初めて、不確かで不完全な「真実の音」を、自らの手で奏でていた。世界は鮮やかな色だけでなく、名もなき無数の感情の陰影でできている。そのことに気づいた彼の心には、静かで、しかし確かな余韻が長く響き渡っていた。