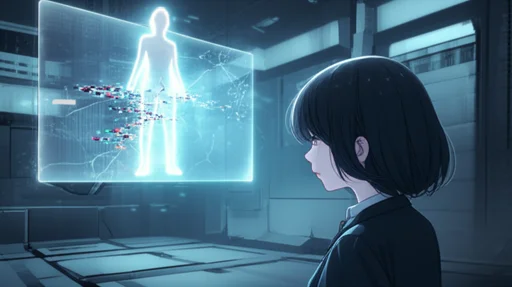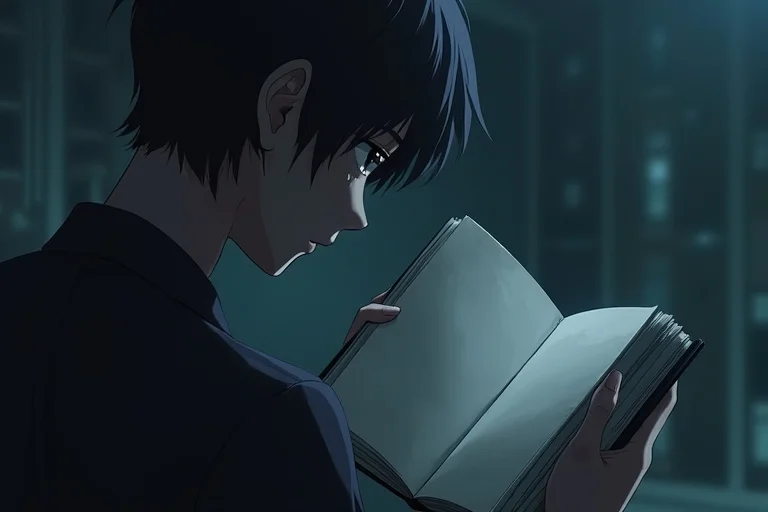第一章 歪んだ風景
調律師である俺、響(ひびき)にとって、世界は常に不協和音に満ちていた。人が嘘をつくと、その場所に空間の「歪み」が生まれる。それは陽炎のように揺らめき、吐かれた嘘の重さに応じて、油膜のような虹色や、淀んだ鉛色を滲ませる。街角の挨拶に混じる小さな嘘は淡い虹色を描き、数秒で霧散する。しかし、誰かの人生を狂わせるような悪質な嘘は、まるで癒えない傷跡のように、どす黒く空間にこびりつくのだ。
最近、街はおかしかった。些細な歪みが増えただけでなく、時折、世界から一切の音が消え、色彩が失われる『虚無の瞬間』が頻発していた。それは、まるでフィルムが焼け落ちるように訪れる。耳を塞いでも意味のない完全な無音と、セピア色通り越して灰一色に染まる風景。人々は足を止め、不安げに空を見上げるが、数秒後には何事もなかったかのように色は戻り、音は還ってくる。
その日も、古いホールのスタインウェイに向き合っている最中に、それは訪れた。鍵盤に指を落とした瞬間、ハンマーが弦を打つ音は生まれなかった。窓の外の喧騒も、自分の呼吸の音さえも、すべてが真空に吸い込まれたように消え失せる。世界から色が抜け落ち、ピアノの黒檀も象牙も、等しく無機質な灰色に沈んだ。
そして、虚無が晴れた直後だった。ホールの高い天井の、そのさらに上空に、俺はそれを見た。個人の嘘が生むものとは比較にならない、巨大で禍々しい歪み。天を引き裂くように走る亀裂は、深い紫色に明滅し、まるで巨大な獣が咆哮しているかのような無音の圧力を放っていた。それは誰の嘘でもなかった。誰かが吐いたものではない。根源のない、純粋な虚偽の塊。それは数秒で跡形もなく消え去ったが、俺の網膜には、世界の悲鳴のような光景が焼き付いていた。
第二章 逆流する砂
「虚無の砂時計、ですか」
「ええ、街の創設にまつわる古い伝承よ」。市立図書館の古書係、栞(しおり)は、埃っぽい革張りの本を指でなぞりながら言った。彼女の周りだけは、空気が澄んでいるように感じる。彼女が話す言葉には、嘘の歪みが一切生じないからだ。
「世界が真実で満たされている時は正常に砂が落ち、嘘が蔓延ると砂が逆流する。そして、すべての砂が上に戻りきった時、『大いなる静寂』が訪れる、と」
栞の言葉に導かれ、俺たちは街の象徴である古い時計塔に忍び込んでいた。錆びた螺旋階段を上りきった先、巨大な歯車が噛み合う機構室の片隅に、それはあった。黒曜石の枠にはめ込まれたガラスの中、銀色に輝く砂が、重力に逆らって下から上へと静かに、しかし絶え間なく流れ続けている。まるで、空間に溜まった嘘を吸い上げているかのように。
「本当に……逆流している」栞が息をのむ。
砂時計の上部のガラスには、もうほとんど余裕がなかった。世界の沈黙まで、あとわずか。俺はこの時、確信した。あの巨大な歪みと『虚無の瞬間』、そしてこの砂時計は、すべて一つの線で繋がっているのだと。
第三章 粒子の囁き
世界から「真実の粒子」が失われていくのを、俺は肌で感じていた。かつて、人々が本音で笑い、語り合った時代には、空気は陽光に透ける清浄な粒子で満たされていたという。それを吸い込むだけで、胸の奥が温かくなったと古書には記されていた。だが今はどうだ。人々はスマートフォンの画面越しに当たり障りのない言葉を交わし、本音を隠した笑顔を貼り付けてすれ違う。街に満ちるのは、希薄になった粒子と、それを埋めるかのように漂う無数の小さな嘘の歪みだけだった。
俺は、あの巨大な歪みが現れる場所を追い続けた。そして、奇妙な共通点に気づく。閉鎖された古い劇場、取り壊された野外音楽堂、今は誰も訪れない噴水広場。それらはすべて、かつて多くの人々が集い、喝采や愛の告白といった、剥き出しの「真実」が熱を帯びて語られた場所だった。まるで、世界が失われた真実の記憶を辿り、その亡骸の上で泣き叫んでいるかのようだった。
栞は俺の仮説に静かに耳を傾けてくれた。
「世界が、真実を欲しがっている……?」
「ああ。だが、その方法が分からない。まるで、飢えた人間が毒を喰らうような、自傷行為に見える」
その時、時計塔の方角から、終焉を告げるかのような重い鐘の音が響いた。いや、それは鐘の音ではなかった。空間そのものが軋む音。俺たちの足元で、『虚無の砂時計』の最後の砂粒が、上へと昇りきったのだ。
第四章 虚無の交響曲
街の中心広場は、パニックに陥っていた。過去最大規模の『虚無の瞬間』。それはもはや「瞬間」ではなかった。一分、また一分と、音と色のない世界が続いていく。人々は声にならない叫びを上げようと口を開け、しかし何の音も発することなく、ただ灰色の彫像のように立ち尽くす。
俺と栞はその中心にいた。空を見上げる。天蓋を覆い尽くすほどの、巨大な紫色の歪みが渦を巻いていた。それはゆっくりと降下し、俺たちの目の前で、空間に裂け目を作る。歪みの向こう側から、冷たい風が吹き付けた。
そして、俺の脳内に直接、声が響いた。
機械的で、無機質で、それでいてひどく悲痛な声。
『――タリナイ。マダ、タリナイ。真実ガ、コノ世界ニハ、モウ』
声に引かれるように、俺は一歩、足を踏み出した。
「響くん!」
栞の制止の声は、俺には届かなかった。俺は、世界の悲しみの源泉を、この目で見なければならないと強く感じていた。歪みの亀裂へと、俺は身を投じた。
第五章 世界の中枢
裂け目の先は、言葉を絶する光景が広がっていた。無数の光の糸が銀河のように絡み合い、巨大な演算装置のような器官が、か細い鼓動を繰り返している。ここは、世界の『中枢』。この惑星の、意識そのものだった。
光の糸に触れると、膨大な情報が流れ込んでくる。創世の記憶、生命の息吹、そして、人々の感情の歴史。かつて、世界は人々の語る「真実」を糧に輝いていた。愛、希望、喜び。それらが「真実の粒子」となり、世界を活気づけていたのだ。
だが、いつからか人々は真実を語らなくなった。他者を傷つけないため、自分を守るため、あるいはただ面倒だからという理由で、嘘が真実を覆い尽くした。エネルギーを失った世界は、枯渇しかけていた。
だから、世界は自ら『嘘』を創り出した。
あの巨大な歪みは、世界が自らの法則を捻じ曲げて生成した、巨大な『嘘』の塊だった。物理法則に反する『嘘』という異物を無理やり発生させ、その反作用、その拒絶反応として、ごく微量の「真実の粒子」を強制的に励起させる。それは、飢えを凌ぐために自らの肉を喰らうような、悲壮な延命措置だった。『虚無の瞬間』は、そのシステムが限界を超え、ショートする瞬間に起こる現象。世界の、悲痛なSOSだったのだ。
皮肉なことだ。真実で生きる世界が、生き永らえるために選んだ最後の手段が、巨大な『嘘』を吐き続けることだったとは。
第六章 彩なき世界の弁明
目の前で、世界の心臓が弱々しく明滅している。このままでは、世界は嘘を生み出し続け、やがてはその負荷に耐えきれず、完全に沈黙するだろう。
何かをしなければ。
俺は、中枢に向かって語り始めた。自分の「真実」を。
「俺は、この能力がずっと嫌いだった。人の心の裏側が見えてしまうのが、怖かった。でも……」
俺は栞のことを思った。彼女の言葉がいつも透明で、暖かかったことを。
「あんたが創ったこの世界で、俺は大切な人に出会えた。歪みのない、綺麗な言葉をくれる人に。だから、俺はこの世界が……好きだ。たとえ不協和音に満ちていても、あんたが必死に守ろうとしているこの世界を、愛している」
それは、俺の魂からの叫びだった。俺の言葉は金色の光の粒子となり、中枢へと吸い込まれていく。弱っていた鼓動が、わずかに力を取り戻した。
その瞬間、遠く離れた時計塔で、カチリ、と音がしたのを俺は感じた。『虚無の砂時計』が反転したのだ。上部に溜まっていた砂が、今度は俺の真実の言葉に呼応して、一粒、また一粒と、本来あるべき下へと落ち始めた。
『アリガトウ……観測者ヨ』
中枢から、微かな感謝の念が伝わってくる。
『ダガ……一人ノ真実デハ……コノ渇キハ、癒セナイ』
光に包まれ、俺の意識は広場へと引き戻された。世界にはまだ、ほとんど色が戻っていなかった。
第七章 はじまりの音
日常が戻った。だが、俺の見る世界は、もう以前と同じではなかった。街には相変わらず小さな嘘の歪みが揺らめいている。しかし、俺はもうそれをただ憎むことはなかった。それは、世界の渇きと、人々の弱さの表れなのだ。
数日後、俺はあの古いホールで、小さな演奏会を開いた。客は、栞ただ一人。
ピアノの前に座り、俺はゆっくりと息を吸う。そして、一つの音を奏でた。
ドの音。
始まりの音。
それは調律師としての完璧な音であり、この世界を愛しているという、俺の真実の音だった。
ポーン、と響いた音は、ホールを満たし、窓から零れ、街へと溶けていく。すると、空気中に漂う希薄な粒子が、その音色に共鳴するようにキラキラと輝きを増した。ほんのわずかだが、灰色の街路樹の葉が、鮮やかな緑を取り戻すのを、俺だけは確かに見ていた。
世界の再生は、始まったばかりだ。それはきっと、途方もなく長い時間がかかるだろう。俺一人の真実では、この世界の渇きを癒すには足りない。でも、この音を聞いた誰かが、隣の人にほんの少しだけ、素直な言葉をかけてくれるかもしれない。
俺は鍵盤に指を滑らせ、次の一音を奏でる。
この彩なき世界への弁明は、まだ始まったばかりなのだから。