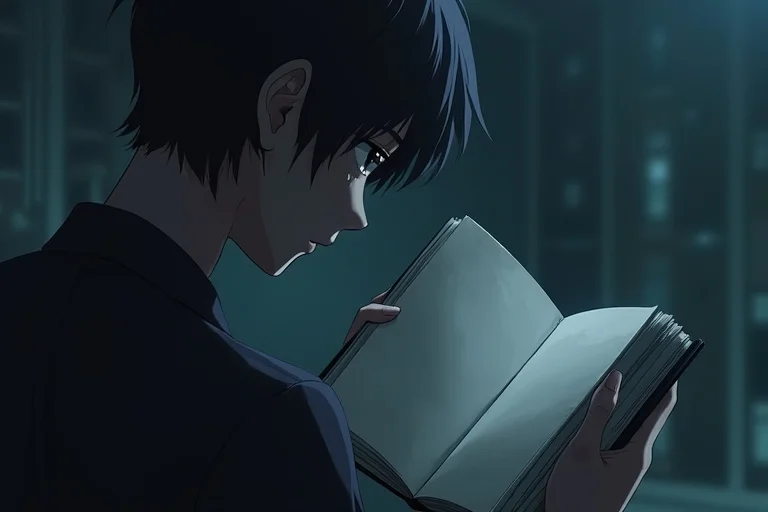第一章 聖人の遺した黒い石
腐った果実のような甘ったるい死臭と、鼻腔を刺す鉄の匂い。
雨脚が強まる古びたアパートの三階で、私は胃の腑からせり上がる吐き気を嚙み殺していた。
「……天野、入れるか」
刑事の神崎が、ハンカチで口元を覆いながら私を見る。
彼女の視線の先、部屋の隅では若い鑑識官が一人、床にうずくまっていた。
彼はガチガチと歯を鳴らし、虚空を掴むように指を痙攣させている。
「……ま、まただ。結晶の残留思念に当てられたな」
神崎が忌々しそうに呟く。
『感情結晶』。
人の情動を物質化する技術が生んだ、現代最悪の産業廃棄物。
現場に残る強い感情は、免疫のない者の神経を容易く焼き切る。
「下がらせろ。彼じゃ耐えられない」
私はサングラスの位置を直し、部屋の奥へと踏み入った。
視界が歪む。
極彩色のノイズが網膜を焼く。
恐怖の紫。絶望の灰色。
そして、それらを蹂躙するように塗りつぶす、ドス黒い赤。
殺意だ。
それも、尋常な濃度ではない。
六畳一間のその部屋は、家主の人柄を無言で語っていた。
擦り切れるまで使い込まれた座布団。
壁に貼られた、教え子たちからの感謝の手紙。
『先生、ありがとう』
『大学受かりました』
色褪せた便箋の束が、この部屋の主が「仏の田所」と呼ばれた所以を静かに叫んでいる。
だが、その中心で突っ伏している老人の遺体だけが、異質だった。
血管が浮き出るほど見開かれた目。
自らの奥歯を砕くほど食いしばった顎。
苦悶ではない。
そこにあるのは、世界すべてを呪うような阿修羅の形相。
「死因は?」
「心不全だ。だが、見てみろ」
神崎が遺体の右手を指差す。
硬直した指の間から、コールタールのような闇色が覗いていた。
ピンセットがそれを摘み上げる。
コロリ、と乾いた音。
光を一切反射しない、暗黒の多面体。
「……触れるか?」
「やるしかないだろう」
私は革手袋を外し、震える指先をその闇へと伸ばした。
接触の瞬間。
錆びた針で脳髄を直接かき回されるような激痛。
「ぐっ……!」
視神経がスパークする。
現実の風景が弾け飛び、他人の記憶が泥水のように流れ込んでくる。
『許さない』
『殺してやる』
『あいつだけは、絶対に』
内臓が焼けただれるような怒り。
誰だ?
誰をそこまで憎んでいる?
私は激痛の中で、トリガーとなった映像を必死に手繰り寄せた。
老人の網膜に最後に焼き付いた敵の姿。
雨の中。
傘もささずに立つ男。
金髪。
右目の下に刻まれた、十字の傷。
(……なんだ、こいつは)
違和感が、背筋を這い上がる。
男の顔は整いすぎていた。
まるで劇画の悪役のように、記号的すぎる。
「……はぁ、はぁ……ッ」
私は床に膝をつき、荒い息を吐いた。
「天野! 何が見えた」
「……男だ。金髪、右目に十字傷」
私はこめかみを強く押し、残像を振り払う。
「だが、おかしい。田所さんのような人間が、これほどの憎悪を抱く相手だ。相当な因縁があるはずなのに……その男の顔には、リアリティがない」
「リアリティ?」
「ああ。まるで……作り物のような」
私はポケットからスケッチブックを取り出した。
記憶が鮮明なうちに書き留めなければならない。
鉛筆を走らせる。
線が重なり、あの「十字傷の男」が紙の上に浮かび上がる。
その時だった。
私の手が止まったのは。
「どうした?」
「……神崎。このスケッチをスマホで撮って、画像検索にかけてくれ。今すぐにだ」
「は? そんなことより鑑識に回して」
「いいからやれ!」
私の剣幕に押され、神崎が端末を取り出す。
数秒後、彼女の顔色がさっと変わった。
「……なんだこれ。ヒットしたぞ」
画面を見せられる。
そこには、無数のSNS投稿が並んでいた。
だが、撮影された写真ではない。
すべて「目撃情報」として描かれた、似顔絵や合成画像だ。
『こいつが犯人だ』
『許せない』
『見つけ出して殺せ』
投稿の日付はバラバラ。場所も無関係。
だが、対象は全員同じ。
金髪の、十字傷の男。
「先週の主婦変死事件。その前のホームレス襲撃事件……。全員、この男への憎悪を残して死んでいる」
神崎が震える声で言う。
「だが、警察のデータベースにはこんな男は存在しない。目撃証言すら、現場には一人もいないんだ」
私はスケッチブックの上の顔を睨みつけた。
鉛筆の黒鉛が、不気味に光っている。
「存在しないはずだ」
私は呟いた。
「こいつは人間じゃない。誰かの憎悪を集めるためだけにデザインされた、幽霊(ファントム)だ」
第二章 ノイズの海
警察署の薄暗い資料室。
モニターの明かりだけが、私と神崎の顔を照らしている。
私はタブレット上で、ウェブ上の「十字傷の男」の画像を拡大し続けていた。
画像の解像度を上げ、ピクセル単位まで分解する。
眼球の虹彩、髪の毛の生え際。
「やっぱりだ」
「何が分かった?」
「これを見てくれ。輪郭線の周辺に、不自然なデジタルノイズが走ってる。これは写真の加工痕じゃない。ゼロから生成されたAI画像の特有のパターンだ」
私は画面を叩いた。
「この男は実在しない。何者かが精巧に作り上げ、ネットの海に放流した『憎悪の器』だ。サブリミナル的に恐怖を煽り、個人の不満をこの架空の敵に結びつけるよう誘導されている」
「そんなことが可能なのか?」
「普通の人間なら無理だ。だが、感情とデジタル信号を同期させる技術を持った人間なら……」
私は別のウィンドウを開く。
そこには、あるベンチャー企業のロゴが表示されていた。
『アニマ・シンセシス』。
感情制御技術の最大手。
「この会社のCEO、御子柴レイ。彼は最近、ある論文を発表している。『集合的無意識の泥抜きについて』」
画面には、白衣を着た優男が映っている。
慈愛に満ちた、聖職者のような微笑み。
だが、私の眼には違うものが見えた。
画面越しですら伝わってくる、彼の放つ波長。
限りなく透明に近い、白。
それは清らかさではない。
すべての色彩を拒絶し、感情を凍結させた「虚無」の色だ。
「……天野」
神崎が低い声で呼ぶ。
「被害者たちのスマホ、すべてにこの会社が開発したメンタルケア・アプリが入っていた。アップデート履歴は、全員が死亡する直前だ」
「ビンゴだな」
私は立ち上がり、ジャケットを羽織った。
「アプリを通じて、被害者たちの深層心理に『十字傷の男』のイメージを植え付けたんだ。社会への漠然とした不安、将来への悲観、隣人への苛立ち。それらすべてを、この男への具体的な『殺意』に変換させた」
「だが、何のために?」
「聞きに行こう。この狂った脚本家に」
外はまだ雨が降っている。
私は傘もささずに署を出た。
雨音に混じって、どこからか聞こえる気がした。
あの優しい田所老人が、最期に漏らしたはずの、誰にも届かなかった悲鳴が。
第三章 善意の怪物
『アニマ・シンセシス』の本社最上階。
そこは、オフィスというよりは巨大なゴミ処理場だった。
足の踏み場もないほど、床に積み上げられた黒い結晶の山。
そのすべてが、ドス黒い憎悪の光を脈動させている。
部屋全体が、低周波のような唸り声を上げていた。
その中心に、御子柴レイは座っていた。
ウェブサイトの写真とは別人のように痩せこけ、目の下にはどす黒い隈が刻まれている。
白衣は薄汚れ、彼自身もまた、廃棄物の一部のように見えた。
「……早かったですね」
御子柴は、我々を見ても驚かなかった。
その声は、ガラスが擦れ合うように枯れている。
「御子柴レイ。公務執行妨害および殺人教唆の疑いで署まで来てもらう」
神崎が銃に手をかけながら告げる。
御子柴は力なく笑った。
「殺人教唆? 違いますよ、刑事さん。私は救済をしたんだ」
彼は震える手で、足元の結晶を一つ拾い上げた。
「見てください、この純粋な黒を。これは元々、誰かが誰かに向けるはずだった暴力だ。DV、虐待、差別、通り魔……。行き場のない悪意が、世界には溢れすぎている」
彼の瞳が、狂気的な熱を帯びる。
「だから私は『彼』を作った。架空の敵、絶対悪の『ファントム』をね。人々は隣人を憎む代わりにファントムを憎む。社会への不満を、実在しない敵への攻撃に転嫁する。そうすれば、現実の人間は傷つかない」
「その結果が、罪のない老人たちの死か!」
私が叫ぶと、御子柴は悲しげに首を振った。
「彼らはフィルターだ。汚れた水を濾過するための、尊い犠牲ですよ。彼らが憎悪を結晶化して死んでくれたおかげで、今、世界の犯罪率は劇的に下がっている」
御子柴が両手を広げる。
その腕には、無数の注射痕があった。
自らもまた、結晶の中毒になっているのだ。
「僕も引き受けているんだ……! この部屋にある結晶を見てくれ。あふれ出した憎悪を、僕自身の精神で中和している。誰も傷つけない世界のために、僕もまた、泥を飲んでいるんだ!」
「……ふざけるな」
私は一歩踏み出した。
ポケットから、田所老人の遺品である結晶を取り出す。
「あんたは感情を『量』でしか見ていない。だが、この中には、あんたの計算外のノイズが混じっている」
私は結晶を突きつけた。
「私が現場で感じた激痛。それは、単なる憎悪の強さじゃなかった。拒絶反応だ」
「拒絶……?」
「『人を憎みたくない』という、彼らの魂の叫びだ」
脳裏にフラッシュバックが走る。
雨の日。
私の腕の中で冷たくなっていった、かつての恋人。
彼女は最期まで、私を庇って犯人の名を口にしなかった。
『憎まないで』
そう言った彼女の笑顔は、雨に濡れて泣いているようだった。
愛する者のために、憎悪を飲み込んで死んでいく苦しみ。
その痛みを知らないお前に、世界を救う資格などない。
「田所さんは、あんたが植え付けた人工的な殺意と、自分自身の良心との間で引き裂かれて死んだんだ! 彼らが死んだのは憎しみのせいじゃない。優しすぎたからだ!」
御子柴の表情が凍りついた。
「優しさ……? そんな非合理なものが……」
「それが人間だ。あんたが切り捨てた『ノイズ』こそが、人が人である証明なんだよ」
私は彼に詰め寄り、その胸倉を掴み上げた。
至近距離で見る彼の瞳。
その奥底にある「虚無」の色が、微かに揺らいでいた。
「あんたの孤独も、私には視える。誰よりも世界に絶望していたのは、あんた自身だろう」
「……黙れ」
「一人で背負ったつもりになるな。それは傲慢だ」
御子柴の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
それは透明ではなく、濁った泥のような色をしていた。
「……僕は、ただ……静かな世界が欲しかっただけなんだ」
その時、神崎が彼の手首に手錠をかけた。
カチャリ、という冷たい音が、部屋の唸り声を断ち切った。
第四章 終わらない雨
事件は解決した。
御子柴レイは逮捕され、『アニマ・シンセシス』のサーバーは押収された。
『十字傷の男』の画像データも、すべて削除されたはずだった。
だが、世界は何も変わらなかった。
雨のそぼ降るスクランブル交差点。
大型ビジョンには、御子柴逮捕のニュースが流れている。
しかし、道行く人々がスマホで見ているのは、別の画面だった。
『御子柴はファントムの手先に過ぎない』
『真犯人の十字傷はまだ逃げている』
『あいつを見つけ出せ』
『殺せ』
削除しても、削除しても、誰かがまた画像をアップロードする。
一度生まれた「共通の敵」を、大衆は手放そうとはしなかった。
彼らは、自分たちの鬱屈を正当化してくれるサンドバッグを必要とし続けている。
「……救いがないな」
隣で傘をさす神崎が、ため息交じりに言った。
「真実なんて誰も求めてない。ただ、石を投げる理由が欲しいだけだ」
「ああ。御子柴の望んだ『平和』は、最悪の形で実現したのかもしれないな」
私は空を見上げた。
分厚い雲が、街の色彩を灰色に塗りつぶしている。
だが、私のポケットの中には、確かな重みがあった。
証拠品として提出する前の、あの黒い結晶。
そこからはもう、刺すような殺意は感じられない。
指先に伝わってくるのは、微かな温もり。
そして、深い悲しみ。
それは、泥のような憎悪の海に沈んでもなお、消えることのなかった田所老人の「人間としての誇り」だ。
「行くぞ、天野。まだ仕事は残ってる」
「分かってる」
私はサングラス越しに、行き交う人々の波長を見た。
誰もが心に小さな棘を持ち、誰かを傷つけ、傷つけられながら歩いている。
その混沌としたノイズこそが、この世界の色だ。
私は歩き出した。
雨はまだ止まない。
だが、濡れたアスファルトに反射する信号機の青は、亡き恋人が好きだった雨上がりの空の色に、少しだけ似ていた。