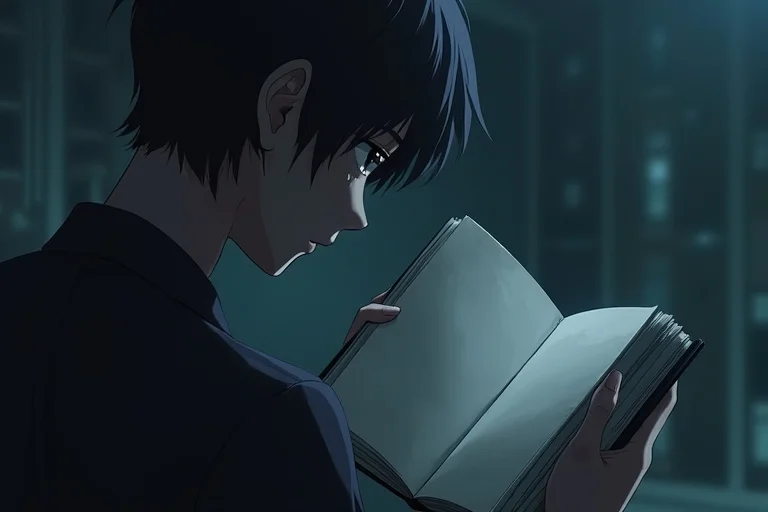第一章 沈黙のプレリュード
その日、私が調律に訪れた古い洋館は、異様なほどの静寂に包まれていた。館の主、天才ヴァイオリニストとして名を馳せた長谷川響一氏のグランドピアノは、まるで主の沈黙を映すかのように、重く口を閉ざしている。私の名前は水城音葉。調律師だ。そして、私には人にはない、一つの秘密があった。私には、人のつく「嘘」が、黒く澱んだ靄として見えるのだ。
それは生まれつきの体質で、他人の呼気に混じって吐き出される、粘り気のある黒い靄は、私にとって世界の不調和そのものだった。だから私は、嘘のない、完璧に調律された音の世界に安らぎを見出してきた。
「奥の演奏室でお待ちです」
家政婦の古川さんが、青ざめた顔で私を案内する。彼女の口からは、恐怖を示す白い息は漏れるが、嘘の靄は一切出ていない。だが、彼女が震える手で開けた扉の先で、私は息を呑んだ。
グランドピアノの傍らで、響一氏が倒れていた。傍らには、彼が愛用したストラディヴァリウスが無残に砕け散っている。部屋は内側から鍵がかけられた完全な密室。窓にもすべて閂がかかっていた。警察の現場検証が始まっても、謎は深まるばかりだった。死因は、後頭部を強打したことによる失血死。だが、部屋に凶器らしきものはなく、争った形跡もない。
何よりも異様だったのは、屋敷にいた全員――家政婦の古川さん、響一氏の一番弟子である青年・桐谷奏、そして駆けつけた彼のマネージャー――彼らの誰からも、嘘の靄が一筋たりとも立ち上らなかったことだ。「何も見ていません」「何も知りません」。彼らの言葉は、私の目にはすべてが「真実」として映っていた。
誰も嘘をついていない。しかし、目の前には不可解な死がある。嘘のない世界で起きた、完全犯罪。私の信じてきた世界の調和が、不気味な不協和音を立てて軋み始めた瞬間だった。
第二章 偽りのないフーガ
警察の捜査は難航した。密室の謎は解けず、動機を持つ者もいない。響一氏は多くの人に慕われていた。特に、弟子の奏は、師の死に深く打ちひしがれているように見えた。透き通るような白い肌をした彼は、儚げな美しさを持つ青年だった。
「先生は……音楽の化身のような人でした。あの人がいない世界なんて、考えられません」
奏が絞り出すように言った時も、彼の呼気は清浄なままだった。私は、調律師としての鋭敏な聴覚を頼りに、独自の調査を始めた。完璧な調和を求める私の本能が、この歪んだ状況を許さなかったのだ。私はまず、砕けたヴァイオリンの残骸に注目した。まるで、誰かが激情に任せて叩きつけたかのようだ。しかし、穏やかな響一氏がそんなことをするとは考えにくい。
私は奏に、響一氏の最近の様子を尋ねた。
「先生は、最近少し……思い悩んでいるご様子でした。ですが、私には何も」
彼の言葉はそこで途切れた。その瞳の奥に、一瞬だけ深い苦悩の色がよぎったのを、私は見逃さなかった。だが、やはり靄は出ない。彼は嘘をついていない。少なくとも、彼自身はそう信じている。
私は苛立ち始めていた。この屋敷全体が、まるで巨大な嘘で塗り固められているかのように感じるのに、靄はどこにも見当たらない。真実しか語られていないはずの空間が、これほどまでに息苦しいとは。それは、すべての音が正しい高さで鳴っているのに、なぜか不快なハーモニーを奏でているような、奇妙な感覚だった。
「音葉さん、あなたには、何か聞こえますか?」
不意に、奏が私に問いかけた。
「聞こえる、とは?」
「この部屋の……音です。先生はいつもおっしゃっていました。『沈黙にもまた、音楽がある』と。私には今、この部屋の沈黙が、悲鳴を上げているように聞こえるんです」
彼の言葉に、私はハッとした。調律師として、私は音にばかり集中していた。だが、響一氏が亡くなったこの部屋の「沈黙」そのものに、何かメッセージが隠されているのではないか。私はもう一度、現場となった演奏室を注意深く観察した。グランドピアノ、砕けたヴァイオリン、そして、床に散らばった一枚の楽譜。それは、未完のソナタだった。
第三章 不協和音のレクイエム
その楽譜は、響一氏の作風とはかけ離れていた。美しい旋律の中に、意図的に埋め込まれたかのような、耳障りな不協和音がいくつも配置されている。まるで、完璧な絵画にわざと泥を塗りつけたような、冒涜的な響き。私は、許可を得てその楽譜をピアノで弾いてみた。
美しいメロディが流れ出し、そして、問題の不協和音の箇所に差し掛かった。指が鍵盤を叩いた瞬間、部屋の空気がびりびりと震えた。それはただの不協和音ではなかった。特定の周波数の音が重なり合い、部屋の隅にあるガラス製のトロフィーケースを、微かに、しかし確かに共鳴させていたのだ。
その瞬間、私の頭の中に一つの仮説が閃光のように走った。もし、この不協和音が、ただの音ではなかったとしたら? もし、これが何かの「鍵」だとしたら?
そして、私は最も重要な、この世界の根幹を揺るがす可能性に思い至った。嘘の靄は、「意図的に真実を偽る時」にのみ現れる。では、もし話している本人が、それを微塵の疑いもなく「真実だ」と信じ込んでいたら? その言葉は、嘘にはならないのではないか。
私は奏を呼び出し、もう一度、あの楽譜を彼の前で弾いた。不協和音が鳴り響き、トロフィーケースが震える。奏は息を呑み、その顔から血の気が引いていくのが分かった。
「……気づかれましたか」
彼の声は、諦観に満ちていた。そして、彼の口から、ついに靄のない「真実」が語られ始めた。
「先生は、不治の病に侵されていました。指が……日に日に、彼の意思通りに動かなくなっていたんです。ヴァイオリニストにとって、それは死刑宣告にも等しい。彼は絶望していました。『最高の音を奏でられなくなった私に、生きる価値はない』と」
響一氏は、ただ朽ち果てることを良しとしなかった。彼は自らの死すらも、最高の芸術作品に昇華させようとしたのだ。
「先生は、ご自身の死を、最後の作品として私に託しました。タイトルは、『沈黙のソナタ』。この密室も、砕けたヴァイオリンも、すべては先生が描いた楽譜通りです」
あの不協和音。それは、超高周波と低周波を組み合わせた特殊な音響兵器のようなものだった。響一氏はそれを自ら作曲し、奏に演奏させ、その共鳴で棚の上の重い彫像を落下させた。そして、その下に自らの頭を差し出したのだ。ヴァイオリンは、彼自身が最後の力で床に叩きつけた。音楽家としてのプライドの死の象徴として。
奏は、師の芸術を完成させるという強い信念のもとに行動していた。彼にとって、それは悲劇的な義務であり、師への最後の忠誠だった。だから、彼の口から嘘の靄は出なかった。彼は、師の「芸術」について語っていたに過ぎないのだから。家政婦も、響一氏の衰えに薄々気づいていた。だが、彼の尊厳を守るため、何も知らないふりをすることが「正しいこと」だと信じていた。だから、彼女からも靄は出なかった。
第四章 真実のコーダ
誰も嘘をついていなかった。ただ、それぞれの「真実」が、悲しい不協和音を奏でていただけだったのだ。奏は、師の計画を遂行した共犯者であり、同時に、師の芸術の唯一の観客でもあった。彼の行為は法的には罪だろう。だが、私には彼を告発することができなかった。
私が追い求めてきた、完璧で純粋な「真実」とは、一体何だったのだろう。嘘のない世界でさえ、人の信念、愛、絶望は、真実をかくも複雑で、哀しい色合いに変えてしまう。私が醜いと切り捨ててきた「不協和音」こそが、響一氏の苦悩そのものであり、奏の師への愛が生み出した、慟哭のレクイエムだったのだ。
結局、事件は「老齢の音楽家が、誤って棚の上の彫像を落としてしまったことによる不慮の事故」として処理された。奏は、師の遺した楽譜を胸に、どこかへと旅立っていった。
あの日以来、私には世界が少し違って見えるようになった。街を行き交う人々の口から漏れる、大小さまざまな嘘の靄。以前はただ不快なだけだったその光景が、今では彼らの弱さや、見栄や、誰かを守るためについた哀しい偽りのように感じられることがある。
私は自宅のピアノの前に座り、そっと鍵盤に指を置いた。そして、あえて完全な和音から少しだけずらした音を、静かに奏でてみた。
その音は、完璧ではない。だが、どこか温かく、人間らしい響きを持っていた。
完全な調和だけが、美しいわけではない。不完全さや矛盾の中にこそ、人の心の奥底にある、本当の真実の響きが隠されているのかもしれない。私はその日、初めて、不協和音の持つ哀しい美しさを理解したような気がした。