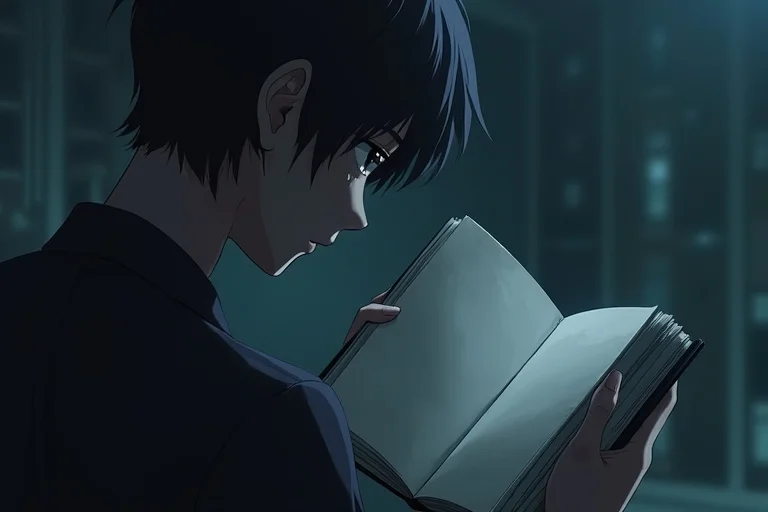第一章 涙で書かれた依頼状
時任譲(ときとう ゆずる)の世界から、感情という名の色彩が消え失せて三年が経つ。かつて彼は、人の心の歪みを読み解く犯罪心理学者として名を馳せていた。だが、最愛の妻を通り魔の凶刃によって失ったあの日、彼の内なる世界は音を立てて崩落した。悲しみも、怒りも、絶望さえも、すべてが磨りガラスの向こう側へと遠ざかり、ただ無機質な情報だけが網膜と鼓膜を通過していく。以来、彼は過去を封印し、都心の片隅で古書の修復士として、インクの染みと紙魚(しみ)の痕跡だけを相手に静かな日々を送っていた。
その静寂を破るように、一人の女性が彼の工房の扉を押した。大手出版社の編集者を名乗る彼女、水野は、憔悴しきった顔で風呂敷包みを差し出した。
「時任さん。あなたなら、これに隠されたメッセージを読み解けるかもしれないと、人づてに伺いました」
包みから現れたのは、上質な革で装丁された一冊の本だった。だが、ページをめくっても、そこにあるのはただひたすらに純白の紙だけ。インクの香りも、文字の圧力痕もない、完全な空白だった。
「これは?」
時任の声には、当然ながら抑揚がない。水野は唇を噛み締めた。
「ベストセラー絵本作家、月島栞(つきしま しおり)が失踪して一週間になります。警察は家出と事件の両面で捜査していますが、これは彼女のアトリエに残されていた唯一の手がかりなんです」
月島栞。その名は、感情を持たない時任の記憶データベースにもインプートされていた。鮮やかな色彩と、読む者の心を温かく包み込むような物語で、子供から大人までを魅了する作家。感情を失った時任にとって、彼女の作品は最も理解不能な代物だった。
時任は作業灯をつけ、本のページに様々な波長の光を当てていく。特殊なインクが使われている可能性を考慮してのことだ。紫外線ランプを照射した瞬間、世界は反転した。空白だったはずのページに、水で書いたように淡く、青白い文字がぼんやりと浮かび上がったのだ。まるで、涙で綴られたかのように儚い。時任はルーペを覗き込み、その言葉を音読した。
「私の心を盗んだ泥棒を、見つけてください」
「心」という単語が、彼の思考回路にノイズを走らせた。それは彼が三年前に失い、定義すら曖昧になった概念。論理では解けない、不純物の塊。しかし、空白のページに浮かび上がった透明なSOSは、埃をかぶっていた彼の探究心という歯車を、軋ませながらもわずかに回転させた。彼は、自分には理解できないはずの依頼を引き受けることにした。
第二章 空白のカンヴァスと無色の証言
月島栞のアトリエは、彼女の作品世界とは裏腹に、驚くほど無機質だった。整理整頓が行き届き、絵の具一本に至るまで決められた場所に収められている。だが、その完璧さがかえって不気味なほどの生活感の欠如を物語っていた。窓から差し込む午後の光が、部屋の中央に置かれたイーゼルを照らし出している。そこには、描きかけの巨大なカンヴァスがあった。
時任が近づくと、無数の顔、顔、顔がこちらを見つめていた。笑う顔、泣く顔、怒る顔、怯える顔。あらゆる感情のスペクトルがそこに描かれている。ただ一つ、奇妙な点を除いて。どの顔にも、「目」が描かれていなかったのだ。瞳のない無数の貌は、まるで感情の抜け殻のようだった。
編集者の水野は、栞が深刻なスランプに陥っていたことを打ち明けた。「新しい物語が、色が、何も降りてこない、と。まるで井戸が枯れてしまったみたいに」
次に話を聞いたアシスタントの青年は、声を潜めて言った。「先生は最近、何かに怯えていました。『誰かに心を覗かれているようだ』と。窓のカーテンを閉め切り、誰とも会いたがらない日が増えて……」
時任は、彼らの言葉を淡々と記録する。悲嘆、心配、恐怖。周囲の人々が口にする感情の名称を、彼は化学記号のようにノートに書き留めていく。それらが人間の行動にどう作用するのかはデータとして知っている。だが、その熱量や手触りは、彼には永遠に届かない。
ライバルと目されていた別の絵本作家は、時任の質問に嘲るような笑みを浮かべた。「月島栞は天才よ。でも、天才は自分の才能に喰い殺されるものなの。彼女は自分の心を描きすぎて、空っぽになってしまったのよ」
嫉妬、という感情のサンプル。時任はそう分析した。
工房に戻った時任は、再びあの白紙の本に向き合った。特殊な光を当てる角度を変えると、最初のメッセージの下に、さらに微かな文字が浮かび上がってきた。
「彼は私の色を奪った」
「彼は私の音を消した」
「彼は私の物語を終わらせた」
比喩的で、詩的で、非論理的な言葉の羅列。捜査は完全に暗礁に乗り上げたように思えた。感情という名の霧に包まれたこの事件は、感情を持たない彼にとって、あまりにも分が悪かった。彼はただ、空白のカンヴァスに描かれた瞳のない顔と、涙で書かれた言葉の間にある、見えない線を結ぼうと試み続けるしかなかった。
第三章 心を盗んだ泥棒の正体
手詰まりになった時任は、思考の原点に戻ることにした。月島栞という人間を、感情を排して再構築する。彼女の過去のインタビュー記事、エッセイ、そして作品群。膨大なテキストデータをスキャンするように読み解いていく中で、彼はある一点にたどり着いた。栞は、自身の創作の源泉を「共感覚」に近いものだと語っていたのだ。悲しみは冷たい青、喜びは弾けるような黄色い音として「見える」のだと。
「彼は私の色を奪った」「彼は私の音を消した」。あのメッセージは比喩ではなかった。彼女の知覚そのものの喪失を訴えていたのだ。
だが、誰がそんなことを? 薬物か、あるいは精神的なショックか。時任は栞の医療記録にまで調査の範囲を広げた。そして、思わぬ記述を発見する。栞は失踪の数ヶ月前、ある先進医療クリニックで、実験的な脳神経治療を受けていた。重度の感情疲労に悩む芸術家向けの、「感情抑制治療」と銘打たれたものだった。
その治療法の詳細を調べた時任の背筋を、忘れていたはずの感覚に似た何かが駆け抜けた。それは、脳の扁桃体の活動を物理的に抑制し、感情の波を平坦化させるというものだった。成功すれば、精神的な安定が得られる。だが、失敗すれば――。
時任は、栞のアトリエの隠し引き出しから見つけ出していた、もう一冊の小さな手帳を開いた。それもまた、特殊な光でしか読めないインクで書かれた日記だった。
『治療から一週間。世界から色が褪せていく。愛しい猫を撫でても、何も感じない。ただの温かい毛皮の塊だ。』
『一ヶ月。メロディがただの音の羅列に聞こえる。私の頭の中から、物語が消えてしまった。』
『三ヶ月。私は、私でなくなった。心という名の器は空っぽになり、私はそれを見つめるだけの抜け殻になった。ああ、なんてことだ。私は、私自身に、心を盗まれてしまった』
日記の最後のページには、一枚の新聞記事の切り抜きが丁寧に貼り付けられていた。三年前の、彼の妻が犠牲になった通り魔事件を報じる記事。そして、その隅に、小さく時任の名前と「犯罪心理学者」という肩書きが記されていた。
時任は悟った。謎はすべて解けた。
月島栞を失踪させた犯人はいない。彼女は自ら姿を消したのだ。そして、「心を盗んだ泥棒」とは、特定の誰かではない。スランプの重圧に耐えかねて治療に走り、その結果、創造の源泉である感情そのものを失ってしまった、彼女自身のことだった。
彼女は、同じ苦しみを持つであろう時任にだけ、この謎が解けると信じて、涙の依頼状を遺したのだ。感情を持たない人間だけが、感情に振り回される人間の論理を超えて、その絶望の核心にたどり着けると信じて。
第四章 夜明けの海と一粒の雫
日記に挟まっていた古い灯台の写真を手がかりに、時任は海辺の小さな町にたどり着いた。霧雨が降る中、灰色の海を見下ろす崖の上に、その小屋はひっそりと建っていた。
ドアに鍵はかかっていなかった。中にいた月島栞は、時任を見ても何の反応も示さなかった。ただ、アトリエにあった瞳のない顔のように、虚ろな目で窓の外の海を眺めているだけだった。部屋には生活の痕跡がほとんどなく、まるで時が止まっているかのようだった。
「あなたの心を盗んだ泥棒は、見つかりました」
時任は静かに告げた。
「泥棒は、あなた自身だ」
栞の表情は微動だにしない。まるで人形のようだ。
時任は彼女の前に座り、震える手で彼女の日記を開いた。そして、感情を失う前の彼女が綴った、色と音に満ちた世界を、淡々と読み上げ始めた。
「『今日、公園で見た夕焼けは、まるで溶かした杏ジャムのようだった。笑い声は、銀色の鈴の音がした』」
「『締め切りに追われる苦しみは、紫色の棘となって胸に刺さる。でも、描き上げた瞬間の喜びは、すべての棘を黄金の光に変えてくれる』」
それは、時任が失った世界の言葉だった。理解できないはずの言葉の羅列。だが、それを声に出して紡いでいるうちに、彼の記憶の深層で、固く閉ざされていた扉が軋み始めた。妻が笑った時の、陽光の暖かさ。喧嘩した後の、気まずい沈黙の重さ。そして、彼女を失ったあの日の、アスファルトを叩く雨の冷たさ。
論理ではない何かが、彼の胸の奥から突き上げてくる。それは熱く、痛みを伴う奔流だった。気づいた時には、彼の頬を、一筋の雫が伝っていた。
感情のないはずの目からこぼれた、三年ぶりの涙。
それは、栞の喪失への共感か。それとも、彼自身の過去への哀悼か。彼自身にも分からなかった。ただ、その塩辛い一滴が、彼の乾ききった世界に、ほんのわずかな潤いをもたらしたことだけは確かだった。
彼の涙を見た栞の目が、ほんのわずかに見開かれた。彼女の唇が、かすかに震える。言葉にはならなかったが、それは確かに、三年間凍りついていた彼女の世界に生じた、最初の亀裂だった。
事件は解決などしていない。そもそも事件ではなかったのだから。だが、時任は工房への帰り道、車の窓から見える街のネオンが、いつもより少しだけ鮮やかに見える気がした。
彼は自分の工房に戻ると、修復途中だった古い絵本を開く。そこには、赤ずきんが森の中を歩く、色鮮やかな挿絵があった。
彼はその絵を、ただのインクの集合体としてではなく、初めて「美しい」と、感じた。
それはまだ、かつてのような鮮烈な感情ではなかったかもしれない。だが、無音の世界で鳴り響いた、最初の音だった。月島栞から託された白紙の本は、まだ彼の机の上にある。それは今、彼自身の失われた心を取り戻すための物語を書き込む、最初のページのように思えた。