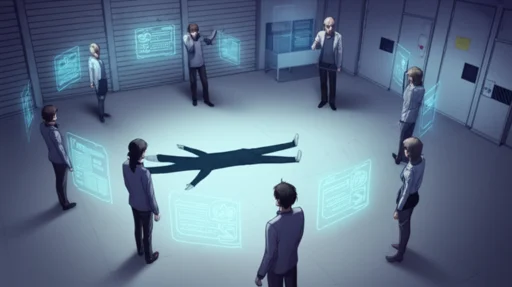第一章 忘れられた色彩
アスファルトを叩く雨の匂いが、街に満ちる忘却の気配を一層濃くしていた。俺、蒼(あお)の眼には、この灰色にくすんだ世界が、時折、ありえない色彩で溢れ出す。それは、誰かから忘れ去られた記憶の断片。人々が失くした過去が、亡霊のように俺の前にだけ姿を現すのだ。
雑踏の中、傘の波間を縫って歩いていると、ふと足が止まった。交差点の向こう側、ショーウィンドウに寄りかかるようにして、ひとりの老人が立っている。ぼろぼろのタキシードを纏い、その顔は恐怖に歪んでいる。しかし、彼の周りを歩く人々は誰一人としてその存在に気づかない。あれは、三日前に「無形の死」を遂げたとされる、高名な音楽家の忘却された記憶。
「無形の死」――命の砂時計が尽きた時、その人間は物理的な死を迎えるのではなく、この世の誰の記憶からも消え去る。家族さえ、友人さえ、まるで最初から存在しなかったかのように、その空白を認識すらしない。それが、この世界の静かで、残酷な法則だった。
最近、その「死」が頻発している。まるで何者かが、人々の砂時計を乱暴に揺さぶっているかのように。
老人の幻影が、震える唇で何かを囁いた。雑音に満ちた世界で、その声だけがクリアに俺の鼓膜を打つ。
「……白い、影が……」
その言葉を最後に、老人の姿は雨に溶けるように掻き消えた。まただ。被害者たちの忘却された記憶は、決まって同じ言葉を口にする。白い影。その正体を突き止めない限り、この静かな連続死は終わらない。俺は濡れたフードを深く被り直し、雨の街へと再び足を踏み出した。この呪われた眼だけが、彼らが確かに存在したという唯一の証なのだから。
第二章 アムネシア・サンドの煌めき
裏路地の奥、古書店を装った情報屋のカウンターに、小さなガラスの小瓶が置かれた。中に満たされた白銀の砂が、薄暗い電球の光を浴びて、星屑のようにきらめいている。
「忘却の砂(アムネシア・サンド)。消えた人間の砂時計からこぼれ落ちた、記憶の結晶だ。気をつけて使いな。こいつは魂を削る」
店主の忠告を背に、俺は小瓶を握りしめ、あの音楽家が暮らしていたという古いアトリエの前に立っていた。雨はとうに上がり、湿った空気が廃墟の匂いを運んでくる。軋むドアを開けると、埃と黴の匂いが鼻をついた。床には、持ち主を失った楽譜が散乱している。
俺は覚悟を決め、小瓶のコルクを抜いた。一粒の砂を指先に乗せる。ひやりとした感触が走ったかと思うと、世界がぐにゃりと歪んだ。
――視界が、老人のものになる。指が鍵盤の上を滑り、美しい旋律を奏でていた。満ち足りた時間。しかし、突如としてピアノの音が狂い始める。不協和音。窓の外に、何かが立っていた。人のかたちをしているが、顔も、服の皺さえもない、のっぺりとした白い影。それはただ、そこにあるだけで、世界の法則をねじ曲げるような圧倒的な違和感を放っていた。恐怖が心臓を鷲掴みにする。砂時計の砂が、滝のように流れ落ちていく感覚。助けて、誰か、俺がここにいたことを、忘れないで――
「う……っ!」
強烈な幻覚から引き戻され、俺はその場に膝をついた。激しい頭痛と目眩が襲う。ポケットに忍ばせた自分自身の砂時計が、微かに熱を持っている。砂の落ちる速度が、ほんの少しだけ、速まっていた。これが、忘却の砂の代償か。それでも、確かな手がかりを掴んだ。あの白い影は、間違いなく「無形の死」に関わっている。
第三章 陽菜の砂時計
次の犠牲者は、花屋を営んでいた若い女性だった。彼女の店先には、主を失った花々が健気に咲き誇っている。俺は再び「忘却の砂」を使い、彼女の最期を追体験した。色とりどりの花に囲まれた幸福な光景が、窓の外に現れた「白い影」によって絶望の色に塗り替えられる。その記憶は、あまりにも鮮烈で、俺の心を深く抉った。
アパートに帰ると、幼馴染の陽菜(ひな)が心配そうな顔で待っていた。
「蒼、また無茶したでしょ。顔色が悪いよ」
彼女が淹れてくれた温かいハーブティーの湯気が、冷え切った俺の指を優しく包む。陽菜だけが、俺のこの能力を知り、孤独な俺の隣にずっと居てくれる唯一の存在だった。
「大丈夫だ」
嘘をつくと、彼女は悲しそうに眉をひそめた。その時、俺は気づいてしまった。陽菜の首にかけられた、小さなペンダント型の砂時計。その中に満たされた生命の砂が、以前よりも輝きを失い、ほんのわずかに、だが確実に量を減らしていることに。
全身の血が凍るような感覚。まさか。この事件は、俺のすぐ傍まで迫ってきているのか。
「陽菜、もうこの件には関わるな」
「でも、蒼が心配で……」
「いいから!」
俺は思わず声を荒らげていた。陽菜を失う恐怖が、俺を冷静でいさせなくする。彼女を守るためなら、どんな代償も厭わない。俺は陽菜を部屋から半ば追い出すようにして、再び夜の街へと駆け出した。焦りだけが、心を焦がしていた。
第四章 影との対峙
犠牲者たちの記憶を繋ぎ合わせ、白い影の出現パターンを割り出した。次の場所は、街外れの廃墟と化した時計塔。錆びついた螺旋階段を駆け上がると、円形の大きな窓から、月明かりに照らされた街並みが広がっていた。
風が吹き抜ける音だけが響く静寂の中、そいつは現れた。
月の光を背に、白い影はそこに立っていた。以前よりも輪郭がはっきりしているように見える。それは敵意も殺意も放っていなかった。ただ静かに、俺を見つめている。
「お前が……人々を消しているのか?」
問いかけに、影は答えない。代わりに、ゆっくりとこちらへ手を伸ばしてきた。その動きは、まるで何かを求めるようでもあり、あるいは何かを与えようとしているようでもあった。俺は身構える。だが、逃げる気はなかった。ここで全てを終わらせる。
影の指先が、俺の額に触れようとした、その瞬間。
――閃光。
脳内に、膨大な情報が濁流のように流れ込んできた。崩壊していく街。砕け散る無数の砂時計。そして、涙を流しながら、砂のように消えていく陽菜の姿。絶望に叫ぶ、俺自身の顔。それは、起こりうる未来のビジョン。悪夢の断片。
混乱する俺の目の前で、白い影ののっぺりとした顔が一瞬だけ揺らぎ、見慣れた――俺自身の顔と、完全に重なった。
「まさか、お前は……」
白い影は、敵ではなかった。警告だったのだ。未来から送られてきた、俺自身の絶望の残響だった。
第五章 繰り返される悲劇の真相
時計塔から戻った俺は、最後の「忘却の砂」を握りしめていた。真実を知るには、これしかない。他人の記憶ではない、俺自身の記憶の最も深い場所へ潜る。陽菜に貰ったお守りを強く握り、俺は意識を記憶の奔流へと投じた。
そこは、何度も何度も繰り返された絶望の世界だった。何度やっても、陽菜が「無形の死」を迎える未来を変えられない。彼女を失った俺は、その悲しみを乗り越えられず、あらゆる手段を尽くして過去へと干渉し、タイムループを繰り返していたのだ。
だが、その行為こそが禁忌だった。過去の出来事に僅かな改変を加えようとするたびに、世界の法則に歪みが生じる。その副作用が、無関係な人々の命の砂時計を狂わせ、砂の落下を加速させていた。俺が陽菜を救おうとすればするほど、新たな犠牲者が生まれていたのだ。
そして、「白い影」。それは、幾千ものループを繰り返し、記憶も言葉も、そして確かな輪郭さえも失い、摩耗しきった未来の俺の成れの果てだった。彼は、過去の自分――今の俺に、この過ちに気づかせ、悲劇の連鎖を断ち切らせるために、最後の力を振り絞って警告を送り続けていたのだ。
全ての記憶が繋がり、パズルのピースがはまった。俺が救おうとしていた世界を、俺自身が壊していた。なんという皮肉か。涙が頬を伝う感覚さえ、現実味を帯びていなかった。
第六章 君のいない世界で、君を憶う
自室の窓から、静かな夜の街を見下ろす。隣には、もう輪郭もおぼろげになった白い影が、静かに佇んでいた。未来の俺。彼は、俺の選択を待っている。
選択肢は二つ。
一つは、このループを終わらせるために、俺自身がこの世界から消えること。原因である俺が存在を止めれば、世界の歪みは修復され、犠牲になった人々も陽菜も元に戻るだろう。だが、俺という存在は、陽菜の記憶からも完全に消え去る。
もう一つは、世界の法則そのものを破壊すること。命の砂時計という理を根底から覆し、誰もが「無形の死」から解放される。だが、それは世界の崩壊を招きかねない、あまりにも危険な賭けだ。
迷いはなかった。陽菜が笑って生きられる世界。たとえそこに、俺がいなくても。
俺は自分の胸元で微かな光を放つ、自分自身の命の砂時計を強く握りしめた。
「さよなら、俺」
そして、ありったけの力を込めて、それを握り潰した。
パリン、とガラスが砕けるよりも澄んだ音が響く。世界が真っ白な光に包まれた。身体が砂のように崩れていく感覚。最後に脳裏に浮かんだのは、陽菜の笑顔だった。忘れないで、とはもう言わない。ただ、幸せでいてくれ。
――季節は巡り、穏やかな春の日差しがカフェのテラスを照らしている。陽菜は友人たちと楽しげに笑い合っていた。満ち足りた、平和な日常。
ふと、彼女は会話を止め、空を見上げた。なぜだろう。胸の奥が、きゅっと締め付けられるように痛む。何か、とても大切で、温かいものを失くしてしまったような、途方もない喪失感。
「……どうしたの、陽菜?」
友人の声に、彼女ははっと我に返る。
「ううん、なんでもない。ただ……今、誰かの名前を呼びたくなった気がして」
誰の名前だったか、思い出せない。けれど、その響きはきっと、世界で一番優しいものだったに違いない。陽菜の瞳から、理由のわからない一筋の涙がこぼれ落ち、春の光を浴びて、きらりと輝いた。