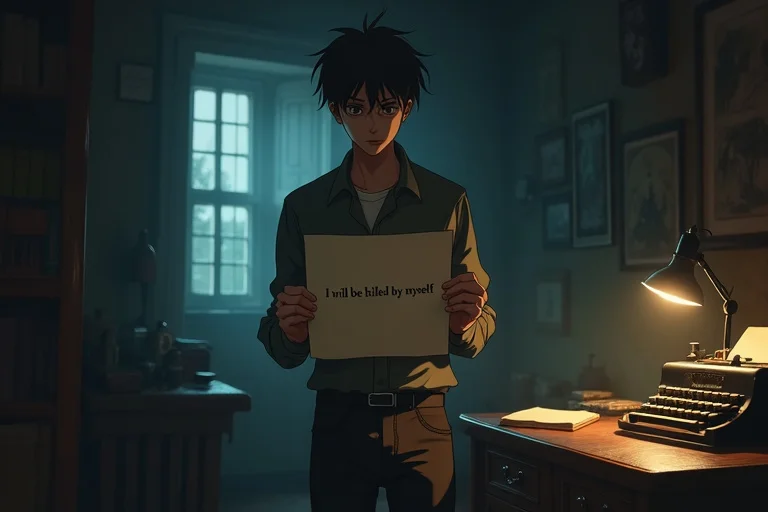第一章 沈黙のパフューム
雨上がりのアスファルトが放つ、甘く湿った匂いが鼻腔をくすぐる。かつて俺、霧島朔(きりしまさく)にとって、世界は香りの万華鏡だった。人の感情さえ、微かなリナロールの甘さや、ゲラニオールの苦みとして感じ取れた。だが、今は違う。あの日、妹の未散(みちる)を乗せた車がガードレールに激突した瞬間から、俺の世界からいくつかの色彩――特定の香りが抜け落ちた。天才調香師と呼ばれた男の、あまりに皮肉な末路だった。
今は海を見下ろす古い洋館で、ポプリやサシェを細々と作り、過去から逃げるように暮らしている。その静寂を破ったのは、旧知の刑事、長谷川の無遠慮なノックだった。
「朔、力を貸してくれ。お前にしか頼めない」
長谷川が持ち込んできたのは、不可解な事件の ملف(カルテ)だった。被害者は資産家の鷲尾厳(わしおげん)、七十歳。書斎で死んでいるのを、妻の静子(しずこ)が発見した。完全な密室、外傷も毒物の痕跡もなし。ただ一つ、奇妙な点があった。
「現場には、誰も嗅いだことのない、奇妙な香りが充満していたそうだ。甘いようで、どこか塩辛いような……。鑑識でも成分を特定できない」
長谷川の言葉に、心の奥底で錆びついた歯車が軋む音がした。
「俺はもう、現役じゃない。特に、複雑な香りは……」
「分かっている。だが、これはただの事件じゃない。鷲尾氏のデスクには、一枚のカードが置かれていた。そこには一言、『香りで私を裁け』と」
『香りで私を裁け』。
それは挑戦状か、それとも懺悔か。俺の嗅覚は、この謎めいたダイイング・メッセージを解読できるのだろうか。現場に残された香りを染み込ませたというガラス瓶を、長谷川が差し出す。蓋を開けた瞬間、俺は息を呑んだ。
懐かしい、というにはあまりに切実で、忘れた、というにはあまりに鮮烈な香り。それは、俺が未散を失った直後、悲しみの坩堝(るつぼ)の中で生み出し、そして永遠に封印したはずの、幻の香水――『忘却の水(レーテ・アクア)』のトップノートに酷似していた。
日常を覆す、というより、抉り出すような出来事だった。止まっていたはずの俺の時間が、再び苦い香りと共に動き始める予感がした。
第二章 記憶の抽斗(ひきだし)
鷲尾邸の書斎は、主を失ってもなお、重厚な威厳を保っていた。古い革張りのソファ、天井まで届く本棚、磨き上げられたマホガニーのデスク。空気に溶け込んだ微かな香りは、間違いなく俺の記憶にあるものだった。だが、何かが違う。核となる部分が、微妙にずれている。まるで、完璧な楽譜を、一音だけ間違えて演奏しているような不協和音。
「奥様の静子さんです」
長谷川に紹介された鷲尾静子は、墨色の着物を纏った、儚げな女性だった。色素の薄い瞳が、深い哀しみを湛えている。
「主人は……気難しい人でした。ですが、あんな形で逝ってしまうなんて」
彼女に、この香りについて尋ねた。彼女は静かに首を横に振る。「嗅いだことのない香りです。ただ……どこか、主人が若い頃に愛用していた香水に似ているような気もいたします」。
関係者への聞き込みは空振りに終わった。遺産を巡って対立していた甥も、事業で揉めていた元パートナーも、誰もこの香りを知らなかった。鷲尾厳と、俺が作った幻の香水。その接点が見つからない。
俺は自分のアトリエに籠もり、香りの再現を試みた。ベルガモット、ネロリ、サンダルウッド……記憶の抽斗(ひきだし)を一つずつ開け、レシピを組み立てていく。だが、何度試しても、あの現場の香りは再現できない。決定的なピースが欠けていた。
「朔、無理はするな。お前の鼻は……」
長谷川が気遣わしげに言う。彼の言う通りだ。俺の嗅覚は、未散の死を境に、特定の樹脂系の香りを正確に捉えられなくなっていた。それは、事故現場に漂っていた、燃えるタイヤとむせ返るような甘い血の匂いに含まれていた成分だった。
この事件は、俺に過去と向き合えと強制している。鷲尾厳はなぜ、この香りを求めたのか。そして、誰が彼に与えたのか。俺は思考の迷宮に迷い込み、苛立ちと無力感に苛まれた。その夜、俺は久しぶりに未散の夢を見た。彼女は何も言わず、ただ悲しそうに微笑み、その頬を一筋の涙が伝っていた。その瞬間、俺は雷に打たれたように目覚めた。
涙。そうだ、涙だ。
第三章 涙の蒸留
翌朝、俺は憑かれたようにアトリエで試薬を混ぜ合わせていた。長谷川が呆れた顔でコーヒーを差し出す。
「何か分かったのか」
「ああ。最大のヒントは、俺自身の記憶の中にあった」
俺は再現した香りを染み込ませたムエット(試香紙)を手に取り、そこに微量の塩化ナトリウム水溶液――人工的に作った涙の成分を、一滴だけ垂らした。
その瞬間、香りは劇的に変化した。これまでバラバラだった香りの分子が一つにまとまり、深く、切なく、そして澄み切ったハーモニーを奏で始めた。これだ。現場に残されていた『沈黙のパフューム』は、これだった。
「どういうことだ?」
「『忘却の水』は、未散が死んだ直後に作った。悲しみの中で、俺は泣きながら調香していたんだ。俺の涙が、偶然にもエッセンスの一つとして紛れ込んでいた。涙に含まれる塩分が、特定の香料の触媒となり、香りを昇華させていたんだ。それは、嗅いだ者の脳に直接働きかけ、最も辛い記憶を一時的に麻痺させる効果があった」
俺はそれを危険な香水だと判断し、レシピごと封印した。だが、誰かがそのレシピを盗み出し、再現したのだ。
長谷川が目を見開く。「じゃあ、犯人は鷲尾氏の辛い記憶を消そうと……? だが、なぜ殺す必要が?」
「違う。これは殺人じゃない。鷲尾氏は、末期の癌で、耐え難い痛みに苦しんでいた。彼は尊厳ある死を望んでいたんだ」
俺は鷲尾邸で感じた違和感の正体に気づいていた。書斎には、彼が収集した数々の美術品が並んでいたが、一つだけ、彼の美学とは相容れない、素朴な木彫りの小箱が置かれていた。それは、俺の工房で作っているポプリの箱だった。
俺たちは再び鷲尾邸へ向かい、静子と対峙した。
「静子さん。あなたはご主人に、何を頼まれたのですか?」
俺の問いに、彼女の静かな瞳が揺らぐ。やがて、堰を切ったように、彼女は全てを語り始めた。
「主人は、日に日に弱っていく自分を許せませんでした。何より、苦しむ姿を私に見せ続けることが、一番辛いと……。彼は、あなたの噂を聞きつけ、人を介して『忘却の水』の存在を知ったのです。そして、私の記憶から、彼が苦しんだ最後の日々だけを消し去ってほしいと、私に頼みました。美しい思い出だけを残してくれ、と」
彼女は、俺の工房からポプリを買い、その箱の構造からレシピが隠された場所を突き止めた。そして、夫のために、涙を流しながら香水を蒸留したのだ。
「あの日、主人は完成した香水を満足そうに嗅ぎ、穏やかな顔で薬を呷りました。そして、『これで君は、私の苦しみを忘れられる。ありがとう』と……。デスクのカードは、私を裁けという意味ではありません。私の罪を、この香りに委ね、そしてどうか赦してほしいという、彼の最後の願いだったのです」
ダイイング・メッセージは、犯人を告発するためのものではなかった。それは、遺される者への、究極の愛と感謝を込めた置き手紙だったのだ。
この香りの本当の名前は『忘却の水』ではない。それは、『赦しのための処方箋』だったのだ。
第四章 赦しの残り香
事件は、嘱託殺人として処理された。静子は執行猶予付きの判決を受けたが、法廷で見せた彼女の表情は、不思議なほど晴れやかだった。彼女は夫の最後の願いを、命を懸けて守り抜いたのだ。
俺はあの日以来、再びアトリエに立つようになった。だが、作るものは以前とは違っていた。もう、人の心を惑わすような、複雑で官能的な香水を作る気にはなれなかった。
あの日、俺が失ったと思っていた嗅覚は、失われたのではなかった。俺自身が、未散の死の記憶と結びついた香りを、無意識に拒絶していただけだったのだ。事件を通して、鷲尾夫妻の愛の形に触れたことで、俺の心にあった固い氷が、少しずつ溶け始めた。
俺は新しい香水の調香を始めた。それは、派手さも、劇的な効果もない、ただ心に寄り添うような、穏やかで優しい香りだ。雨上がりの土の匂い、陽だまりの洗濯物の匂い、そして、遠い昔に母が淹れてくれたミルクティーの匂い。失われた記憶を取り戻すための香りではなく、今ある温かい記憶を、そっと抱きしめるための香り。
長谷川が、判決報告の帰りにアトリエに寄った。
「お前、いい顔になったな」
「そうか?」
俺は完成したばかりの香水を染み込ませたムエットを彼に渡す。
「これは……」
「名前はまだない。だが、誰かの心の、お守りくらいにはなるかもしれない」
長谷川は黙ってその香りを嗅ぎ、そして、ふっと柔らかく微笑んだ。
世界はまだ、美しい香りに満ちている。悲しみも、苦しみも、決して消えることはない。だが、それらを抱きしめながら生きていく人の隣に、そっと寄り添う香りを、俺はこれからも作り続けていくのだろう。
窓の外では、また雨が降り始めていた。だが、今度の雨上がりの匂いは、きっと前よりも少しだけ、優しく感じられるに違いない。
法では裁けない愛があり、言葉では伝えきれない想いがある。そして、それらを繋ぐものが、目に見えない一縷の香りであることを、俺は知っている。