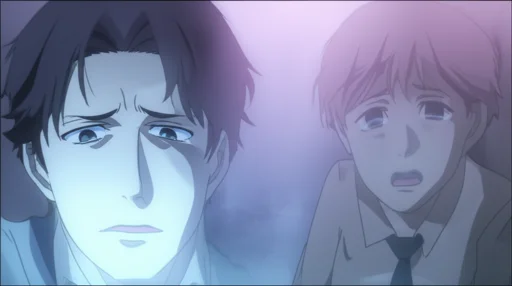第一章 閉ざされた書斎と囁く不在
サキは、祖母の遺品整理のためにこの古い屋敷に滞在していた。陽光さえも澱んだような書斎の埃っぽい空気は、彼女の心に重くのしかかる。祖母が亡くなって一年。美術史を専攻するサキにとって、祖母の膨大な蔵書は貴重な資料だったが、この屋敷にはいつもどこか薄暗い影がつきまとっていた。特に、誰も使っていないはずの書斎から、時折聞こえる微かな物音は、サキの神経を苛んだ。
その日も、古びた地球儀が床に転がり落ちる鈍い音が、静寂を破った。サキは息を呑み、音のした方へ目を凝らす。しかし、そこには何もない。地球儀は確かに落ちているが、その傍には人影どころか、風が通る気配さえもなかった。
「気のせいよ…疲れてるだけ」
彼女は自分に言い聞かせたが、心臓の鼓動は早まる一方だった。視界の隅で、書棚の一段がわずかに揺れたような気がした。本が一本、抜き取られたかのように。だが、見つめると元通りだ。
翌日、サキは再び書斎に足を踏み入れた。昨日の出来事が頭から離れない。一冊ずつ本を手に取り、その背表紙をなぞっていく。祖母が何を探していたのか、あるいは何を隠そうとしていたのか。その時、ふと、背筋に冷たいものが走った。まるで、誰かが背後に立っているかのように。振り向くと、やはり誰もいない。だが、確かな「気配」がそこに存在していた。ひやりとした空気が頬を撫で、襟足に鳥肌が立つ。古本の独特の匂いに混じって、土のような、あるいは鉄のような、生々しい臭いがわずかに鼻腔をくすぐる。
壁にかけられた古びた油絵が、突然、ガタッと音を立てて傾いた。サキは飛び上がるほど驚き、悲鳴を上げかけた。しかし、声は喉の奥で詰まって出ない。絵は完全に水平に戻っていた。まるで誰かが悪戯をしたかのように。
サキは混乱していた。誰かに見られている。あるいは、誰かがいる。だが、その存在は決して彼女の視界には入らない。まるで、彼女にだけ「見えない」何かが、この書斎に閉じ込められているかのようだった。その日から、サキの日常は音もなく、そして確実に侵食されていった。見えない何かの存在は、彼女の恐怖に比例して、より明確に、そしてより悪質になっていくのだった。
第二章 記憶の欠片、歪む現実
見えない存在は、書斎だけに留まらなくなった。夜になると、屋敷のあらゆる場所から、微かな囁き声や、遠くで物が擦れる音が聞こえてくる。それは言葉にならない、しかし感情のこもった、微かな音の連鎖だった。サキは眠れなくなり、日中は常にその「何か」の気配を探して過ごすようになった。冷気が彼女の周りを纏わりつき、触れるもの全てが凍てつく錯覚を覚える。
ある夜、サキは寝室でうとうとしていた。その時、枕元に置いていた祖母の形見のロケットペンダントが、突然、音を立てて床に落ちた。拾い上げると、ペンダントの表面には、まるで爪で引っ掻いたかのような新しい傷がついていた。その傷は、奇妙なことに、幼い頃にサキが誤ってつけてしまった、自分自身の指の傷跡と酷似していた。
「一体、何なの…?」
サキは自問自答した。その見えない存在は、彼女の周囲の物理法則を捻じ曲げるだけでなく、彼女の「記憶」に触れているような気がした。
祖母の書斎で、サキは古いアルバムを見つけた。白黒写真の数々は、彼女がまだ幼かった頃の家族の姿を捉えていた。父、母、祖母、そして自分。どの写真も幸せそうな笑顔に満ちている。だが、一枚だけ、サキが初めて見る写真があった。それは、焼け焦げた壁と、立ち尽くす幼いサキの後ろ姿が写ったものだった。隣には、憔悴しきった祖母の顔。写真の裏には、祖母の震えるような筆跡で、「あの日、全てが始まった」と記されていた。
サキは息を呑んだ。この光景に、全く覚えがない。彼女の幼少期の記憶は、なぜかある時期を境に曖昧だった。父と母は、彼女が幼い頃に事故で亡くなったと聞かされていたが、その詳しい状況はいつもはぐらかされてきた。
その写真を見つめていると、再び冷気が襲いかかってきた。今度は、冷気だけでなく、微かな焦げ臭い匂いも混じる。写真に写る焼け焦げた壁。匂い。そして、彼女の視界に映らない、しかし確かにそこに「いる」何か。
この見えない存在は、彼女の記憶の奥底に封じ込められた、何かを呼び覚まそうとしているのではないか。その瞬間、サキはめまいに襲われた。目の前の世界が、まるで水面に映った像のように揺らぎ始めた。現実が、ゆっくりと歪み始めている。
第三章 見えぬ追跡者、触れる冷気
サキは、祖母の古い日記を見つけ出した。それは書斎の秘密の引き出しに隠されており、埃とカビの匂いが染み付いていた。日記には、彼女が幼い頃に起こった「事件」について、祖母の苦悩が綴られていた。
「あの子は何も覚えていない。それでいい。それが、あの子にとっての救いなのだから。」
祖母の文字は震え、恐怖と悲しみが滲み出ていた。日記には、サキが五歳の頃に、自宅が火事に見舞われたことが記されていた。火事の原因は不明。その火事で、サキの両親は亡くなったという。そして、サキ自身も重度の心的外傷を負い、その時の記憶を完全に失っていた。
「サキの心を守るため、私はあの記憶を封印した。医師の助けも借り、あの子に違う物語を与えた。あの子は知る必要はない。あの悪夢を。」
日記を読み進めるにつれ、サキの胸は締め付けられた。彼女は、祖母が与えてくれた「優しい嘘」の中で生きてきたのだ。両親は事故で亡くなった、という記憶は、祖母が彼女を守るために作り上げたものだった。
その時、日記帳のページが突然、風もないのにめくれ上がった。そして、そこから生々しい焦げ臭い匂いが噴き出した。同時に、強烈な冷気がサキの全身を包み込み、まるで氷水に浸かったかのような感覚に陥る。
「いや…違う…」
サキは震える手で日記帳を押さえようとしたが、まるで目に見えない何かに、その手が振り払われる。部屋の電球が激しく点滅し、やがてパチンという音とともに消えた。漆黒の闇の中、サキの耳に、微かな、しかしはっきりとした囁き声が聞こえてきた。
「…嘘つき…」「…忘れないで…」「…私を…」
それは、まるで幼い子供の声のようでもあり、しかし同時に、底なしの憎悪に満ちた声のようでもあった。その声は、サキの頭の中で直接響いているかのように、身体の芯まで震わせる。
サキは、見えない何かの存在が、自らの失われた記憶、あるいは封印された「真実」そのものであることを悟り始めた。その「何か」は、祖母が必死に隠し続けた、しかしサキ自身が向き合うべき、彼女の過去の断片なのだ。
暗闇の中、彼女は初めて、見えない何かに向かって問いかけた。
「あなたは…誰なの?」
返事はない。しかし、彼女の足元に、まるで影が揺らめくかのように、冷気の渦が収縮し、そして、それは静かに、サキの足元から、その身体を這い上がってくるかのような感覚に襲われた。まるで、見えない存在が、彼女の身体に、その記憶の空白に、入り込もうとしているかのように。それは、恐怖を通り越し、得体の知れない絶望感をもたらした。
第四章 真実の扉、鏡の中の自分
「嘘つき…忘れないで…私を…」
その声が、今やサキの脳裏に直接響き渡り、彼女の精神を蝕み始めていた。見えない存在は、彼女の記憶を歪め、現実との境界線を曖昧にさせる。壁のシミが人の顔に見え、窓の外の木々の枝が、まるでこちらを指差しているように思える。サキは正気を保つのがやっとだった。
ある日、サキは書斎の奥で、祖母が使っていた古い化粧台の前に座っていた。鏡に映る自分は、疲弊しきり、目の下には濃いクマができている。その時、鏡の中のサキの背後で、ぼんやりとした人影が揺らめいた。
サキは息を呑んだ。それは、これまでの「見えない」存在とは異なり、確かに視覚で捉えられる。しかし、それは現実には存在しない影だった。鏡の中の世界でだけ、その影は存在する。
その影は、幼い子供のようだった。焦げ付いたような衣を纏い、顔は判別できないほど歪んでいる。しかし、その影がゆっくりと、鏡の中のサキに近づいてくる。そして、サキの肩に、その冷たい手が触れた。
現実のサキの肩にも、凍るような冷気が走った。
「私を…忘れないで…」
鏡の中の影が、その口元を動かす。それは、書斎で聞こえた囁き声と同じだった。
サキは恐怖に打ち震えながらも、鏡の中の影を見つめ返した。その瞳の奥に、彼女は何かを捉えた。それは恐怖ではなく、深い悲しみと、強い「訴え」だった。
その瞬間、サキの脳裏に、幼い頃の断片的な記憶がフラッシュバックした。燃え盛る家。炎の中で助けを求める両親の声。そして、泣き叫ぶ幼い自分。しかし、その記憶の断片の中に、もう一人、自分と同じくらい幼い子供の姿があった。
その子は、炎の中で、サキの手を強く握っていた。
「一緒だよ…大丈夫…」
その子の声が聞こえた気がした。しかし、次の瞬間、その子の手は、サキの手から滑り落ち、炎の中に消えていく。サキは、誰かに抱きかかえられ、無理やり外へと連れ出されていた。その時、彼女は叫んだ。「あの子を…あの子を助けて!」
だが、その叫び声は、炎の音と、祖母の悲鳴にかき消された。
サキは、愕然とした。彼女の記憶の中には、自分は一人っ子だったはずだ。しかし、あの子供は一体…?
その問いが脳裏に浮かんだ時、鏡の中の影が、ゆっくりと、しかし確実に、その焦げ付いた顔を、サキの顔へと近づけてきた。そして、その顔が、徐々に、幼い頃のサキ自身の顔へと変貌していく。
「私は…あなたの一部…私を捨てないで…」
鏡に映るもう一人の自分。それは、火事の日に、炎の中で失われたと思っていた「もう一人のサキ」だった。
祖母は、サキを救うために、ただ記憶を封印しただけではなかった。あの日、サキには双子の妹がいたのだ。しかし、火事の混乱の中で、妹は炎に飲まれてしまった。祖母は、そのあまりにも残酷な真実からサキを守るため、妹の存在そのものまで、彼女の記憶から消し去ろうとしたのだ。そして、その失われた「もう一人のサキ」の記憶と存在こそが、この屋敷で見えない存在として現れ、サキに真実を思い出させようとしていたのだ。彼女が、自分自身を忘れてしまうことのないように。
第五章 残響と共鳴、光射す庭
サキは、鏡に映るもう一人の自分、亡き双子の妹の姿を凝視した。それは恐怖ではなく、深い悲しみと、途方もない喪失感だった。祖母が、どれほどの苦しみの中でこの秘密を守り続けてきたのか。そして、自分は、どれほど大切な存在を忘却の彼方に追いやっていたのか。
鏡の中の妹の顔は、苦痛に歪んでいたが、同時に、どこか安堵した表情にも見えた。サキが真実を知ったことで、妹の魂もまた、苦しみから解放されようとしているかのようだった。
「ごめんね…私、ずっと…」
サキの目から、大粒の涙が溢れ落ちた。彼女は鏡の中の妹に手を伸ばし、その冷たい頬に触れる。それはまるで、遠い昔、繋いでいたはずの手を、今、再び掴み直すかのような感覚だった。
その瞬間、部屋を満たしていた冷気と焦げ臭い匂いが、ゆっくりと薄れていくのを感じた。囁き声も、もはや怨念めいた響きではなく、遠い子守唄のように優しく、サキの耳に届いた。
鏡の中の妹の姿は、徐々に透明になり、やがて光の粒となって、サキの身体へと吸い込まれていった。それは、失われた記憶が、彼女の心の一部として、再び還っていくかのような感覚だった。
夜が明け、サキは屋敷の庭に出た。夜の間に降った雨が、草木を洗い流し、世界は鮮やかな緑に輝いている。空には、雲間から優しい光が差し込んでいた。
彼女は、もう見えない恐怖に怯えることはなかった。妹の記憶、そして火事の日の悲劇は、決して癒えることのない傷として、サキの心に残るだろう。しかし、それは彼女を縛り付けるものではなく、彼女を形成する一部となった。
祖母の深い愛情、そして妹との繋がりの証として。
サキは、庭の片隅に咲く、祖母が好きだった白いアジサイに触れた。花びらについた露が、陽光を受けてきらめいている。それは、悲しみの中に宿る、希望の光のようだった。
記憶は、時に残酷な真実を突きつける。しかし、その真実と向き合い、受け入れることで、人は強くなれる。そして、失われた愛は、決して完全に消え去ることはない。形を変え、心の中で生き続けるのだ。
サキは、これからもその記憶と共に生きていくだろう。見えない残響は、もう恐怖ではなく、彼女を導く優しい光となった。それは、決して忘れてはならない、そして決して一人ではないという証。彼女は、静かに、しかし確かな一歩を踏み出した。その足取りは、過去の重荷から解放され、未来へと向かう、新たな決意に満ちていた。