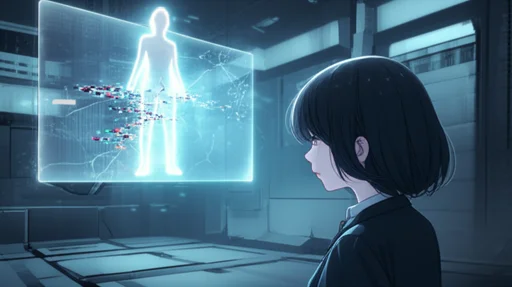第一章 無音の絶叫
響奏(ひびきかなで)の日常は、音で構築されていた。彼はフリーの音声修復師。古びたレコードに刻まれたノイズの海から、忘れ去られた歌手の息遣いを掬い上げ、ひび割れたテープの残骸から、歴史の証言者の肉声を蘇らせる。彼の耳は、常人にはノイズとしか認識できない音の洪水の中から、意味を持つ周波数の粒だけを選り分ける、精緻なフィルターを備えていた。完璧な調和、純粋な音響。それが奏の追求するすべてであり、彼の世界の秩序だった。
その秩序が、耳鳴りのような静寂によって破壊されたのは、木犀の香りが街角に満ち始めた秋の日のことだった。
「兄さん……」
アトリエのドアを開けて入ってきた妹の澪(みお)の口が、確かにそう動いたのを奏は見た。だが、彼の鼓膜を震わせるものは何もなかった。あるのは、唇の動きと、必死な眼差しだけ。そこに音は存在しなかった。
「澪? どうしたんだ、声が……」
言いかけて、奏は息を呑んだ。澪は泣きそうな顔で、何度も口をパクパクさせている。しかし、その喉からは、囁き声一つ、吐息一つ漏れてこないのだ。まるで、彼女の中から「声を出す」という機能だけが、綺麗にくり抜かれてしまったかのようだった。
慌てて駆けつけた大学病院の耳鼻咽喉科で、医師は困惑した顔で首を傾げた。声帯にも、脳にも、神経にも、いかなる異常も見当たらない。機能性失声症、あるいは心因性のものだろうと結論づけられたが、澪に大きなストレスがあったとは考えにくかった。彼女は昨日まで、大学の合唱サークルで、天使のようだと評されるソプラノを響かせていたのだ。
アトリエに戻り、茫然と筆談で状況を聞く。澪が最後に声を出したのは、昨夜、大学からの帰り道にある古い公園だったという。『なんだか、とても静かだった。空気が吸い取られるみたいに』と、彼女はメモ帳に震える字で書いた。
奏の胸に、冷たい疑惑の棘が突き刺さる。単なる失声症ではない。これは、何者かによる「奪取」だ。彼の鋭敏な聴覚が、澪の不在の声を、その空白を、異常なノイズとして捉えていた。それは、ただ音が無いのではない。本来そこにあるべき音の領域が、不自然に削り取られている感覚。まるで完璧な楽曲から、一つのパートだけが忽然と消え去ったような、冒涜的な違和感だった。
奏は録音機材を手に取った。妹の声を奪った「何か」を、この耳で見つけ出す。彼の世界を構成していた調和を取り戻すために。それは、音響のプロフェッショナルとしてのプライドを賭けた、静かなる宣戦布告だった。
第二章 囁きの断片
奏は、澪が最後に声を出したという古い公園にいた。昼間だというのに、そこは奇妙なほど静かだった。鳥の声も、風が木々を揺らす音も、どこか遠く、くぐもって聞こえる。奏は高性能の指向性マイクを構え、公園の空気を「聴いた」。
ほとんどが環境音だ。しかし、注意深く耳を澄ますと、ごく微かな、電子的なノイズが混じっていることに気づいた。人間の可聴域の、すぐ外側で囁くような高周波。奏はそれを録音し、アトリエに持ち帰って解析を始めた。
スペクトラムアナライザにかけた波形は、異様だった。自然界には存在し得ない、極めて人工的で、かつ不安定なパターンを描いている。それはまるで、音声を無理やり圧縮し、別の媒体に「ダビング」しようとして失敗した時のような、歪んだ残響の断片だった。
「声を、録音しているのか……? いや、違う。これはもっと……侵略的だ」
奏は過去の新聞記事やネットの海を漁り始めた。「突然声が出なくなる奇病」というキーワードで検索すると、数は少ないながらも、いくつかの事例がヒットした。数年前のストリートミュージシャン。一年前の朗読家。そして半年前のオペラ歌手志望の学生。いずれも、澪と同じように、医学的に説明のつかない形で、ある日突然、美しい声を失っていた。被害者たちの失踪現場はバラバラだったが、一つだけ共通点があった。彼らは皆、その類稀なる「声」で、人々を魅了していたのだ。
これは連続事件だ。犯人は「声」を蒐集しているコレクターなのだと、奏は確信した。しかし、何のために? どうやって? 警察に相談しても、心因性の問題として片付けられるのが関の山だろう。
奏は独自の調査を続けた。被害者たちの関係者に話を聞き、失われた声がどのような声だったのか、その特徴をデータとして集めていく。ソプラノ、テノール、アルト。力強い声、優しい声、透き通る声。まるで、壮大なコーラスを構成するためのパートを集めているかのようだ。
そんな中、奏は一つの名前に辿り着く。間宮響一郎(まみやきょういちろう)。かつて音響修復の世界で伝説と謳われた男。奏が若い頃、唯一尊敬し、目標としていた人物だった。しかし、間宮は数年前に最愛の妻を亡くして以来、忽然と業界から姿を消していた。彼の妻は、病で声を失った後、生きる気力をなくし、衰弱して亡くなったと聞いている。
胸騒ぎがした。奏は、間宮が隠遁生活を送っていると噂される、郊外の古い洋館を訪ねる決意を固めた。もし、犯人が彼だとしたら、その動機は……。
洋館の前に立った奏の耳に、またあの高周波のノイズが届いた。以前公園で録音したものよりも、ずっと強く、明瞭に。それは、館の中から漏れ出しているようだった。ノイズに混じって、何か、微かなメロディが聞こえる。それは、恐ろしくも美しい、複数の声が重ね合わされた、奇妙なハーモニーだった。
第三章 模倣された追憶
洋館の重い扉は、鍵がかかっていなかった。軋む蝶番の音さえ飲み込むような、濃密な静寂が奏を迎える。埃と古い木の匂いに混じり、微かにオゾンのような機械的な匂いがした。導かれるようにして地下室へ続く階段を降りると、そこには信じがたい光景が広がっていた。
壁一面に並べられた、大小様々なガラスのシリンダー。その一つ一つが淡い光を放ち、中では複雑な音波の波形が立体的に揺らめいていた。まるで、蝶の標本のように「声」が封じ込められている。部屋の中央には、老人が一人、古びた肘掛け椅子に深く身を沈めていた。間宮響一郎だった。
「来ると思っていたよ、響君」
間宮は、奏の耳に直接響くような、不思議な音質の声で言った。彼の傍らに置かれた機械から、その声が発せられているようだ。彼自身の声も、とうに失われているらしかった。
「なぜこんなことを……。澪の声を、返してください」
奏の詰問に、間宮はゆっくりと首を振った。
「返すことはできない。あれはもう、私のコレクションの、大切な一部なのだから」
間宮は語り始めた。最愛の妻、小夜子(さよこ)を亡くした絶望。彼女の声を永遠に失った喪失感。彼は、残された録音テープから彼女の声を修復しようとしたが、それはただの音の記録でしかなかった。彼が求めたのは、声に宿る温もり、感情、そして「記憶」そのものだった。
「私は気づいたのだよ。声とは、単なる空気の振動ではない。その人の生きた記憶の結晶なのだ。だから私は、この装置を作った。人の声帯から、記憶ごと『声』を抽出する装置を」
奏は戦慄した。これは単なる声のコレクションではない。他人の記憶の盗掘だ。
「あなたは狂っている!」
「狂っているかね? 私はただ、妻を忘れたくなかっただけだ」
その時、奏は気づいた。間宮の瞳が、時折、虚空を彷徨うように焦点を失うことに。彼の言葉は明瞭だが、どこか脈絡が途切れる瞬間がある。アルツハイマー病。その言葉が脳裏をよぎった。彼は、失われていく自身の記憶を、他人の声に宿る鮮やかな記憶で補おうとしていたのだ。愛する妻の記憶さえも薄れていく恐怖から逃れるために。
「君の妹の声は素晴らしかった。純粋で、喜びの記憶に満ちていた。だが、私のコレクションはまだ完成しない。最後のピースが足りないのだ」
間宮は、震える手で奏を指差した。
「響君。君の『耳』が、君の声が欲しい。すべてを聞き分けるその絶対的な聴覚と、音に宿る微細な感情を読み解くその声。それさえあれば、私は小夜子の声を……彼女の記憶を、完璧に再現できる」
間宮の背後で、装置が不気味な起動音を立て始めた。ガラスのシリンダーたちが一斉に明滅し、蒐集された声たちが、助けを求めるように不協和音を奏でる。奏は後ずさった。完璧な音を追求してきた自分が、今、その完璧さゆえに、最も冒涜的なコレクションの最後の逸品になろうとしていた。彼の価値観が、音を立てて崩れ落ちていく。完璧さとは、時に人を狂わせる毒なのだ。
第四章 不完全なハルモニア
絶体絶命の窮地。間宮の装置が、奏の声を捉えようと、不快な高周波を放ち始める。奏の頭が、鋭い痛みで割れるように痛んだ。だが、その瞬間、彼の脳裏に、今は声を発することのできない妹、澪の笑顔が浮かんだ。彼女が、少し音程を外しながらも楽しそうに鼻歌を歌っていた、何気ない日常の記憶。
完璧じゃなくてもいい。
その思いが、奏の中で一つの確信に変わった。彼は、間宮に向き直った。
「あなたのやり方は間違っている。記憶は、完璧に保存することなどできない。だからこそ、人は不完全な記憶を抱きしめ、語り継ごうとするんじゃないのか」
奏は逃げる代わりに、アトリエから持参していたポータブルスピーカーとPCを操作し始めた。間宮が怪訝な顔で見つめる中、奏は、彼がかつて公開していた、妻・小夜子の数少ない音声データの修復作業を、その場で始めたのだ。ノイズまみれの、途切れ途切れの音声。
「間宮さん、あなたの耳を貸してください。あなたの記憶を、貸してください」
奏は、自身の絶対的な聴覚と、間宮の断片的な記憶を頼りに、音を再構築していく。
「この時の彼女の笑い声は、もっと……そう、風鈴のような響きがあったはずだ」
「この『ありがとう』は、少し掠れて、陽だまりのような温かさがあった……」
二人の天才的な聴覚が、過去の残響をたぐり寄せる。それは、完璧な再現ではなかった。ノイズは完全には消せず、音の隙間は奏の想像で補うしかなかった。しかし、スピーカーから流れ始めたその声は、確かに、間宮の愛した小夜子の温もりを宿していた。
「さよ……こ……?」
不完全で、途切れ途切れの、それでも愛に満ちた妻の声を聞き、間宮の瞳から大粒の涙がこぼれ落ちた。彼は、自分が集めた完璧な声のコレクションではなく、この不完全な音の断片にこそ、真実の妻がいることを悟ったのだ。彼は自らの手で装置の主電源を落とした。途端に、ガラスのシリンダーの光が消え、凝縮されていた声たちが解放され、囁きとなって空気中に溶けていった。
数日後、澪の声が戻った。以前と全く同じではなかった。少しだけハスキーで、高音域が僅かに掠れるようになった。だが、澪は「この声も、私の一部みたいで、なんだか好きだよ」と笑った。
奏は、彼女のその不完全な声に、これまで感じたことのないほどの愛おしさを感じていた。彼の耳はもう、完璧な周波数だけを追い求めない。ノイズや歪みの中にこそ存在する、人の温かさや、記憶の揺らぎを聴き取ることができるようになっていた。
アトリエの窓から、夕日が差し込んでいる。奏は、修復しかけた小夜子の音声を、そっと保存した。それは永遠に完成することのない、不完全なハルモニア。だが、その不完全さこそが、失われたものへの愛と、遺された者の生の、何よりの証明なのだと、彼は知っていた。彼の世界は、もう完璧な音で構成されてはいない。だが、遥かに豊かで、優しい音色に満ちあふれていた。