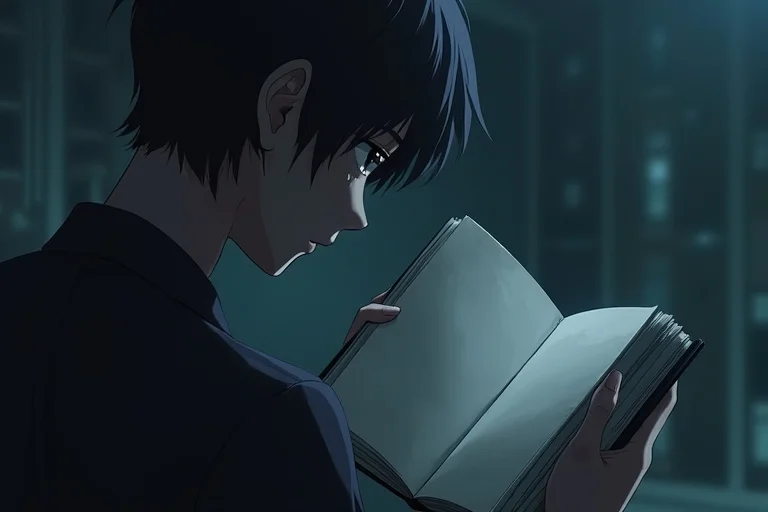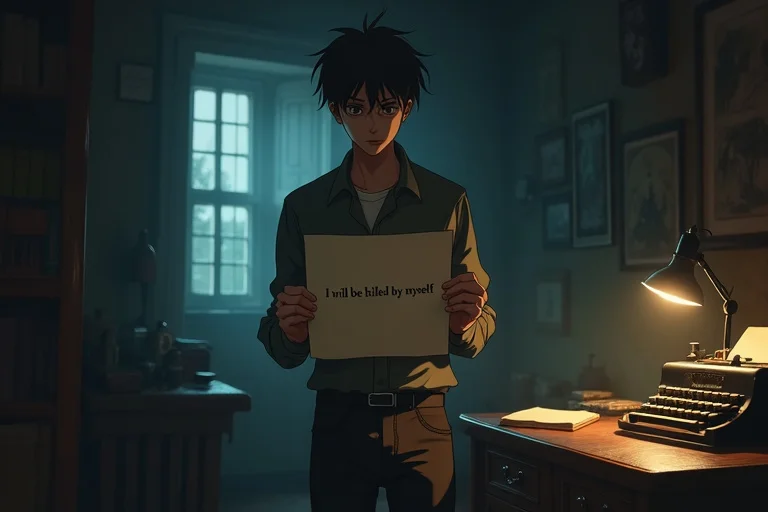第一章 欠けた旋律
カイの仕事は、他人の心に空いた穴を繕うことだった。人々が失くした記憶、『欠けた時間』を、自らの記憶の一部と引き換えに補完する。それが「忘却の補綴師」と呼ばれる彼の生業であり、呪いだった。
古い雑居ビルの三階、埃と古書の匂いが混じり合う彼の事務所の扉が、軋みながら開いた。現れたのは、エリアと名乗る女性だった。雨に濡れたコートから覗くワンピースは色褪せ、その瞳は深い湖のように、静かな絶望を湛えていた。
「恋人との、最後の一日の記憶がありません」
彼女の声は、ひび割れたガラスのようだった。その声が、カイの心の空洞で微かに共鳴する。
人々が記憶を失うのは珍しいことではなかった。この世界では『時間蝕(タイムイクリプス)』が頻発していたからだ。特定の場所、特定の時間が、まるで最初から存在しなかったかのように、人々の認識から綺麗に消え去る。カイだけが、その消された時間の輪郭を、幽かな残響として感じ取ることができた。
「彼が何を話し、どんな顔で笑っていたのか。思い出そうとすると、霧がかかったように……」
カイはエリアの手にそっと触れた。目を閉じると、温かい記憶の奔流が彼女から流れ込んでくる。公園のベンチ、甘い珈琲の香り、夕暮れの街並み。だが、ある一点で記憶はぷつりと途切れ、冷たい空白が広がっていた。その空白の深さは、カイがこれまで触れたどんなものよりも暗く、底が見えなかった。
彼女の記憶を補完しようと試みた瞬間、カイ自身の頭の中で、幼い頃に母と歩いた砂浜の記憶が、波に攫われる砂のようにさらさらと消えていくのを感じた。代償だ。しかし、彼は構わなかった。自分の過去が曖昧になるほど、他者の温かい記憶で自分を埋められる気がしたからだ。
「……難しいかもしれません。これは、ただの忘却ではない」
カイが告げると、エリアの瞳が不安に揺れた。その揺らぎの中に、カイはなぜか、遠い昔に見たことがあるような懐かしい光を見た気がした。
第二章 残光の砂時計
エリアの『欠けた時間』は、強力な時間蝕によるものだった。通常の補完では、世界の修正力に弾き返されてしまう。カイは数日間、彼女の記憶の断片を手繰り寄せようと試みたが、得られたのはノイズ混じりの音と、燃えるような夕焼けの色の残像だけだった。
自分の記憶がさらに薄れていく焦燥感の中、カイは街の裏通りに潜む情報屋の老婆を訪ねた。老婆は水煙管を燻らせながら、低い声で囁いた。
「時間蝕の震源地には、ごく稀に『残光の砂時計』が残されるという。砂の入っていない、空っぽの砂時計がな。それを手にすれば、消えた時間の残光が見えるというが……」
老婆は皺だらけの指で、自らのこめかみを指した。
「気をつけな。時間を覗く者は、やがて時間に覗き返される」
カイは、エリアの記憶が途切れた場所――街の外れにある「鐘楼の丘」へと向かった。そこは一月前の大規模な時間蝕によって、一帯が丸ごと消失した場所だった。今はただ、不自然なほど静かな荒れ地が広がっているだけだ。空気は薄く、音という概念すら存在しないかのように、世界が沈黙していた。
瓦礫と化した教会の跡地を、カイは一心不乱に探し続けた。指先が傷つき、血が滲む。そして、半ば土に埋もれた祭壇の下に、鈍い光を見つけた。
『残光の砂時計』だった。
精緻な銀細工が施されたそれは、上下の硝子球にくびれがあるだけで、肝心の砂は一粒も入っていなかった。カイがそれを手に取った瞬間、まるで凍てつくような冷気が腕を駆け上り、心臓が軋むような痛みに襲われた。世界が、この異物を拒絶している。そんな感覚だった。
第三章 侵食する真実
事務所に戻ったカイは、目の前に座るエリアに静かに告げた。
「少し、危険な方法を試します」
エリアはこくりと頷いた。彼女の信頼が、カイの背中を押していた。
カイは残光の砂時計をそっと逆さにした。
刹那、世界から音が消えた。
砂時計の中で、存在しないはずの砂が燐光を放ちながら流れ落ち始める。そしてカイの脳裏に、断片的な映像が洪水のように流れ込んできた。
鐘楼の丘で、楽しげに笑うエリア。
隣には、優しそうな目をした青年がいる。ユーリ、とカイの知らないはずの名が唇から漏れた。二人は手を繋ぎ、夕日に染まる街を見下ろしている。鐘楼の鐘が、祝福するように鳴り響いていた。なんて幸福な光景だろう。
「……見えた」
カイが呟くと、エリアは期待に満ちた目で彼を見つめた。
「彼は、笑っていましたか?」
「ええ、とても……幸せそうに」
カイは砂時計を何度も振った。そのたびに、幸福な時間の断片が彼の心を温め、同時に砂時計のガラスには蜘蛛の巣のような微細な亀裂が広がっていく。そして、カイ自身の存在もまた、少しずつ侵食されていった。昨日の夕食に何を食べたか思い出せない。自分の親の顔が、靄の中に霞んでいく。
エリアは、日に日に憔ें翠していくカイの姿を痛ましげに見守っていた。
「もう、いいんです。カイさん。あなたのほうが、消えてしまいそうだわ」
「もう少しだ」
カイはかぶりを振った。
「君の笑顔を、完全に取り戻したいんだ」
それはエリアのためであると同時に、空っぽの自分を埋めるための、悲しい渇望だった。
第四章 破滅の鐘
最後の一片を繋ぎ合わせるため、カイは残った全ての精神を集中させ、砂時計を強く振った。
パリン、とガラスの砕ける音が響き、砂時計は粉々に砕け散った。
同時に、カイの意識は真実の奔流に呑み込まれた。
見えた光景は、幸福な一日などではなかった。
鐘楼の丘。狂気に満ちた目で装置を操作する青年ユーリ。彼は時間蝕の研究者だった。彼は、人類の過ちを消去するため、意図的に巨大な時間蝕を引き起こし、歴史を改変しようとしていたのだ。
「これで世界は救われるんだ!」
エリアが泣きながら彼を止めようとしている。
「やめて、ユーリ! それは救済じゃない、ただの破壊よ!」
そして、その場にはもう一人、人物がいた。
ユーリの隣で、冷たい笑みを浮かべて装置のレバーを握る、若き日の自分自身の姿が。
――そうだ、俺が、ユーリの協力者だった。
――俺が、彼の歪んだ理想に共鳴し、この世界の破滅の引き金を引いたんだ。
『時間蝕』は、自然現象などではなかった。あの鐘楼の丘でカイとユーリが引き起こした、世界を終焉させるほどの巨大な時間の歪み。それを「なかったこと」にするために、世界そのものが必死に過去を喰らい、消し去ろうとしていた自己防衛本能だったのだ。
カイの能力は、人々を救うためのものではなかった。消されたはずの破滅の分岐点を、世界の傷口をこじ開け、膿んだ過去を呼び戻す、呪われた力だった。
真実を思い出した瞬間、世界が悲鳴を上げた。
事務所の窓の外で、空が血のような赤黒い色に染まっていく。地面が唸りを上げ、遠くから人々の狼狽する声が聞こえてくる。消え去ったはずの「破滅の未来」が、今、この瞬間に蘇ろうとしていた。
第五章 君が忘れる世界で
「……思い、出したわ」
目の前で、エリアが静かに涙を流していた。彼女はカイの犯した罪も、全てを思い出したのだ。
世界が崩壊していく音の中で、彼女は震える声で言った。
「あなたも……忘れたかったのね。自分がしたことを」
その言葉は、どんな罵倒よりも深くカイの胸を抉った。そうだ、俺は逃げたかった。犯した罪の重さから、記憶を失うことで。そして、他人の記憶を補うという偽善で、自分の罪を覆い隠そうとしていた。
破滅か、偽りの平和か。
選択肢は二つ。このまま蘇った真実を確定させ、世界をあの日と同じ結末に導くか。あるいは――。
カイはゆっくりと立ち上がり、泣きじゃくるエリアの頬に触れた。彼の指先は、すでに半ば透き通り、向こうの景色が揺らいで見えた。
「君が笑っていられる世界がいい」
彼の声は、風のように穏やかだった。
カイは最後の力を振り絞った。それは他者の記憶を補完する力ではない。自らの存在そのものを代償に、世界の記憶を「上書き」する力。
彼はエリアの記憶に深く潜り、ユーリとカイに関する全ての記憶を、ただの「鐘楼の丘で過ごした、美しくも切ない恋の思い出」へと書き換えた。罪も、破滅も、狂気も、全てを優しい忘却の光で包み込んでいく。
「さよなら、エリア」
その言葉を最後に、カイの身体は無数の光の粒子となって霧散し、激しくなる時間蝕の奔流の中へと完全に溶けて消えた。
***
穏やかな午後の日差しが差し込むカフェ。
エリアは一人、窓の外を眺めていた。全てが元通りになった平和な世界。だが、なぜだろう。胸にぽっかりと穴が空いたような、耐え難い喪失感が彼女を襲っていた。
理由もわからず、一筋の涙が頬を伝う。
自分は、ここで誰かを待っていた気がする。とても大切な、誰かを。
テーブルの上には、彼女がなぜ持っているのかも思い出せない、空っぽの砂時計が置かれていた。
砕け散ったはずのそれは、いつの間にか修復され、ただ静かに、午後の光を反射していた。