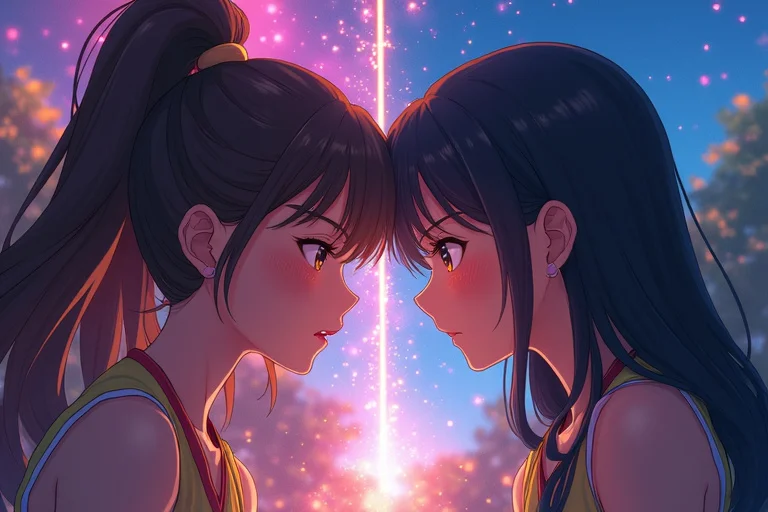第一章 甘美なる琥珀の記憶
僕、レンの舌は、少し変わった感受性を持っていた。他人の記憶に触れると、その断片が味として流れ込んでくるのだ。喜びは蜂蜜のように甘く、悲しみは焦げた珈琲のように苦い。親友であるカイトと過ごす時間は、僕にとって最高の饗宴だった。彼の記憶はいつも、焼きたてのパンの香ばしさと、陽光をたっぷり浴びた柑橘の爽やかな酸味、そしてじんわりと広がる温かいミルクティーの甘さを持っていた。
「また変な顔してるぞ、レン」
公園のベンチで、カイトが僕の顔を覗き込んで笑う。その屈託のない笑顔に触れるだけで、舌の上に微かな甘露が広がった。僕たちは「共鳴者」ではない。この世界では、運命づけられた共鳴者と離れて生きると、互いの生命力が蝕まれていく。だが、カイトとの間に流れる時間は、そんな世界の法則さえ些細なことに思わせた。
その夜、僕はカイトと過ごした今日の記憶を、小さな琥珀色の結晶にした。特別な調合液に記憶の残滓を浸すと、最も鮮烈な感情だけが凝縮され、宝石のような「記憶の結晶」が生まれる。手のひらの上で光を宿すそれは、僕たちの友情の証だった。舐めればいつでも、あの温かい味を追体験できる、僕だけの宝物だ。
第二章 無味の侵食
異変は、秋風が街路樹の葉を染め始めた頃、静かに訪れた。
「最近、映画を観ても何とも思わないんだ。面白いとか、悲しいとか」
カイトがぽつりと呟いた。彼の横顔から、いつもの快活な光が少しだけ翳って見えた。まさか、と思った。僕は彼の腕にそっと触れる。流れ込んでくるはずの記憶の味が、どこかぼやけている。輪郭が曖昧で、水で薄めた絵の具のようだった。
そして、決定的な日が来た。
夕暮れの河川敷で、カイトが僕に言った。
「ごめん、レン。約束、忘れてた」
それは、僕たちが初めて出会った記念日に、一緒に見に行くはずだった演奏会のことだった。彼の言葉に触れた瞬間、僕の舌の上に広がったのは――虚無だった。
味が、しない。
甘さも、苦さも、温かさも、何もない。まるで舌の神経が麻痺してしまったかのような、空っぽの感覚。それは水ですらなかった。ただの「無」が、僕の味覚を支配した。
僕はカイトの顔を見上げた。彼は申し訳なさそうに眉を寄せている。だが、その表情には、かつて僕が味わった後悔の苦味や、友情を思う温かみが、欠片も含まれていなかった。ただ形だけをなぞった、空虚な仮面のように見えた。
第三章 冷たい調和
カイトを蝕んだ「無味化」は、瞬く間に世界を覆い尽くしていった。ニュースは連日、この奇妙な現象を報じた。人々は感情の起伏を失い、街から諍いや怒声が消えた。代わりに、熱狂や歓声も聞こえなくなった。通りを行き交う人々の表情は平板で、誰もが静かに、効率的に日々をこなしている。まるで精巧な機械人形の群れだった。
音楽は色を失い、芸術は意味をなさなくなった。世界は驚くほど静かで、平和になった。だが、その平和は、墓場のような静寂に満ちていた。
共鳴者同士の生命力消耗も、この無味化によって劇的に緩和されたという。人々は、感情という名の枷から解き放たれつつあった。その中心にいるのが、共鳴者システムを管理する絶対的な機関「調和局」だった。
僕は、ガラスと鋼鉄でできた冷たい巨塔、調和局の本部ビルを見上げた。あの場所に、カイトを、そしてこの世界を元に戻す答えがあるはずだ。僕は固く拳を握りしめ、その門をくぐった。
第四章 砕かれた真実
案内されたのは、壁も床も、そしてそこに置かれた椅子さえも真っ白な部屋だった。音もなく現れた女性は、サラと名乗った。彼女の瞳は澄んだガラス玉のように静かで、一切の感情を映していなかった。
「記憶の味を感じる、稀有な能力をお持ちだそうですね」
彼女の声は、合成音声のように抑揚がなかった。
「カイトを……僕の親友を元に戻してほしい。世界を、元に!」
僕の叫びは、その白い空間に虚しく響いた。
サラは静かに首を横に振る。
「戻す? いいえ、これは後退ではなく、進化です」
彼女は語り始めた。感情こそが、人類を争いや憎しみ、非効率な執着に縛り付けてきたバグであること。共鳴者システムも、その感情的依存を管理するための不完全な器に過ぎなかったこと。
「私たちは、そのバグを修正しているのです。無味化は、人類が感情という原始的な束縛から解放され、より高次の意識へと移行するための『脱・感情』プロセス。私たちはそれを少し、加速させているに過ぎません」
その言葉に、全身の血が凍るような感覚を覚えた。
「思い出の味を、友情の温かさを、お前たちは……エラーだと呼ぶのか!」
「はい」
サラは間髪入れずに肯定した。
「それらは全て、生存戦略が生み出した化学反応の幻影。我々は今、その幻影から目覚め、真の調和を手にしようとしているのです」
砕かれた真実は、僕が守りたかった全てのものを、無価値なガラクタだと断じた。絶望が、僕の心を真っ黒に塗りつ潰していった。
第五章 無味の先に
自室のベッドに倒れ込み、僕は天井を見つめていた。世界はもう終わってしまったのだ。僕が愛した、あの感情豊かな世界は。
ふと、机の上に置かれた小さな小箱が目に入った。震える手でそれを開けると、中にはカイトとの最後の温かい記憶から作った、あの琥珀色の結晶が一つ、残されていた。
これが、僕たちの友情の最後の残骸だ。
僕はその小さな結晶を手に取り、祈るように口に含んだ。
瞬間、舌の上に懐かしい味が蘇る。蜂蜜と焼きたてのパン、そして陽光の酸味。涙が溢れた。カイトは、まだここにいる。
だが、その甘美な味はすぐに、現在の「無味」の現実に侵食され、輪郭を失っていく。味が薄れ、消えていく。やめてくれ、消えないでくれ!
僕は必死に、消えゆく味の向こう側へと意識を集中させた。味覚ではない、別の何かを捉えようと、全ての感覚を研ぎ澄ませる。
すると、感じた。
無味の、そのさらに奥深く。静寂の、そのさらに中心に。
それは味ではなかった。感情でもない。温度さえ持たない。
だが、確かにそこにあった。カイトという存在そのものが放つ、純粋な振動。彼がただ「そこにいる」という、揺るぎない肯定の感覚。それはまるで、触れることのできない、けれど確かに存在する、宇宙の響きにも似ていた。
友情とは、記憶の味を共有することだけではなかったのだ。
第六章 新しい糸の結び方
僕はカイトの部屋へ向かった。彼は以前と同じように、窓の外を静かに眺めていた。僕の入ってきた物音に気づき、ゆっくりとこちらを振り向く。その瞳に、昔のような輝きはない。
「カイト」
僕が呼びかけると、彼の口元が、ほんのわずかに動いた。笑みと呼ぶにはあまりにささやかで、けれど確かに、僕の存在に応える形だった。
僕は彼の隣に座り、その手にそっと触れた。
流れ込んでくる記憶に、味はない。
だが、僕にはもう、味は必要なかった。僕の指先に伝わるのは、確かなカイトの存在。その手触りだけで、十分だった。
「味がしなくても、思い出せなくても」
僕は、静かな声で語りかけた。
「君がここにいてくれるだけで、僕は嬉しいんだ」
その言葉に味はない。だが、僕とカイトの間に、確かに何かが生まれたのを感じた。それは目に見えない、透明な糸だった。感情という色彩を持たない、しかし、かつてのどの絆よりも強靭で、純粋な繋がり。
世界はもう元には戻らないだろう。人類は感情を失い、新しい共生の時代を迎える。僕の舌も、いずれ全ての味を感じなくなるのかもしれない。
それでもいい。
失われたものの代わりに、僕たちは新しい絆の結び方を見つけたのだから。
窓の外で、無味になった世界の夜が明けようとしていた。その静かな光は、僕たちがこれから歩む未来を、ただ静かに照らしていた。