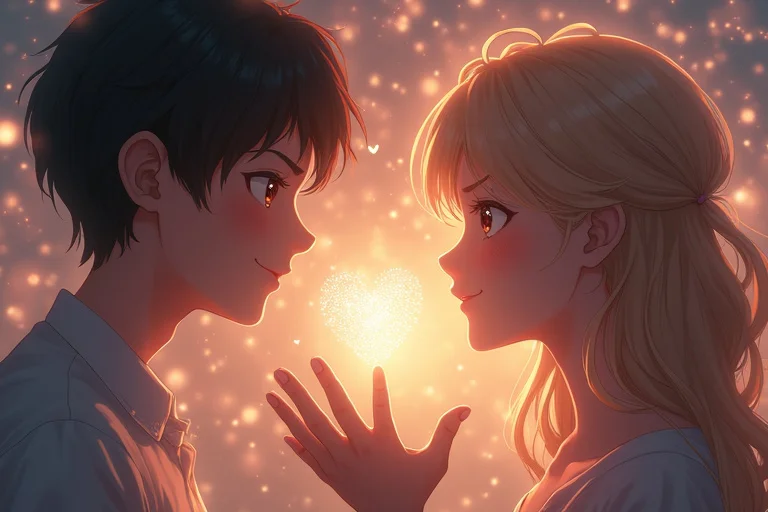第一章 滲むインクと消えた君
月島陽がこの世界から消えたのは、七月の蒸し暑い、蝉の声だけがやけに響く日だった。まるで最初から存在しなかったかのように、何の痕跡も残さずに。警察は家出か事件か判断しかねていたが、僕、水野蒼には分かっていた。これは、そのどちらでもない。陽は、もっと根源的な意味で「いなくなった」のだ。
陽は僕の唯一の親友だった。内向的で、いつも一歩踏み出すことを躊躇してしまう僕の手を、ためらいなく引いてくれる太陽のような存在。そんな陽がいなくなって、僕の世界は色を失った。途方に暮れる僕を見かねた陽の両親が、「何か手がかりになるかもしれないから」と、陽の部屋へ入ることを許してくれた。
陽の部屋は、昨日まで彼女がそこで笑っていたかのように、生活の匂いが満ちていた。読みかけの本、窓辺に置かれた小さなサボテン、壁に貼られた映画のポスター。そのすべてが、彼女の不在をより一層際立たせる。ベッドの下の埃っぽい箱の中に、僕はそれを見つけた。藍色の布張りの、少し古びた日記帳。表紙には拙い文字で『未来交換日記』と記されていた。
胸騒ぎを覚えながらページをめくる。そこには、二つの異なる筆跡があった。一つは、僕がよく知る陽の、丸くて元気な文字。もう一つは、少し大人びた、流れるような美しい文字。日付を見ると、陽の文字の隣には『一年後の私より』と添えられている。陽が、未来の自分と交換日記をしていた?馬鹿げている。でも、陽ならやりかねない。そんな不思議な魅力が彼女にはあった。
日記には、僕たちの他愛ない日常が綴られていた。「今日は蒼と海に行った。蒼は相変わらず水が苦手で面白かった」「未来の私へ。蒼はちゃんと自分の意見を言えるようになった?」そんな微笑ましいやり取りが続く。しかし、読み進めるうちに、僕は奇妙な点に気づいた。日記の所々が、まるで水滴が落ちたかのように、インクが滲んで判読できなくなっているのだ。特に、僕たちの未来に関わるような、重要な部分ほど滲みが酷い。
「どういうことだ…?」
僕が指先でそっと滲んだ箇所に触れた、その瞬間だった。じわり、とインクの染みが引いていき、ぼやけていた文字が、まるで乾いた砂が水を吸うように、一つの単語をくっきりと浮かび上がらせた。
――『忘れないで』。
それは、陽の文字だった。心臓が大きく跳ねる。これはただの日記じゃない。陽が僕に残した、唯一の手がかりだ。僕は日記を強く握りしめ、窓の外の、あまりにも青い空を睨みつけた。陽、君はどこにいるんだ。そして、この日記は、一体何を伝えようとしているんだ。
第二章 記憶の道標
『未来交換日記』が示すヒントは、あまりにも曖昧だった。僕が陽との思い出を強く心に思い描くとき、滲んだ文字が少しずつ読めるようになる。それはまるで、僕の記憶が、この世界から消えかけた陽の存在を繋ぎ止めるための鍵であるかのようだった。
最初の道標は、「塩の匂いがする図書館」という言葉だった。すぐに思い当たる場所があった。海辺の町にある、古い市立図書館。僕たちはよく、窓から潮風が入り込む二階の閲覧室で、本を読んだり、未来について語り合ったりした。
僕は電車に飛び乗り、懐かしいその場所へと向かった。埃と古い紙、そして微かな潮の香りが混じり合った独特の空気が、僕の肺を満たす。あの日と同じ席に座り、目を閉じる。隣でページをめくる陽の気配、僕の名を呼ぶ優しい声、窓の外で鳴くカモメの鳴き声。記憶の断片が、色鮮やかに蘇る。
「陽…」
鞄から日記を取り出すと、果たして、滲んでいた一節が読めるようになっていた。
『蒼との約束、覚えてる?「時のかけら」を見つけたら、世界を救えるって話。馬鹿みたいだけど、私は本気だよ。最初のかけらは、始まりの場所にある』
「時のかけら…?」聞いたことのない言葉だった。でも、「始まりの場所」という言葉には心当たりがあった。僕と陽が初めて出会った、丘の上の公園。夕陽が世界で一番美しく見える、僕たちの秘密基地だ。
公園に着くと、西の空が茜色に染まり始めていた。錆びたブランコに腰掛け、日記を膝に置く。陽と出会ったのは、僕がイジメられて一人で泣いていた時だった。陽は何も言わずに隣に座り、自分のポケットから取り出したビー玉を僕にくれた。「これ、夕陽を閉じ込めたんだ。綺麗だろ?」そのビー玉は、今も僕の机の引き出しに大切にしまってある。
そうだ、あれが始まりだった。陽はいつも、僕に小さな勇気と、世界の美しさを教えてくれた。僕はずっと、彼女の背中を追いかけているだけだった。彼女がいない今、僕は一人で立っていることさえ覚束ない。
「違う、一人でやらなきゃ…」
僕は強く自分に言い聞かせた。陽が僕にこれを託したのなら、僕が前に進むことを望んでいるはずだ。陽に頼りきりだった弱い自分を乗り越えなければ。その決意が、新たな記憶の扉を開いた。夕陽の光が日記のページに差し込み、滲んでいたインクが、次々とその姿を現していく。そこに浮かび上がったのは、僕の思考を完全に停止させる、信じがたい一文だった。
『未来の私へ。蒼に真実を話す時が来た。私が、本当は誰なのかを』
第三章 昨日が書き換わる日記
心臓が氷水に浸されたように冷たくなった。日記のページを震える指でめくる。そこに綴られていたのは、僕の理解を、常識を、そして陽と過ごした全ての時間を根底から覆す、驚愕の真実だった。
日記を書いていたのは、陽と「一年後の陽」ではなかった。
陽の筆跡と、もう一つ。それは、僕自身の、水野蒼の未来の筆跡だったのだ。
『未来の私(蒼)へ。
計画は最終段階に入った。月島陽としての私の存在は、この時間軸から急速に希薄になっている。目的は果たされた。あの夏の日の事故は、もう起こらない。過去の私(蒼)は、あの日、親友を失うことはない。
君がこの日記を読んでいるということは、私はもう君の隣にはいないだろう。ごめん。でも、こうするしかなかったんだ。』
頭が真っ白になった。ページを繰る手が止まらない。そこには、僕が忘却の彼方に押しやっていた、忌まわしい記憶が記されていた。
小学生の頃、僕には陽とは別の、もう一人の親友がいた。名前は、本物の「月島陽」。僕たちは三人でいつも一緒だった。しかし、あの日、丘の上の公園で僕が突き飛ばしたせいで、彼女は階段から転げ落ち、頭を強く打った。命に別状はなかったものの、彼女の家族は僕を許さず、遠くへ引っ越してしまった。僕は、僕のせいでたった一人の親友を失った。
その罪悪感と後悔が、僕の心を何年も蝕み続けた。そして未来、科学者になった僕は、ついに禁断の技術に手を伸ばした。不完全な時間遡行理論。過去の自分を救うため、僕は自らの記憶の一部を封印し、容姿を変え、失われた親友「月島陽」として、過去の自分の前に現れたのだ。
僕が今まで親友だと思っていた陽は、未来の僕自身だった。
彼女(僕)の目的はただ一つ。事故そのものを回避し、僕が罪悪感に苛まれる未来を変えること。そして、内向的で臆病だった僕に、一人でも強く生きていける勇気を与えること。
日記の滲みは、タイムパラドックスによる存在の歪みだった。僕が彼女との記憶を思い出す行為は、この時間軸における彼女の存在を一時的に確定させ、日記の文字を浮かび上がらせる唯一の方法だったのだ。陽が消えたのは、家出でも事件でもない。全ての役目を終え、改変された時間軸から弾き出されるように、本来いるべき未来へと強制的に送還されたからだった。
「そんな…」
声にならない声が漏れた。陽が僕に見せてくれた優しさも、笑顔も、僕を励ましてくれた言葉も、すべては未来の僕が、過去の僕のために用意した、壮大な自作自演だったというのか。
友情だと思っていたものは、僕の弱さが見せた幻だったのか。
夕陽が地平線に沈み、世界が藍色の闇に包まれていく。僕はただ、膝の上の日記を抱きしめることしかできなかった。体中の力が抜け、涙さえも流れなかった。
第四章 未来への返信
どれくらいの時間、そうしていたのだろう。冷たい夜風が頬を撫で、僕はゆっくりと顔を上げた。空には、数えきれないほどの星が瞬いている。陽がよく、「星は過去の光なんだよ。何万年も前の光が、今ここに届いてるって、すごくない?」と言っていたのを思い出す。
陽は、未来の僕だった。
でも、僕が彼女と過ごした時間は?分かち合った喜びも、喧嘩した日の痛みも、全てが偽物だったというのか?
違う。
たとえ彼女が誰であろうと、僕が感じた想いは本物だ。僕の手を引いてくれた温もりは、暗闇の中にいた僕を照らしてくれた光は、紛れもなく本物だった。陽は、僕自身が僕自身に贈った、最高の友情だったのだ。僕が失ったと思っていた親友は、形を変えて、ずっと僕のそばにいてくれた。そして、僕が本当に失っていたのは、親友ではなく、自分を許し、前へ進む勇気だった。
陽は、それを僕に与えるために、全てを賭してくれた。
僕は日記の最後のページを開いた。そこは、まだ何も書かれていない、真っ白な未来。僕は鞄からペンを取り出すと、震える手で、ゆっくりと文字を綴り始めた。未来の僕へ、そして、僕の最高の親友、陽へ宛てた、最初で最後の返信を。
『未来の僕へ。そして、陽へ。
ありがとう。君がしてくれたこと、全部わかったよ。辛かっただろう。寂しかっただろう。一人で、本当にありがとう。
君がくれた勇気は、ちゃんとここにある。僕はもう大丈夫。君がいなくても、一人でちゃんと歩いていける。だから、君は君の世界で、幸せになってくれ。
僕も、この世界で、君が守ってくれたこの現在(いま)を、精一杯生きていくから。
さようなら、僕の、たった一人の親友。』
書き終えた瞬間、日記帳が淡い光を放ち始めた。星の光を集めたような、暖かく、優しい光。ページの一文字一文字が光の粒子となって宙に舞い、僕の周りを一度だけ旋回すると、夜空に溶けるように消えていった。手の中に残されたのは、夜の空気の冷たさだけだった。
陽はもういない。僕の記憶の中にしか。
でも、それでいい。友情とは、隣にいることだけではない。たとえ会えなくても、時間や空間に隔てられても、相手を想い、その想いを胸に生きていくこと。それもまた、友情の形なのだから。
僕は空を見上げた。一番強く輝く星が、まるで陽が瞬きしたように見えた。僕はそっと微笑み、丘を下り始めた。新しい明日へ向かって、今度は、僕自身の足で。