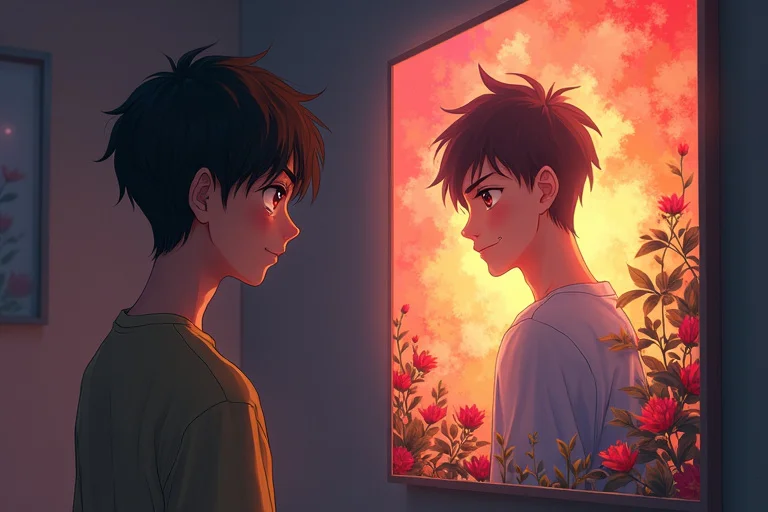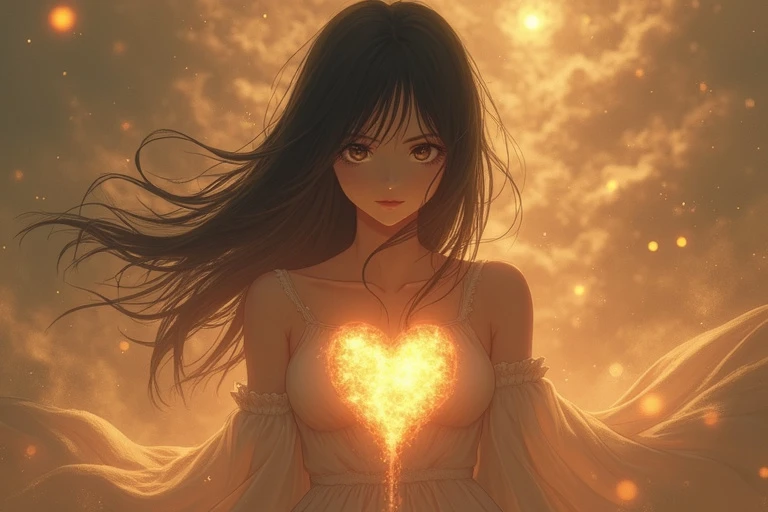第一章 砕けた追憶の欠片
雨の匂いがした。窓の外は、アスファルトを焦がすような真夏の日差しが照りつけているというのに、俺、水無月涼介の脳内には、しっとりと湿った土と草いきれの匂いが満ちていた。それは、俺自身の記憶ではない。
「……またか」
こめかみを押さえ、深く息を吐く。ここ一週間、俺は断続的に、見知らぬ誰かの感覚に襲われていた。赤錆びたブランコの軋む音、指先に残るざらついた砂の感触、そして、頬を伝う生温かい涙の味。それらは全て、俺のものではない、誰かの過去の断片だった。
原因は分かっている。親友の陽斗が失踪したあの日、郵便受けに無造作に放り込まれていた、一つの小箱。中には、乳白色の光を鈍く放つ、指先ほどの大きさの鉱石が入っていた。忘却晶(ぼうきゃくしょう)。この世界で、人々が最も重く、辛い記憶を封じ込めるために使う石だ。そして、その石には、ひびが入っていた。
本来、忘却晶に封じられた記憶は、持ち主以外が触れても何も起こらない。だが、破損した石からは、封じられた記憶の断片が霧のように漏れ出し、周囲の人間に影響を与えることがあるという。俺を苛む他人の感覚は、間違いなくこの石のせいだった。
問題は、なぜこれが俺の元にあるのか、だ。そして、陽斗はどこへ消えたのか。
陽斗は、俺とは正反対の男だった。太陽みたいに笑い、誰にでも気さくに話しかけ、その周りにはいつも人が集まっていた。俺が一人で本を読んでいると、決まって隣にやってきては、屈託のない笑顔で話しかけてきた。彼がいたから、俺の灰色だった大学生活は、少しだけ色づいた。
最後の連絡は、一週間前の短いメッセージ。「少し遠くへ行く。心配するな」という、素っ気ない文面だけ。電話は繋がらず、彼のアパートはもぬけの殻だった。そして、謎の忘却晶。
俺と陽斗の友情は、互いの深い部分には決して立ち入らない、心地よい距離感の上に成り立っていると思っていた。俺は自分の過去を話したことがないし、彼も深くは聞いてこなかった。だが、このひび割れた忘却晶は、俺たちの間に横たわる、俺の知らない何かを雄弁に物語っているようだった。
陽斗はどこで、誰の記憶を、こんなことになるまで抱えていたんだ?
俺は机の上の忘却晶を睨みつけた。乳白色の石の奥で、知らない誰かの悲しみが、静かにまたたいている。俺は陽斗を見つけなければならない。それは、唯一の友人に対する義務感からか、それとも、この忌々しい感覚から解放されたいだけなのか。自分でも分からなかったが、俺は立ち上がるしかなかった。陽斗が残した、ほとんど手掛かりにもならないこの記憶の欠片だけを頼りに。
第二章 沈黙の共有者たち
陽斗の部屋から持ち出した数少ない私物の中に、古びた一冊のノートがあった。几帳面な彼の字で、地名と名前、そして短い記号だけが羅列されている。これが唯一の手がかりだった。俺はリストの最初にあった「汐見崎・小野寺」という記述を頼りに、海沿いの古びた町へ向かった。
汐見崎は、潮風が路地の隅々まで吹き抜ける、寂れた港町だった。古い木造家屋が立ち並ぶ一角に、「小野寺古書店」という看板を見つける。店の奥で、老婆が一人、静かに文庫本を読んでいた。
「陽斗くんのお友達かい」
俺が事情を話すと、店主の小野寺さんは、柔らかい皺の刻まれた顔をほころばせた。「あの子には、本当に救われたんだよ」。彼女は、数年前に亡くした夫の記憶に苛まれ、夜も眠れない日々を送っていたという。そんな時、旅の途中でふらりと立ち寄った陽斗が、彼女の話を何時間も聞き、そして忘却晶のことを教えた。
「夫との幸せだった記憶まで、悲しみに塗りつぶされていくのが耐えられなかった。だから、一番辛い、最期の日の記憶だけを石に預けたんだ。そうしたら、不思議と、夫との楽しかった思い出だけが、綺麗に残ってね」。
彼女は、陽斗が預かった忘却晶を、大切に保管していると言った。陽斗は、他人の記憶を預かる「記憶の預かり人」だったのだ。彼は、人々の最も深い悲しみを、その背中に静かに背負っていた。俺が知っている、おどけた彼の笑顔の裏に、そんな横顔があったとは思いもしなかった。
次に訪れたのは、山間の小さな村だった。ノートにあった「霧ヶ峰・伊吹」という名前を頼りに訪ねた家で、若い陶芸家の男、伊吹と会った。彼は、かつてコンクールで不正を働き、その罪悪感に苛まれていた過去を打ち明けた。
「陽斗は、俺を責めなかった。ただ、『その重荷、少しだけ俺に預けてみないか』って、笑うんだ。あいつに記憶を預けてから、俺はもう一度、土と向き合う勇気をもらえた」。
伊吹も、小野寺さんも、陽斗の行方は知らなかった。だが、彼らの話を聞くうちに、俺の胸には焦燥感とは別の、ちくりとした痛みが広がり始めていた。俺は陽斗の何を知っていたのだろう。彼が人知れず抱えていた重荷に、気づくことさえしなかった。俺はただ、彼の差し出す陽だまりのような優しさを、一方的に享受していただけじゃないのか。
俺たちの友情は、対等なんかじゃなかった。俺が心を閉ざしている間、陽斗はずっと、一人でたくさんの悲しみを背負っていた。俺の元に届いたあの忘却晶は、彼が抱えきれなくなった無数の悲しみの、ほんの一滴に過ぎないのかもしれない。そう思うと、胸が張り裂けそうだった。
第三章 忘却の洞窟
陽斗のノートを何度も読み返し、地名のリストにある種の法則性を見出したのは、旅を始めて二週間が過ぎた頃だった。それらは全て、古い地層や鉱脈にまつわる土地だった。そして、リストの最後には、一つの座標だけが記されていた。俺は、その座標が示す山深くの森へと、最後の望みを託して足を踏み入れた。
森の奥深く、苔むした岩壁に隠れるようにして、その洞窟は口を開けていた。ひんやりとした空気が頬を撫でる。中へ進むと、信じられない光景が広がっていた。
洞窟の壁一面に、無数の忘却晶が埋め込まれ、それぞれが青白い、あるいは乳白色の微かな光を放っていた。まるで、満天の星空を洞窟の中に閉じ込めたかのようだ。人々の忘れたいと願った記憶が、ここでは静かな光となって眠っている。その星空の中心に、陽斗はいた。
痩せこけ、虚ろな目で宙を見つめている。俺が知っている快活な面影はどこにもなかった。
「……涼介か」
か細い声だった。彼はこちらを見ようともしない。
「来ると思ってたよ。もう、限界なんだ。この声が、聞こえるか?」
陽斗がそう言った瞬間、俺の脳内に、再びあの感覚が流れ込んできた。いや、前回の比ではない。何百、何千という人々の後悔、悲しみ、絶望が、濁流となって俺の意識を飲み込もうとする。愛する人を失った慟哭、取り返しのつかない過ちへの懺悔、叶わなかった夢への渇望。俺は立っていることさえできず、その場に膝をついた。
「陽斗、お前、これを……一人で……」
「平気だったんだ、最初は。でも、だんだん石たちの声が大きくなって……僕自身の記憶との境界が、分からなくなっていくんだ」
陽斗は、ゆっくりとこちらを向いた。その瞳には、深い疲労と諦観が浮かんでいた。そして、彼は俺の価値観を根底から覆す、衝撃の事実を告げた。
「涼介、君が一番最初に、僕に記憶を預けてくれたんだよ」
言葉の意味が理解できなかった。俺は、誰にも話したことのない、心の奥底に蓋をした記憶がある。だが、それを陽斗に預けた覚えはない。
「覚えていないのも無理はない。君自身が、忘れることを強く望んだからだ。子供の頃……君の目の前で起きた、あの事故の記憶だよ」
陽斗の言葉が、固く閉ざされた俺の記憶の扉をこじ開ける。そうだ。俺は、忘れていた。幼い頃、俺の不注意が原因で、妹が命を落とした事故。血の匂い。鳴り響くサイレン。両親の悲痛な顔。その全てを、俺は自分の心から切り離し、生きてきたのだ。
「大学で再会した時、君がその記憶の重みで壊れかけているのが分かった。だから、僕が預かったんだ。君が、普通の毎日を送れるように。それが、僕にとっての友情の証だったから」
陽斗が差し出した彼の手のひらの上で、ひときわ大きく、そして暗い光を放つ忘却晶が鎮座していた。それが、俺自身の、失われた記憶だった。陽斗の失踪は、他の誰でもない、俺の記憶の重さに耐えきれなくなったことが、最後の引き金だったのだ。
第四章 夜明けのレクイエム
洞窟の中には、沈黙だけが満ちていた。何千もの声なき声が放つ微かな光が、俺と陽斗の顔を青白く照らし出す。俺は、陽斗の手にある黒ずんだ忘却晶を、ただ見つめていた。あれが、俺の過去。俺が目を背け、陽斗一人に背負わせてきた、罪の記憶。
「陽斗……ごめん」
絞り出した声は、情けないほど震えていた。謝罪の言葉など、何の慰めにもならないことは分かっていた。彼が一人で耐えてきた年月の重さに比べれば、あまりにも軽く、空虚だった。
だが、陽斗は静かに首を振った。
「謝らないでくれ、涼介。僕は、君に笑っていてほしかっただけなんだ。僕が勝手にやったことだ」
その言葉が、ナイフのように俺の胸を抉った。彼の優しさが、あまりにも痛かった。
俺は、ゆっくりと立ち上がった。そして、陽斗の前に進み出ると、彼の手から俺自身の忘却晶を、そっと受け取った。ひんやりとした石の感触が、手のひらにずしりと重い。
「返すよ、これは俺の記憶だ。お前一人に背負わせるものじゃない」
「やめろ、涼介!それを解放したら、君は……!」
陽斗の制止を振り切り、俺は忘却晶を強く握りしめた。石に意識を集中させると、封じられていた記憶が、堰を切ったように俺の魂へと流れ込んでくる。
妹の最後の笑顔。アスファルトに広がる赤。絶望に染まる両親の瞳。罪悪感、無力感、そして、自分だけが生き残ってしまったという、身を裂くような痛み。それは、俺の精神を粉々に砕くほどの激痛だった。だが、不思議と、その痛みの奥底に、陽斗が何年も感じてきたであろう孤独と疲労が、温かい共鳴のように伝わってきた。
俺は、初めて陽斗の痛みを理解した。本当の意味で、彼の心に触れた気がした。
長い、あるいは一瞬のような時間が過ぎ、俺はゆっくりと目を開けた。頬を涙が伝っていた。しかし、心は不思議なほど静かだった。失われた半身を取り戻したような、完全な感覚。
「陽斗」
俺は、彼の名を呼んだ。今度は、もう声は震えていなかった。
「ありがとう。お前のおかげで、俺は今日まで生きてこられた。そして、やっと自分の足で立てる」
俺は洞窟の壁に目を向けた。無数の忘却晶が、まるで鎮魂歌を奏でるように、静かにまたたいている。これら全てが、誰かの悲しみの証なのだ。
「今度は、俺の番だ」
俺は陽斗に向き直り、はっきりと告げた。
「お前が抱えきれないなら、俺が半分持つ。それが、俺たちの友情だろ?」
陽斗の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、長い孤独の終焉を告げる、夜明けの光のように見えた。彼は、ただ小さく頷いた。
俺たちは、言葉もなく、洞窟に並んで腰を下ろした。これから先、俺たちの道は、決して平坦ではないだろう。世界中の人々の悲しみを背負い、その声なき声に耳を傾けながら生きていく。だが、もう一人ではない。隣には、互いの痛みを分かち合える、唯一無二の友がいる。
洞窟に差し込む朝の光が、無数の忘却晶に反射し、まるでレクイエムのように、俺たちの新たな始まりを静かに照らしていた。