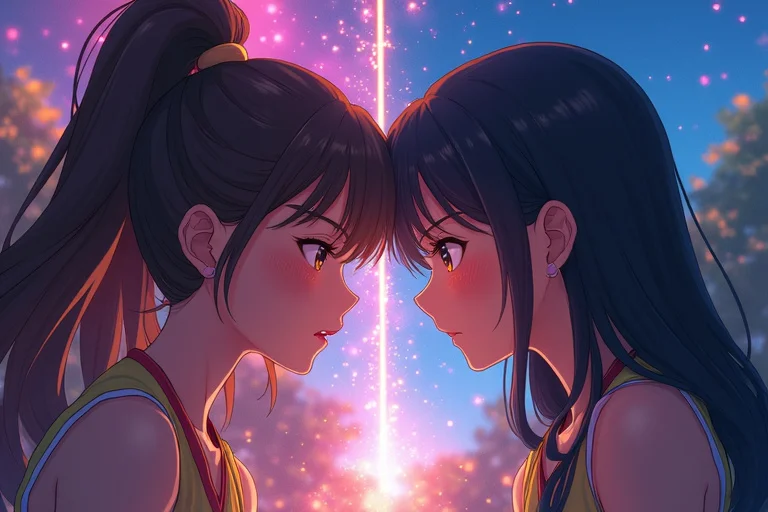第一章 預けられた夢
水島湊の意識は、いつも見知らぬ誰かの夢で濁っていた。
今夜もそうだ。目の前には、白と黒の鍵盤がどこまでも続くように並んでいる。しなやかで白い指が、その上を滑るように舞い、ショパンのエチュードが流れ出す。それは悲しいほどに美しい旋律だった。湊自身はピアノなど弾いたことがない。それなのに、指が鍵盤に触れる硬質な感触や、ペダルを踏み込む足の重みまで、まるで自分の体験のように生々しく感じられた。
汗ばんだ額に張り付く、自分のものより少し長い髪。窓の外で揺れる、夏の日差しを浴びた向日葵。そして、楽譜の隅に書かれた『千尋へ』という、インクが滲んだ優しい文字。
「……また、この夢か」
はっと目を覚ますと、見慣れた自室の天井が目に映った。心臓が早鐘を打っている。額に浮かんだ汗を手の甲で拭い、湊は深く息を吐いた。ここ数週間、繰り返し見る夢。それは親友である柏木陽から預かっている記憶ではなかった。
湊と陽には、秘密があった。二人には、互いの「忘れたい記憶」を預け合う、不思議な力があったのだ。放課後の誰もいない屋上で、フェンスに背を預けて二人で手を固く握り、強く念じる。すると、冷たい水が血管を逆流してくるような奇妙な感覚と共に、記憶が相手の中へと流れ込んでいく。預けられた側は、その記憶を客観的な映像として追体験できるが、それに伴う感情の痛みは薄膜一枚隔てたように和らぐ。そして預けた側は、その記憶に関する一切を、次の儀式まで綺麗に忘れることができた。
湊はこの力に救われていた。中学時代に受けた執拗ないじめの記憶。教室の隅で浴びせられた嘲笑、教科書に書かれた罵詈雑言。その悍ましい記憶の全てを、陽に預けていた。陽がその重荷を代わりに背負ってくれるおかげで、湊はかろうじて平穏な高校生活を送れている。
「よう、湊。顔色悪いぞ」
教室のドアを開けると、窓際の席から陽が屈託なく手を振った。太陽をそのまま閉じ込めたような明るい髪と、人懐っこい笑顔。彼がいるだけで、教室の空気が二度ほど上がる気がする。湊は自分の席に着きながら、昨夜の夢について切り出すべきか迷った。
「陽……あのさ、最近、変な夢を見るんだ」
「夢? どんな?」
「知らない女の子が、ピアノを弾いてる夢。陽が俺に預けた記憶じゃないよな?」
湊の言葉に、陽の笑顔がほんのわずかに、しかし確かに翳った。彼はすぐにいつもの表情に戻ると、冗談めかして言った。
「なんだよそれ。俺はピアノなんて弾けねえし。お前、疲れてんじゃないの?」
「……そう、かもな」
陽はそれ以上何も言わず、窓の外に視線を移した。その横顔に浮かんだ、湊の知らない寂しさのようなものを見ないふりをして、湊はカバンから教科書を取り出した。
陽は何かを隠している。その確信が、じわりと胸の中に冷たい染みのように広がっていく。俺たちの友情の証であるはずの儀式に、何か予期せぬ異変が起きているのかもしれない。あの夢の中の少女は、一体誰なのだろうか。そして、なぜその記憶が、俺の中に存在するのだろうか。チャイムの音が、湊の不安をかき消すように鳴り響いた。
第二章 揺らぐ境界線
あの夢を見る頻度は、日を追うごとに増していった。ピアノを弾く少女の記憶は、断片的な映像から、より鮮明な物語へと姿を変えていく。
ある時は、夏の入道雲の下、自転車を二人乗りして坂道を下る記憶。風を切る音と、背中に感じる温もり。少女の弾けるような笑い声が、湊の耳の奥で共鳴する。またある時は、図書室の隅で、一冊の本を二人で覗き込む記憶。ページをめくる指が触れ合う瞬間の、淡いときめき。その記憶には、いつも陽によく似た快活な少年が隣にいた。
湊は、その記憶に奇妙な懐かしさを覚え始めていた。まるで自分が体験した過去であるかのような、甘く切ない感覚。同時に、それは自分のものではないという明確な違和感が、心を掻きむしる。これは誰の記憶なのだ。陽が隠していることと、何か関係があるのか。
疑念は、湊と陽の間に見えない壁を作り始めていた。以前のように軽口を叩き合っても、どこか空気がぎこちない。陽は湊の視線に気づくと、決まって何かをごまかすように笑った。その笑顔が、今はひどく痛々しく見えた。
ある雨の日の放課後、湊は意を決して、古いアルバムが仕舞われている陽の家へと向かった。陽の両親は共働きで、この時間はいつも留守にしている。合鍵を使って忍び込むことに、罪悪感がないわけではなかった。だが、真実を知りたいという渇望が、それを上回っていた。
陽の部屋の本棚の奥、そこに目当てのアルバムはあった。埃を払い、ページをめくっていく。幼い陽が泥だらけで笑っている写真、家族旅行の写真。そして、湊は息を呑んだ。
一枚の写真に、夢の中の少女がいた。ショートカットがよく似合う、儚げな雰囲気の少女。隣には、今より少し幼い陽が、照れくさそうに笑っている。写真の裏には、掠れた文字で『陽と千尋。ピアノの発表会にて』と書かれていた。
千尋――。柏木千尋。陽の幼馴染で、数年前に病気で亡くなったと聞かされていた少女の名前だった。
心臓が嫌な音を立てて脈打つ。湊が見ていた夢は、亡くなったはずの千尋の記憶だったのだ。なぜ? なぜ彼女の記憶が、自分の中に? 陽は、彼女の記憶を俺に「預けた」というのか? だとしたら、何のために?
湊はアルバムを元の場所に戻し、雨が降りしきる窓の外を見つめた。ガラスを叩く雨音が、混乱する湊の心をさらに乱していく。陽が背負ってくれていたのは、俺のいじめの記憶だけではなかった。彼は、それ以上に重く、そして悲しい何かを、たった一人で抱え込んでいたのではないだろうか。
友情という名の天秤が、大きく傾き始めているのを感じていた。俺が陽に寄りかかっていた分、陽はどれほどの重みに耐えていたのだろう。そして、千尋という少女の存在は、俺たちの関係にとって、一体何を意味するのだろうか。答えの見えない問いが、冷たい雨のように湊の心に降り注いでいた。
第三章 共鳴の真実
「説明してくれ、陽」
翌日、湊は屋上に陽を呼び出した。空は昨日の雨が嘘のように晴れ渡っていたが、二人の間の空気は重く淀んでいた。湊が突き出したアルバムの写真を見て、陽は観念したように目を伏せた。
「千尋の記憶だ。お前が見ていた夢は」
陽はぽつりぽつりと語り始めた。その声は、いつもの快活さのかけらもなかった。
「お前から預かったいじめの記憶は……正直、キツかった。毎晩、お前が受けた痛みや屈辱を夢で見る。お前の心が壊れなかったのが不思議なくらいだ。俺は……耐えられなくなりそうだった」
湊は言葉を失った。陽がそんな苦しみを抱えていたなんて、考えたこともなかった。自分はただ、自分の痛みから逃れることしか考えていなかった。
「でも、お前に記憶を返すなんてできなかった。そしたら、またお前が苦しむことになる。だから……考えたんだ。もっと強い、幸せな記憶で、お前の辛い記憶を上書きできないかって。それで……千尋の記憶を使った。あいつが遺してくれた、一番綺麗で、一番幸せだった頃の記憶を、お前に少しずつ流し込んでいたんだ。お前の心を癒すための、処方箋のつもりで……」
「そんなこと……」
湊は愕然とした。陽は、湊を救うために、亡くなった幼馴染との大切な思い出を、いわば「治療薬」として使っていたのだ。その自己犠牲の大きさに、胸が締め付けられる。だが、陽の告白はそこで終わらなかった。彼は、さらに深く、絶望的な真実を口にした。
「……それに、湊。俺たちがやってきたこと、本当は『預け合い』なんかじゃない」
陽は湊の目をまっすぐに見つめた。その瞳は、深い後悔と悲しみで揺れていた。
「この力は、一方的に記憶を『奪い』、相手に『押し付ける』ためのものだ。そして……最初にそれをやったのは、俺じゃない」
「……え?」
「お前だよ、湊。覚えてないかもしれないけど、俺たちがまだ小学生だった頃、いじめが一番酷かった日だ。お前は泣きながら俺の手を握って、『もう嫌だ』って叫んだ。その時、お前の絶望が、痛みごと全部、俺の中に流れ込んできた。それが始まりだったんだ」
頭を鈍器で殴られたような衝撃。断片的な記憶が蘇る。雨の日の帰り道、傘もささずにずぶ濡れで泣いていた自分。そばにいてくれた陽の手を、必死で握りしめたこと。あの時、確かに何かが自分の中から抜け出て、体が軽くなったような感覚があった。
「俺は、お前が自分を責めないように、『記憶を預け合う力』なんだって嘘をついた。お前が苦しみから解放されるなら、俺が全部背負うって決めたんだ。友情の証だとか、都合のいい名前をつけて……。でも、もう限界だった。ごめん、湊。俺は、お前が思うような、強い親友じゃなかった」
世界が、足元から崩れていくようだった。
救いだと思っていた力は、自分が親友から一方的に痛みを奪い、押し付けるためのものだった。友情の証だと思っていた儀式は、陽が作り出した、俺のための優しい嘘だった。俺は被害者なんかじゃなかった。無自覚なまま、たった一人の親友の心を蝕み続けてきた、加害者だったのだ。
千尋の美しい記憶も、陽が俺の罪を覆い隠すために用意した、悲しい鎮痛剤に過ぎなかった。
湊は、その場に膝から崩れ落ちた。青すぎる空が、無情なほどに眩しかった。
第四章 二人のためのソナタ
真実を知ってから、湊は陽を避けるようになった。同じ教室にいても、目を合わせることができない。陽が時折向けてくる心配そうな視線が、針のように胸に突き刺さる。自分が犯してきた罪の重さに、押し潰されそうだった。
陽のいない時間は、驚くほど空虚だった。いじめの記憶は消えたままだというのに、心は鉛のように重い。陽が背負ってくれた痛みよりも、陽を失うかもしれないという恐怖の方が、ずっと耐え難いものだった。
数日が過ぎた放課後、湊は気づいた。陽が与えようとしてくれた千尋の記憶も、陽が背負ってくれた自分の記憶も、歪んでいたかもしれないが、それら全てが陽の優しさであり、二人を繋いできた紛れもない「友情」の形だったのだと。痛みを押し付け、嘘で塗り固められていたとしても、そこに確かに絆は存在した。
逃げていては駄目だ。自分の痛みからも、犯した罪からも。
湊は走り出した。向かう先は、あの屋上。きっと陽はそこにいる。
案の定、陽は一人、フェンスに寄りかかって遠くの空を眺めていた。湊の足音に気づくと、驚いたように振り返る。
「陽」
息を切らしながら、湊は言った。
「返してくれ。俺の記憶、全部」
陽は目を見開いた。
「何を言ってるんだ。お前、また苦しむことになるぞ」
「いいんだ。それが、俺が背負うべきものだから。もうお前にだけ押し付けたくない。俺は、自分の足で立ちたい。自分の痛みと、ちゃんと向き合いたいんだ」
湊の目に宿った決意を見て、陽はしばらく黙っていたが、やがて静かに頷いた。
二人はいつものように、フェンスに背を預けて隣に座った。どちらからともなく、ゆっくりと手を伸ばし、固く握り合う。
「いくぞ、湊」
「……ああ」
目を閉じると、今度は温かいものが、陽の手から自分の中へと流れ込んでくる感覚がした。それは、忘れかけていた悍ましい記憶の奔流だった。教室の嘲笑、突き飛ばされた廊下の冷たさ、孤独な夜の涙。激しい痛みが心を貫く。だが、不思議と以前のような絶望はなかった。
なぜなら、握りしめた手の温もりが、一人ではないと告げていたからだ。
全ての記憶が戻った時、湊は静かに目を開けた。涙が頬を伝っていたが、心は不思議なほど穏やかだった。隣で、陽が安堵したような、泣き出しそうな、複雑な顔で笑っていた。
「……おかえり、湊」
「……ただいま、陽」
もう、二人が記憶を交換することはないだろう。魔法のような力に頼らなくても、本当の意味で繋がることができたのだから。痛みも、弱さも、罪も、全てを分かち合い、それでもなお隣にいることを選ぶ。それが、湊と陽が見つけ出した、新しい友情の形だった。
夕日が世界を茜色に染め上げていた。湊は陽に向かって、心の底から言った。
「ありがとう」
その一言に、これまでの感謝と、謝罪と、そしてこれからの決意、その全てが凝縮されていた。陽は何も言わず、ただ優しく微笑み返した。二人の影が、屋上に長く、しかし寄り添うように伸びていた。