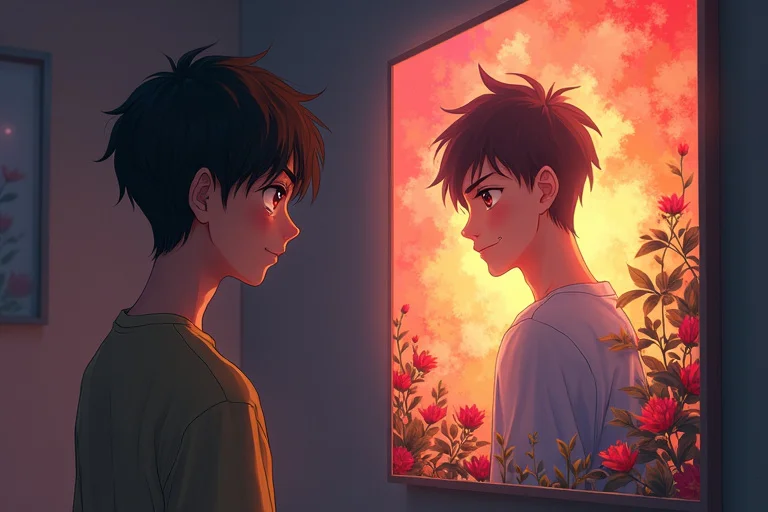第一章 錆びたポストの招待状
桜木修斗の日常は、グレーのグラデーションだった。色のない世界で、唯一の救いはファインダー越しの四角い切り抜き。彼はいつも風景を撮った。人のいない、静かで、完成された景色。人をフレームに入れると、途端に構図が乱れる気がして苦手だった。
そんな彼のモノクロームな世界に、鮮やかな原色を叩きつけた男がいた。橘陽介。太陽と呼ぶのが相応しい、彼の唯一の親友。その陽介が、理由も告げずに姿を消して、もう一年が経つ。
ある日の午後、アパートの錆びついたポストに、見慣れない一通の封筒が差し込まれていた。差出人の名はない。ざらりとした厚手の紙。その質感に妙な胸騒ぎを覚えながら封を切ると、中から滑り落ちたのは一枚の写真と、短いメモだった。
写真は、高校時代に撮ったものだ。海沿いの崖に立つ、蔦の絡まるレンガ造りの廃墟。夕陽がそのシルエットを燃えるようなオレンジ色に染めている。修斗自身が撮った、思い出の一枚。だが、何かがおかしかった。写真の裏には、陽介の筆跡でこう書かれていた。
『あの場所で待ってる』
心臓が氷の塊に鷲掴みにされたような衝撃が走った。一年間、警察でさえ行方を掴めなかった陽介からの、あまりにも突然のメッセージ。なぜ今? どこから? 疑問が渦を巻く。修斗は写真を握りしめた。あの廃墟は、二人だけの秘密基地だった。陽介が失踪する直前、「少し遠くへ行く」とだけ言い残した、あの日の彼の寂しげな横顔が脳裏に蘇る。
待っている、というのなら、行かなくてはならない。
修斗は、防湿庫の奥で眠っていた愛用のカメラを手に取った。陽介のいない一年で溜め込んだ埃を払うように、彼は静かに、しかし確かな足取りで部屋を出た。鈍色の空の下、世界がほんの少しだけ、色づいた気がした。
第二章 潮騒のレクイエム
電車を乗り継ぎ、バスに揺られて数時間。終着のバス停から、潮の香りがまとわりつく海沿いの道をひたすら歩く。ざあざあと寄せては返す波音が、まるで鎮魂歌のように修斗の耳に響いた。
陽介との出会いは、大学の入学式だった。教室の隅で壁と同化していた修斗に、「お前、面白い顔してるな。撮らせろよ」と、屈託なく笑いかけてきたのが陽介だった。彼はいつも輪の中心にいたが、不思議と修斗の隣を居心地良さそうにしていた。陽介がいたから、修斗の灰色の日々は、時折、予期せぬ色彩に彩られた。
だが、陽介は時折、ふっと遠い目をした。誰もいない海を見つめるような、深い孤独の色を瞳に宿していた。修斗はそれに気づきながらも、どう声をかければいいのか分からなかった。その踏み込めなかった一歩が、今も棘のように胸に刺さっている。
崖の上に、目的の廃墟が見えてきた。かつては結核患者の療養所だったと聞く建物は、赤錆びた鉄骨を覗かせ、崩れかけた壁を蔦に覆われながらも、夕陽を背に威厳を保っていた。陽介と二人で、探検と称して何度も忍び込んだ場所だ。
軋む扉を開けると、かびと潮と埃の混じった匂いが鼻をついた。床に散らばるガラス片を踏まないように、慎重に足を進める。壁には陽介がスプレーで描いた、稚拙だが生命力に溢れた宇宙人の落書きが残っていた。何もかもがあの頃のままだ。だが、陽介の姿はどこにもなかった。
がらんとしたホールの中央。そこに、ぽつんと小さなテーブルが置かれ、見覚えのあるものが載っていた。一台の、古いデジタルカメラ。修斗が数年前に陽介に貸したままになっていた、旧式のモデルだった。
「陽介…?」
呼びかけても、応えるのは風の音だけ。修斗はゆっくりとカメラに歩み寄り、そっと手に取った。ひんやりとした金属の感触が、彼の指先に確かな重みを伝えてきた。
第三章 レンズ越しの告白
震える指で、修斗はデジタルカメラの電源を入れた。液晶画面がぼんやりと光を発し、最新の撮影画像を表示する。そこに写っていたのは、見慣れた大学の講義室と、ノートを取る自分の横顔だった。
「え…?」
思わず声が漏れた。再生ボタンを押し、次々と画像を送る。そこに収められていたのは、膨大な数の、修斗自身の写真だった。学食で一人、カレーを食べている姿。図書館の窓際で本を読む姿。公園のベンチに座り、空を仰ぐ姿。そのどれもが、修斗自身も気づかなかった、彼の日常の断片だった。構図は不安定で、ピントが甘いものもある。だが、すべての写真に、撮り手の温かい眼差しのようなものが宿っている気がした。
陽介は、ずっと近くにいたのだ。
自分が「見捨てられた」と孤独に沈んでいた、この一年間。陽介は、姿を見せずに、ただひたすら自分のことを見守り、撮り続けていたのだ。なぜ? どうして?
混乱する頭で写真データの最後まで送ると、一つだけ、動画ファイルが存在した。再生ボタンを押す。砂嵐のようなノイズのあと、画面に陽介の顔が映し出された。一年ぶりに見る親友の顔は、記憶の中よりもずっと痩せこけ、病的なほど青白かった。背景は、見覚えのない殺風景な白い部屋。
『よぉ、修斗。これ、見てるってことは、ちゃんとここまで来てくれたんだな。サンキュ』
画面越しの陽介は、力なく笑った。その声は掠れ、弱々しかった。
『驚かせたよな、ごめん。黙って消えたこと、ずっと謝りたかった。…俺さ、病気なんだ。あんまり長くは、生きられないんだと』
陽介は淡々と、しかし言葉を選びながら語り始めた。彼が患っていたのは、進行性の難病だった。治療法はなく、残された時間は限られていた。
『お前に心配かけたくなかった。俺のせいで、お前の時間を奪いたくなかった。お前はさ、一人でも大丈夫だって、分かってたから。でも…やっぱり心配でさ。お前が撮る写真は、いつも綺麗だけど、どこか寂しいんだ。世界から一歩引いてるみたいで。だから、俺が撮ってやろうと思った。お前が気づいていない、お前のいる世界の、何気ない美しさを』
陽介は、カメラを構えるジェスチャーをした。
『お前の周りには、ちゃんと世界が広がってるんだぜ。お前が思ってるより、ずっと優しくて、彩りに満ちてる。俺がいなくなっても、お前にはそれを見ていてほしかった』
涙が、修斗の頬を伝って流れ落ちた。見捨てられたのではなかった。陽介は、最後まで自分のことを想い、自分の未来を案じてくれていた。彼の孤独は、修斗を孤独にさせないための、あまりにも優しすぎる嘘だったのだ。
『このカメラ、お前に返す。…これからはさ、もっと人を撮れよ、修斗。お前のファインダー越しに見る世界は、きっと、すごく優しいから。俺が保証する。じゃあな…最高の、親友』
動画はそこで途切れた。永遠の沈黙が、廃墟を支配した。修斗は、もう陽介がこの世にいないことを悟った。嗚咽が喉からこみ上げる。手の中のカメラが、陽介の遺した最後の温もりのように感じられた。
第四章 君のいない風景
どれくらいの間、その場に蹲っていただろうか。夕陽が廃墟の窓を茜色に染め、床に長い影を落としていた。修斗はゆっくりと立ち上がり、涙で滲む目で、窓の外に広がる海を見つめた。陽介も、この景色を見ていたのだろうか。
彼は、自分の首から提げていた愛用のカメラを構えた。ファインダーを覗くと、燃えるような空と、穏やかな海のコントラストが広がっている。いつものように、完璧に静かで、美しい風景。シャッターを半押しする。だが、指が動かなかった。この風景には、何かが足りない。決定的に、大切なものが。
修斗はカメラを下ろし、代わりに陽介のデジタルカメラを手に取った。そして、自分のカメラを、陽介が座っていたであろうテーブルの上に置いた。セルフタイマーを十秒に設定する。
彼は、カメラの前に立った。そして、レンズの向こうにいるはずの陽介に語りかけるように、不器用に、ほんの少しだけ口角を上げた。
カシャッ。
乾いたシャッター音が響く。液晶に映し出されたのは、夕陽を背に立つ、泣き笑いのような表情の自分だった。初めて撮った、自分のポートレート。それは、陽介が撮ってくれたどの写真よりも、不格好で、そしてどうしようもなく正直な一枚だった。
陽介、聞こえるか。
お前が見たかったのは、これなんだろ。
俺はもう、大丈夫だ。一人じゃない。お前がくれたこの眼差しがあるから。
修斗は二台のカメラを手に、廃墟を後にした。背中を押すのは、湿った潮風と、陽介が残してくれた数えきれないほどの記憶。彼の世界は、まだ少しだけ悲しみに満ちていたが、もう灰色ではなかった。陽介がレンズ越しに教えてくれた、柔らかな光と色彩が、確かにそこにあった。
これから撮る写真には、きっと人が写り込むだろう。笑う人、泣く人、そして、何気ない日常を生きる人々。そのフレームの中に、今はもういない親友の笑顔を重ねながら、修斗は歩き出す。
君のいない風景を、君が愛したこの世界を、俺は撮り続けていく。
ファインダーの向こうで、また会う日まで。