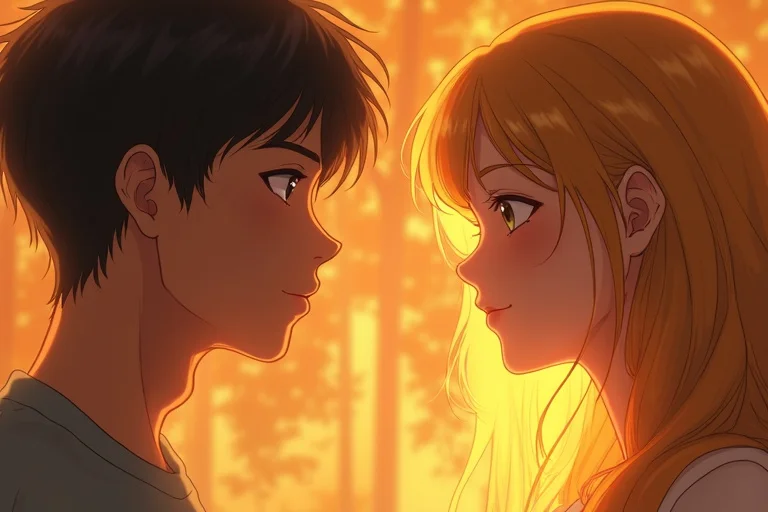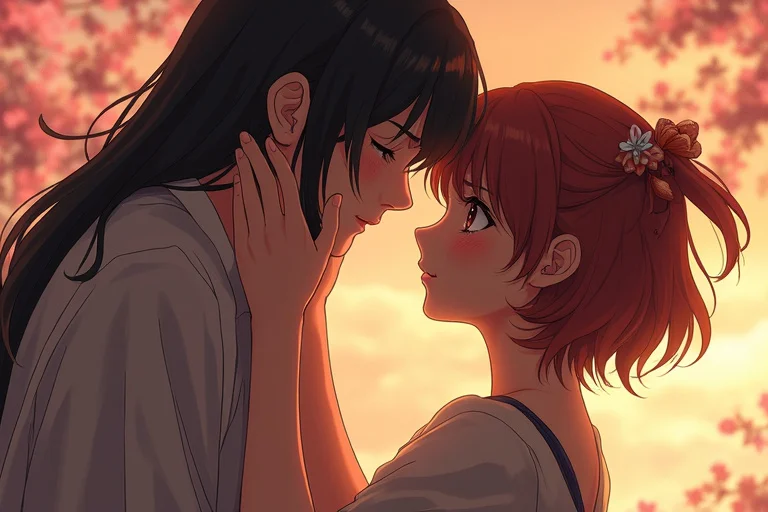第一章 見知らぬデジャヴ
神保町の古書街の片隅に佇む「雨宿り書房」のカウンターで、水野咲は文庫本のページを繰っていた。古い紙の匂いと、静寂だけが満ちるこの場所が、彼女の世界のすべてだった。窓から差し込む午後の光が、埃を金色にきらめかせる。その光景を眺めていると、心の奥に沈殿した哀しみが、ほんの少しだけ和らぐ気がした。
三年前、恋人だった悠人を事故で失ってから、咲の時間は止まったままだ。彼の笑い声、優しい眼差し、指先の温もり。すべてが昨日のことのように蘇り、そのたびに胸が鋭く痛む。世界は色を失い、咲は自ら本棚の迷宮に閉じこもった。
その日、店のドアベルがちりんと乾いた音を立てた。入ってきた男を見て、咲は息を呑んだ。長身で、少し癖のある黒髪。人懐っこそうな笑顔。それだけなら、よくいる客の一人だ。だが、彼が胸ポケットから取り出した万年筆に、咲の心臓は凍りついた。
黒檀の軸に、銀のクリップ。悠人が世界中を探してようやく手に入れた、限定生産の逸品。彼が何よりも大切にしていた、あの万年筆と寸分違わなかった。
「こんにちは。この店、すごく落ち着きますね」
男は屈託なく笑いかけ、カウンターに肘をついた。咲は声が出ない。どうして、あなたがそれを持っているの? その問いが喉まで出かかって、消えた。
「俺、桐谷遥って言います。実は、あなたに一目惚れしちゃって。昨日、店の前を通りかかった時から、ずっと気になってたんです」
唐突な告白に、咲の思考はさらに混乱した。遥と名乗る男は、まるで悠人の影をなぞるように、強引で、けれどどこか憎めない空気をまとっていた。咲は反射的に一歩後ずさり、固く心を閉ざした。悠人以外の誰かを、この心に入れる隙間なんて、もうないのだから。
「……人違いです」
かろうじて絞り出した声は、自分でも驚くほど冷たく響いた。しかし遥は怯むことなく、ただ楽しそうに目を細めるだけだった。その瞳の奥に、咲は一瞬、見覚えのある寂しさの影を見た気がした。
第二章 溶け合う時間
遥は、それから毎日のように「雨宿り書房」に顔を出した。咲がどんなに素っ気ない態度をとっても、彼は気にした風もなく、棚から抜き出した本について熱心に語りかけたり、彼女の好きな作家の話をどこからか仕入れてきては、嬉しそうに話したりした。
ある雨の日、遥は小さな紙袋を手に現れた。
「これ、よかったら」
中には、手のひらに収まるほどの、青いガラスでできた雫の形のオブジェが入っていた。光にかざすと、深い海の底のような、吸い込まれそうな青がきらめく。
「ガラス工芸家なんです、俺。うまくいかなくて、失敗作ばっかりだけど」
照れ臭そうに頭をかく遥に、咲は何も言えなかった。ただ、その青い雫の冷たさと滑らかさが、指先に心地よかった。
遥がもたらす鮮やかな色彩は、咲のモノクロームの世界に、少しずつ沁み込んでいった。彼の存在は、悠人の記憶を呼び覚ます痛みでありながら、同時に、忘れていたはずの微かなときめきをもたらした。悠人への罪悪感と、遥に惹かれていく自分への戸惑い。二つの感情が、咲の中で激しくせめぎ合った。
夏の終わりの夕暮れ時、店の片付けをする咲に、遥がぽつりと言った。
「咲さんのこと、もっと知りたいな。あなたの世界を、俺にも見せてくれない?」
真摯な眼差しに、咲は抗えなかった。この人になら、話せるかもしれない。悠人のこと、そして、止まってしまった自分の時間のこと。気づけば咲は、小さく頷いていた。この決断が、自分の世界を根底から覆すことになるなど、知る由もなかった。
第三章 約束の在り処
咲の小さなアパートは、本の城だった。壁一面の本棚には、悠人と集めた本がぎっしりと並んでいる。緊張した面持ちの遥を部屋に招き入れ、咲は一枚の写真立てを手に取った。海を背景に、満面の笑みを浮かべる悠人と、少し恥ずかしそうに寄り添う自分。
「……彼が、悠人です。三年前に、事故で……」
言葉が途切れる。涙が溢れそうになるのを、必死でこらえた。
遥は黙って写真を見つめていた。その横顔は、いつもの明るさが嘘のように、深い哀しみに沈んでいる。やがて彼は、ゆっくりと口を開いた。その声は、咲が今まで聞いたことのないほど、重く、掠れていた。
「……知ってる。その事故の時、俺も同じ車に乗ってたんだ」
時間が、止まった。耳鳴りがする。遥が何を言っているのか、理解できなかった。
「俺は、悠人の親友だった。でも、事故で頭を打って……俺は生き残ったけど、記憶の一部を失った。特に、悠人に関する記憶のほとんどを」
遥はポケットからあの万年筆を取り出した。
「これは、悠人の遺品の中から見つかったんだ。彼の部屋を片付けていたご両親が、俺にって。そして、一冊の日記も。そこには、君のことが、びっしりと書かれていた。それから……『もし俺に何かあったら、咲を頼む』って、俺へのメッセージも」
咲は立っていられなかった。床にへなへなと座り込む。遥が自分に近づいてきたのは、恋心からではなかった。友情から生まれた、死者との「約束」を果たすためだったのだ。彼の中に見ていた悠人の面影は、幻などではなく、二人が分かち合った時間の残滓だった。
「ごめん。最初は、本当に約束のためだった。失くした記憶のピースを探すみたいに、君に会いに来た。でも、違ったんだ。君と話して、笑い合って……気づいたら、本気で……」
遥の言葉は、もう咲の耳には届かなかった。優しさだと思っていたものは、同情だったのか。運命の出会いだと思ったものは、仕組まれた感傷だったのか。価値観が、世界が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。
「……帰って」
絞り出した声は、ガラスの破片のように冷たかった。
第四章 未来を照らす光
遥が去った部屋で、咲は一人、夜明けを迎えた。彼が置いていった青いガラスの雫を握りしめる。冷たいはずなのに、なぜか彼の体温が残っているような気がした。
遥のいない「雨宿り書房」は、元の静寂を取り戻した。だが、それはもはや安らぎではなく、耐え難い空虚さだった。咲は気づいたのだ。自分は悠人の死を乗り越えたのではなく、ただ分厚い本の壁の内側に隠れていただけだった。遥は、その壁を打ち破り、無理やりにでも咲を光の中へ引きずり出そうとしていたのだ。過去と向き合うことから逃げていたのは、自分自身だった。
数日後、咲は地図を頼りに、郊外にある遥のガラス工房を訪ねた。むっとする熱気が満ちた工房の隅に、咲は息を呑んだ。そこには、歪んだり、ひびが入ったりした、青い雫の失敗作が山のように積まれていた。不器用なまでに繰り返された、彼なりの真摯な想いの欠片たち。
「……どうして、来たんだ」
振り返った遥の顔は、ひどく憔悴していた。咲と出会ったことで、彼もまた、失われた記憶の扉を開けてしまったのだ。親友を失った悲しみと、自分だけが生き残った罪悪感。その苦しみが、彼の瞳を翳らせていた。
「あなたに、会いたかったから」
咲はまっすぐに遥を見つめた。
「悠人のことは、一生忘れない。私の心の中で、ずっと生き続ける。でも、それはもう、私を縛る鎖じゃない」
遥の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
「約束から始まったのかもしれない。悠人の記憶を探していたのかもしれない。でも、今は違う。君といると、忘れていたはずの感情が、まるで初めてみたいに輝き出すんだ。悠人のためじゃない。俺が、君のそばにいたい」
二人はどちらからともなく歩み寄り、そっと抱きしめ合った。溶けたガラスのような熱い想いが、静かに混じり合っていく。
季節は巡り、冬が訪れた。二人は、悠人が好きだった海辺を歩いていた。咲の胸には、遥が新しく作ってくれたガラスのペンダントが光っている。それはどんな形でもない、ただの光の塊のような、透明なガラスだった。過去も未来も、喜びも哀しみも、すべてを乱反射させて、キラキラと輝いている。
悠人が繋いでくれた縁なのかもしれない。でも、今、この冷たい私の手を温めてくれているのは、あなただ。
咲は、隣を歩く遥の手に、そっと自分の指を絡めた。空っぽだと思っていたインク壺に、いつの間にか温かい光が満ちていた。その光は、止まっていた時間を溶かし、二人がこれから歩む未来を、静かに照らし始めている。