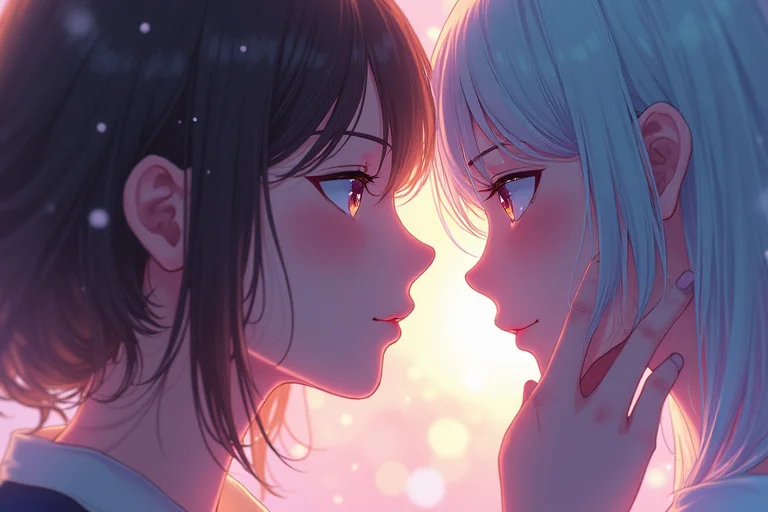第一章 硝子の不協和音
俺、蒼(アオイ)の仕事は、愛の残骸を拾い集めることだ。人はそれを『絆結び師』と呼ぶ。客が持ち込む思い出の品にそっと手をかざすと、込められた想いが熱を帯び、やがて指先に小さな結晶となって現れる。他者の「愛の残留思念」を結晶化させる、それが俺の能力。結晶の色は情熱の赤、形は悲しみの雫、輝きは幸福の強さを示す。俺はその小さな標を頼りに、人々が失くした、あるいはまだ見ぬ『運命の糸』の在り処を指し示すのだ。
今日もまた、若い女性が持ち込んだ万年筆から、澄んだ空色の結晶が生まれた。遠い初恋の相手を忘れられないのだという。俺は結晶が放つ微かな光を辿り、その相手が今も彼女を想っていることを告げた。涙ながらに礼を言う彼女を見送り、俺は深く息を吐く。他人の幸福を形にすることは、俺自身の心を少しずつ削っていく作業にも似ていた。
自宅のドアを開けると、恋人の結奈(ユイナ)が「おかえり」と柔らかな笑顔で迎えてくれた。彼女の淹れてくれる珈琲の香りが、仕事でささくれ立った神経を穏やかに溶かしていく。この部屋に満ちる穏やかな空気、結奈の隣にあるという事実。それこそが俺の救いだった。
しかし、その救いですら、俺を苛む影を完全に振り払うことはできない。
結奈が席を立った隙に、俺はテーブルに置かれた彼女のペンダントに指を伸ばした。彼女が幼い頃から肌身離さずつけているという、銀細工の小さな鳥籠。触れた瞬間、指先に馴染みのある感覚が走る。現れたのは、淡く金色に輝く小さな結晶の欠片。それは燃えるような情熱でも、凍てつくような悲しみでもない。ただひたすらに暖かく、そしてどこか途方もなく古い、追憶の色をしていた。
それは、俺の愛の結晶ではなかった。
視線を窓辺の『共鳴する砂時計』に向ける。結奈と暮らし始めた日に用意した、二人の愛の均衡を計るための硝子のオブジェ。相思相愛ならば砂はゆっくりと、想いに齟齬があれば速く落ちる。その砂が、今日もまた、サラサラと焦るように落ちていくのを、俺はただ無力に見つめることしかできなかった。
第二章 空虚な器
俺の能力は、残留思念を結晶化させるだけではない。意識を集中させれば、人の内にある『運命の糸』の源を視ることができる。それは生命の根源に絡みつく、魂の錨のようなものだ。
結奈が眠りについた夜、俺はそっと彼女の胸に手をかざした。頼む、と祈るような気持ちで意識を沈めていく。
だが、何度試みても結果は同じだった。彼女の体内にあるのは、静かで、冷たい、底なしの空洞だけ。愛が育むはずの『運命の糸』の萌芽すら、そこには存在しなかった。まるで、最初から愛という機能が備わっていない器のように。
「結奈は、俺を愛しているか?」
ある日、耐えきれずに尋ねてしまったことがある。結奈は一瞬きょとんとした後、困ったように眉を下げて笑った。
「愛、なのかな。私、よくわからないの。でも、蒼さんといると、胸のあたりが温かくなる。それじゃ、だめかな?」
その表情に嘘の色は見いだせない。だが、俺の心は晴れなかった。愛を失った者は、糸が消滅する際に魂に刻まれる激しい痛みの記憶を持つ。しかし結奈には、その傷跡すらなかった。
俺の愛は、この空虚な器に注がれ、ただただ吸い込まれて消えていく一方通行の想いなのだろうか。ならば、彼女のペンダントから現れる、あの古い金色の結晶は一体誰の想いなのだ。俺ではない誰かと、彼女は今も途切れぬ糸で結ばれているというのか。疑念は黒い染みのように、俺の心を蝕んでいった。
第三章 金色の追憶
答えを見つけなければ、俺たちの関係は砂時計の砂と共に尽きてしまう。意を決した俺は、結奈がシャワーを浴びている隙に、再びあの鳥籠のペンダントを手にした。今度はただ結晶を出すだけではない。俺の能力のすべてを懸けて、結晶に秘められた記憶の断片を読み解くのだ。
指先に全神経を集中させる。淡い金色の結晶が現れると同時に、俺はさらに深く、その核心へと意識を潜り込ませた。
脳裏に流れ込んできたのは、特定の誰かとの甘い記憶ではなかった。
それは、日だまりの中で分厚い本に夢中になる少女の姿。
雨音にじっと耳を澄ませ、世界から切り離されたような寂しさを湛える少女の横顔。
小さな子猫を抱きしめ、慈しむように涙を流す少女の温もり。
いくつもの情景が、寄せては返す波のように俺の意識を洗う。そこに恋人の姿はない。あるのは、様々な感情を豊かに経験していた、かつての結奈自身の姿だった。それは誰かへの愛ではなく、世界へ、生命へ、物語へ向けられた、純粋で無垢な「愛する」という感情そのものの煌めきだった。
俺は、はっと息を呑んだ。この結晶は、誰か別の男の残留思念などではない。これは、結奈がかつて持っていた「愛する心」そのものの残滓なのだ。
ではなぜ、その心は今、彼女の中から消え失せてしまったのだろう。
第四章 砂時計の終焉
その夜、事件は起きた。
けたたましい振動音に、俺はベッドから跳ね起きた。窓辺に置かれた『共鳴する砂時計』が、まるで生命を宿したかのようにガタガタと震えている。
「蒼さん、これ…!」
隣で眠っていた結奈も目を覚まし、恐怖に染まった顔でそれを見つめていた。砂時計の中では、残されていた砂が滝のような勢いで下の球へと流れ落ちていく。まるで、俺たちの関係の終焉を告げるカウントダウンのように。
止まれ、と叫ぶ俺の声は届かない。
そして、最後の一粒が落ちきった、その瞬間。
砂時計は閃光を放った。パリン、とガラスの悲鳴のような音が響き渡り、砂時計全体が内側から光を放ちながら、みるみるうちに乳白色の結晶へと姿を変えていく。俺の能力が暴走でもしたかのような、ありえない現象だった。
「あっ……!」
隣で、結奈が鋭く息を吸い込み、自らの胸を強く押さえた。その顔は苦痛に歪んでいる。
「痛い……胸の奥が、何か、熱いものが……!」
俺は咄嗟に彼女の肩を抱いた。触れた瞬間、凄まじいエネルギーの奔流が俺の体を貫く。それは、あのペンダントから感じていたものと同じ、暖かくも悲しい、金色の光の奔流だった。世界が、白く染まっていく。
第五章 切り離された絆
光の中で、俺は視た。
幼い日の結奈が、たった一人の家族だったであろう人物を、冷たい亡骸として見つめている光景を。その小さな肩は、世界のすべての悲しみを背負ったかのように震えていた。
絶望の淵で、少女は自らの胸に小さな手を当てる。そこから伸びていたはずの、か細く、頼りない『運命の糸』を、彼女は確かにその手で掴んだ。
『もう、いやだ』
少女の悲痛な心の声が響く。
『こんなに痛いなら、もう誰も愛さない。二度と、こんな想いはしない』
次の瞬間、彼女は涙と共に、その糸を力任せに引きちぎった。魂が裂けるような絶叫が、音もなく俺の心に突き刺さる。
すべてを理解した。結奈に『運命の糸』がなかったのではない。彼女はあまりの痛みから自分を守るために、愛する能力ごと、自らの手で糸を「切り離した」のだ。
ペンダントから現れていた結晶は、切り離された糸の端末が、彼女の中に僅かに残っていた「愛の記憶」を核として、かろうじて形を保っていた魂の欠片。そして、俺が彼女を愛し、そのペンダントに触れ続けたことで、俺の能力が触媒となり、バラバラになった糸の端末を無意識のうちに再構築しようとしていたのだ。
砂時計の結晶化は、その再構築が臨界点に達し、新たな絆が生まれようとする瞬間の、産声のようなどよめきだったのだ。
第六章 糸の夜明け
「大丈夫だ、結奈」
俺は現実世界に戻り、苦痛に喘ぐ結奈を強く、強く抱きしめた。
「君はもう一人じゃない。俺がいる」
俺は自らの魂の中心、体内に宿る『運命の糸』の源に意識を集中させる。そして、その温かい光のすべてを、結奈へと注ぎ込んだ。それは、断ち切られた彼女の糸の端末と、俺自身の糸を結びつけようとする、祈りにも似た行為だった。
結奈の胸を苛んでいた灼熱の痛みが、次第に穏やかな温もりへと変わっていく。彼女の瞳から、一筋の涙が静かにこぼれ落ちた。それは、絶望の涙ではない。長年の間、心の奥底に凍りついていた何かが溶け出し、再び流れ始めた証だった。
俺は再び、彼女の体内を視た。
そこはもう、空虚な器ではなかった。
静まり返った闇の底から、一本の、か細く、しかしどこまでも純粋な光を放つ糸が、ゆっくりと生まれていた。そしてその糸は、確かな意志を持って、俺の糸へと手を伸ばし始めていた。
ふと視線を窓辺に向けると、完全に結晶化した砂時計が、朝陽を浴びて虹色に輝いていた。砂はもう二度と落ちることはない。それは終わりではなく、二人の愛の均衡が、今この瞬間から始まったことを告げる、永遠のモニュメントだった。
俺は結奈の手をそっと握る。伝わってくる確かな温もりは、これまで俺が生み出してきたどんな美しい結晶よりも、遥かに尊く、真実の色をしていた。