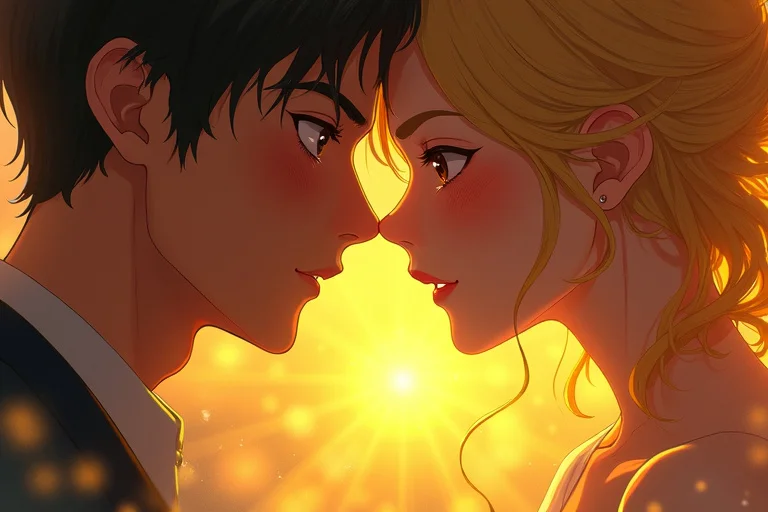第一章 祝福という名の呪い
その兆候は、ある雨の日の午後、唐突に現れた。アトリエの窓を叩く雨音を聞きながら、リヒトは描きかけのキャンバスからふと目を離し、パレットナイフを握る自分の右手を見た。薬指の先、爪の生え際に、まるで砂糖菓子のかけらのような、微細な光の粒が一つ、埋まっていた。はじめは絵の具の破片かガラスの粉末かと思った。だが、布で拭っても、爪で引っ掻いても、それは皮膚の内側から淡い虹色の光を放ち続けていた。
心臓が氷の塊になったかのように冷たく、重くなった。
『結晶病』――通称“恋晶病”。
誰かを深く愛したときにのみ発症する、奇病。恋心が芽生えると身体の末端から結晶化が始まり、愛が深まるにつれて、その美しい侵食は心臓へと向かう。全身が水晶に変わったとき、人は輝くオブジェとなって、永遠の沈黙を迎える。人々はそれを「愛の究極の形」と詩的に呼んだが、リヒトにとっては死の宣告に他ならなかった。
彼は、人を愛することを、愛されることを、ずっと避けて生きてきた。イラストレーターとして、孤独なアトリエでキャンバスに向かう日々。その静寂こそが、彼の聖域だった。誰にも心を揺さぶられず、波立たせることなく、ただ世界を観察し、描く。それだけで満たされていたはずだった。
「誰だ……? 俺が、誰を……」
絞り出すような声は、雨音にかき消された。ここ数ヶ月、仕事以外で誰かと深く関わった記憶はない。それなのに、呪いは確かに彼の内に芽吹いていた。恐怖に駆られ、リヒトはアトリエを飛び出した。冷たい雨が容赦なく彼の身体を打つ。どこへ行けばいいのかも分からず、ただ足を動かした。人でごった返す駅前を抜け、見知らぬ商店街に迷い込む。その一角に、まるでそこだけが雨の灰色から切り取られたかのように、色鮮やかな花々で満たされた小さな店があった。
ガラス張りの店内から、柔らかな光が漏れている。吸い寄せられるように、リヒトは店のドアを開けた。むわりと立ちのぼる、甘く湿った土と花の香り。その香りの源の中心に、彼女はいた。
霧吹きでアジサイの葉に水をやりながら、彼女は静かに鼻歌を歌っていた。振り返った彼女と、目が合った。ミルクティーのような優しい色の髪。そばかすの散った頬。そして、まるで春の陽光をすべて集めたかのような、屈託のない笑顔。
「いらっしゃいませ。すごい雨ですね。よかったら、タオル使ってください」
彼女が差し出した清潔なタオルを受け取りながら、リヒトは気づいてしまった。ああ、この人だ、と。数週間前、新しい画材を探しに街を歩いていたとき、道端で風に飛ばされた彼女の帽子を拾ってやった。ほんの数分、言葉を交わしただけ。それだけのはずだった。だが、彼女の笑顔は、リヒトが守り続けてきた心の壁に、気づかぬうちに小さな、しかし致命的な亀裂を入れていたのだ。
彼女の名は、ユナというらしい。リヒトは何も言えず、ただそこに立ち尽くす。指先の小さな結晶が、彼女の笑顔に応えるかのように、ズキリと痛みを伴って、また一つ輝きを増した気がした。
第二章 きらめきと痛みの日々
リヒトの日常は、幸福と絶望が混ざり合った、奇妙な色合いに染まっていった。彼は結晶病の恐怖から逃れるように、一度はユナの花屋へ足を運ぶのをやめた。しかし、彼女の不在は、彼の世界から色彩を奪った。キャンバスに向かっても、描きたいものは何も浮かんでこない。指先の結晶は、まるで彼の渇望を嘲笑うかのように、日に日にその数を増やし、小さな宝石のクラスターを形成し始めていた。
結局、彼は抗えなかった。一週間後、リヒトは再びその店のドアを開けていた。
「あ、また来てくれたんですね!」
ユナは彼を覚えていた。彼女の笑顔を見るたび、胸の奥が甘く痛み、同時に左手の指先が疼く。それは、愛という名の毒が、ゆっくりと彼の身体を蝕んでいく感覚だった。
彼は病気のことを隠したまま、ユナとの時間を重ねた。彼女はリヒトがイラストレーターだと知ると、子供のようにはしゃいで彼の作品を見たいと言った。リヒトはアトリエに彼女を招いた。静寂の聖域だったはずの空間が、ユナの笑い声と花の香りで満たされていく。彼女は、リヒトの描く、どこか物悲しい風景画をじっと見つめ、「あなたの絵の中の光は、とても優しい色をしていますね」と呟いた。
その言葉が、リヒトの心を強く打った。誰も気づかなかった、彼の絵に込めた微かな希望。それを見つけてくれたのは、ユナだけだった。
「この花、アトリエに飾ってください。きっと、もっと素敵な光が描けますよ」
そう言って彼女が贈ってくれたのは、一輪のガーベラだった。太陽のような、鮮やかなオレンジ色。リヒトはそれを窓辺に飾った。花瓶に差されたガーベラは、まるでユナ自身のように、アトリエ全体を明るく照らした。
会うたびに、リヒトの左手の結晶化は進行した。指先から始まった侵食は、手の甲を覆い、手首にまで達しようとしていた。光にかざすと、皮膚の下で無数の水晶がプリズムのように輝き、息を呑むほど美しい。だがそれは、彼の命の砂時計が着実に落ちている証拠でもあった。彼は長袖のシャツでそれを隠し、ユナに決して左手を見せなかった。
ある夜、二人は公園のベンチで星を見ていた。隣に座るユナの体温を感じる。彼女がふと、リヒトの右手を取った。その自然な仕草に、リヒトの心臓は大きく跳ねた。
「リヒトさんの手、大きいですね。この手から、あの素敵な絵が生まれるんだ」
そう言って、彼女は自分の頬にリヒトの手をそっと押し当てた。その温かさに、涙が出そうになる。この幸福が、自分を殺す。この温もりが、自分を冷たい水晶に変えてしまう。矛盾した感情の渦の中で、リヒトはただ、この時間が永遠に続けばいいと願うことしかできなかった。彼の左手、シャツの袖の下で、水晶の蔓がまた一本、静かに脈を打った。
第三章 記憶を喰らう薬
季節は秋に移ろい、リヒトの左腕は肘のあたりまでが完全に水晶に覆われていた。それはもはや隠しきれるものではなく、日常生活にも支障をきたし始めていた。左腕は重く、冷たく、時折、神経を逆撫でするような鋭い痛みが走る。そして何より、リヒトはユナを騙しているという罪悪感に苛まれていた。
このままではいけない。すべてを話し、彼女の前から消えよう。それが、彼女をこれ以上危険な「愛」に巻き込まないための、唯一の方法だった。
リヒトはユナをアトリエに呼び出した。いつものように笑顔でやってきた彼女を前に、彼は言葉を切り出せない。覚悟を決めて、彼はゆっくりと左腕のシャツの袖をまくり上げた。
「ユナ……俺は……」
陽光を反射してきらめく、水晶の腕。それを見たユナは、息を呑んだ。しかし、彼女の表情はリヒトが予想したような恐怖や哀れみではなかった。そこにあったのは、深い、深い悲しみと、そして、何かを知っている者の瞳だった。
「……結晶病、なの」
「ごめん。ずっと、黙っていて」リヒトは床に目を落とした。「君に会ってから、始まったんだ。だからもう、会うわけにはいかない」
沈黙が落ちる。リヒトが顔を上げると、ユナの瞳から大粒の涙がこぼれ落ちていた。彼女は震える声で言った。
「私のせい……ごめんなさい……」
「違う!君のせいじゃない!俺が勝手に……」
「ううん」ユナはかぶりを振った。そして、リヒトの心を根底から揺るがす、衝撃的な事実を告げた。「私ね、本当はあなたの気持ち、ずっと前から気づいてた。だって……私にも、同じものがあるから」
そう言うと、ユナは自分のカーディガンの袖をまくった。彼女の華奢な右腕。その手首に、まるでブレスレットのように、小さな水晶の粒が点々と輝いていた。
「え……?」
「私も、あなたを愛してるから」
リヒトは混乱した。ユナも結晶病? なのに、なぜ彼女の症状はこんなにも軽いままなのか。リヒトの疑問を見透かしたように、ユナは鞄から小さな薬瓶を取り出した。中には、真珠のような白い錠剤が入っている。
「治療薬があるの。数年前に開発されたのよ」
希望の光が見えた気がして、リヒトは身を乗り出した。だが、ユナの次の言葉が、彼を再び絶望の淵に突き落とした。
「この薬は、結晶化の進行を止めてくれる。でも……副作用があるの。病気の原因になった恋愛感情と……その相手に関する記憶を、全部消してしまうの」
ユナは静かに語り始めた。彼女も以前、別の誰かを愛し、結晶病を発症したこと。死の恐怖から薬にすがり、一命を取り留めたこと。そして、その代償に、愛した人の顔も名前も、共に過ごした時間も、すべてを失ってしまったこと。
「だから、私の結晶はこれ以上大きくならない。あなたに出会って、また恋に落ちたけど……前の恋の記憶がないから、病気が再発しても、進行がすごく遅いの。でもあなたは違う。あなたがこの薬を飲んだら……私のことを、全部、忘れてしまう」
ユナは涙で濡れた顔で、リヒトの水晶の腕をそっと両手で包み込んだ。「生きてほしい。あなたが死んでしまうなんて、耐えられない。だから、お願い。この薬を飲んで。私のことなんて、忘れてくれていいから……」
愛の記憶を抱いたまま、輝くオブジェとなって死ぬか。
愛のすべてを忘れ去り、空っぽの心で生き永らえるか。
究極の選択が、重く、冷たく、リヒトの胸に突きつけられた。
第四章 あなたが灯した光
リヒトは、決断を下した。
彼は、薬を飲むことを選んだ。しかし、それは今すぐではなかった。彼はユナに、一枚だけ、最後の絵を描く時間がほしいと告げた。ユナは何も言わず、ただ静かに頷いた。
その日から、リヒトの壮絶な制作が始まった。彼はアトリエに籠り、寝食も忘れ、一枚の巨大なキャンバスに向かった。それは、ユナの肖像画だった。彼は、自分の消えゆく記憶のすべてを、その絵に刻み込もうとした。
彼女のミルクティー色の髪、陽光を思わせる笑顔、そばかすの散った頬。公園で星を見上げた夜、花屋で鼻歌を歌う横顔、アトリエに初めて来たときの少しはにかんだ表情。一つ一つの思い出を、脳の引き出しからすべて取り出し、絵筆にのせていく。
制作が進むにつれ、彼の結晶化もまた、恐ろしい速さで進行した。左腕は肩まで完全に水晶と化し、右腕にも侵食が始まった。彼は砕いた水晶の破片を絵の具に混ぜ込んだ。そうすることで、この絵の中に自分の命の一部を、ユナへの愛の証を、永遠に閉じ込めることができると信じて。
指が思うように動かなくなっていく。それでも、彼は描き続けた。ユナとの記憶が、この世界から、自分の中から完全に消えてしまう前に。この愛が確かに存在したという、唯一の証明を残すために。
数週間後、絵は完成した。
それは、神々しいまでに美しいユナの肖像画だった。背景には、彼らが過ごした季節の風景が万華鏡のように描かれ、絵全体が、混ぜ込まれた水晶の粒子によって、光を受けるたびに無数の虹色のきらめきを放っていた。絵の中のユナは、少しだけ悲しそうに、けれど、どこまでも優しく微笑んでいる。
絵を描き終えたリヒトの身体は、胸のあたりまでが水晶に変わっていた。彼は最後の力を振り絞り、絵の隅にタイトルを記した。
『水晶の心音』
そして、彼はユナが置いていった薬瓶を手に取り、白い錠剤を静かに飲み干した。
数ヶ月後。
あるギャラリーの壁に、一枚の絵が飾られていた。多くの人がその絵の前で足を止め、その圧倒的な美しさと、どこか切ない輝きに見入っている。
一人の青年が、その絵の前にふらりとやってきた。彼はリヒトだった。記憶を失い、今はごく普通の、健康な青年として日々を送っている。彼は自分がなぜこのギャラリーに来たのかもよく分かっていなかった。ただ、何かに強く引かれたのだ。
彼は絵を見上げた。描かれた女性の顔も、背景の風景も、まったく見覚えがない。それなのに、なぜだろう。胸が締め付けられるように苦しくなり、理由も分からないまま、頬に熱いものが伝った。
「……きれいだ」
かすれた声で呟く。その絵は、まるで自分の魂の半分がそこにあるかのように感じられた。
その時、隣にそっと寄り添う気配があった。見ると、ミルクティー色の髪をした女性が、彼と同じように絵を見上げていた。
「この絵、素敵ですよね」
彼女はリヒトに微笑みかけた。初めて会うはずの女性。なのに、その笑顔はひどく懐かしく、リヒトの心の空洞に温かい光を灯した。
「ええ……とても」
リヒトは彼女から目が離せなかった。すると、彼は気づいてしまった。彼女が差し出したパンフレットを受け取ろうとした、その指先。薬指の爪の生え際に、まるで砂糖菓子のかけらのような、微細な光の粒が一つ、キラリと輝いていたのを。
ユナは、もう薬を飲んでいなかった。彼女は、再び愛と共に生きることを選んだのだ。たとえそれが、茨の道だとしても。
記憶は消えても、魂は惹かれ合う。二人は見つめ合った。ギャラリーの柔らかな光の中で、新たな物語の、最初の心音が、静かに響き始めていた。