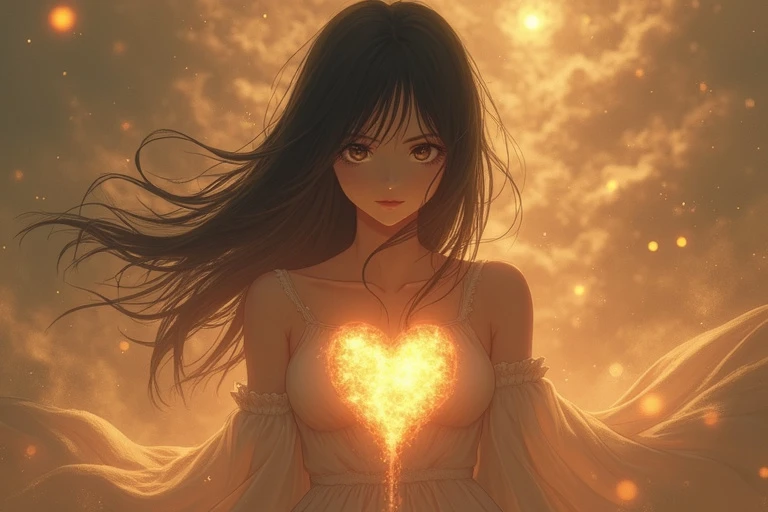第一章 光の粒子と隔壁
この世界で、人々は光を纏って生きていた。『信頼』という感情が、目に見える粒子となって身体から放たれるのだ。親密な者同士が交わす会話は、金色の霧が舞うように煌めき、疑念や不信は、その光を淀ませ、灰色に沈ませる。しかし、その光は美しいだけではなかった。信頼が深まりすぎると粒子は密度を増し、互いの存在を弾き合う物理的な力となる。だから人々は、愛する者とでさえ、一定の距離を保って生きていくことを宿命づけられていた。
僕、レンの世界は、さらに歪だった。誰かと本当の友情を育んでしまうと、その相手との間に『不可視の隔壁』が生まれる。それは信頼の光が反発し合うのとは違う、もっと絶対的で、冷たい断絶だった。声は届く。思考さえも伝わる気がする。けれど、同じ空気を吸うことも、指先一本触れることも叶わなくなる。僕はその呪いを恐れ、心を閉ざして生きてきた。
カイと出会うまでは。
彼だけが、唯一の例外だった。僕との間に決して隔壁を作らず、その温かい手に触れることを許してくれた、たった一人の親友。そのカイが、ある日忽然と世界から消えた。彼がいたはずの場所には、虚空が口を開けているだけだった。
机の上には、彼と初めて会った日に交換した『共鳴する砂時計』が静かに置かれている。心臓の鼓動を模した二つのガラス球が繋がった、奇妙なオブジェだ。僕の砂時計は、カイが消えたあの日から、ぴたりと時の流れを止めている。そして、彼のものであったはずのもう片方は、重力に逆らうように、一粒、また一粒と、砂をゆっくりと逆流させていた。
第二章 共鳴する砂時計
カイの部屋は、彼の不在を信じられないほど、彼の匂いで満ちていた。読みかけの本、脱ぎっぱなしのシャツ、窓辺に置かれた小さなサボテン。すべてが昨日の続きを待っているかのように、息を潜めている。僕は彼のベッドに腰を下ろし、止まった砂時計をそっと手に取った。冷たいガラスの感触が、失われた彼の体温を思い出させ、胸の奥がきしんだ。
彼との出会いは、古い図書館の片隅だった。誰もが放つ信頼の光が、彼の周りだけは不思議なほど穏やかで、揺らめく水面のように澄んでいた。僕が持つ隔壁の呪いを打ち明けた時も、彼は驚きもせず、ただ静かに頷いた。
「面白いね、それ」
彼は屈託なく笑い、僕に手を差し出した。
「試してみようよ。俺と君の間にも、壁ができるかどうか」
僕は恐怖に震えながら、恐る恐るその指先に触れた。覚悟していた断絶は、なかった。代わりに、これまで感じたことのない温もりが、僕の凍てついた心を溶かしていくのが分かった。僕の身体から溢れ出した感謝と喜びの光が、彼の穏やかな光と混ざり合い、部屋の埃を黄金色に染め上げた。
「ほらね。俺たちは特別なんだよ、レン」
その言葉は、僕にとって救いだった。この日交換した砂時計は、僕たちの特別な絆の証。だが今、その砂は不可解な動きを続けている。まるで、僕たちの時間が、ねじれてしまったことを示すかのように。
第三章 失踪の残響
カイが消えたのは、風の強い午後だった。僕たちは街を見下ろす丘の上に座り、他愛もない話をしていた。空を流れる雲、遠くで響く教会の鐘の音、道行く人々が放つ色とりどりの光の粒子。すべてが完璧な一日になるはずだった。
「ねえ、レン」
不意に、カイが僕の名前を呼んだ。その声には、聴き慣れない微かな翳りがあった。彼の身体から放たれる光が、陽炎のように揺らいで見える。
「もし、俺がいなくなったら、どうする?」
「馬鹿なこと言うなよ。どこにも行かせないさ」
僕がそう答えて笑いかけた瞬間、奇妙な感覚が全身を襲った。これまで僕とカイの間には、隔壁こそなかったものの、ごく僅かな、意識しなければ分からないほどの「境界」のようなものが存在していた。それが、ふっと消え失せたのだ。まるで、薄いガラスが砕け散ったように。
世界が、ひとつになった。
その解放感に満たされて、僕は彼の肩に触れようと手を伸ばした。だが、指先が触れる直前、カイの身体が淡い光を帯びて透け始めた。彼の輪郭が曖昧になり、風景に溶けていく。
「カイっ!」
僕の叫びは、彼に届かなかった。
「ごめん、レン。時間が来たんだ」
その声だけが風に乗り、僕の鼓膜を震わせた。次の瞬間、彼の身体は無数の光の粒子となって霧散し、風に攫われて消えてしまった。後には、彼のものだった砂時計だけが、ころりと芝生の上に転がっていた。
第四章 逆流の果て
季節がひとつ巡った。カイの砂時計の、逆流を続けていた砂が、ついに全て上の硝子球へと戻りきった。
その瞬間だった。
砂時計が、眩いほどの純白の光を放った。二つのガラス球が微かに共鳴し、高く澄んだ音を立てる。光が収まると、今まで何もなかった黒檀の台座に、複雑な幾何学模様が青白い光で浮かび上がっていた。それは、星図のようでもあり、古代の紋様のようでもあった。
僕は息を呑み、カイの部屋を再び訪れた。彼の机の引き出しの奥、彼が大切にしていた革のノートを開く。最後のページに、見慣れた彼の筆跡があった。
『砂が満ちる時、君は隔壁の本当の意味を知るだろう。俺を追わないでほしい。これは俺のエゴだから。でも、もし君がそれでも俺に会いたいと願うなら――この砂時計が道標だ』
心臓が大きく脈打った。カイの失踪は、単なる別れではなかった。これは、彼が僕に残した謎であり、招待状なのだ。隔壁は、ただ人を隔てる呪いではない。その向こうには、僕の知らない真実が隠されている。僕は紋様の浮かび上がった砂時計を強く握りしめた。君のいた場所へ、必ず行ってみせる。
第五章 時間軸の扉
街で最も古い記録を収める中央古文書館。その空気は、埃と古い紙の匂いが混じり合い、まるで時間そのものが堆積しているかのようだった。僕は砂時計に浮かんだ紋様の写しを片手に、何日も書架の間を彷徨った。
そして、ついに見つけたのだ。禁書に指定された一冊の古びた書物に、あの紋様と酷似した図が描かれていた。『時渡りの蓋然性に関する異説』と題されたその本には、こう記されていた。
「魂が抱く強すぎる信頼は、時空に歪みを生じさせる。それは、本来交わるはずのない異なる時間軸に存在する魂を、互いに引き寄せる力となる。だが、二つの時間は決して混じり合うことはない。その境界に現れる絶対的な断絶こそ、人々が『隔壁』と呼ぶ現象の正体である」
全身から血の気が引いた。隔壁は、友情が深まりすぎた者同士が、異なる時間軸に弾き飛ばされるのを防ぐための、世界の安全装置だったのだ。
カイは、僕と同じ時間の人間ではなかった。
だからこそ、僕たちは「特別」だったのだ。彼は、僕の時間軸に属さない異物だったから、隔壁という安全装置が正常に作動しなかった。彼が消えたあの日、僕たちの絆が世界の法則をも超えるほど深まり、僕たちの間にあった僅かな時間軸の境界線が、完全に消滅してしまったのだ。
砂時計が再び光を放ち、僕の行く先を照らす。それは、カイがいたであろう、遥か未来へと続く道を示していた。
第六章 再会と真実
砂時計に導かれた先は、時空の裂け目だった。目の前に広がるのは、僕の知る街並みではない。高くそびえるガラスの塔はひび割れ、空は鈍色の雲に覆われている。荒廃した未来の世界。その一室で、僕はカイを見つけた。
彼は、生命維持装置と思しき無数の管に繋がれ、静かにベッドに横たわっていた。その顔は穏やかだったが、かつての快活な光はなく、消え入りそうなほどに儚い。
僕と彼の間に、再びあの『不可視の隔壁』が立ち塞がっていた。触れることはできない。けれど、声は届く。僕の姿を認めたカイの唇が、かすかに動いた。
「…来てくれたんだ、レン」
その声は、機械音に混じって、かろうじて聞き取れるほど弱々しかった。
「どうして…こんな…」
「これが、俺の本当の姿だよ。俺の時代では、もう治療法のない病でね…死ぬ前に、どうしても本当の友達が欲しかったんだ」
彼は、最期の力を振り絞り、意識だけを過去の世界…僕のいる時代へと飛ばしていたのだ。健康な身体の幻影を纏い、僕と出会うために。彼が消えたのは、彼の本来の時間が尽きたから。彼の生命が、燃え尽きたからだった。
「君と過ごした時間は、俺の人生の全てだった。あの丘で話したこと、図書館で笑い合ったこと…全部が、俺にとっての宝物だ」
僕たちは隔壁を挟んで、最後の言葉を交わした。物理的には、世界で最も遠い場所にいる。けれど、僕たちの魂は、これまでで一番近くにあった。僕たちの周りには、時間も空間も超えて共鳴する、強く、そして切ない信頼の光が、満天の星のように輝いていた。
第七章 隔壁の向こうへ
カイに繋がれていたモニターの波形が、一本の直線になった。
その瞬間、彼の身体から放たれていた最後の光の粒子が、僕たちを隔てていた壁を静かに通り抜け、雪のように僕の身体に降り注いだ。それは温かく、カイの感謝と友情の全てが込められているようだった。そして、僕を縛り続けてきた隔壁が、音もなく消滅した。
物理的な隔たりは、もうない。けれど、そこにカイの姿はなかった。
僕は自分の時代に戻っていた。手の中には、両方の砂が流れを止め、永遠の静寂を刻む砂時計だけが残されている。
街の景色は何も変わらない。人々は相変わらず美しい光を放ち、互いに距離を保ちながら生きている。だが、僕の世界は、もう以前とは違っていた。隔壁を恐れる心は、もうない。本当の絆は、触れ合うことでも、同じ時間を生きることでもないのだと知ったから。
僕は空を見上げた。カイがいた未来の空が、幻のように今の空に重なって見える。彼の声が、風に乗って聞こえた気がした。
『ありがとう、レン』
僕は一人、静かに歩き出す。胸の中には、触れることのできない親友との、時を超えた絆が永遠に刻まれている。隔壁の向こう側に、確かに君はいたのだ。それで、十分だった。