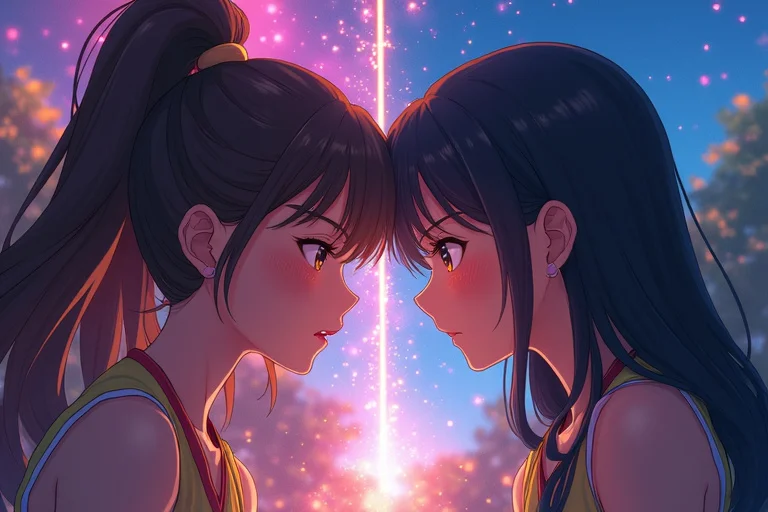第一章 遺された約束の箱
「もし俺が死んだら、これを」
そう言って天野陽向が差し出したのは、古びた木製の小箱だった。つるりとした黒檀の表面には、螺鈿細工で北斗七星が埋め込まれている。俺、桐谷朔は、システムの仕様書から顔を上げた。モニターの青い光が、親友の悪戯っぽい笑顔を照らしていた。
「死んだら? 冗談はよせ。お前は雑草よりしぶとい」
「ひどい言い草だなあ。でも、万が一ってことがあるだろ? そしたら、朔にしか頼めない。この箱を開けて、中に入ってる『約束』を果たしてほしいんだ」
陽向は芸術家の卵で、いつも突拍子もないことを言い出す。俺は彼の言葉を、また始まったいつもの気まぐれだと片付けた。俺たちの友情は、ロジックとパッション、水と油のように正反対の性質ながら、不思議と二十年以上も続いていた。俺がプログラムの論理構造に美しさを見出すように、陽向は夕焼けのグラデーションに宇宙の真理を見ていた。
その会話から、わずか一週間後のことだった。陽向は、画材の買い出しに出かけた交差点で、信号を無視したトラックにはねられ、あっけなくこの世を去った。あまりに突然で、非現実的な出来事だった。俺の頭は、エラーを起こしたコンピュータのように真っ白になり、感情という名のプログラムが正常に機能しなくなった。
葬儀が終わり、陽向の部屋を整理していた時、本棚の隅にあの黒檀の小箱を見つけた。まるで、俺に見つけてもらうのを待っていたかのように。震える指で蓋を開ける。中には、強い油彩の匂いと共に、三つのものが入っていた。
一つは、描きかけのキャンバス。深い藍色の夜空に、銀河が渦を巻いているが、中心部分だけがぽっかりと空白になっている。
二つ目は、一枚の古びたメモ用紙。「星屑の湖へ」とだけ、陽向の癖のある丸い字で書かれていた。
そして三つ目は、何かの設計図。手書きで細かく寸法が記されたそれは、古い形式の天体望遠鏡のものらしかった。
「星屑の湖」。それは俺たちが子供の頃、裏山の秘密基地で語り合った空想の場所だ。満天の星が湖面に映り込み、まるで宇宙を泳いでいるかのような錯覚に陥る、世界で一番美しい場所。
約束とは、この絵を完成させることだろうか。そして、それを「星屑の湖」へ届けること? 馬鹿げている。非効率で、感傷的で、何の意味もない行動だ。だが、陽向の最後の頼みだ。俺の思考は、初めてロジックを放棄した。俺は陽向の遺志を継ぐため、この意味不明な旅に出ることを決めた。陽向が遺した最後のバグを、デバッグするために。
第二章 色褪せた地図の旅
「星屑の湖」への具体的な手がかりはない。俺はまず、陽向のアトリエに残されたスケッチブックをめくった。そこには、俺たちの思い出の場所が、陽向の温かいタッチで無数に描かれていた。海辺の古い灯台、夏祭りの夜に見上げた神社の鳥居、初めて二人で旅した田舎町の駅。メモの裏に微かに残されたインクの染みは、その田舎町の地名と一致していた。
俺は有給休暇を申請し、最小限の荷物と、キャンバスと設計図を詰め込んだバッグを背負って旅に出た。目的地の駅に降り立つと、潮の香りと錆の匂いが混じった風が頬を撫でた。記憶の中にある風景と寸分違わない。陽向は、この場所で何をしようとしていたのだろう。
駅前の小さな食堂に入ると、壁に陽向が描いたらしい海の絵が飾られていた。店の老婆は、俺が陽向の友人だと知ると、目を細めて語り始めた。
「あの子、半年前にも来てたよ。ずいぶん痩せちゃってねえ。でも、ここのアジの干物が世界一だって、嬉しそうに笑うんだ」
半年前。その頃の陽向は、新しいコンペの準備で忙しいと俺に言っていた。嘘だったのか。陽向の言葉の裏に、俺の知らない時間が隠されていることに気づき、胸がざわついた。
旅を続けるうちに、俺は陽向のパズルを一つずつ解いていくような感覚に陥った。彼が訪れた場所、彼が言葉を交わした人々。そのすべてが、陽向という人間の輪郭を、俺の知らない側面からくっきりと浮かび上がらせていく。彼はただ自由奔放に生きていたのではなかった。彼は自分の残り時間が少ないことを、おそらく知っていたのだ。そして、俺に何かを伝えようとしていた。俺が लॉジックの壁の内側で気づかなかった、何かを。
夕暮れの灯台で海を眺めていると、陽向の声が聞こえた気がした。
「なあ朔、見てみろよ。世界はこんなに美しいのに、お前はモニターの数字ばっかり見てる。もったいないだろ」
俺は、陽向が隣にいないという事実の重さに、初めて涙を流した。非効率な感情の奔流が、俺の心を洗い流していくようだった。
第三章 星屑の湖の真実
旅の最後のヒントは、陽向がよく口にしていた童話の一節だった。「迷子のフクロウは、丘の上のガラスの瞳に導かれる」。それは、俺たちの故郷の町外れにある、閉鎖された小さな天文台のことだと直感した。子供の頃、俺たちはそこを「ガラスの瞳のフクロウ」と呼んでいた。そこが、本当の「星屑の湖」だったのだ。
錆びた鉄の扉を押し開けると、カビと埃の匂いが鼻をついた。ドーム状の天井から差し込む月光が、巨大な天体望遠鏡のシルエットをぼんやりと照らしている。その望遠鏡はひどく傷んでおり、レンズの一部が欠けていた。
望遠鏡の操作卓に、見覚えのある黒檀の小箱がもう一つ置かれていた。俺の心臓が大きく跳ねる。箱の中には、一通の手紙が入っていた。陽向の字だった。
『朔へ
この手紙を読んでいるってことは、ちゃんとここまで辿り着いてくれたんだな。ありがとう。
ごめんな、ずっと嘘をついてて。俺は病気だった。もう長くないこともわかってた。お前に言えなかったのは、お前がきっと、俺を救おうと無茶をすると思ったからだ。お前のロジックと優しさは、いつだって自分より他人に向かうからな。
なあ朔。俺が死んだら、お前はきっと自分の殻に閉じこもってしまう。世界と自分を隔てる分厚い壁を作って、一人きりになってしまう。それが怖かった。俺にとって、それだけが唯一の心残りだった。
だから、この旅を計画した。俺が遺した約束は、絵を完成させることじゃない。設計図は、この壊れた天文台の望遠鏡を直すためのものだ。絵の空白は、お前がこれから見つけるべき新しい星を描くために、俺がわざと空けておいたスペースなんだよ。
俺がいなくても、お前は一人じゃない。旅の途中で、いろんな人と話しただろ? 世界は、お前が思っているよりずっと温かくて、美しいもので満ちている。
だから、約束してくれ。俺がいなくなった世界でも、ちゃんと顔を上げて、歩いていくって。新しい人々と出会って、笑って、泣いて、生きていくって。
それが、俺がお前に本当に果たしてほしかった、たった一つの『約束』だ。
じゃあな、親友。俺の自慢の、たった一人の親友。
陽向』
手紙を持つ手が震え、涙が次から次へと溢れ出して止まらなかった。陽向。お前は、最後の最後まで、俺のことばかり考えていたのか。俺が非効率だと切り捨ててきた、人の繋がりや感情の揺らぎこそが、陽向が俺に遺したかった宝物だったのだ。俺は、その場に崩れ落ち、子供のように声を上げて泣いた。ドームの隙間から見える星空が、陽向の涙のように滲んでいた。
第四章 新しい星を探して
夜が明けても、俺は天文台から動けなかった。陽向の想いの重さと温かさが、俺の全身を包んでいた。俺は立ち上がり、陽向が遺した設計図を広げた。複雑だが、緻密で、美しい設計図。それはまるで、陽向自身が書いた詩のようだった。
俺は町に下り、鉄工所やガラス工房の扉を叩いた。人付き合いが苦手な俺にとって、それは途方もなく高いハードルだった。だが、陽向の顔を思い浮かべると、不思議と勇気が湧いてきた。
「友人の……最後の夢なんです。この望遠鏡を、もう一度空に向けさせてやりたい」
俺の拙い説明に、職人たちは最初はいぶかしげな顔をしたが、陽向が遺した情熱のこもった設計図と、俺の必死の形相に、次第に心を動かしてくれた。一人、また一人と協力者が現れ、天文台の修理は、いつしか町の人々を巻き込んだ一大プロジェクトになっていた。
汗と油にまみれ、笑い合い、時には意見をぶつけ合う。非効率で、無駄だらけで、けれど信じられないほど温かい時間。俺は、陽向が俺に見てほしかった世界を、確かにこの目で見ていた。
数ヶ月後、望遠鏡はついに息を吹き返した。修復を祝うささやかなパーティーが開かれ、町の人々が天文台に集まった。俺は、あの描きかけだったキャンバスをイーゼルに立てた。空白だった中心に、俺は修理されたばかりの望遠鏡を描き加えた。それは、陽向の星と、俺たちのこれからを繋ぐ架け橋のようだった。
その夜、俺は一人、接眼レンズを覗いた。調整されたレンズが捉えたのは、寸分の狂いもなく輝く、冬のダイヤモンドだった。星々の光が、まるで祝福するように瞳に飛び込んでくる。なんて、美しいんだ。
陽向、聞こえるか。お前のいない世界は、確かに寂しい。でも、お前が教えてくれた通り、温かくて、美しい。俺はもう、大丈夫だ。
心の中で呟くと、一つの流れ星が、夜空をすっと横切った。まるで、陽向が「それでいい」と笑いかけてくれたようだった。
陽向という一番星を失った俺の空は、それでも満天の星で満たされている。これから俺は、自分の足で歩き、自分の瞳で、新しい星を一つずつ見つけていくだろう。陽向との友情という名のテレスコープを胸に抱いて。その輝きが、俺の道を永遠に照らし続けてくれると信じながら。